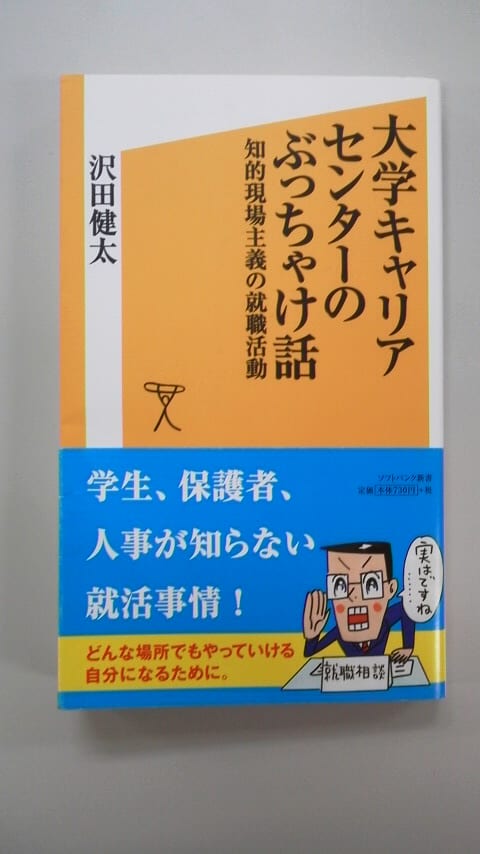========================
パライソメッセージ 2015.07.31 N0.44
Mail : isokawas@goo.jp
Blog : http://blog.goo.ne.jp/isokawas
========================
今こそ、反ファシズム統一戦線を②
礒洋輔首相補佐官は集団安全保障の発動に関わって「法的安定性は関係ない」と言った。このことが通るなら、警察や裁判所といった司法は不要である。順法性や立憲主義、憲法判断は関係ないと蔑ろにすることを公言している。つまりは自公連立政権と安倍首相の判断を憲法・法律の上に置くということである。そして司法は権力者の下に置くということに繋がっていく。
安倍チルドレンとか安倍取り巻きとか言われている連中の暴言が続く。「八紘一宇」「マスコミを懲らしめる」とか今回の「法的安定性は関係ない」そして安倍応援団の一部によるヘイトスピーチ。これらに対して自公連立安倍政権は、言葉だけの遺憾の意を表明しているが、事実上の放置を決め込んでいる。私は、これは大変危険な事態の兆候であり、『彼らを通してはいけない』と痛切に思っている。つまりこういった『失言』『軽口』『流言』は段々と日常化し、ファシズムへの道の露払いをするというのは、旧日本軍国主義やヒットラーナチスドイツの台頭でも見られた歴史の教訓ではないか。
今回の礒崎発言は、旧日本軍国主義やナチスドイツよりも、もっと酷いのではしてないか。つまり、かつてのファシストは『国家総動員法』とか『全権委任法』といった最悪の犯罪的法であっても一応「法的安定性」の体裁をとった。それは『法』をなくせばファシズムの秩序が維持できないからである。そのために司法をファシストの下に置き、日本でもドイツでも、憲兵やヒットラーユーゲントが『法』にかこつけた大犯罪を犯した。
今回の礒崎氏は法をも蔑ろにする発言はもちろんだが、他の『軽薄』発言も、現行法を無視もしくは蹂躙するということでは、クーデターからファシズムへの露払いである、ということが私の危機意識である。彼らは表面的には謝罪や弁明や殊勝なこと言うが、本音ではそんなことは露とも思っていないのではないか。こういったプロパガンダとでもいうべきものの蔓延は、その奥にある意図を露わにし、その危険性について広く危機意識を共有し、その先にある『彼ら』の野望を広汎な国民の手によって葬り去らなければならないと思う。
今こそ、反ファシズム統一戦線を!!
若者も戦争体験者もママもそして広く国民が【主権在民】と【立憲主義】の2点で一致して自公連立安倍政権を辞めさせたい。戦争法案反対は自民党の現職地方議員も自民党・公明党の重鎮も勇気と心ある創価学会員からもどんどんと湧き上がってきている。絶対支持率2割に満たない自民党が圧倒的多数の議席をバックグラウンドにファシズムへの道を歩むなら、それを許してきた小選挙区制を利用して、反ファシズムで1本化し自公を国政から退場させることも逆に可能だ。各野党政党には頑張ってもらいたい。党利党略やセクト主義を留保して、反ファシズムの旗でまとまって、解散・総選挙に臨んでもらいたい。心からそう思う。
==イソじいの「一押しBOOK」==

題名:『永続敗戦論 戦後日本の心』
著者:白井聡 1977年生まれ。早稲田大学政経学部政治学科卒業。一ツ橋大学社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。現在は京都精華大学教授。戦争法案や安倍首相の言う「戦後レジーム」などをめぐって、最近注目の若手研究者で論客。著書に『未完のレーニン――「力」の思想を読む』『『物質』の放棄を目指して――レーニン、<力>の思想』など。
発行所:株式会社太田出版 2013年3月27日第1刷発行、2014年7月2日第13刷発行
内容:
本書は最近注目を浴びている。白井氏自身も最近は引っ張りだこの様子。私はこの本は2014年の2月に市民図書館から借りて読んだが、かなりロジカルではあるがタイムリーでもあり一気に読み通した。
「戦後」とは言うが「敗戦後」とは言わないのはなぜか。いろんな角度から今日の権力者に対するアンチテーゼの論理展開。ポツダム宣言やサンフランシスコ講和条約は「敗戦後」の秩序だから認めない。尖閣や竹島やサンフランシスコ講和条約外の千島列島も「敗戦後」秩序そのものを認めず、偏狭なナショナリズムで世論を煽る。従軍慰安婦や南京大虐殺の否定も本質は「敗戦」の否認。安倍首相の言う戦後レジームからの脱却も「敗戦」の否認であり、偏狭なナショナリストやヘイトスピーチへの共感に至る。筆者のメッセージは「敗戦」に向き合い、そこからの新たな秩序の構築を提起している。
私は、白井氏ら若手論客も参加して、反ファシズム統一戦線を今こそ立ち上げたい、本当にそう思う。
イソの評価:★★★★☆