『木口木版画は、現代ではその制作者を数多く持たない時代であるけれど、自分はこの仕事を、自分なりに発展させたいと考えるのだ。
この作業ではネをあげることが許されないかわり、せっかちな世間のわずらわしい時間にまどわされることもない。
それは、陽の光りの射してくる前の薄明であり、夜を中心とした黄昏を結ぶ雄弁であるより沈黙を土台としたつぶやきである。
暗い闇の深淵よりさしてくる亀裂の光をビュランは捉えなければならない。
陸では森林が良く、海では深海が良い。青空よりも宇宙の彼方がなお良いと思う。
それは木口木版画に使われるツゲやツバキの木の密な年輪が要求する材質のせいでもあるし、これら樹木の記憶がビュランを握る手によって呼びさまされるのであるかもしれない。
暗闇の中から光で何物かを取り出すこと、それは過去と未来を結ぶ手立てかも知れない。
もしそうでなくて何百年か先の世界を予言することができるかもしれない。
それを私はねがう。』
……日和崎尊夫の文章より抜粋
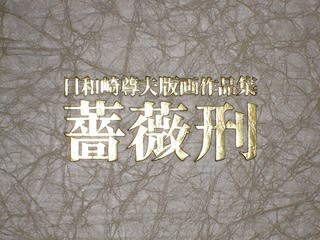
薔薇刑の表紙
1986年に、金鈴画廊の岡田さんから購入した日和崎尊夫の木口木版の版画集「薔薇刑」を今日は紹介します。
1960年代、駒井哲郎、池田満寿夫とともに現代版画の旗手として頭角を現した日和崎尊夫は、五百数十点の木口木版の作品を遺し、1992年に50歳の若さで亡くなりました。

薔薇魚

蛾

樹木
木を輪切りにして繊維の詰まった堅い面を版に、刃先の鋭いビュランで彫り込む木口木版技法は18世紀にイギリスで始まりました。
その精緻な表現が書物の挿画としてさかんに用いられましたが、その後の写真製版にとってかわられ急速に衰微してしまいます。
廃れていた木口木版画技法を独学で身につけ現代に蘇らせ、『闇を刻む詩人』とも言われる日和崎尊夫は、詩画集や版画集も多く手がけました。

焔

花

海
そのまま刷れば、黒一色の世界となる木口に、その暗闇から微細な線で紡ぎ出す日和崎尊夫の木口木版の世界は、長い長い年月の果てに形成された年輪のように、凝縮された美しさを私に感じさせます。
その世界は、日和崎自身の心の中の世界であり、また芸術家の鋭い感性で見つめたこの世の姿なのかも知れません。
鋭いビュランを使い堅い木口に緻密に線を刻む作業は、彼を精神的に極限状態に追い込むこともあったでしょう。
彼の版画は、私に微笑みかけてはくれない。
微細に切り込んだ白い線の背景にある、暗黒の世界が持つ不安や恐れや無常の上に漂う、現世の危うさ を私に語りかけてくるようです。

薔薇刑

寓話

凝視
木版画は、木を彫って版を作る技法で、版画技法としては最も古いものです。
また、木版の技法には二つあり、一つは木の幹を縦に切り、木目が水平に出るように挽いた木の板を彫って版木とする、最も一般的な版画技法の『板目木版』がまずあります。
棟方志功の版画や浮世絵などがその例で、主に日本で発達した技法です。

『花』一部拡大図
もう一つは、堅い木の幹を輪切りにして、その堅い中心部を使い版木を作る今回紹介した『木口木版』の技法があります。
木口木版はイギリスで生まれ発達し、木口の版木はとても硬いため彫刻刀は使えず、銅版画の道具であるビュランを使って彫ります。
木口木版は板目木版とくらべて精巧で密度の高い彫版が可能ですが、現在においては少数派の技法となっています。
また木版画には、輪郭線を彫り残して輪郭線にインクがつく陽刻法と、輪郭線を彫ることにより輪郭線にはインクがつかない陰刻法があり、ほとんどの木版画はその二つの技法を駆使して版を刻むことになります。

『海』一部拡大図
この時期、私は版画に興味を持ち、萩原英雄「赤の幻想」「石の花(赤)」、山中現、中山正、黒田茂樹、斉藤清、井上公三、畦地梅太郎、中林忠良、相笠昌義、浜田知明、野田哲也、多賀新、木下恵介、東谷武美、北川民次、香月泰男、芹沢介、アイオーなどの作品を集めました。
又、日本版画協会が出した、『東京百景』(東京の風景を主題に1年に10作家、10年で計10集100人の作品を収録)も購入。

葉

寓意

死
現代の木口木版作家としては、柄澤 齎、小林 敬生、平野 明、齋藤 修などを挙げることが出来ます。
木口木版の微細な線を刻む緻密な作業は、手の器用な日本人に適した版画とも言え、今後の若い作家に期待したい。
【日和崎尊夫略歴】
1941年高知県に生まれる。
1963年武蔵野美術学校西洋画科を卒業する。同年日本美術家連盟の版画工房で畦地梅太郎の講習会を受講し、木版画をはじめる。
1964年恩地孝四郎の著書を通じて木口木版に関心を持ち、木口版画をはじめる。
1966年日本版画協会新人賞、翌年日本版画協会賞を受賞する。
1968年ごろ『老子』、『法華経』から仏教哲学の概念である「カルパ」(43億2000万年という超時間)を知り、以降〈KALPA〉の連作を中心に「永遠」をモチーフとする。
1969年フィレンツェ国際版画ビエンナーレ金賞を受賞、国際的な注目を集める。
1974年から75年にかけて文化庁在外研修員としてヨーロッパに滞在する。
1977年木口木版画家の会[鑿の会]結成に参加。
1991年山口源大賞を受賞
1992年没する。
黒地に点刻した白い形が浮び上る密度の濃い作品で知られ、日本の現代版画に木口木版の地位を確立した先駆者。

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします

この作業ではネをあげることが許されないかわり、せっかちな世間のわずらわしい時間にまどわされることもない。
それは、陽の光りの射してくる前の薄明であり、夜を中心とした黄昏を結ぶ雄弁であるより沈黙を土台としたつぶやきである。
暗い闇の深淵よりさしてくる亀裂の光をビュランは捉えなければならない。
陸では森林が良く、海では深海が良い。青空よりも宇宙の彼方がなお良いと思う。
それは木口木版画に使われるツゲやツバキの木の密な年輪が要求する材質のせいでもあるし、これら樹木の記憶がビュランを握る手によって呼びさまされるのであるかもしれない。
暗闇の中から光で何物かを取り出すこと、それは過去と未来を結ぶ手立てかも知れない。
もしそうでなくて何百年か先の世界を予言することができるかもしれない。
それを私はねがう。』
……日和崎尊夫の文章より抜粋
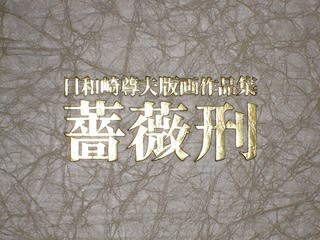
薔薇刑の表紙
1986年に、金鈴画廊の岡田さんから購入した日和崎尊夫の木口木版の版画集「薔薇刑」を今日は紹介します。
1960年代、駒井哲郎、池田満寿夫とともに現代版画の旗手として頭角を現した日和崎尊夫は、五百数十点の木口木版の作品を遺し、1992年に50歳の若さで亡くなりました。

薔薇魚

蛾

樹木
木を輪切りにして繊維の詰まった堅い面を版に、刃先の鋭いビュランで彫り込む木口木版技法は18世紀にイギリスで始まりました。
その精緻な表現が書物の挿画としてさかんに用いられましたが、その後の写真製版にとってかわられ急速に衰微してしまいます。
廃れていた木口木版画技法を独学で身につけ現代に蘇らせ、『闇を刻む詩人』とも言われる日和崎尊夫は、詩画集や版画集も多く手がけました。

焔

花

海
そのまま刷れば、黒一色の世界となる木口に、その暗闇から微細な線で紡ぎ出す日和崎尊夫の木口木版の世界は、長い長い年月の果てに形成された年輪のように、凝縮された美しさを私に感じさせます。
その世界は、日和崎自身の心の中の世界であり、また芸術家の鋭い感性で見つめたこの世の姿なのかも知れません。
鋭いビュランを使い堅い木口に緻密に線を刻む作業は、彼を精神的に極限状態に追い込むこともあったでしょう。
彼の版画は、私に微笑みかけてはくれない。
微細に切り込んだ白い線の背景にある、暗黒の世界が持つ不安や恐れや無常の上に漂う、現世の危うさ を私に語りかけてくるようです。

薔薇刑

寓話

凝視
木版画は、木を彫って版を作る技法で、版画技法としては最も古いものです。
また、木版の技法には二つあり、一つは木の幹を縦に切り、木目が水平に出るように挽いた木の板を彫って版木とする、最も一般的な版画技法の『板目木版』がまずあります。
棟方志功の版画や浮世絵などがその例で、主に日本で発達した技法です。

『花』一部拡大図
もう一つは、堅い木の幹を輪切りにして、その堅い中心部を使い版木を作る今回紹介した『木口木版』の技法があります。
木口木版はイギリスで生まれ発達し、木口の版木はとても硬いため彫刻刀は使えず、銅版画の道具であるビュランを使って彫ります。
木口木版は板目木版とくらべて精巧で密度の高い彫版が可能ですが、現在においては少数派の技法となっています。
また木版画には、輪郭線を彫り残して輪郭線にインクがつく陽刻法と、輪郭線を彫ることにより輪郭線にはインクがつかない陰刻法があり、ほとんどの木版画はその二つの技法を駆使して版を刻むことになります。

『海』一部拡大図
この時期、私は版画に興味を持ち、萩原英雄「赤の幻想」「石の花(赤)」、山中現、中山正、黒田茂樹、斉藤清、井上公三、畦地梅太郎、中林忠良、相笠昌義、浜田知明、野田哲也、多賀新、木下恵介、東谷武美、北川民次、香月泰男、芹沢介、アイオーなどの作品を集めました。
又、日本版画協会が出した、『東京百景』(東京の風景を主題に1年に10作家、10年で計10集100人の作品を収録)も購入。

葉

寓意

死
現代の木口木版作家としては、柄澤 齎、小林 敬生、平野 明、齋藤 修などを挙げることが出来ます。
木口木版の微細な線を刻む緻密な作業は、手の器用な日本人に適した版画とも言え、今後の若い作家に期待したい。
【日和崎尊夫略歴】
1941年高知県に生まれる。
1963年武蔵野美術学校西洋画科を卒業する。同年日本美術家連盟の版画工房で畦地梅太郎の講習会を受講し、木版画をはじめる。
1964年恩地孝四郎の著書を通じて木口木版に関心を持ち、木口版画をはじめる。
1966年日本版画協会新人賞、翌年日本版画協会賞を受賞する。
1968年ごろ『老子』、『法華経』から仏教哲学の概念である「カルパ」(43億2000万年という超時間)を知り、以降〈KALPA〉の連作を中心に「永遠」をモチーフとする。
1969年フィレンツェ国際版画ビエンナーレ金賞を受賞、国際的な注目を集める。
1974年から75年にかけて文化庁在外研修員としてヨーロッパに滞在する。
1977年木口木版画家の会[鑿の会]結成に参加。
1991年山口源大賞を受賞
1992年没する。
黒地に点刻した白い形が浮び上る密度の濃い作品で知られ、日本の現代版画に木口木版の地位を確立した先駆者。

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします



























モノトーンで細やかな小さい中に
無限の世界を表現する能力は、
日本人の真骨頂なのだと思っています。
木口木版にこだわってくれる作家が
若い世代にたくさん出るといいと思います。
驚いて貴ブログを読みました。
小山富士夫(古山子)の検索から入り、
「美術鑑賞」のブログ部分から見ています。
「焼き物鑑賞・蒐集」もご趣味のよう!?
小山富士夫かしらと思う「焼き物」(つるべ形の信楽焼のようで、【古山】と小さな陶印が押されているようですが、はっきりとは判らずに
検索していました(^^)。
これからもいろいろと、ブログにお寄りして勉強してみたいので、「お気に入り」ボタンを押しました(^=^)17:48分。