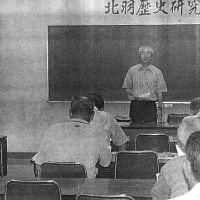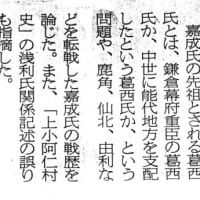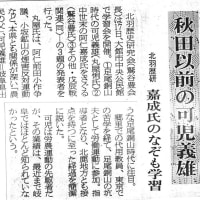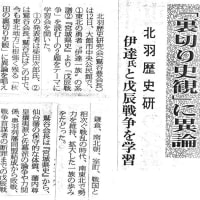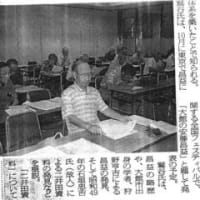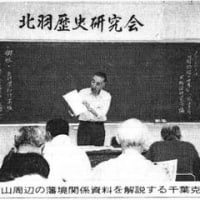中世浅利氏の盛衰と大館の浅利館
1、浅利姓について、1)浅利姓全国分布表、2)秋田県内、津軽、北海道の浅利姓分布、市町村別、 2、浅利氏の元祖、1)甲斐源氏系譜、2)初代浅利義成について、3)菩提寺と法名、3)浅利地名考察と浅利庄について。3、浅利系図、1)山梨県白根町浅利藤正氏系図、2)武田信繁から、武田虎在から等系図、3)長岐久蔵氏による浅利系図の操作について、
4、中世浅利氏の記録、(年代・史資料名) 1)浅利義遠1189吾妻鏡、2)浅利太郎知義1221承久軍記1227吾妻鏡、3)浅利遠江守1272浅瀬石文書、4)浅利六郎四郎清連1334津軽降人交名注進状1338浅利清連注進状(岩手県中世文書)、
5)浅利尾張守・南朝方降参1353和賀常陸権守義綱軍中(鬼柳文書)、 6)沙弥浄光11354甲斐国青島庄浅利郷・惣領彦四郎・五郎次郎1354(沙弥浄光譲状・岩手県中世文書)、註・沙弥浄光は、浅利尾張守である要素が高い。
7)浅利・願阿弥陀仏あ1380時衆過去帳、8)松峰山修復の浅利氏1405応永12年比内庄司浅利家代々修復(松峰神社伝承)、 註・比内地方の統治者として代々続いていたことを示す。 9)浅利但州(覚阿弥陀仏)1417時衆過去帳、10)浅利遠江入道但阿弥1441那智山願文・徳子之源遠江入道但阿弥子息二位殿隆慶(米良文書) 11)円福書状の浅利氏1441-1457岩手県中世文書、
12)浅利勘兵衛則章1468応仁二年扇田住、浅利勘兵衛則章十八歳(黒甜瑣語) 註・則章の存在は、鎌倉時代に源流をもつ浅利氏が、室町時代には、比内地方を大方において掌握し続けていたことの確実な証明です。
13)浅利貞義1525男鹿本山古来棟札写、領主大旦那安倍朝臣沙弥洪廓大願主浅利朝臣貞義(湊文書)、註・湊安東氏に属していた比内浅利氏が、安東堯李(洪廓)亡きあと、湊安東が檜山安東氏に合一されていく過程の中で隔たりを深めていったこと。また世代後においては、檜山安東氏と敵対関係に発展していくことなどが、事後の情勢として推察もされてくるように思います。
5、中世末から浅利氏四代 系図・朝頼ー則頼ー、浅利則頼の勢力圏図 、各世代の勢力時期の図表表示、1)則頼から則祐、2)長岡城主浅利勝頼。 註・各世代は、『秋田の中世・浅利氏』鷲谷豊著より引用説明。
6、浅利則頼分限帳(長崎家文書) 則頼の勢力分布図と照合して見る。鹿角郡扱人、鹿角郡目付に注意。給人住所の大館城廻り百五十人などに注意。この時代での石高表示は考察に留意を要すること等。
7、大館城主浅利則平 比内浅利氏の終末段階、1)天正18年秋田実李が浅利頼平を比内還住とす。 2)文禄二年浅利賦課未納、秋田離脱を策す、 3)文禄4年浅利おとな衆秋田氏に走る。頼平は津軽の支援をうけ秋田氏にそむく。米代川合戦8~11月。 4)慶長元年2月山田合戦、大阪より矢止め命令くる。 5)慶長2年浅利頼平上洛、慶長3年1月浅利頼平が大阪で急死。大館浅利氏は断絶。
8、大館の浅利館 1)各地の浅利城館・元祖義成の館址、ほか3城館。 2)大館の浅利館位置図 3)当該城館後の従来の説明。A大舘市広報 B鷲谷豊箸『大館地方の歴史散歩』記述の茂内館については訂正とす、 3)浅利館と記した古文書資料、『戊辰秋軍功取調書』狩野徳蔵・西家文書。 4)鬼ケ城は山であって城館跡ではない。史料・戊辰戦争絵図参照。 5)鬼ケ城と鍋越は同じ山の山名、古文書『御膳番日誌』西家文書の記述コピーを参照。 6)大館・鷹巣の中世城館名一覧。
ーーーーー以上、2月17日・大館市民カレッジ、講座テキストのレジメ項目、
以上、