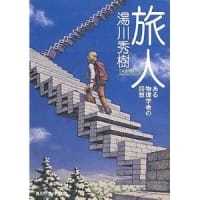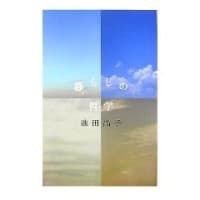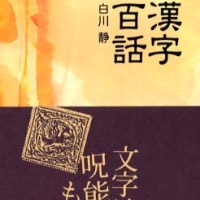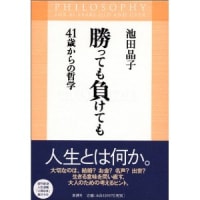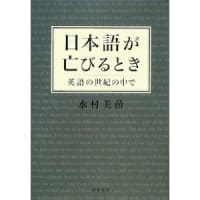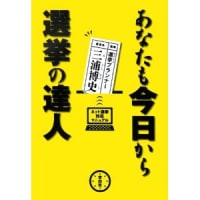(「その1」からの続きです。)
判事補と彼は、それぞれに沈黙を挟んで言葉を交わしながら、深い自問自答を繰り返していた。生まれた子供を前にすれば、命の重さは絶対的な価値を持つ。よって、「避妊すればこの子は生まれなかったのに」と語ってしまえば、必然的に激しい良心の葛藤が呼び起こされる。そうかと言って、すべてを「命の重さ」の一言で片付けることに対しては、どこかで論理がすり替えられているとの気持ち悪さが残る。
それでは、今回のように、生まれた子供が殺されてしまった場合はどうか。ここにおいて、「避妊すればこの子は生まれなかったのに」と語ることが初めて許されるように彼には感じられる。最初から生まれなかった場合と比較してみても、不存在という点で現象は等価値だからである。ここにおいて、「命の重さ」の一言で問題を片付け、論理をすり替えて逃げていた問題に人間は直面する。
判事補と彼は、殺された赤ちゃんの死体写真を挟んで、同じ問題に向き合っている。固く閉じられた赤ちゃんの目に、油断すると2人とも吸い込まれそうになる。一度でもこの世に生を受けて数ヶ月生きた後に殺されることと、一度もこの世に生を受けないこととでは、一体どちらが幸せなのか。どちらが悲惨なのか。どちらが残酷なのか。何よりも人の命が重いというならば、一度でも生まれたほうに軍配が上がるようにも思える。しかし、どうにも問題自体が上手く問題として立っているようには思えない。
生まれてすぐ殺されるくらいであれば、最初から生まれないほうが幸せだと言いたくもなる。しかし、幸・不幸や残酷さを問題にできるのは、実際に生まれた人間に対してのみであり、最初から生まれない人間に対しては評価の前提を欠く。生まれなかった人間は、実のところ、生まれてから殺された人間との比較においてのみ存在していると言ってよい。人は生まれた瞬間に死に向かって歩き始めるならば、生まれない人間が死に向かうことはあり得ない。
判事補は、結局のところ、過去の多くの判例も参考にして、検察官の求刑の8割という無難な結論に落ち着いたのだと語った。自分の命よりも大事な我が子の命という感覚のない者に対して、真面目に善悪を説くことは空しい。弁護人は、子育てに対する社会全体の構造や支援体制の不備に根本的な問題があるのであり、被告人夫婦を厳罰に処したところで何も解決しないと熱弁を振るっていた。これはその通りである。死者が帰らない限り、根本的な解決はあり得ない。
彼は判事補に対し、「我が子」という言葉の不思議さを語った。被告人夫婦は、自分の子を自分の所有物として扱い、最後まで好き勝手に操っていた。そして、独立の人格を持った人間として尊重していなかった。文法的な意味とは逆に、人はこのような親について、「我が子」の親であるとは言わない。人は、自分の子を別人格の人間として尊重するからこそ、その者が初めて「我が子」となり得る。この点を取り違えると、我が子を失った親に対して、「まだ他の子供が残っている」「子供ならまた産めばいい」といった慰めがなされることになる。
帰りがけ、判事補は彼に対して、「もし将来あなたが人の親になったならば、たとえ如何なることが起きたとしても、我が子を虐待することだけはないでしょう」と語った。彼は、「それは裁判官も同じでしょう」と語り、お互いに複雑な笑いを浮かべた。被告人夫婦の気楽さと比して、彼らには残酷な運命が待ち構えている可能性がある。もし我が子に先立たれた場合、恐らく彼は人間の形をした抜け殻として一生を送ることになる。しかし、殺された赤ちゃんの閉じられた目に賭けても、そこから逃げようとは断じて思わない。
彼と判事補が時間をかけて自問自答することができたのは、その場にいた人間が2人だけだったからだと彼は思う。時代は移り、重罪事件の量刑は6人の裁判員と3人の裁判官の評議によって決められることとなった。9人の評議の中で、人々はいかにして自問自答を経て割り切れない感情に折り合いをつけ、全体としての結論を導いていくのか。彼にはよくわからない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フィクションです。
判事補と彼は、それぞれに沈黙を挟んで言葉を交わしながら、深い自問自答を繰り返していた。生まれた子供を前にすれば、命の重さは絶対的な価値を持つ。よって、「避妊すればこの子は生まれなかったのに」と語ってしまえば、必然的に激しい良心の葛藤が呼び起こされる。そうかと言って、すべてを「命の重さ」の一言で片付けることに対しては、どこかで論理がすり替えられているとの気持ち悪さが残る。
それでは、今回のように、生まれた子供が殺されてしまった場合はどうか。ここにおいて、「避妊すればこの子は生まれなかったのに」と語ることが初めて許されるように彼には感じられる。最初から生まれなかった場合と比較してみても、不存在という点で現象は等価値だからである。ここにおいて、「命の重さ」の一言で問題を片付け、論理をすり替えて逃げていた問題に人間は直面する。
判事補と彼は、殺された赤ちゃんの死体写真を挟んで、同じ問題に向き合っている。固く閉じられた赤ちゃんの目に、油断すると2人とも吸い込まれそうになる。一度でもこの世に生を受けて数ヶ月生きた後に殺されることと、一度もこの世に生を受けないこととでは、一体どちらが幸せなのか。どちらが悲惨なのか。どちらが残酷なのか。何よりも人の命が重いというならば、一度でも生まれたほうに軍配が上がるようにも思える。しかし、どうにも問題自体が上手く問題として立っているようには思えない。
生まれてすぐ殺されるくらいであれば、最初から生まれないほうが幸せだと言いたくもなる。しかし、幸・不幸や残酷さを問題にできるのは、実際に生まれた人間に対してのみであり、最初から生まれない人間に対しては評価の前提を欠く。生まれなかった人間は、実のところ、生まれてから殺された人間との比較においてのみ存在していると言ってよい。人は生まれた瞬間に死に向かって歩き始めるならば、生まれない人間が死に向かうことはあり得ない。
判事補は、結局のところ、過去の多くの判例も参考にして、検察官の求刑の8割という無難な結論に落ち着いたのだと語った。自分の命よりも大事な我が子の命という感覚のない者に対して、真面目に善悪を説くことは空しい。弁護人は、子育てに対する社会全体の構造や支援体制の不備に根本的な問題があるのであり、被告人夫婦を厳罰に処したところで何も解決しないと熱弁を振るっていた。これはその通りである。死者が帰らない限り、根本的な解決はあり得ない。
彼は判事補に対し、「我が子」という言葉の不思議さを語った。被告人夫婦は、自分の子を自分の所有物として扱い、最後まで好き勝手に操っていた。そして、独立の人格を持った人間として尊重していなかった。文法的な意味とは逆に、人はこのような親について、「我が子」の親であるとは言わない。人は、自分の子を別人格の人間として尊重するからこそ、その者が初めて「我が子」となり得る。この点を取り違えると、我が子を失った親に対して、「まだ他の子供が残っている」「子供ならまた産めばいい」といった慰めがなされることになる。
帰りがけ、判事補は彼に対して、「もし将来あなたが人の親になったならば、たとえ如何なることが起きたとしても、我が子を虐待することだけはないでしょう」と語った。彼は、「それは裁判官も同じでしょう」と語り、お互いに複雑な笑いを浮かべた。被告人夫婦の気楽さと比して、彼らには残酷な運命が待ち構えている可能性がある。もし我が子に先立たれた場合、恐らく彼は人間の形をした抜け殻として一生を送ることになる。しかし、殺された赤ちゃんの閉じられた目に賭けても、そこから逃げようとは断じて思わない。
彼と判事補が時間をかけて自問自答することができたのは、その場にいた人間が2人だけだったからだと彼は思う。時代は移り、重罪事件の量刑は6人の裁判員と3人の裁判官の評議によって決められることとなった。9人の評議の中で、人々はいかにして自問自答を経て割り切れない感情に折り合いをつけ、全体としての結論を導いていくのか。彼にはよくわからない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フィクションです。