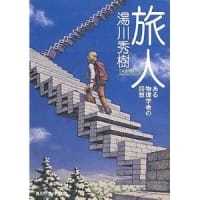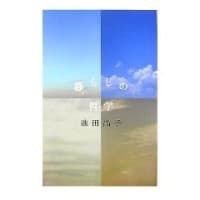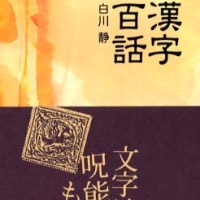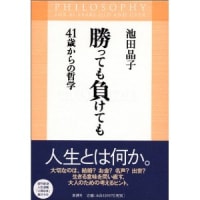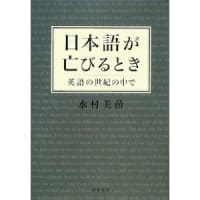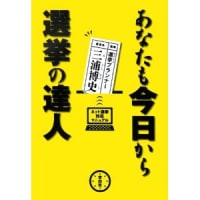p.112~
言語の特性の6番目としてあげられるのは、実体ではないものごと、抽象的な概念を実体であるかのように感じさせる傾向です。何かを言うこと、命題を立てることは、そこで使われている語彙を主題化して固定的に示すことを必ず含みますから、どうしても実体化傾向を免れません。これは、作用やはたらきや関係についての観念でしかないものごとを、そういうものが物理的実体としてあるかのように思わせてしまいます。
「神」や「素粒子」とか「時間」などという概念も、いったん立てられると、この実体化傾向を免れません。そこで、「神は存在するか」とか、「時間とはいったい何か」といった悩ましい哲学的問題が発生して、真剣に悩む一部の人たちが出てくるわけです。「神」という言葉をつくったのはどこかの人間ですから、それをつくった人間自身は、ある世界把握の仕方、みずからの世界感受の志向性をそう呼んだのであって、そういう世界把握をするにとって、神はある「概念」として存在するに決まっています。ある観念や把握の志向性に対して言葉を割り振っておきながら、それが存在するかしないかをあとから証明しようとするのは、考えてみればおかしな話です。
厳密な抽象的思惟、演繹を標榜する哲学にしてからがそうなので、まして私たちの日常的な言語使用では、抽象的な概念を実体であるかのようにもてあそぶ傾向から免れることは至難のワザです。これは、言語のもつ本質的な限界なのです。そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか、と言われそうですが、事実、この実体化傾向から完全に免れて何かを表現しようなどということは不可能なのです。そこで、いかに免れるかと考えるより、ある抽象的な概念を実体的に用いることで、どういう効能を得られるかと考えるほうが生産的です。観念世界の概念を、物理的な世界のものごとのように説いていくことは、それがうまくいけば強い心当たり感を引き出して、すっきりとさせる、深い納得をもたらす効用があるのだと思います。
***************************************************
上記のような言語の持つ限界を語ってしまうと、世間的な会話のやりとりの中では、ほぼ間違いなく変な顔をされると思います。いったん動き始めた社会の言語システムは、あまりに抽象的な概念の実体化から逃れがたくなっているため、改めて上記のような真実を投げ込むことには勇気がいります。現に、「給料が安い」「残業が多い」「休暇が取れない」といった問題が語られている際に、「『給料』も『残業』も『休暇』も抽象的な概念であって実体ではない」との問題提起をしたところで、変人扱いされるだけでしょう。
しかしながら、この世の中に実際に起きている事実の中には、この言語の持つ本質的な限界に切り込まなければ、どうしても的を外してしまうものもあります。そのような場合には、「そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか」という地点を経由すること、さらには「『そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか』と言えていること」に驚くことなくして、お互いに言葉が通じることはないでしょう。上記のような「強い心当たり感」、あるいは「深い納得」というものは、これが生じない種類の言語をいくら積み重ねても生じるものではなく、逆にこれが生じる言語が語られた時には一瞬で生じるものだと思います。
言語の特性の6番目としてあげられるのは、実体ではないものごと、抽象的な概念を実体であるかのように感じさせる傾向です。何かを言うこと、命題を立てることは、そこで使われている語彙を主題化して固定的に示すことを必ず含みますから、どうしても実体化傾向を免れません。これは、作用やはたらきや関係についての観念でしかないものごとを、そういうものが物理的実体としてあるかのように思わせてしまいます。
「神」や「素粒子」とか「時間」などという概念も、いったん立てられると、この実体化傾向を免れません。そこで、「神は存在するか」とか、「時間とはいったい何か」といった悩ましい哲学的問題が発生して、真剣に悩む一部の人たちが出てくるわけです。「神」という言葉をつくったのはどこかの人間ですから、それをつくった人間自身は、ある世界把握の仕方、みずからの世界感受の志向性をそう呼んだのであって、そういう世界把握をするにとって、神はある「概念」として存在するに決まっています。ある観念や把握の志向性に対して言葉を割り振っておきながら、それが存在するかしないかをあとから証明しようとするのは、考えてみればおかしな話です。
厳密な抽象的思惟、演繹を標榜する哲学にしてからがそうなので、まして私たちの日常的な言語使用では、抽象的な概念を実体であるかのようにもてあそぶ傾向から免れることは至難のワザです。これは、言語のもつ本質的な限界なのです。そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか、と言われそうですが、事実、この実体化傾向から完全に免れて何かを表現しようなどということは不可能なのです。そこで、いかに免れるかと考えるより、ある抽象的な概念を実体的に用いることで、どういう効能を得られるかと考えるほうが生産的です。観念世界の概念を、物理的な世界のものごとのように説いていくことは、それがうまくいけば強い心当たり感を引き出して、すっきりとさせる、深い納得をもたらす効用があるのだと思います。
***************************************************
上記のような言語の持つ限界を語ってしまうと、世間的な会話のやりとりの中では、ほぼ間違いなく変な顔をされると思います。いったん動き始めた社会の言語システムは、あまりに抽象的な概念の実体化から逃れがたくなっているため、改めて上記のような真実を投げ込むことには勇気がいります。現に、「給料が安い」「残業が多い」「休暇が取れない」といった問題が語られている際に、「『給料』も『残業』も『休暇』も抽象的な概念であって実体ではない」との問題提起をしたところで、変人扱いされるだけでしょう。
しかしながら、この世の中に実際に起きている事実の中には、この言語の持つ本質的な限界に切り込まなければ、どうしても的を外してしまうものもあります。そのような場合には、「そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか」という地点を経由すること、さらには「『そんなことを言ったら何も言えなくなるじゃないか』と言えていること」に驚くことなくして、お互いに言葉が通じることはないでしょう。上記のような「強い心当たり感」、あるいは「深い納得」というものは、これが生じない種類の言語をいくら積み重ねても生じるものではなく、逆にこれが生じる言語が語られた時には一瞬で生じるものだと思います。