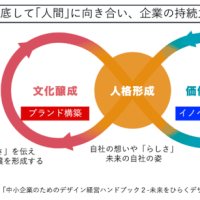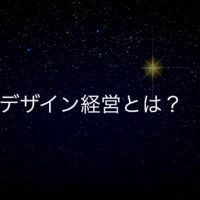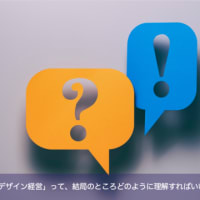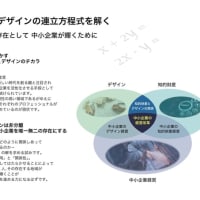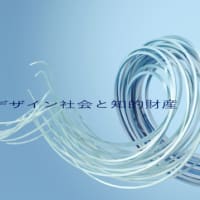私が知財セミナーの講師を担当する際には、いつも「知的財産」とは何か、その意味を共有するところからスタートしています。拙著「元気な中小企業はここが違う! 」にも書きましたが、「知的財産」の意味を、
」にも書きましたが、「知的財産」の意味を、
(1)「特許権などの知的財産権」と狭く捉えるのか、
(2)「企業活動から生み出された他と差異化された技術・ブランドなどの無形資産」と広く捉えるのか、
そもそもの対象の定義にコンセンサスを得られていないことが多いためです。
これまでセミナーの参加者に(1)か(2)かを尋ねた経験からは、平均するとおおよそ半々くらいに分かれている印象です。
現在関わっているある事業で行った中小企業を対象にしたアンケート調査では、さらに(1)と(2)の中間(知的財産権+ノウハウとして保護される財産)も加えて尋ねたところ、回答は概ね1/3ずつにきれいに分かれてしまっているような状況です。
「知的財産」をどちらの意味で捉えているかということによる影響はいろいろなところに現れてきて、例えば「知財活用」について議論しようとすると、
(1)であれば、「知的財産権をどう活用するか」という問題意識から、権利侵害への対応やライセンスといった話になりやすく、
(2)であれば、「差異化された要素をどう事業に活かすか」という問題意識から、事業戦略と密接に結びついた話になりやすい、
という違いが生じます。このようにコンセンサスを得られていない状態で、安易に「知財活用」という言葉を使うのはなんだか気持ち悪いものがあります。自分としては(2)の前提で話そうとしているのに、まだまだ(1)のように捉える人が多い中で「知財活用」の言葉を使ったが故に、「うちは特許権をもっていないから関係ないよ」、「そんなことは専門家や担当者マターでしょう」、と経営者に「知財活用」の話題を敬遠されることにつながってしまいやすいためです。
また、「知財の重要性を伝える」といった場合にも、
(1)であれば、模倣被害にあったり、侵害警告を受けたりすると大変なことになります、だから重要です、
(2)であれば、自社にしかない強みを明確に認識して、それを活かすことが競争力の強化につながります、だから重要です、
となり、これも相当伝えるべき内容が異なるため、伝え手に求められる知識や経験、資質も異なってくることになるはずです。
おそらく知財関係者に限って「知的財産」の定義を問うと、ほとんどの人は(2)を選択すると思います。
ところが、「知財を活用する」「知財の重要性を伝える」となったとたんに、いつの間にやら(1)の定義を前提にしてしまっている。
そうなると、そこに関心を示すのは「知的財産権」に関する悩み、すなわち模倣品の被害を受けている、あるいは侵害警告を受けているといった問題を抱えている企業に対象が限定され、「知的財産」を意識することによってできることの可能性は限られたものになってしまいます。今は困っていなくても将来そういうことが起こるかもしれませんよ、といった苦し紛れの説明では、企業が今現在抱えているリアルな課題の前では簡単に吹き飛ばされてしまうでしょう。
定義が(2)であるならば、「知財活用」も「知財の重要性」も(2)を前提に考えるべきです。
新分野の開拓を課題としている企業が、特許取得のプロセスを通じて自社のオリジナリティーを客観的に見える化して、新たな用途を探っていくのも「知財活用」です。生産性の向上を課題としている企業が、属人的な優れたノウハウを見える化して他のメンバーと共有し、生産性を高めるのも「知財活用」です。営業力の強化を課題としている企業が、自社のオリジナリティを知的財産権の取得によって客観的に裏付けて、営業部隊の支援材料に使っていくのも「知財活用」です。こうした効果を引っくるめて、自社の商品やサービスにおいて差異化された要素を客観的に抽出することからスタートする知財活動の有用性が、「知財の重要性」ということになるのでしょう。
ここで必要なことは、関係者間でのコンセンサスが得られているということなので、(1)ならば(1)でもよいのですが、(1)で考えられることは当然に(2)にも含まれるので、「知的財産」に対する取組みの可能性をより広げていくためには(2)で捉えるほうがよいことは明らかです。前述のアンケート調査からも、(2)で捉えるようがよいことを示す興味深い傾向が表れているのですが、いずれそのこともお伝えてしていければと考えています。
(1)「特許権などの知的財産権」と狭く捉えるのか、
(2)「企業活動から生み出された他と差異化された技術・ブランドなどの無形資産」と広く捉えるのか、
そもそもの対象の定義にコンセンサスを得られていないことが多いためです。
これまでセミナーの参加者に(1)か(2)かを尋ねた経験からは、平均するとおおよそ半々くらいに分かれている印象です。
現在関わっているある事業で行った中小企業を対象にしたアンケート調査では、さらに(1)と(2)の中間(知的財産権+ノウハウとして保護される財産)も加えて尋ねたところ、回答は概ね1/3ずつにきれいに分かれてしまっているような状況です。
「知的財産」をどちらの意味で捉えているかということによる影響はいろいろなところに現れてきて、例えば「知財活用」について議論しようとすると、
(1)であれば、「知的財産権をどう活用するか」という問題意識から、権利侵害への対応やライセンスといった話になりやすく、
(2)であれば、「差異化された要素をどう事業に活かすか」という問題意識から、事業戦略と密接に結びついた話になりやすい、
という違いが生じます。このようにコンセンサスを得られていない状態で、安易に「知財活用」という言葉を使うのはなんだか気持ち悪いものがあります。自分としては(2)の前提で話そうとしているのに、まだまだ(1)のように捉える人が多い中で「知財活用」の言葉を使ったが故に、「うちは特許権をもっていないから関係ないよ」、「そんなことは専門家や担当者マターでしょう」、と経営者に「知財活用」の話題を敬遠されることにつながってしまいやすいためです。
また、「知財の重要性を伝える」といった場合にも、
(1)であれば、模倣被害にあったり、侵害警告を受けたりすると大変なことになります、だから重要です、
(2)であれば、自社にしかない強みを明確に認識して、それを活かすことが競争力の強化につながります、だから重要です、
となり、これも相当伝えるべき内容が異なるため、伝え手に求められる知識や経験、資質も異なってくることになるはずです。
おそらく知財関係者に限って「知的財産」の定義を問うと、ほとんどの人は(2)を選択すると思います。
ところが、「知財を活用する」「知財の重要性を伝える」となったとたんに、いつの間にやら(1)の定義を前提にしてしまっている。
そうなると、そこに関心を示すのは「知的財産権」に関する悩み、すなわち模倣品の被害を受けている、あるいは侵害警告を受けているといった問題を抱えている企業に対象が限定され、「知的財産」を意識することによってできることの可能性は限られたものになってしまいます。今は困っていなくても将来そういうことが起こるかもしれませんよ、といった苦し紛れの説明では、企業が今現在抱えているリアルな課題の前では簡単に吹き飛ばされてしまうでしょう。
定義が(2)であるならば、「知財活用」も「知財の重要性」も(2)を前提に考えるべきです。
新分野の開拓を課題としている企業が、特許取得のプロセスを通じて自社のオリジナリティーを客観的に見える化して、新たな用途を探っていくのも「知財活用」です。生産性の向上を課題としている企業が、属人的な優れたノウハウを見える化して他のメンバーと共有し、生産性を高めるのも「知財活用」です。営業力の強化を課題としている企業が、自社のオリジナリティを知的財産権の取得によって客観的に裏付けて、営業部隊の支援材料に使っていくのも「知財活用」です。こうした効果を引っくるめて、自社の商品やサービスにおいて差異化された要素を客観的に抽出することからスタートする知財活動の有用性が、「知財の重要性」ということになるのでしょう。
ここで必要なことは、関係者間でのコンセンサスが得られているということなので、(1)ならば(1)でもよいのですが、(1)で考えられることは当然に(2)にも含まれるので、「知的財産」に対する取組みの可能性をより広げていくためには(2)で捉えるほうがよいことは明らかです。前述のアンケート調査からも、(2)で捉えるようがよいことを示す興味深い傾向が表れているのですが、いずれそのこともお伝えてしていければと考えています。