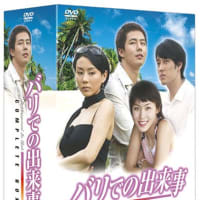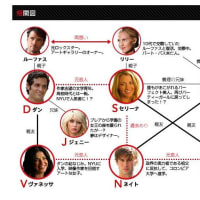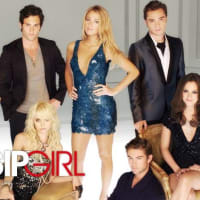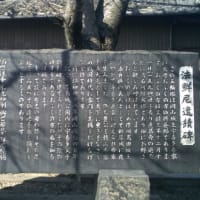コメントに「支那は蔑称だから使うな」という助言があったが、小生は蔑称ではなく、敵対の意味を少し込めて使ったのであった。
日支事変、東シナ海、支那そば、シナチク、「支那の夜」、「支那扇の女」などで「支那」が使われる。日支事変は今は日華事変となり、東シナ海とシナチクは今も使われ、支那そばは中華ソバかラーメンになった。「支那の夜」は戦前に渡辺はま子という歌手が歌ってヒットしたが、抗議があって今は歌われないそうだ。「支那扇の女」は横溝正史の短篇で今も読むことができる。
なぜ、支那が蔑称だとみなされたのか。戦前、日本在住の華僑が「このシナ人め」と罵倒される時に言われたからであろう。「この朝鮮人め」、「この台湾人め」などと同様である。
本来、支那というのは中国の通称であり、日本で普通に使われていた。中国は政権が替わるごとに国名が変わったので通称が必要であったのであろうことは推測できる。
この支那の語源は、西欧でチャイナと呼ばれていたことからきていると思っていた。ローマ帝国が秦(しん)という帝国を発音したものがもとになっているのだと。しかし、検索してみれば、「大辞林」に【中国語の「秦」が梵語(サンスクリット語、インドの言葉)に入り、その言葉が仏典によって中国に逆輸入された時、中国人自身が「支那」と音をあてたのである】と書かれている。中国人が初めて「支那」と書いたようだ。だから、日本での「支那」の語源は後者だろうか。
中国という国名は中華人民共和国の略称である。この中華の意味は広辞苑によると【中国で、漢民族が、周囲の文化的におくれた各民族(東夷トウイ・西戎セイジユウ・南蛮ナンバン・北狄ホクテキと呼ぶ)に対して、自らを世界の中央に位置する文化国家であるという意識をもって呼んだ自称】となっている。東夷に日本は含まれている。こちらから中国と呼ぶと逆蔑称になるかもしれない。
日本の国名の語源だって聖徳太子の隋への国書の「日出づる処の天子、日没する処の天子へ・・・」から来ているともいわれているので攻められないが。国名というのは、他国に対して付けられるので、多かれ少なかれ、そういう意味が含まれることは許容されるべきか。
数年前、中国でSina.comというヤフーのようなポータルサイトが立ち上がって、日本にいる華僑が抗議したそうだ。それに対して【Sina.com側は,この名前は「China」と「Sino」を合体したもので中国の蔑称ではなく尊称であると主張している。シナは英語のチャイナの過去の発音。中国の英語名を変える必要がありますか。シナに侮辱の意味が込められているというなら、自身の国家を強大にすればいいだけの話。シナを世界のブランドにし、中国人が誇れる呼び名にすると批判を一蹴】したそうだ。
そういう状況だから、蔑称の意味でないなら使ってもいいだろう。
今は「朝鮮人」も「台湾人」も蔑称でないはずである。どうせ、一党独裁政権が替わると国名も替わるのではないか。長期歴史的に見て通称「支那」でいいではないか。
日支事変、東シナ海、支那そば、シナチク、「支那の夜」、「支那扇の女」などで「支那」が使われる。日支事変は今は日華事変となり、東シナ海とシナチクは今も使われ、支那そばは中華ソバかラーメンになった。「支那の夜」は戦前に渡辺はま子という歌手が歌ってヒットしたが、抗議があって今は歌われないそうだ。「支那扇の女」は横溝正史の短篇で今も読むことができる。
なぜ、支那が蔑称だとみなされたのか。戦前、日本在住の華僑が「このシナ人め」と罵倒される時に言われたからであろう。「この朝鮮人め」、「この台湾人め」などと同様である。
本来、支那というのは中国の通称であり、日本で普通に使われていた。中国は政権が替わるごとに国名が変わったので通称が必要であったのであろうことは推測できる。
この支那の語源は、西欧でチャイナと呼ばれていたことからきていると思っていた。ローマ帝国が秦(しん)という帝国を発音したものがもとになっているのだと。しかし、検索してみれば、「大辞林」に【中国語の「秦」が梵語(サンスクリット語、インドの言葉)に入り、その言葉が仏典によって中国に逆輸入された時、中国人自身が「支那」と音をあてたのである】と書かれている。中国人が初めて「支那」と書いたようだ。だから、日本での「支那」の語源は後者だろうか。
中国という国名は中華人民共和国の略称である。この中華の意味は広辞苑によると【中国で、漢民族が、周囲の文化的におくれた各民族(東夷トウイ・西戎セイジユウ・南蛮ナンバン・北狄ホクテキと呼ぶ)に対して、自らを世界の中央に位置する文化国家であるという意識をもって呼んだ自称】となっている。東夷に日本は含まれている。こちらから中国と呼ぶと逆蔑称になるかもしれない。
日本の国名の語源だって聖徳太子の隋への国書の「日出づる処の天子、日没する処の天子へ・・・」から来ているともいわれているので攻められないが。国名というのは、他国に対して付けられるので、多かれ少なかれ、そういう意味が含まれることは許容されるべきか。
数年前、中国でSina.comというヤフーのようなポータルサイトが立ち上がって、日本にいる華僑が抗議したそうだ。それに対して【Sina.com側は,この名前は「China」と「Sino」を合体したもので中国の蔑称ではなく尊称であると主張している。シナは英語のチャイナの過去の発音。中国の英語名を変える必要がありますか。シナに侮辱の意味が込められているというなら、自身の国家を強大にすればいいだけの話。シナを世界のブランドにし、中国人が誇れる呼び名にすると批判を一蹴】したそうだ。
そういう状況だから、蔑称の意味でないなら使ってもいいだろう。
今は「朝鮮人」も「台湾人」も蔑称でないはずである。どうせ、一党独裁政権が替わると国名も替わるのではないか。長期歴史的に見て通称「支那」でいいではないか。