(前回の記事はこちら)
私は、「4島返還論は米国の圧力の産物か?」で、もう一点、オコジョさんの表現に疑問を呈しました。
それに対するオコジョさんの「日米関係と「北方領土」問題――再び「ダレスの恫喝」での返答はこうです。
緒方が当時吉田派のボスであったこと、そしてCIAとつながっていたことは事実です。
だからといって、どうして吉田派が「米国の意思を体現していた」と言えるのでしょうか。
「体現」とは、「思想・観念などを具体的な形であらわすこと。身をもって実現すること」(デジタル大辞泉)です。
「米国の意思を体現していた」とは、米国のエージェント、悪く言えば米国の走狗であることを意味します。
彼ら吉田派は、単にそのような存在にすぎなかったのでしょうか。自らの意思は存在しなかったのでしょうか。
私が疑問に思うのは オコジョさんが彼らの主体性というものをまるで考慮しようとしないことです。
彼ら自身としては4島返還でも2島返還でも、あるいは交渉決裂による0島返還でも何でもよかった、ただ米国に言われるがままに、自民党内における2島返還への抵抗勢力として機能した、と考えておられるようです。
なるほど吉田は米国と密接な関係にあり、また外務省にも根を下ろしていました。緒方はCIAの協力者であり、資金提供を受けていました。
ならば彼らの行動は全て「体現」と見るべきなのでしょうか。彼ら自身の意志はなかったのでしょうか。
彼らは彼らで、米国の意思をはじめとするさまざまな要素を考慮した上で、そのように行動したのではないのでしょうか。
また、○○が××から資金提供を受けていた、あるいは××と密接な関係にあった、よって○○は××の意思を体現していたというストレートな表現が許されるのなら、何だって言えてしまうのではないでしょうか。
日本社会党や日本共産党がソ連の資金提供を受けていたことがソ連崩壊後に明らかになった。したがって、両党はわが国においてソ連の意思を体現していた。
いわゆる南京大虐殺を報じた記者ティンパーリは中国国民党から資金援助を受けていた。あるいは国民党の工作員であった。したがって、彼の報道は国民党の意思を体現したものであり、信用に値しない。
ハル・ノートを起草したハリー・デクスター・ホワイトはコミンテルンのスパイであった。したがって、ハル・ノートは米国を第二次世界大戦に巻き込もうとするコミンテルンの意思を体現したものであった。
菅直人の資金管理団体が、北朝鮮による日本人拉致事件の容疑者の長男が所属する政治団体から派生した政治団体に献金していた。したがって、菅は北朝鮮の意思を体現していた。
私はこんなことは到底言えないと思いますし、言うべきでないとも思います。
そうした思いから「何故言えるのでしょうか。」と書いたのですが、オコジョさんには理解していただけなかったようです。
とのことですが、曖昧なことは曖昧にしか言いようがないというのが私の考えです。
推測を事実であるかのように語るのは、私の趣味ではありません。
ボールの例えもいただきました。
確かに、おっしゃるとおりなら、「『このボールは青い』とは書いていない」と主張することは無意味でしょう。
しかし、この例えに倣って言うなら、私は「このボールの色は赤か青である」「このボールは赤くはない」という2つの前提が成立するのかどうかに疑問を呈しているのです。
その判断が妥当かどうかは、読者に委ねたいと思います。
オコジョさんは、続く記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」の冒頭で、「オッカムの刃」の話を持ち出されています。
私は、ウィリアム・オッカムの名は知っていましたが、この「オッカムの刃」については知りませんでした。
しかし、歴史を見る際にこうした考え方を適用してしまうと、いわゆる陰謀論との親和性を高めてしまうのではないでしょうか。
私には「採用するべき」とは思えません。
例えば、わが国は何故第二次世界大戦に敗れ降伏したのか、それはコミンテルンに籠絡された蒋介石によって泥沼の日中戦争に引きずり込まれ、続いてコミンテルンのスパイが起案したハル・ノートによって対米英蘭戦を余儀なくされたからだ、全てはコミンテルンの陰謀である――といった見方があります。
また、何故わが国は原爆が2発も落とされるまで降伏しなかったのか、それは米国が原爆を実験したかったがために、わざとポツダム宣言の内容を即時受諾困難なものとしたのだ――といった見方があります。
どちらも、当時の情勢におけるさまざまな要素を考慮に入れるよりは、「素直な考え方、単純な理論」です。
だからといって、こうした見方が妥当だとはとても思えません。
オコジョさんのブログで、一連の北方領土関係のものではありませんが、こんな趣旨の記述もあったように記憶しています。
〈私は嘘はつきませんが、ハッタリは使います。相手の出方を見てみたいからです〉。
オコジョさんが、直截な物言いを好まれる方だということはわかりました。
私はオコジョさんの記事を読むのは最初にトラックバックをいただいた
「ダレスの恫喝」について――「北方領土問題」をめぐって
が初めてでしたので、私の感覚に基づいてオコジョさんの表現に対していくつか申し上げましたが、これからは「そういう方」だということを前提にして読むようにします。
しかし、そういう方と「議論」が成立するのか疑問です。何故なら、その方の発言の全てにわたって、これは事実なのか、それともハッタリなのかといちいち検証するのは容易なことではありませんし、それでは結局のところ「言ったもん勝ち」になりかねないと思えるからです。
(続く)
私は、「4島返還論は米国の圧力の産物か?」で、もう一点、オコジョさんの表現に疑問を呈しました。
しかし、「吉田派が、米国の意思を体現していた」などと何故言えるのでしょうか。
それに対するオコジョさんの「日米関係と「北方領土」問題――再び「ダレスの恫喝」での返答はこうです。
これは、蓋然性が非常に高い妥当な推測、ほぼ事実というところでしょうか。
分かりやすい例を書くと、緒方竹虎がCIAとつながっており、資金提供も受けていたのは証明ずみの「歴史的事実」です。コードネーム「POCAPON」も知られています(ふざけたネームみたいですが、正力松太郎の「PODAM」は既によく知られていますね。「PO」の部分が日本を意味するのだとか)。
緒方が当時吉田派のボスであったこと、そしてCIAとつながっていたことは事実です。
だからといって、どうして吉田派が「米国の意思を体現していた」と言えるのでしょうか。
「体現」とは、「思想・観念などを具体的な形であらわすこと。身をもって実現すること」(デジタル大辞泉)です。
「米国の意思を体現していた」とは、米国のエージェント、悪く言えば米国の走狗であることを意味します。
彼ら吉田派は、単にそのような存在にすぎなかったのでしょうか。自らの意思は存在しなかったのでしょうか。
私が疑問に思うのは オコジョさんが彼らの主体性というものをまるで考慮しようとしないことです。
彼ら自身としては4島返還でも2島返還でも、あるいは交渉決裂による0島返還でも何でもよかった、ただ米国に言われるがままに、自民党内における2島返還への抵抗勢力として機能した、と考えておられるようです。
なるほど吉田は米国と密接な関係にあり、また外務省にも根を下ろしていました。緒方はCIAの協力者であり、資金提供を受けていました。
ならば彼らの行動は全て「体現」と見るべきなのでしょうか。彼ら自身の意志はなかったのでしょうか。
彼らは彼らで、米国の意思をはじめとするさまざまな要素を考慮した上で、そのように行動したのではないのでしょうか。
また、○○が××から資金提供を受けていた、あるいは××と密接な関係にあった、よって○○は××の意思を体現していたというストレートな表現が許されるのなら、何だって言えてしまうのではないでしょうか。
日本社会党や日本共産党がソ連の資金提供を受けていたことがソ連崩壊後に明らかになった。したがって、両党はわが国においてソ連の意思を体現していた。
いわゆる南京大虐殺を報じた記者ティンパーリは中国国民党から資金援助を受けていた。あるいは国民党の工作員であった。したがって、彼の報道は国民党の意思を体現したものであり、信用に値しない。
ハル・ノートを起草したハリー・デクスター・ホワイトはコミンテルンのスパイであった。したがって、ハル・ノートは米国を第二次世界大戦に巻き込もうとするコミンテルンの意思を体現したものであった。
菅直人の資金管理団体が、北朝鮮による日本人拉致事件の容疑者の長男が所属する政治団体から派生した政治団体に献金していた。したがって、菅は北朝鮮の意思を体現していた。
私はこんなことは到底言えないと思いますし、言うべきでないとも思います。
そうした思いから「何故言えるのでしょうか。」と書いたのですが、オコジョさんには理解していただけなかったようです。
深沢さんが何を目的に、そう何もかもを曖昧にしてしまいたがるのか私には理解できません。やはり、米国をよき友人と信じたい心情がすべてに優先しているのでしょうか。
とのことですが、曖昧なことは曖昧にしか言いようがないというのが私の考えです。
推測を事実であるかのように語るのは、私の趣味ではありません。
ボールの例えもいただきました。
深沢さんの議論のあまりのナイーブさに少々びっくりしてしまいます。
たとえるなら、こんな感じでしょうか。
○ここに一つのボールがある。
○このボールの色は赤か青である。
○このボールは赤くはない。
こんな三つの言明があったとして、深沢さんは「どこにも『このボールは青い』とは書いていない」と主張しているのです。
それは、たしかに書いてはいません。だからといって、ボールが青いことを否定するのは無茶苦茶な議論です。
極端な喩えを持ち出しましたが、深沢さんの行論はこれと五十歩百歩です。議論の性質というものをもう一度しっかりと確認していただきたいと私は思います。
確かに、おっしゃるとおりなら、「『このボールは青い』とは書いていない」と主張することは無意味でしょう。
しかし、この例えに倣って言うなら、私は「このボールの色は赤か青である」「このボールは赤くはない」という2つの前提が成立するのかどうかに疑問を呈しているのです。
その判断が妥当かどうかは、読者に委ねたいと思います。
オコジョさんは、続く記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」の冒頭で、「オッカムの刃」の話を持ち出されています。
思考経済の法則ともいわれています。一つのことを説明するのに、10の前提を必要とする理論と、3の前提だけで説明できる理論とがあった場合、後者を採用すべきだという考え方です。
日常的な言葉でいうなら、素直な考え方、単純な理論の方が、ややこしいものよりは正しい可能性が高い、とでもなりましょうか。
歴史的事実が、必ずしも単純であるかどうかは何とも言えません。しかし、歴史的事実を解釈するときには、やはりこの「オッカムの刃」を採用するべきでしょう。
私は、ウィリアム・オッカムの名は知っていましたが、この「オッカムの刃」については知りませんでした。
しかし、歴史を見る際にこうした考え方を適用してしまうと、いわゆる陰謀論との親和性を高めてしまうのではないでしょうか。
私には「採用するべき」とは思えません。
例えば、わが国は何故第二次世界大戦に敗れ降伏したのか、それはコミンテルンに籠絡された蒋介石によって泥沼の日中戦争に引きずり込まれ、続いてコミンテルンのスパイが起案したハル・ノートによって対米英蘭戦を余儀なくされたからだ、全てはコミンテルンの陰謀である――といった見方があります。
また、何故わが国は原爆が2発も落とされるまで降伏しなかったのか、それは米国が原爆を実験したかったがために、わざとポツダム宣言の内容を即時受諾困難なものとしたのだ――といった見方があります。
どちらも、当時の情勢におけるさまざまな要素を考慮に入れるよりは、「素直な考え方、単純な理論」です。
だからといって、こうした見方が妥当だとはとても思えません。
オコジョさんのブログで、一連の北方領土関係のものではありませんが、こんな趣旨の記述もあったように記憶しています。
〈私は嘘はつきませんが、ハッタリは使います。相手の出方を見てみたいからです〉。
オコジョさんが、直截な物言いを好まれる方だということはわかりました。
私はオコジョさんの記事を読むのは最初にトラックバックをいただいた
「ダレスの恫喝」について――「北方領土問題」をめぐって
が初めてでしたので、私の感覚に基づいてオコジョさんの表現に対していくつか申し上げましたが、これからは「そういう方」だということを前提にして読むようにします。
しかし、そういう方と「議論」が成立するのか疑問です。何故なら、その方の発言の全てにわたって、これは事実なのか、それともハッタリなのかといちいち検証するのは容易なことではありませんし、それでは結局のところ「言ったもん勝ち」になりかねないと思えるからです。
(続く)










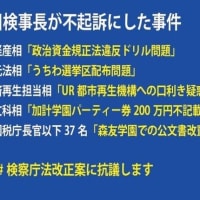

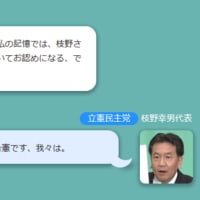
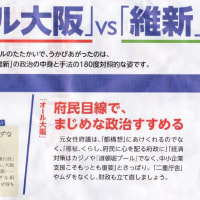


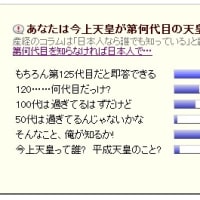
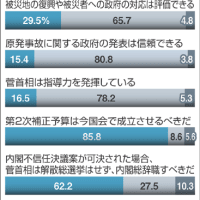

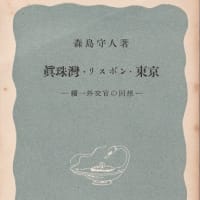
>私は、ウィリアム・オッカムの名は知っていましたが、この「オッカムの刃」については知りませんでした。
ここを見て、へぇ~~と思いました。
僕は「オッカムの剃刀」という言葉は知ってましたが、オッカムって何をした人なのか知りませんでした。
ところで、
>一つのことを説明するのに、10の前提を必要とする理論と、3の前提だけで説明できる理論とがあった場合、後者を採用すべきだという考え方です。
この説明の仕方って、あってるのかな?
「オッカムの剃刀」でそぎ落とすべきはあくまで「必要ない前提」であって、「必要な前提」はそぎ落としてはいけないはずですが。
つまり、10の前提が必要なら、10のままにしておくのが「オッカムの剃刀」だと思ってたんですが。
あと、あくまでこれは「思考方法」であって、真偽を判定するための基準ではないということにも注意が必要ですね。
確か、「わかりやすい説明が正しいとは限らない」って名言もあったはずですけどね。
私も「何をした人なのか」はよく知りません。
高校生の時に、世界史に強い関心があったので、用語集に出ていたのを覚えたのだと思います。
中世英国のスコラ哲学者で、実在論と対立する唯名論に立ったとか何とか。
用語の意味はもはやさっぱりですが。
「オッカムの剃刀」で検索したら、kotobankでは「法則の辞典」の解説として「科学的単純性の原則 参照」と出ます。
そちらを参照すると、
科学的単純性の原則 【principle of scientific simplicity】
別名をオッカムの剃刀という.むしろこちらのほうが通用範囲が広い.倹約の法則ともいう.14世紀のイングランドの哲学者オッカム(W. Occam)が述べた「あることを説明するために導入する仮説は,必要以上に複雑なものであってはならない」という原則.
とあります。
「必要以上に」とありますから、TOMさんのおっしゃるとおりなんでしょうか。