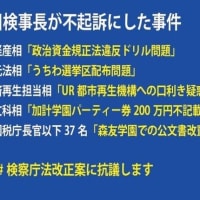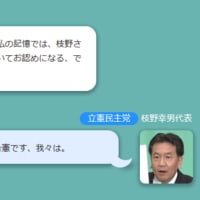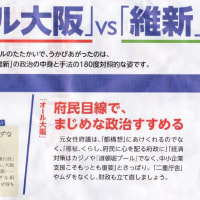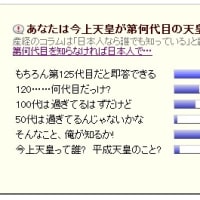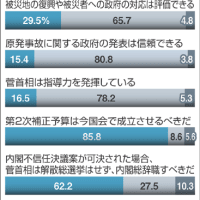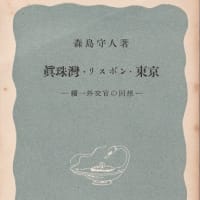(前回の記事はこちら)
前回と前々回で、議論の本筋である「米国の意思」に関わるオコジョさんの二つの表現――私が疑問を呈し、オコジョさんが説明された点――について述べました。
今回は、「米国の意思」それ自体をどう見るかという、より本質的な点について述べます。
オコジョさんは、2島返還論から4島返還論への転換は
「単純に日本の意思だけに帰すことはできません」
「米国からの圧力がなかったわけではなく、」
と述べておられますが、私は、単純に日本の意思だけに帰するとは言っていませんし、米国からの圧力がなかったとも言っていません。
オコジョさんも引用しているように、米国からの申し入れがあったことは松本も書いており、私も認識しています。
しかし、そうした米国からの圧力があったがために、わが国は2島返還論から4島返還論に転じたと言えるのかという疑問が、ご批判いただいた私の記事
4島返還論は米国の圧力の産物か?
の主旨です(タイトルもそれを示しています)。
したがって、オコジョさんがこの記事を批判するのであれば、転換が米国からの圧力によるものだったことを、具体的に立証すれば済むことです。
ところが、オコジョさんの記事にこの点についての具体的な話は出てきません。
オコジョさんが述べる根拠らしきものは、次のような話です。
1.重光外相は国交回復交渉に非常に消極的であった
2.吉田茂はより強硬に国交回復に否定的であった
3.吉田派の緒方竹虎はCIAとつながっており、資金提供も受けていた
4.「外務省は吉田派の巣窟のようなもの」だから、マリクが歯舞・色丹の返還を示唆したことは「吉田の耳に間違いなく入っていたはずです」、吉田を通じて「米国にも情報が届いたのは間違いありません」、米国が「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実で」ある
5.鳩山を蚊帳の外に置いて、重光ら外務省は2島返還での妥結には応じない方針を固め、鳩山に事後承諾させた
6.そんな経緯のあと、外務省は松本に4島返還の新訓令を打電した。つまり「わざわざ新たな障碍をつくった」
7.ダレスの言動にとどまらず「もっと広く深く日本の内部にまで浸透していた意思があった」
これらが仮に事実だとしても、それでどうして米国からの圧力によってわが国が2島返還論から4島返還論に転じたと言えるのか、わかりません。
圧力はいつ、どのようにして行使されたのでしょうか。
それは、当時の外交文書が全て公開されているわけではない以上、確証を示すことは不可能だ。しかし、当時の情勢や現在でも公開されている外交文書その他の資料を検討し、「オッカムの刃」をもってすれば、そう見るのが妥当である。
オコジョさんは、このようにおっしゃるかもしれません。
しかし私には、それが妥当だとは思えません。
(念のために申し上げておきますが、私は、米国からの圧力によってわが国が2島返還論から4島返還論に転じたなどということは有り得ない、と言っているのではありません。そうした説が成り立ち得ることは否定しません。現時点では、そのように断定できる状態ではないのではないかと言っているのです)
オコジョさんが典拠としているらしい和田春樹氏の『北方領土問題』を読んでみました。
和田氏は、同書のp.230~249において、米国の外交文書も用いて、マリクが歯舞・色丹の返還を示唆した前後のわが国と米国の動きを仔細に検討しています。これを私なりに要約すると、次のようになります。
・1955年1月、ドムニツキー書簡が鳩山邸に届けられ、日ソ国交回復交渉が始動。米国は当初、歯舞、色丹がサンフランシスコ平和条約で放棄した千島列島の一部ではなく日本の領土であるという日本の主張を支持していた。
・同年2月、日本外務省は米国に対し、国交回復交渉に当たって千島列島の返還要求を出すので、米国がこれを支持するよう要請。受け入れ可能な最低条件は、ソ連が日本の千島列島領有の主張に希望を残しながら、歯舞、色丹を返還することだとも述べる。
・同年3月、国家安全保障会議でアレン・ダレスCIA長官が、日本政府高官は「歯舞、色丹と同様にクリル諸島のすくなくとも二つの島の返還を望むと告白した」と報告。
・4月、米国は、千島列島に対する日本の要求を米国が支持することについて、法律的には難しいが、政治的には認めるべきであり、最低その要求に反対しないとの方針を固め、日本に伝える。
・5月、歯舞、色丹の返還を最低条件とした「訓令第一六号」が閣議決定され、2日後に自由党と両社会党に説明される。
・6月、第1次ロンドン交渉開始。アリソン米駐日大使は、鳩山政権では対ソ妥結論が支配的であり、ソ連が日米関係を悪化させることを狙って譲歩をしてくることに対して日本は無防備であるとし、歯舞、色丹、さらにもしかしたら南千島までの日本の潜在主権への同意、日本の国連加入、日本の再軍備に関する寛大な制限などの譲歩をしてくる可能性があるとワシントンに報告。
・8月、マリク、松本に歯舞、色丹の引き渡しを示唆。松本電を受けた重光は秘匿を命じて墓参に発ち、帰京後アリソンと会い、外務省の幹部会で4島返還を求める新方針を決定。ソ連の譲歩が報じられていない段階で新方針を新聞にリークし、わが国が南樺太、全千島から4島に要求を切り下げたとの印象を作りだした上で、訪米し、鳩山の事後承諾を得る。
注目すべきは、2月の段階で日本外務省が千島列島の返還をソ連に要求することを米国に明らかにしていること、3月のダレス報告はそれが少なくとも2島、すなわち択捉、国後であることを想起させること、そして4月には米国がその要求に反対しないとの方針を既に固めていることです。
つまり、4島返還論は、オコジョさんが記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」で「講釈」されたように、歯舞、色丹の引き渡しというソ連の譲歩を受けて突如持ち出されたものではなく、あらかじめ検討されていたものだということです。
それでは「訓令第一六号」との整合性がとれなくなりますが、それがどういう事情によるものかはまだわかりません。外務省としては4島返還論を検討していたが、民主党が2島返還を最低ラインに引き下げたといったことも考えられるでしょう。また、後述しますが、「訓令第一六号」はわが国の最終的な方針ではありませんでした。
そして、ソ連の譲歩を受けて、吉田派や米国がどう動いたのかも定かではありません。
たしかに、和田氏は『北方領土問題』p.243で、外務省内吉田派が吉田にこの重大ニュースを伝えなかっただろうか、伝えたとすれば吉田からダレスないしアリソンに極秘の連絡が行っただろう、鳩山がこの内容で妥結することは全力を挙げて阻止しなければならないとして秘かな協議があったと考えることもできる、と述べています。
しかしこれらは全て和田氏の推測であり、具体的な根拠は何も示されていません。
ここで和田氏はこんなことを書いています。
しかし、それまでに和田氏が挙げている米国の文書には、「進ませるという既定の方針」に当たるものは見当たりません。
米国が日本の千島列島の要求に反対しないという方針はあります。また、ソ連の譲歩により米国の立場が損なわれることを懸念する報告もあります。しかし、日ソ国交回復阻止のために日本が南千島を要求するように進ませるとの方針をとっていたととれる記述はありません。
この点をはじめ、和田氏の文章には、米国がわが国を4島返還に進ませたと印象づけようとするいくつかの仕掛けがあります。しかし、その仕掛けを取り除いて、和田氏が呈示する根拠を検討してみると、私には必ずしもそのようには読み取れません。
余談ですが、和田氏の前掲書を検討していて、オコジョさんの「米国の意思と「北方領土問題」――「訓令第一六号」など」の記述
に、次のような疑問が湧きました。
ア.「外務省は吉田派の巣窟のようなもの」だから「以上の動きはすべて吉田の耳に間違いなく入っていたはずです。」と何故言い得るのか。そもそも外務省が下野後の吉田に重要事項を逐一報告していたという実例があるのか。また、私の「はずです」を「単にご自分の希望を述べているだけ」と一蹴したが、この「はずです」こそそうではないのか。
イ.仮に「米国が」「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実」であるとしても、それだけでは「吉田を通じて」「米国にも情報が届いたのは間違いありません」とする根拠とはならない。「吉田を通じて」「米国にも情報が届いたのは間違いありません」と見る根拠は何か。下野後の吉田が重要情報を米国に提供していたという実例があるのか。
ウ.「米国が」「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実」と言う根拠は何か。「間もなく」とはいつの時点か。和田氏の前掲書は、田中孝彦氏が発掘した、米国務省のブファイラーが8月22日付けで作成した文書を取り上げている。これは日本外務省の新方針を反映したものではあるが、ソ連の2島引き渡しの申し出は反映されていないという。重光は23日から訪米しているので、それ以降に米国が2島引き渡しの情報を入手しているのは当然だが、それより前に入手しているという「歴史的事実」はあるのか。
さて、4島返還論への転換が米国の圧力の産物なのであれば、重光が松本電を受けてから新方針を決定するまでに米国から何らかの働きかけがあったということになりますが、この点も和田氏の『北方領土問題』からは定かではありません。
重光は16日に東京に戻り、17日にアリソンと会っています。
「アリソンがソ連の譲歩をすでに知っていれば、重光に南千島返還案について何らかの示唆を行った可能性がある」と和田氏は言います。なるほどそうでしょう。しかし、知っていても行わなかった可能性もあります。さらに、譲歩を知らなかった可能性もあります。これもまた、仕掛けの一つです。
和田氏によると、公開された米国務省の資料の中には、8月中のアリソン大使の本国への報告が一本もないそうです。「これはすべて隠されているということである」と和田氏は言います。
他方、ロンドンの駐英大使館からの国務長官宛の8月17日、24日、31日の電報が機密不解除であることを示す記録がファイルの中に残されているそうです。「このような資料公開の状況はソ連譲歩の決定的なニュースをめぐって深刻な文書の往来があったことをうかがわせる」と和田氏は言います。
和田氏の言うとおりだとすると、隠されている部分の内容は、隠されていない部分から推測するしかありません。そこでもっともらしい内容を推測することは可能でしょうが、推測は所詮推測でしかありません。推測を事実と取り違えてはなりません。
重光については、有馬哲夫氏の『CIAと戦後日本』(平凡社新書、2010)第二章「重光葵はなぜ日ソ交渉で失脚したのか」が、CIAの報告書などを用いて戦後の重光の軌跡を概観しているので、興味をもって読んでみましたが、この2島返還論から4島返還論への転換についての言及はありません。
もっとも、和田氏と有馬氏だけが研究者ではありませんし、『北方領土問題』は1999年の著作です。その後新資料が公開されたり発掘されるなどして、研究が進んで、和田氏の推測が裏付けられているといった事情がもしあるのでしたら、是非ご教示願いたいと思います。
ところが、オコジョさんは、記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」で、突然こんなことを言い始めます。
「米国の意思に従った」と「米国の意思を顧慮した」では意味が異なります。
「顧慮」とは「ある事をしっかり考えに入れて、心をくばること。「相手の立場を―する」」(デジタル大辞泉)です。
オコジョさんがこう言い出したのは、米国だけではなくわが国においても4島返還論が検討されていたことに気付いたか、わが国の行動のどこまでが米国の圧力によるもので、どこまでがわが国の主体的な意思によるものかを説明することなど、極めて困難だということに気付いたからではないかと思われます。
「自主的な意思による」とは、米国の意思にかかわらず、わが国独自の判断によるものだという意味でしょうか。
さらに、オコジョさんが後に拙記事「4島返還論は米国の圧力の産物か?」に寄せられたコメントでは、こんなことをおっしゃっています。
私は同じ記事の本文で、次のように述べています。
これを、米国の意思とわが国の意思は無関係であるという「信念」の表明と読み取られるのであれば、私はオコジョさんの読解力に不審の念を抱かざるを得ません。
この箇所は、米国の意思があったからといって、わが国がそれだけの理由で方針を転換したとは言えない、わが国はわが国で、米国の意思を考慮し、その他さまざまな要素も考慮した上で、4島返還論に転換したのではないかという意味です。
したがって、オコジョさんが「顧慮」と言い換えるのであれば、私にも異論はありません。
「棚上げ」も何も、オコジョさんと私の認識は一致しているのですから。
あとは、表現方法の問題です。
これについては、前回申し上げたように、私はオコジョさんが独特の表現方法をお好みの方だと理解しましたので、もはや特に述べることはありません。今後は、オコジョさんが「そういう方」だという認識の下に記事を読むことにします。
これで、本筋についての私の話は終わりです。
あとは オコジョさんが北方領土問題について、及びそれに関連して示されたいくつかの見解について、私の考えを述べておきます。
まずは「日米関係と「北方領土」問題――再び「ダレスの恫喝」」の末尾で述べておられた、日ソ交渉を米国に相談していたという点と、重光の後の戦後の外務大臣に外務省出身者がいないという点について。
日ソの交渉の機微を第三国に知らせることなど本来あり得ないというのは、通常の外交関係においては、おそらくはおっしゃるとおりなのでしょう。
しかし、当時の日米関係が、通常の外交関係とは異なるものであったことも考慮すべきでしょう。
米国の占領下に置かれ、米国によって新憲法をはじめとする諸改革を断行され、米国の支持の下で独立を果たし、わが国は米国に基地を提供する義務を負うが米国はわが国を防衛する義務を負わないという片務的な旧安保体制の下にありました。ソ連の反対により国連にも加盟することもできず、韓国とも中共とも国交はありませんでした。
端的に言えば、わが国は米国の庇護下にあったと言えるでしょう。
そしてまた、日ソ国交回復交渉が通常の外交ではなかったことも考慮すべきでしょう。
ソ連は単に交戦国の1つというだけでなく、共産圏のリーダーであり、当時は冷戦の真っ只中でした。
また、日ソの領土問題がどのような形で解決するかは、米国の極東戦略にも多大な影響を及ぼす要素でした。
だからこそ、吉田に比べて米国と距離があった鳩山の政権においても、日ソ交渉の内実を米国に明らかにせざるをなかったのではないでしょうか。
これは、具体的にどういう外交が有り得たとお考えなのでしょうか。
そして、「有効な取り引き材料」も何も、「ダレスの恫喝」に見られるように、沖縄はむしろ日本側の弱み、日米関係におけるアキレス腱であったのではないのでしょうか。
次に、外務大臣に外務省出身者がいないという点については、たしかにおっしゃるとおりですが、それは、何より外交官から政治家へ転身する者が少ないからではないのでしょうか。
戦前と異なり、戦後は閣僚が国会議員であることが普通となりました。閣僚の中でも外相は花形ポストであり、それなりの有力者でなければ就任は困難です。
有力な国会議員に外務省出身者がほとんどいなければ、外相に外務省出身者がいないという事態も起こり得るでしょう。
私が無知だからかもしれませんが、戦後派の著名な政治家で外務省出身者をほとんど思いつきません。加藤紘一がいますが、彼は2世です。
理由はよくわかりませんが、官僚の中でも外交官は独自の世界を築いており、政党政治の世界には足を踏み入れようとしなかったのかもしれません。
むしろ、芦田均、松岡洋右、広田弘毅、幣原喜重郎、吉田茂、そして重光葵のような外交官出身の有力政治家が続出した戦中・戦後期が異常だったのかもしれません。
そういう見方もあるんですね、としか言いようがありません。
次回は、「四島返還論の出自」を取り上げます。
(続く)
前回と前々回で、議論の本筋である「米国の意思」に関わるオコジョさんの二つの表現――私が疑問を呈し、オコジョさんが説明された点――について述べました。
今回は、「米国の意思」それ自体をどう見るかという、より本質的な点について述べます。
オコジョさんは、2島返還論から4島返還論への転換は
「単純に日本の意思だけに帰すことはできません」
「米国からの圧力がなかったわけではなく、」
と述べておられますが、私は、単純に日本の意思だけに帰するとは言っていませんし、米国からの圧力がなかったとも言っていません。
オコジョさんも引用しているように、米国からの申し入れがあったことは松本も書いており、私も認識しています。
しかし、そうした米国からの圧力があったがために、わが国は2島返還論から4島返還論に転じたと言えるのかという疑問が、ご批判いただいた私の記事
4島返還論は米国の圧力の産物か?
の主旨です(タイトルもそれを示しています)。
したがって、オコジョさんがこの記事を批判するのであれば、転換が米国からの圧力によるものだったことを、具体的に立証すれば済むことです。
ところが、オコジョさんの記事にこの点についての具体的な話は出てきません。
オコジョさんが述べる根拠らしきものは、次のような話です。
1.重光外相は国交回復交渉に非常に消極的であった
2.吉田茂はより強硬に国交回復に否定的であった
3.吉田派の緒方竹虎はCIAとつながっており、資金提供も受けていた
4.「外務省は吉田派の巣窟のようなもの」だから、マリクが歯舞・色丹の返還を示唆したことは「吉田の耳に間違いなく入っていたはずです」、吉田を通じて「米国にも情報が届いたのは間違いありません」、米国が「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実で」ある
5.鳩山を蚊帳の外に置いて、重光ら外務省は2島返還での妥結には応じない方針を固め、鳩山に事後承諾させた
6.そんな経緯のあと、外務省は松本に4島返還の新訓令を打電した。つまり「わざわざ新たな障碍をつくった」
7.ダレスの言動にとどまらず「もっと広く深く日本の内部にまで浸透していた意思があった」
これらが仮に事実だとしても、それでどうして米国からの圧力によってわが国が2島返還論から4島返還論に転じたと言えるのか、わかりません。
圧力はいつ、どのようにして行使されたのでしょうか。
それは、当時の外交文書が全て公開されているわけではない以上、確証を示すことは不可能だ。しかし、当時の情勢や現在でも公開されている外交文書その他の資料を検討し、「オッカムの刃」をもってすれば、そう見るのが妥当である。
オコジョさんは、このようにおっしゃるかもしれません。
しかし私には、それが妥当だとは思えません。
(念のために申し上げておきますが、私は、米国からの圧力によってわが国が2島返還論から4島返還論に転じたなどということは有り得ない、と言っているのではありません。そうした説が成り立ち得ることは否定しません。現時点では、そのように断定できる状態ではないのではないかと言っているのです)
オコジョさんが典拠としているらしい和田春樹氏の『北方領土問題』を読んでみました。
和田氏は、同書のp.230~249において、米国の外交文書も用いて、マリクが歯舞・色丹の返還を示唆した前後のわが国と米国の動きを仔細に検討しています。これを私なりに要約すると、次のようになります。
・1955年1月、ドムニツキー書簡が鳩山邸に届けられ、日ソ国交回復交渉が始動。米国は当初、歯舞、色丹がサンフランシスコ平和条約で放棄した千島列島の一部ではなく日本の領土であるという日本の主張を支持していた。
・同年2月、日本外務省は米国に対し、国交回復交渉に当たって千島列島の返還要求を出すので、米国がこれを支持するよう要請。受け入れ可能な最低条件は、ソ連が日本の千島列島領有の主張に希望を残しながら、歯舞、色丹を返還することだとも述べる。
・同年3月、国家安全保障会議でアレン・ダレスCIA長官が、日本政府高官は「歯舞、色丹と同様にクリル諸島のすくなくとも二つの島の返還を望むと告白した」と報告。
・4月、米国は、千島列島に対する日本の要求を米国が支持することについて、法律的には難しいが、政治的には認めるべきであり、最低その要求に反対しないとの方針を固め、日本に伝える。
・5月、歯舞、色丹の返還を最低条件とした「訓令第一六号」が閣議決定され、2日後に自由党と両社会党に説明される。
・6月、第1次ロンドン交渉開始。アリソン米駐日大使は、鳩山政権では対ソ妥結論が支配的であり、ソ連が日米関係を悪化させることを狙って譲歩をしてくることに対して日本は無防備であるとし、歯舞、色丹、さらにもしかしたら南千島までの日本の潜在主権への同意、日本の国連加入、日本の再軍備に関する寛大な制限などの譲歩をしてくる可能性があるとワシントンに報告。
・8月、マリク、松本に歯舞、色丹の引き渡しを示唆。松本電を受けた重光は秘匿を命じて墓参に発ち、帰京後アリソンと会い、外務省の幹部会で4島返還を求める新方針を決定。ソ連の譲歩が報じられていない段階で新方針を新聞にリークし、わが国が南樺太、全千島から4島に要求を切り下げたとの印象を作りだした上で、訪米し、鳩山の事後承諾を得る。
注目すべきは、2月の段階で日本外務省が千島列島の返還をソ連に要求することを米国に明らかにしていること、3月のダレス報告はそれが少なくとも2島、すなわち択捉、国後であることを想起させること、そして4月には米国がその要求に反対しないとの方針を既に固めていることです。
つまり、4島返還論は、オコジョさんが記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」で「講釈」されたように、歯舞、色丹の引き渡しというソ連の譲歩を受けて突如持ち出されたものではなく、あらかじめ検討されていたものだということです。
それでは「訓令第一六号」との整合性がとれなくなりますが、それがどういう事情によるものかはまだわかりません。外務省としては4島返還論を検討していたが、民主党が2島返還を最低ラインに引き下げたといったことも考えられるでしょう。また、後述しますが、「訓令第一六号」はわが国の最終的な方針ではありませんでした。
そして、ソ連の譲歩を受けて、吉田派や米国がどう動いたのかも定かではありません。
たしかに、和田氏は『北方領土問題』p.243で、外務省内吉田派が吉田にこの重大ニュースを伝えなかっただろうか、伝えたとすれば吉田からダレスないしアリソンに極秘の連絡が行っただろう、鳩山がこの内容で妥結することは全力を挙げて阻止しなければならないとして秘かな協議があったと考えることもできる、と述べています。
しかしこれらは全て和田氏の推測であり、具体的な根拠は何も示されていません。
ここで和田氏はこんなことを書いています。
アリソンとしては、むしろ二島返還どまりで安堵さえしたかもしれない。そして、二島返還を要求するだけでは妥結することになってしまうのだから、クリル諸島の一部、南千島の要求に進ませるという既定の方針が推進されることになったと考えられる。
しかし、それまでに和田氏が挙げている米国の文書には、「進ませるという既定の方針」に当たるものは見当たりません。
米国が日本の千島列島の要求に反対しないという方針はあります。また、ソ連の譲歩により米国の立場が損なわれることを懸念する報告もあります。しかし、日ソ国交回復阻止のために日本が南千島を要求するように進ませるとの方針をとっていたととれる記述はありません。
この点をはじめ、和田氏の文章には、米国がわが国を4島返還に進ませたと印象づけようとするいくつかの仕掛けがあります。しかし、その仕掛けを取り除いて、和田氏が呈示する根拠を検討してみると、私には必ずしもそのようには読み取れません。
余談ですが、和田氏の前掲書を検討していて、オコジョさんの「米国の意思と「北方領土問題」――「訓令第一六号」など」の記述
また、外務省は吉田派の巣窟のようなものですから、以上の動きはすべて吉田の耳に間違いなく入っていたはずです。また、吉田を通じて――重光も報告に行っているのですが――米国にも情報が届いたのは間違いありません。米国が――どういう径路からであろうと――そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実です。
に、次のような疑問が湧きました。
ア.「外務省は吉田派の巣窟のようなもの」だから「以上の動きはすべて吉田の耳に間違いなく入っていたはずです。」と何故言い得るのか。そもそも外務省が下野後の吉田に重要事項を逐一報告していたという実例があるのか。また、私の「はずです」を「単にご自分の希望を述べているだけ」と一蹴したが、この「はずです」こそそうではないのか。
イ.仮に「米国が」「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実」であるとしても、それだけでは「吉田を通じて」「米国にも情報が届いたのは間違いありません」とする根拠とはならない。「吉田を通じて」「米国にも情報が届いたのは間違いありません」と見る根拠は何か。下野後の吉田が重要情報を米国に提供していたという実例があるのか。
ウ.「米国が」「そうした情報を間もなく入手していることは歴史的事実」と言う根拠は何か。「間もなく」とはいつの時点か。和田氏の前掲書は、田中孝彦氏が発掘した、米国務省のブファイラーが8月22日付けで作成した文書を取り上げている。これは日本外務省の新方針を反映したものではあるが、ソ連の2島引き渡しの申し出は反映されていないという。重光は23日から訪米しているので、それ以降に米国が2島引き渡しの情報を入手しているのは当然だが、それより前に入手しているという「歴史的事実」はあるのか。
さて、4島返還論への転換が米国の圧力の産物なのであれば、重光が松本電を受けてから新方針を決定するまでに米国から何らかの働きかけがあったということになりますが、この点も和田氏の『北方領土問題』からは定かではありません。
重光は16日に東京に戻り、17日にアリソンと会っています。
「アリソンがソ連の譲歩をすでに知っていれば、重光に南千島返還案について何らかの示唆を行った可能性がある」と和田氏は言います。なるほどそうでしょう。しかし、知っていても行わなかった可能性もあります。さらに、譲歩を知らなかった可能性もあります。これもまた、仕掛けの一つです。
和田氏によると、公開された米国務省の資料の中には、8月中のアリソン大使の本国への報告が一本もないそうです。「これはすべて隠されているということである」と和田氏は言います。
他方、ロンドンの駐英大使館からの国務長官宛の8月17日、24日、31日の電報が機密不解除であることを示す記録がファイルの中に残されているそうです。「このような資料公開の状況はソ連譲歩の決定的なニュースをめぐって深刻な文書の往来があったことをうかがわせる」と和田氏は言います。
和田氏の言うとおりだとすると、隠されている部分の内容は、隠されていない部分から推測するしかありません。そこでもっともらしい内容を推測することは可能でしょうが、推測は所詮推測でしかありません。推測を事実と取り違えてはなりません。
重光については、有馬哲夫氏の『CIAと戦後日本』(平凡社新書、2010)第二章「重光葵はなぜ日ソ交渉で失脚したのか」が、CIAの報告書などを用いて戦後の重光の軌跡を概観しているので、興味をもって読んでみましたが、この2島返還論から4島返還論への転換についての言及はありません。
もっとも、和田氏と有馬氏だけが研究者ではありませんし、『北方領土問題』は1999年の著作です。その後新資料が公開されたり発掘されるなどして、研究が進んで、和田氏の推測が裏付けられているといった事情がもしあるのでしたら、是非ご教示願いたいと思います。
ところが、オコジョさんは、記事「四島返還論の出自――引き続き「北方領土」問題」で、突然こんなことを言い始めます。
私の主張は、ぎりぎり譲って、以下のようになります。
○領土問題は二島返還で妥結することができた
○しかし、四島返還が持ち出されたので妥結しなかった
○日本が四島返還を持ち出したのは、妥結させないためだった
なぜ妥結させなかったのかについては、「米国の意思に従った」と私は主張してきたわけですが、これを「米国の意思を顧慮した」と言い換えてもいいでしょうか。
「米国の意思に従った」と「米国の意思を顧慮した」では意味が異なります。
「顧慮」とは「ある事をしっかり考えに入れて、心をくばること。「相手の立場を―する」」(デジタル大辞泉)です。
オコジョさんがこう言い出したのは、米国だけではなくわが国においても4島返還論が検討されていたことに気付いたか、わが国の行動のどこまでが米国の圧力によるもので、どこまでがわが国の主体的な意思によるものかを説明することなど、極めて困難だということに気付いたからではないかと思われます。
深沢さんは、日本政府の自主的な意思によると言っておられるのですね。
とりあえず、妥結させなかった主体については今回は譲歩して、尖閣の領土権のように「棚上げ」してもいい、というわけです。
「自主的な意思による」とは、米国の意思にかかわらず、わが国独自の判断によるものだという意味でしょうか。
さらに、オコジョさんが後に拙記事「4島返還論は米国の圧力の産物か?」に寄せられたコメントでは、こんなことをおっしゃっています。
4島返還論への転換に米国の意思が関わっていないという御「信念」は、ただそうあってほしいという深沢さんの願望だけに基づいているものですから、なるべく早いところ脱却した方がいいのではないかとは、心配しているところではあるのです。
私は同じ記事の本文で、次のように述べています。
米国の意思はあったのでしょう。だがわが国の意思はなかったのでしょうか。
これを、米国の意思とわが国の意思は無関係であるという「信念」の表明と読み取られるのであれば、私はオコジョさんの読解力に不審の念を抱かざるを得ません。
この箇所は、米国の意思があったからといって、わが国がそれだけの理由で方針を転換したとは言えない、わが国はわが国で、米国の意思を考慮し、その他さまざまな要素も考慮した上で、4島返還論に転換したのではないかという意味です。
したがって、オコジョさんが「顧慮」と言い換えるのであれば、私にも異論はありません。
「棚上げ」も何も、オコジョさんと私の認識は一致しているのですから。
あとは、表現方法の問題です。
これについては、前回申し上げたように、私はオコジョさんが独特の表現方法をお好みの方だと理解しましたので、もはや特に述べることはありません。今後は、オコジョさんが「そういう方」だという認識の下に記事を読むことにします。
これで、本筋についての私の話は終わりです。
あとは オコジョさんが北方領土問題について、及びそれに関連して示されたいくつかの見解について、私の考えを述べておきます。
まずは「日米関係と「北方領土」問題――再び「ダレスの恫喝」」の末尾で述べておられた、日ソ交渉を米国に相談していたという点と、重光の後の戦後の外務大臣に外務省出身者がいないという点について。
日ソの交渉の機微を第三国に知らせることなど本来あり得ないというのは、通常の外交関係においては、おそらくはおっしゃるとおりなのでしょう。
しかし、当時の日米関係が、通常の外交関係とは異なるものであったことも考慮すべきでしょう。
米国の占領下に置かれ、米国によって新憲法をはじめとする諸改革を断行され、米国の支持の下で独立を果たし、わが国は米国に基地を提供する義務を負うが米国はわが国を防衛する義務を負わないという片務的な旧安保体制の下にありました。ソ連の反対により国連にも加盟することもできず、韓国とも中共とも国交はありませんでした。
端的に言えば、わが国は米国の庇護下にあったと言えるでしょう。
そしてまた、日ソ国交回復交渉が通常の外交ではなかったことも考慮すべきでしょう。
ソ連は単に交戦国の1つというだけでなく、共産圏のリーダーであり、当時は冷戦の真っ只中でした。
また、日ソの領土問題がどのような形で解決するかは、米国の極東戦略にも多大な影響を及ぼす要素でした。
だからこそ、吉田に比べて米国と距離があった鳩山の政権においても、日ソ交渉の内実を米国に明らかにせざるをなかったのではないでしょうか。
ソ連との交渉を一つの有効な取り引き材料にして、例えば沖縄の早期返還を促す、というような外交が当然考えられます。
これは、具体的にどういう外交が有り得たとお考えなのでしょうか。
そして、「有効な取り引き材料」も何も、「ダレスの恫喝」に見られるように、沖縄はむしろ日本側の弱み、日米関係におけるアキレス腱であったのではないのでしょうか。
次に、外務大臣に外務省出身者がいないという点については、たしかにおっしゃるとおりですが、それは、何より外交官から政治家へ転身する者が少ないからではないのでしょうか。
戦前と異なり、戦後は閣僚が国会議員であることが普通となりました。閣僚の中でも外相は花形ポストであり、それなりの有力者でなければ就任は困難です。
有力な国会議員に外務省出身者がほとんどいなければ、外相に外務省出身者がいないという事態も起こり得るでしょう。
私が無知だからかもしれませんが、戦後派の著名な政治家で外務省出身者をほとんど思いつきません。加藤紘一がいますが、彼は2世です。
理由はよくわかりませんが、官僚の中でも外交官は独自の世界を築いており、政党政治の世界には足を踏み入れようとしなかったのかもしれません。
むしろ、芦田均、松岡洋右、広田弘毅、幣原喜重郎、吉田茂、そして重光葵のような外交官出身の有力政治家が続出した戦中・戦後期が異常だったのかもしれません。
あれこれの根拠は抜きにして私の推測をそのまま書かせていただきますと、外務省に外交をやらせていては日本の国益を確保することなどできないというのが「外務大臣=非・外務省出身者」の理由です。
外務省に米国の意思が浸透していることの一つの表れだと私は思います。
そういう見方もあるんですね、としか言いようがありません。
次回は、「四島返還論の出自」を取り上げます。
(続く)