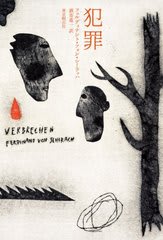
『犯罪』 フェルディナント・フォン・シーラッハ ☆☆☆☆★
ドイツの作家さんである。というか、本業は弁護士さんで、その人が実話をベースに書いた連作犯罪小説集である。面白い。しかも面白いだけじゃなく文学的香気もある。普通は弁護士が書いた実話小説というとドキュメンタリー・タッチで、専門的な知識をこれでもかと盛り込んであるイメージだが、これは全然そうじゃない。ストーリーテリングは簡潔で、ディテールの正確さや専門知識で圧倒しようという意図はこれっぽっちも感じられない。特に弁護士である語り手「私」の行動についてはほぼポイントのみの描写に留めてあり、そのせいで「私」が前面に出ることはなくむしろ陰の中に引っ込み、黒子となり、ミステリアスな存在感すら漂う。
そのかわりにスポットが当たるのはもちろん犯罪者たち、そして被害者たちである。簡潔な筆致によってすばやく描き出されるこれらの人々の人生はいびつで、真摯で、劇的である。冷静で淡々とした文体は端正をきわめ、その端正さの中にうっすらと詩情が漂う。これは明らかに文芸作家の筆致だ。
さっき書いたようにどの短編も語り手は弁護士なのだが、この「私」はまるで神の如き全能をもって登場人物たちの人生を語る。その時その場所で何が起きたか、どう感じたか、何を考えたか、「私」はすべてを知っていて断定的に語っていくのである。そして時折自分も物語の中に分け入ってある役割を演じるのだが、それはまるで神が弁護士の姿を借りて物語に介入するかの如くだ。しかもこの弁護士、読んだ印象ではとびきり有能である。まあ実際に著者もそうなのだろうが、これらの作品がリアリズム小説でありながらどこか現実離れして感じられるのは、そういう要素によるものだと思う。都会の神話の趣がある。話のタイプや雰囲気は違うが、ほぼ全能の語り手が物語に介入していくという意味では、楳図かずおの『おろち』をちょっと思い出した。
プロットのパターンも一定ではない。色んなタイプの短編が収められている。犯罪者の人生を語るものあり、トリッキーな裁判ものあり、アイロニカルなものあり、ヒューマニスティックな感動ものあり。きわめて多彩だ。ミステリー的な要素が皆無じゃないが、いわゆるミステリー小説ではない。かつ、話の展開が融通無碍である。「ひねりのきいた」などという常套句をあっさり越える斬新さだ。
個人的なフェイバリットをあげると「ハリネズミ」と「正当防衛」だろうか。「ハリネズミ」はスラムで育った天才少年が強盗で捕まった兄を救おうとする話。兄は単なるチンピラで頭も良くない。目撃者もいるし証拠もある。少年はどんな手を使って兄を無罪にするのか?
「正当防衛」は異様な話だが、これも実話なのだろうか? 一種の殺し屋小説である。見かけはごく普通の男が、からんできた二人のチンピラを一瞬の早業で殺害する。警察に捕まり、尋問されるが、一言も口を利かない。ここで、身元不詳の有力者から「私」に依頼が来る。「私」はこの不思議な男の殺人を「正当防衛」だと考えるが……。暗示的な結末が強い印象を残す、異色の殺し屋小説といっていいと思う。正直、私はこの男が活躍する長編ノワールを読んでみたい。
しかしどの短編も、あっさりしているようでなかなかの読み応えだ。短編集としては久々のヒットかも知れない。お薦めします。
ドイツの作家さんである。というか、本業は弁護士さんで、その人が実話をベースに書いた連作犯罪小説集である。面白い。しかも面白いだけじゃなく文学的香気もある。普通は弁護士が書いた実話小説というとドキュメンタリー・タッチで、専門的な知識をこれでもかと盛り込んであるイメージだが、これは全然そうじゃない。ストーリーテリングは簡潔で、ディテールの正確さや専門知識で圧倒しようという意図はこれっぽっちも感じられない。特に弁護士である語り手「私」の行動についてはほぼポイントのみの描写に留めてあり、そのせいで「私」が前面に出ることはなくむしろ陰の中に引っ込み、黒子となり、ミステリアスな存在感すら漂う。
そのかわりにスポットが当たるのはもちろん犯罪者たち、そして被害者たちである。簡潔な筆致によってすばやく描き出されるこれらの人々の人生はいびつで、真摯で、劇的である。冷静で淡々とした文体は端正をきわめ、その端正さの中にうっすらと詩情が漂う。これは明らかに文芸作家の筆致だ。
さっき書いたようにどの短編も語り手は弁護士なのだが、この「私」はまるで神の如き全能をもって登場人物たちの人生を語る。その時その場所で何が起きたか、どう感じたか、何を考えたか、「私」はすべてを知っていて断定的に語っていくのである。そして時折自分も物語の中に分け入ってある役割を演じるのだが、それはまるで神が弁護士の姿を借りて物語に介入するかの如くだ。しかもこの弁護士、読んだ印象ではとびきり有能である。まあ実際に著者もそうなのだろうが、これらの作品がリアリズム小説でありながらどこか現実離れして感じられるのは、そういう要素によるものだと思う。都会の神話の趣がある。話のタイプや雰囲気は違うが、ほぼ全能の語り手が物語に介入していくという意味では、楳図かずおの『おろち』をちょっと思い出した。
プロットのパターンも一定ではない。色んなタイプの短編が収められている。犯罪者の人生を語るものあり、トリッキーな裁判ものあり、アイロニカルなものあり、ヒューマニスティックな感動ものあり。きわめて多彩だ。ミステリー的な要素が皆無じゃないが、いわゆるミステリー小説ではない。かつ、話の展開が融通無碍である。「ひねりのきいた」などという常套句をあっさり越える斬新さだ。
個人的なフェイバリットをあげると「ハリネズミ」と「正当防衛」だろうか。「ハリネズミ」はスラムで育った天才少年が強盗で捕まった兄を救おうとする話。兄は単なるチンピラで頭も良くない。目撃者もいるし証拠もある。少年はどんな手を使って兄を無罪にするのか?
「正当防衛」は異様な話だが、これも実話なのだろうか? 一種の殺し屋小説である。見かけはごく普通の男が、からんできた二人のチンピラを一瞬の早業で殺害する。警察に捕まり、尋問されるが、一言も口を利かない。ここで、身元不詳の有力者から「私」に依頼が来る。「私」はこの不思議な男の殺人を「正当防衛」だと考えるが……。暗示的な結末が強い印象を残す、異色の殺し屋小説といっていいと思う。正直、私はこの男が活躍する長編ノワールを読んでみたい。
しかしどの短編も、あっさりしているようでなかなかの読み応えだ。短編集としては久々のヒットかも知れない。お薦めします。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます