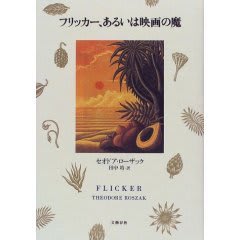
『フリッカー、あるいは映画の魔』 セオドア・ローザック ☆☆☆☆☆
再読。何度読んでも面白い。これはもう、映画好きは絶対に読まなければならない小説であって、映画ファンのための『薔薇の名前』である。まして映画ファンであり小説ファンでもある私みたいな人間にとっては猫にマタタビ状態、脳からドーパミン出まくりになる至福の書と言っても過言ではない。
ストーリーをざっくりいうと、「ぼく」ことジョナサン・ゲイツはLAの名画座でマックス・キャッスルというマイナーな映画監督の映画に出会い、その魅力にとりつかれて散逸していたフィルムを追い求め、研究し、やがて映画学科の教授になり、しだいにキャッスル映画に秘められた恐ろしい秘密へと足を踏み入れていく。
本書は基本的には実在架空を問わずさまざまな映画に言及しつつ、映画にとりつかれた人間達のドラマを緻密に追いかけていく「映画命」な物語だが、一方で映画とヨハネ騎士団、カタリ派、カソリックと異端の血で血を洗う争いの歴史、など宗教的なモチーフとを奇想天外なアイデアで結びつけ、しまいには世界の破滅にまで広がる壮大な終章へと突き進んでいく恐るべき幻想小説でもあるのだった。だからこれを単なる映画好きのオマージュ小説だと思って読むと痛い目を見る。これは途方もなく凶暴かつ巧緻なフィクションである。
しかしどうやって映画とヨハネ騎士団やカタリ派が結びつくのか。そもそも中世には映画は存在しない。『ダヴィンチ・コード』みたいなわけにはいかない。しかし結びついてしまうのである、この小説では。プレ映画的装置であるゾーエトロープや幻灯、それから映写機に使われるマルタクロス歯車などのマニアックな小道具を通じて、あるいは「嵐の孤児たち」というカタリ派の組織(ここでは孤児たちに映画技術を教育する)を設定することによって。そしてマックス・キャッスルの映画における稲妻ライティング、スライド効果、アンダーホールドなどの異様なテクニックのディテールに分け入っていくことによって。キャッスルの映画と同じように、この小説も複雑に「多層化」されている。
何よりも素晴らしいのは、モノクロの古いホラー/サスペンス映画が持つどこかまがまがしいムードを最大限に紙上に再現し、いつの間にか中世の異端へとつなげていくその手法の巧みさである。単に奇想天外なアイデアを組み合わせたという頭でっかちで不自然なところがまったくない。映画好きなら誰しも、昔のホラー映画、例えば『カリガリ博士』や『吸血鬼ノスフェラトゥ』(リメイクじゃなくてムルナウ版の方ね)などが持つ独特の呪縛力を知っているはずだ。ドライヤーの神秘的な映像に満ちた『ヴァンパイア』などを思い出してもらってもいい。白黒で画面が荒いからこそ、かえって無意識に突き刺さってくるような戦慄がある。本書で語られるマックス・キャッスルはそういう類の映画監督なのである。
キャッスルの映画はもちろん詳細に紹介される、最初はB級ホラー映画監督として。映画のタイトルも『鮮血の館』『ラザロ伯爵の呪い』『シンシン刑務所の影』『枢軸スパイ網』などいかにもなネーミング。深夜映画でやってそうだ。プリントの状態も悪い。ジョナサンは低予算のくだらないホラーだと思うが、一方で妙にひきつけられるものを感じる。独特の強烈なイメージ、まがまがしい呪縛力。やがてドイツ時代の初期の映画、『魔術師シモン』『われら万人のユダ』などのフィルムが発見されるにつれ、その凄さがだんだん分かってくる。やがてキャッスルの下で働いたカメラマンのジップ老人が所有するオリジナルのプリントを見て、ジョナサンはその秘められた芸術性に圧倒される。同時にキャッスルが駆使する怪しいテクニックに興味を持つ。キャッスルは目に見えないサブリミナル映像を映画の中にちりばめていたのだった。しかもそのイメージはことごとく病んでいる。
このあたりから現実離れした撮影・編集テクニックがマニアックに語られ始め、表面的な映画の下に別の映画が仕込まれている、なんて話になり、それがピークに達するのがサン=シールが提唱する神経記号学である。神経記号学では光と闇がまたたくフリッカー現象だけが映画の価値となり、観客のアテンション・スパンの遷移を表すグラフや関数が批評の根拠となる。物語や作家性は余計なものとして無視される。極端で荒唐無稽だが、おそろしく巧緻だ。これは映画批評をテーマにしたサブプロットである。
映画批評についていえば、本書の重要な登場人物としてジョナサンの恋人にして教育者のクレア、別名クラリッサ・スワンがいる。クラリッサ・スワンはさびれた名画座の経営者、後に高名な映画評論家となる女性で、病んだ連中が大量に現れるこの物語の中で健全な映画芸術の守護者としてふるまう。非常に魅力的なキャラクターである。ある人物がパゾリーニの『ソドムの市』を「あれはすべてを客体化して突き放した反ファシスト映画ですよ」と擁護するのに反論し、クレアは言う「野獣どもにいくらその正体を提示して見せても、やつらを打ち負かすことはできないわ。『ソドムの市』のような映画はわれわれの内なる彼らの同類を甘やかすだけだわ。ファシズムに対抗する唯一の手段は彼らとまったく無縁なものを繰り返し提示すること。人生の歓び、愛、無垢な心、そして『雨に歌えば』。あれこそ究極の反ファシスト映画よ」
もちろん、『市民ケーン』『天井桟敷の人々』『恋人たち』『博士の異常な愛情』『勝手にしやがれ』『野いちご』『サイコ』『オルフェ』などさまざまな実在の映画への言及もある。映画批評もある。アングラ実験映画の話もあれば、ポルノについても語られる。カメラや映写機など機材についても語られるし、映画館という場所についても語られる。『ジャングル娘ニーナ』のエピソードでは子供向けB級アクション映画におけるエロティシズムも語られる。オーソン・ウェルズも登場するし、実際にオーソン・ウェルズが作ろうとして頓挫した『闇の奥』についても語られる(しかもマックス・キャッスルが重要な関与をしていたという、ストーリー上とても重要な位置づけで)。とにかく、映画にまつわるありとあらゆる事象が語られる。
そして後半クローズアップされるのがスプラッター、ホラー映画の恐さである。おぞましい血みどろの低俗スプラッターのガラクタの中から、世紀末の預言者、病んだイメージを創造する天才少年サイモン・ダンクルが出現する。サイモンが制作した恐るべき「ゲロ吐き」映画の数々、そしてその決定版といえる悪魔的傑作『サブサブ』の描写は真に迫っていて、実際にその映画を見ているようなすさまじい戦慄を感じる。暗くおぞましい『下水道の悲しきベイビー』も同じで、背筋が寒くなる。
とにかくこの小説ではこういう架空の映画に存在感を持たせるのがものすごくうまい。特にマックス・キャッスルのホラー映画などは雰囲気がまざまざと伝わってきて、観たくてたまらなくなる。ちなみに本書の最後にはキャッスルのフィルモグラフィーがついていて、美術監督として『カリガリ博士』『巨人ゴーレム』に参加したことになっている。フリッツ・ラングと共同監督したことにもなってる。『妖婦リリス』という映画だが、これは架空みたいだ。
終盤、物語はあっと驚く展開となるが、そこから先は書かないでおく。ある意味それまでのプロットからはぐらかされたような、しかし考えてみると必然的であるような、なんとも不思議な世界で物語は終わっていく。最後の最後に出てくる映画、ありとあらゆる映画の集大成的映画『ジ・エンド』のアイデアも大変に美しい。とにかく壮大で怖ろしく快楽的な小説である。一体どうやったらこんな小説が書けるのか、作者の頭の中を見てみたい。
再読。何度読んでも面白い。これはもう、映画好きは絶対に読まなければならない小説であって、映画ファンのための『薔薇の名前』である。まして映画ファンであり小説ファンでもある私みたいな人間にとっては猫にマタタビ状態、脳からドーパミン出まくりになる至福の書と言っても過言ではない。
ストーリーをざっくりいうと、「ぼく」ことジョナサン・ゲイツはLAの名画座でマックス・キャッスルというマイナーな映画監督の映画に出会い、その魅力にとりつかれて散逸していたフィルムを追い求め、研究し、やがて映画学科の教授になり、しだいにキャッスル映画に秘められた恐ろしい秘密へと足を踏み入れていく。
本書は基本的には実在架空を問わずさまざまな映画に言及しつつ、映画にとりつかれた人間達のドラマを緻密に追いかけていく「映画命」な物語だが、一方で映画とヨハネ騎士団、カタリ派、カソリックと異端の血で血を洗う争いの歴史、など宗教的なモチーフとを奇想天外なアイデアで結びつけ、しまいには世界の破滅にまで広がる壮大な終章へと突き進んでいく恐るべき幻想小説でもあるのだった。だからこれを単なる映画好きのオマージュ小説だと思って読むと痛い目を見る。これは途方もなく凶暴かつ巧緻なフィクションである。
しかしどうやって映画とヨハネ騎士団やカタリ派が結びつくのか。そもそも中世には映画は存在しない。『ダヴィンチ・コード』みたいなわけにはいかない。しかし結びついてしまうのである、この小説では。プレ映画的装置であるゾーエトロープや幻灯、それから映写機に使われるマルタクロス歯車などのマニアックな小道具を通じて、あるいは「嵐の孤児たち」というカタリ派の組織(ここでは孤児たちに映画技術を教育する)を設定することによって。そしてマックス・キャッスルの映画における稲妻ライティング、スライド効果、アンダーホールドなどの異様なテクニックのディテールに分け入っていくことによって。キャッスルの映画と同じように、この小説も複雑に「多層化」されている。
何よりも素晴らしいのは、モノクロの古いホラー/サスペンス映画が持つどこかまがまがしいムードを最大限に紙上に再現し、いつの間にか中世の異端へとつなげていくその手法の巧みさである。単に奇想天外なアイデアを組み合わせたという頭でっかちで不自然なところがまったくない。映画好きなら誰しも、昔のホラー映画、例えば『カリガリ博士』や『吸血鬼ノスフェラトゥ』(リメイクじゃなくてムルナウ版の方ね)などが持つ独特の呪縛力を知っているはずだ。ドライヤーの神秘的な映像に満ちた『ヴァンパイア』などを思い出してもらってもいい。白黒で画面が荒いからこそ、かえって無意識に突き刺さってくるような戦慄がある。本書で語られるマックス・キャッスルはそういう類の映画監督なのである。
キャッスルの映画はもちろん詳細に紹介される、最初はB級ホラー映画監督として。映画のタイトルも『鮮血の館』『ラザロ伯爵の呪い』『シンシン刑務所の影』『枢軸スパイ網』などいかにもなネーミング。深夜映画でやってそうだ。プリントの状態も悪い。ジョナサンは低予算のくだらないホラーだと思うが、一方で妙にひきつけられるものを感じる。独特の強烈なイメージ、まがまがしい呪縛力。やがてドイツ時代の初期の映画、『魔術師シモン』『われら万人のユダ』などのフィルムが発見されるにつれ、その凄さがだんだん分かってくる。やがてキャッスルの下で働いたカメラマンのジップ老人が所有するオリジナルのプリントを見て、ジョナサンはその秘められた芸術性に圧倒される。同時にキャッスルが駆使する怪しいテクニックに興味を持つ。キャッスルは目に見えないサブリミナル映像を映画の中にちりばめていたのだった。しかもそのイメージはことごとく病んでいる。
このあたりから現実離れした撮影・編集テクニックがマニアックに語られ始め、表面的な映画の下に別の映画が仕込まれている、なんて話になり、それがピークに達するのがサン=シールが提唱する神経記号学である。神経記号学では光と闇がまたたくフリッカー現象だけが映画の価値となり、観客のアテンション・スパンの遷移を表すグラフや関数が批評の根拠となる。物語や作家性は余計なものとして無視される。極端で荒唐無稽だが、おそろしく巧緻だ。これは映画批評をテーマにしたサブプロットである。
映画批評についていえば、本書の重要な登場人物としてジョナサンの恋人にして教育者のクレア、別名クラリッサ・スワンがいる。クラリッサ・スワンはさびれた名画座の経営者、後に高名な映画評論家となる女性で、病んだ連中が大量に現れるこの物語の中で健全な映画芸術の守護者としてふるまう。非常に魅力的なキャラクターである。ある人物がパゾリーニの『ソドムの市』を「あれはすべてを客体化して突き放した反ファシスト映画ですよ」と擁護するのに反論し、クレアは言う「野獣どもにいくらその正体を提示して見せても、やつらを打ち負かすことはできないわ。『ソドムの市』のような映画はわれわれの内なる彼らの同類を甘やかすだけだわ。ファシズムに対抗する唯一の手段は彼らとまったく無縁なものを繰り返し提示すること。人生の歓び、愛、無垢な心、そして『雨に歌えば』。あれこそ究極の反ファシスト映画よ」
もちろん、『市民ケーン』『天井桟敷の人々』『恋人たち』『博士の異常な愛情』『勝手にしやがれ』『野いちご』『サイコ』『オルフェ』などさまざまな実在の映画への言及もある。映画批評もある。アングラ実験映画の話もあれば、ポルノについても語られる。カメラや映写機など機材についても語られるし、映画館という場所についても語られる。『ジャングル娘ニーナ』のエピソードでは子供向けB級アクション映画におけるエロティシズムも語られる。オーソン・ウェルズも登場するし、実際にオーソン・ウェルズが作ろうとして頓挫した『闇の奥』についても語られる(しかもマックス・キャッスルが重要な関与をしていたという、ストーリー上とても重要な位置づけで)。とにかく、映画にまつわるありとあらゆる事象が語られる。
そして後半クローズアップされるのがスプラッター、ホラー映画の恐さである。おぞましい血みどろの低俗スプラッターのガラクタの中から、世紀末の預言者、病んだイメージを創造する天才少年サイモン・ダンクルが出現する。サイモンが制作した恐るべき「ゲロ吐き」映画の数々、そしてその決定版といえる悪魔的傑作『サブサブ』の描写は真に迫っていて、実際にその映画を見ているようなすさまじい戦慄を感じる。暗くおぞましい『下水道の悲しきベイビー』も同じで、背筋が寒くなる。
とにかくこの小説ではこういう架空の映画に存在感を持たせるのがものすごくうまい。特にマックス・キャッスルのホラー映画などは雰囲気がまざまざと伝わってきて、観たくてたまらなくなる。ちなみに本書の最後にはキャッスルのフィルモグラフィーがついていて、美術監督として『カリガリ博士』『巨人ゴーレム』に参加したことになっている。フリッツ・ラングと共同監督したことにもなってる。『妖婦リリス』という映画だが、これは架空みたいだ。
終盤、物語はあっと驚く展開となるが、そこから先は書かないでおく。ある意味それまでのプロットからはぐらかされたような、しかし考えてみると必然的であるような、なんとも不思議な世界で物語は終わっていく。最後の最後に出てくる映画、ありとあらゆる映画の集大成的映画『ジ・エンド』のアイデアも大変に美しい。とにかく壮大で怖ろしく快楽的な小説である。一体どうやったらこんな小説が書けるのか、作者の頭の中を見てみたい。




















本はなんども読み返しました。
何度読んでも面白かった。
紹介文ははじめて読みました。
他の紹介も読んでみたいと思います。
お気に入りに入れますね。
ラスト、「お見事!」とうなりますよね。