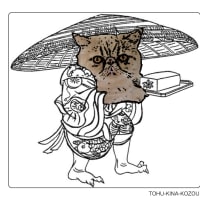以前、このブログで松本清張氏の「密宗律仙教」という短編小説が「いわゆる立川流」に題材をとってはいるが、ミステリになっておらず何を書きたかったのかわからない、という主旨の短文を書いたことがある。これは、その後日談である。
清張誕生100年の記念行事の一環であろうか、新潮社から作家や研究者によるテーマ別清張セレクトが出ているが、最近刊行された桐野夏生氏セレクトの『憑かれし者ども』に、「密宗律仙教」が納められていたのに気づいた。桐野氏の解説によれば、氏はこの短編に描かれた「事件」を「天理研究会事件」と関連づけ、清張の『昭和史発掘』にその事件が書かれていると紹介していた。
私は「天理研究会事件」と聞いてまったくぴんと来なかったのであるが、『昭和史発掘 新装版 2』(文春文庫、2005年)を読んで「ほんみち」の言葉が見えたので何となく思い出したのだった。ちなみに、『昭和史発掘』の「天理研究会事件」の初出は『週刊文春』1965年10月11日付から11月22日である。
教団としての宗教にはまったく興味のない(教義の内容を分析するのはほぼ仕事であるが)私だが、奈良の大学に通っていたとき、特に卒論作成の資料集めで天理大学付属図書館にお世話になっていたし、その後研究者になってからもここの膨大な貴重書群を拝見に行ったことは少なくない(最近はなかなか閲覧が叶わなくなった)。
天理大学までは、近鉄天理駅から徒歩で数十分かかるが、その道々には天理教の関連施設がずらりと並んでいたし、日に数回あるという信者さんの礼拝のシーンも目にしていたので、さほど知らない宗教団体ではなかった。「ほんみち」の話もそういった時に知ったのだろうと思う。
「天理研究会事件」の内容は『昭和史発掘』に詳しいのであまり述べないが、教祖・中山みきに神が降りたことが発端となって生まれた天理教の布教師であった大西愛治郎という人物が、みきの言葉を書き取った「お筆先」の理解をめぐって天理教本部と対立し、教会を離脱して自ら新たな宗教集団を作ったところ、激烈な弾圧を受けたというものである。
弾圧というのは天理教そのものも、また、よく知られているように大本教も受けており、そのいちばんの理由は不敬罪だった。新興宗教の場合、日本書紀や古事記といった神話をベースにする神道系のものは特にそうだが、万世一系であるはずの天皇家や天皇制じたいを否定するかに読める教義はことごとく弾圧の対象となったらしい。
さて、桐野氏がこの「天理研究会事件」と「密宗律仙教」との間にいわゆる「邪教的なるもの」というつながりを見いだしているのは間違いないと思うが(それぞれが「邪教」かどうかはともかくとして)、必ずしも「天理研究会事件」が「密宗律仙教」のモデルとなったかというと、私はそうではないと思うのである。
「密宗律仙教」の初出は『オール読物』1970年2月号であり、『昭和史発掘』の「天理教会事件」執筆から5年の年月がたっており、モデルとするにはちょっと時間があきすぎているように思われる。
また、「密宗律仙教」は「いわゆる立川流」(なぜ「いわゆる」なのかということについては過去の私のブログをご参照いただきたい)を元にしていることが本文にも示されており、「いわゆる立川流」の教義のおおもととされる「理趣経」と、その独自解釈である性的な教義がかなりの枚数を使って展開されている。「赤白二」という、男女の性的な体液が合一することを尊ぶ教義は、「いわゆる立川流」でかつてしきりに喧伝されたものである。これらは神道系の「天理研究会」とはまったく異なるものである。
そして、「密宗律仙教」の主人公である尾山武次郎(後、定海と名乗る。この僧名は明らかに真言系のものである)の性的な目覚めと、教団組織が彼と性的関係を結んだ女性たちを中心に運営されることは、「天理研究会」にはまったく見られない要素である。
では、「密宗律仙教」にはモデルがあったのだろうか。
もちろん「いわゆる立川流」がモデルであることは間違いないのだが、気になるのは清張が本文で相当この教義について専門的なことを書き込んでいることである。これは、どう考えても清張自身が「いわゆる立川流」の研究文献を読んでいたとしか考えられない。「いわゆる立川流」は平安末に萌芽し、鎌倉から南北朝時代に発展をみたとされるが、現在、神奈川県立金沢文庫に関係資料が蔵されていることはわかっているものの、1970年以前には関係する原典は表に出されることはほとんどなかったといってよい。もちろん、網野善彦氏の『異形の王権』はずーと後である(1986年)。
1970年以前に公刊されている「いわゆる立川流」の研究書として、まずあげられるのは水原堯栄氏の『邪教立川流の研究』(大正12年、冨山房書店→再版1968年)である。本書の再版と前後して、守山聖真氏の『立川邪教とその社会的背景の研究』(1965年、碩文社)が出版されている。「いわゆる立川流」の「実態」(かなりおぞましいと思われていた)が活字で読めるようになったのは、おそらくこの二書によると思われる。想像ではあるが、清張はこのどちらか、あるいは二書ともを読んでいた可能性があろう。
もともと宗教に関心があったと思われる清張さんであるので、「邪教」などと題名に明記されている本を見逃すとは思えない。あるいは、誰かが教示したのかもしれない(ちなみに、梓林太郎氏の『回想の松本清張』には本書についての記載は見えない)。
私が想像するのは、1970年代に「いわゆる立川流」について何かはやりのようなものがあったのかもしれない、ということである。というのは、村松剛氏が『死の日本文学史』(1975年5月、新潮社)と『帝王後醍醐』(初出は『歴史と人物』1976年8月号から翌年12月号まで連載)に「いわゆる立川流」について言及し、そのもっともグロいところを詳しく記しているからである。グロいところというのは、頭蓋骨を本尊として「和合水」をそれに塗りつけると髑髏は未来を予言するようになる、というようなところである。まあ、だいたい「いわゆる立川流」に興味を持つような人は、ここに驚いて関心を深めるのである(高校時代の私がまさにそうだった)。
この頃、ほかの作家で「いわゆる立川流」を小説などに使っているのは、今のところ山田風太郎氏の『婆娑羅』くらいしか知らないのだが、「もう戦後ではない」といわれてさらに十年たち、大阪万博とバラ色未来学が日本を覆っていた時期、もし「いわゆる立川流」に注目が集まったとしたら、それは南北朝時代や後醍醐帝にまつわる戦時中の暗い記憶を払拭しようとしてのことだったかも知れない。これはあくまで推測であるが、南北朝時代について大っぴらに語る(しかも、戦後の歴史学の文脈で語る)ことがおこなわれようとしたのかも知れない。
以上はあくまで私の推測であり、確たる証拠があって書いているわけではないので読み流していただきたいが、自分が南北朝時代の仏教説話を専門にしていることと、南北朝時代への理解や再認識の歴史への関心とはけっして無関係ではないのだろうと思う。
それにしても、今年は「○○××年」のイベントが多いねえ・・・。
清張誕生100年の記念行事の一環であろうか、新潮社から作家や研究者によるテーマ別清張セレクトが出ているが、最近刊行された桐野夏生氏セレクトの『憑かれし者ども』に、「密宗律仙教」が納められていたのに気づいた。桐野氏の解説によれば、氏はこの短編に描かれた「事件」を「天理研究会事件」と関連づけ、清張の『昭和史発掘』にその事件が書かれていると紹介していた。
私は「天理研究会事件」と聞いてまったくぴんと来なかったのであるが、『昭和史発掘 新装版 2』(文春文庫、2005年)を読んで「ほんみち」の言葉が見えたので何となく思い出したのだった。ちなみに、『昭和史発掘』の「天理研究会事件」の初出は『週刊文春』1965年10月11日付から11月22日である。
教団としての宗教にはまったく興味のない(教義の内容を分析するのはほぼ仕事であるが)私だが、奈良の大学に通っていたとき、特に卒論作成の資料集めで天理大学付属図書館にお世話になっていたし、その後研究者になってからもここの膨大な貴重書群を拝見に行ったことは少なくない(最近はなかなか閲覧が叶わなくなった)。
天理大学までは、近鉄天理駅から徒歩で数十分かかるが、その道々には天理教の関連施設がずらりと並んでいたし、日に数回あるという信者さんの礼拝のシーンも目にしていたので、さほど知らない宗教団体ではなかった。「ほんみち」の話もそういった時に知ったのだろうと思う。
「天理研究会事件」の内容は『昭和史発掘』に詳しいのであまり述べないが、教祖・中山みきに神が降りたことが発端となって生まれた天理教の布教師であった大西愛治郎という人物が、みきの言葉を書き取った「お筆先」の理解をめぐって天理教本部と対立し、教会を離脱して自ら新たな宗教集団を作ったところ、激烈な弾圧を受けたというものである。
弾圧というのは天理教そのものも、また、よく知られているように大本教も受けており、そのいちばんの理由は不敬罪だった。新興宗教の場合、日本書紀や古事記といった神話をベースにする神道系のものは特にそうだが、万世一系であるはずの天皇家や天皇制じたいを否定するかに読める教義はことごとく弾圧の対象となったらしい。
さて、桐野氏がこの「天理研究会事件」と「密宗律仙教」との間にいわゆる「邪教的なるもの」というつながりを見いだしているのは間違いないと思うが(それぞれが「邪教」かどうかはともかくとして)、必ずしも「天理研究会事件」が「密宗律仙教」のモデルとなったかというと、私はそうではないと思うのである。
「密宗律仙教」の初出は『オール読物』1970年2月号であり、『昭和史発掘』の「天理教会事件」執筆から5年の年月がたっており、モデルとするにはちょっと時間があきすぎているように思われる。
また、「密宗律仙教」は「いわゆる立川流」(なぜ「いわゆる」なのかということについては過去の私のブログをご参照いただきたい)を元にしていることが本文にも示されており、「いわゆる立川流」の教義のおおもととされる「理趣経」と、その独自解釈である性的な教義がかなりの枚数を使って展開されている。「赤白二」という、男女の性的な体液が合一することを尊ぶ教義は、「いわゆる立川流」でかつてしきりに喧伝されたものである。これらは神道系の「天理研究会」とはまったく異なるものである。
そして、「密宗律仙教」の主人公である尾山武次郎(後、定海と名乗る。この僧名は明らかに真言系のものである)の性的な目覚めと、教団組織が彼と性的関係を結んだ女性たちを中心に運営されることは、「天理研究会」にはまったく見られない要素である。
では、「密宗律仙教」にはモデルがあったのだろうか。
もちろん「いわゆる立川流」がモデルであることは間違いないのだが、気になるのは清張が本文で相当この教義について専門的なことを書き込んでいることである。これは、どう考えても清張自身が「いわゆる立川流」の研究文献を読んでいたとしか考えられない。「いわゆる立川流」は平安末に萌芽し、鎌倉から南北朝時代に発展をみたとされるが、現在、神奈川県立金沢文庫に関係資料が蔵されていることはわかっているものの、1970年以前には関係する原典は表に出されることはほとんどなかったといってよい。もちろん、網野善彦氏の『異形の王権』はずーと後である(1986年)。
1970年以前に公刊されている「いわゆる立川流」の研究書として、まずあげられるのは水原堯栄氏の『邪教立川流の研究』(大正12年、冨山房書店→再版1968年)である。本書の再版と前後して、守山聖真氏の『立川邪教とその社会的背景の研究』(1965年、碩文社)が出版されている。「いわゆる立川流」の「実態」(かなりおぞましいと思われていた)が活字で読めるようになったのは、おそらくこの二書によると思われる。想像ではあるが、清張はこのどちらか、あるいは二書ともを読んでいた可能性があろう。
もともと宗教に関心があったと思われる清張さんであるので、「邪教」などと題名に明記されている本を見逃すとは思えない。あるいは、誰かが教示したのかもしれない(ちなみに、梓林太郎氏の『回想の松本清張』には本書についての記載は見えない)。
私が想像するのは、1970年代に「いわゆる立川流」について何かはやりのようなものがあったのかもしれない、ということである。というのは、村松剛氏が『死の日本文学史』(1975年5月、新潮社)と『帝王後醍醐』(初出は『歴史と人物』1976年8月号から翌年12月号まで連載)に「いわゆる立川流」について言及し、そのもっともグロいところを詳しく記しているからである。グロいところというのは、頭蓋骨を本尊として「和合水」をそれに塗りつけると髑髏は未来を予言するようになる、というようなところである。まあ、だいたい「いわゆる立川流」に興味を持つような人は、ここに驚いて関心を深めるのである(高校時代の私がまさにそうだった)。
この頃、ほかの作家で「いわゆる立川流」を小説などに使っているのは、今のところ山田風太郎氏の『婆娑羅』くらいしか知らないのだが、「もう戦後ではない」といわれてさらに十年たち、大阪万博とバラ色未来学が日本を覆っていた時期、もし「いわゆる立川流」に注目が集まったとしたら、それは南北朝時代や後醍醐帝にまつわる戦時中の暗い記憶を払拭しようとしてのことだったかも知れない。これはあくまで推測であるが、南北朝時代について大っぴらに語る(しかも、戦後の歴史学の文脈で語る)ことがおこなわれようとしたのかも知れない。
以上はあくまで私の推測であり、確たる証拠があって書いているわけではないので読み流していただきたいが、自分が南北朝時代の仏教説話を専門にしていることと、南北朝時代への理解や再認識の歴史への関心とはけっして無関係ではないのだろうと思う。
それにしても、今年は「○○××年」のイベントが多いねえ・・・。