前回の補足を。
如何にして顧客の日常となり得るか ~ 「ゼロの力」とググタスの未来 ~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/4c9821ec2aceb2416ab5aa3af807c062
AKB48を語るときに知っておきたい「フリー」
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/82ed0d579063ea817ff35cfff964832d
今回も参考図書としてクリス・アンダーソン『FREE フリー <無料>からお金を生み出す新戦略』を使います。
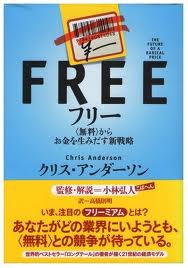
--------------------
■ゼロの歴史
上のリンク先でも述べたのだが、ゼロの歴史は古代バビロニアまで遡る。
古代文明において文字が発明されたのは契約や管理の必要性に迫られたからだとする学説が有力であるが、おそらくゼロにも類似した背景があったと思われる。
(中国の甲骨文字は宗教的背景により生まれたとされている。)
(古代バビロニアは時間を基にした60進法だったので、時間との相性が良い。)
数の数え方を工夫する必要があったのだ。
ただ、多くの文明が記号としてゼロを使っても、「概念としてのゼロ」にはたどり着かなかった。
古代ローマ人はローマ数字でゼロを使わなかったし、古代ギリシャ人ははっきりとゼロを拒絶した。
彼らの数学は幾何学に基づいていたので、数字は長さや角度、面積などの空間を表すものだった。
そのため「ゼロの空間」は意味を成さなかったのだ。
ギリシャの数学を代表するのはピタゴラスとピタゴラス学派で、算数がマイナスの数字や無理数、さらにはゼロを生み出すことを理解していたが、それらは自然の形ではないという理由で否定していた。
■概念としてのゼロ
この視野狭窄もわからないでもない。
数学が現実の物事を表すものだとされる社会では、何もないことを表す数字は必要ない。
それは抽象的な考えであって、抽象的な数学の世界に出てくるものに過ぎない。
イギリスの数学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドは1911年に次のように記した。
ゼロについて大事なことは、日常生活ではそれを使う必要がないことだ。
誰も魚をゼロ匹買いに行かない。
ある意味でゼロは奇数の中で最も洗練された数字で、洗練された思考のために必要となるに過ぎない。
インド人は数字が現実の物事だけを表すものだとは見ずに、概念としても捉えた。
東洋の神秘主義は陰と陽の二重性を通して、有形と無形のモノを両方とも取り込んだ。
シヴァ神は世界の創造者であると同時に破壊者だ。
ニシュカラ・シヴァ神の一側面は、「何もない」、つまり空のシヴァだった。
数字を現実の物質と切り離すことで、インド人は代数学を考え出せたのだ。
数学を発展させていき、9世紀までには、マイナスの数字とゼロなどを論理的に導き出していた。
「zero」の語源はインドにある。
インドでゼロは「空」を意味する「sunya」であり、それがアラビア語の「sifr」に転じて、西洋の学者がラテン語化し「zephirus」として、それから現在の「zero」になったのだ。
■武器となるフリー
「ゼロの概念」を理解することは、「フリー」を考える上で非常に重要だ。
今日、市場に参入する最も破壊的な方法は、既存のビジネスモデルの経済的意味を消滅させることだ。
既存ビジネスが収益源としている商品(商品を規定している重要な要素)をタダ(ゼロ)にするのだ。
すると、その市場の顧客はいっせいにその新規参入者のところへ押しかけるので、そこで別のモノを売りつければよい。
(クレイトン・クリステンセンは既存のビジネスモデルの中で中核となっている要素を無効化するそのようなイノベーションを「破壊的イノベーション」と呼んだ。)
■潤沢な時代
20世紀には、人々がフリーを概念として受け入れはじめただけではなく、そのフリーを現実のものにするための重要な現象も起きた。
それは、モノが潤沢にある時代の到来だ。
それ以前のほとんどの世代は、衣食住の欠乏を常に心配していたが、この50年ほどの間に先進国に生まれた人は、モノが潤沢になることが当たり前になっている。
そして、人間が生きるために最も必要な食料において、この潤沢さは顕著なのだ。
この50年ほどの間に、農業の世界では劇的な変化が起きて、人間は植物を育てるのがとてもうまくなった。
技術革新によって稀少だった農作物が潤沢になったのだ。
そして、この話からは、稀少な主要資源が潤沢に生産されるようになるときに何が起こるかを知る手がかりになる。
■農業革命<緑の革命>
農作物を育てるのに必要な要素は5つである。
太陽、空気、水、土地(栄養)、労働力の5つだ。
太陽と空気はタダだし、農作物を育てる場所の降雨量が多ければ、水もタダになる。
(繁栄した文明は大規模な灌漑施設を作って水の問題を解決していた。)
残るのは土地(肥料)と労働力ということになるが、これはタダではないので、農作物の価格の大半はその費用となる。
産業革命は19世紀になると農業を機械化し、労働コストを大きく下げて、収穫量を増やした。
だが、食糧経済を本当に変えたのは、1960年代に発展途上国で農業の効率化を進め、労働力の削減へと繋がった「緑の革命」だ。
この第2の革命の鍵は、化学にあった。
人類の歴史の大半において、人間が得られる植物の量を決めてきたのは、実は「肥料」である。
農作物の収穫高は、動物と人間の排泄物を中心とした肥料をどれだけ使えるかで決まった。
そして、農地で家畜と作物による栄養サイクルの相乗効果を望むのであれば、両者の使う土地を分けざるを得なかった。
しかし、19世紀の終わりに、植物学者は植物に必要な主栄養が「窒素」と「リン」、「カリウム」であることを解明しはじめたのだ。
20世紀に入ると、一部の化学者がそれらの栄養素を合成する研究にとりかかり、そして飛躍的進歩はBASF社で働くフリッツ・ハーバーの発見によってもたらされた。
空気と天然ガスを高圧・高温下で混ぜることによって、空気の中から窒素をアンモニアの形で取り出すことに成功したのだ。
安価な窒素肥料は1910年代にカール・ボッシュの手で商品化された。
それにより農作物の生産量は大きく増え、マルサス主義的災厄、つまり人口爆発による飢餓という長年危惧されてきた辞退を避けられるようになった。
現在、アンモニアの製造で世界の天然ガスの約5%を消費していて、それは世界のエネルギー消費の2%に当たる。
この窒素肥料は、肥やしに頼っていた農民を解放した。
窒素肥料と化学殺虫剤、化学除草剤によって緑の革命は成し遂げられ、世界の食料生産量を約100倍に増やすことで地球は増加する人口を養えるようになった。
特に、新たに登場した中産階級は食物連鎖の高いレベルにある食べ物を望み、穀物よりも資源集約的な肉を好むようになった。
食料生産量が上がった効果は劇的だった。
先進国の家庭の平均収入に占める食費の割合はかなり低下したのだった。
■潤沢さの象徴:トウモロコシ
農作物の潤沢さを私たちが実感できるものといえば、「トウモロコシ経済」だ。
実にデンプンが詰まったこの特別な植物は、人間が何千年もの間、品種改良により実を大きくしてきたので、1単位面積あたりの生産高は地上のどの作物よりも高い。
歴史家は、米と小麦、トウモロコシという3つの穀物を通して主要な古代文明を見てきた。
米はたんぱく質が豊富だが、育てるのが難しい。
小麦は育てやすいが、たんぱく質が少ない。
トウモロコシだけが育てるのが簡単な上、たんぱく質が豊富なのだ。
それらの穀物が必要とする労働力に対する実に含まれるたんぱく質の量の割合が、その穀物を主食とする文明の進む道に影響を与えた。
その割合が高ければ高いほど、少ない労働で自分たちを養えるので「社会の余剰」が発生する。
それが与える影響は肯定的なものに限らない。
米と小麦を主食とする社会は農耕社会で、内側へ向く文化になりやすい。
おそらく米と小麦を育てる過程で彼らはかなりのエネルギーをとられてしまうからだ。
一方、マヤやアステカなどトウモロコシを主食とする分化は、時間とエネルギーが余っていたので、よく近隣の部族を攻撃したという。
この観点に立てば、アステカ人を好戦的にしたのは潤沢なトウモロコシだったのだ。
(実際の歴史は、このトウモロコシによって支えられた文明は大陸からやってきた侵略者に征服されてしまう。これはトウモロコシの品種改良には非常に長い時間がかかっており、古代文明の食糧生産における優位性は小麦や米のほうに軍配が上がるからだ。また南北アメリカ大陸には大型動物が生息していなかったため、動物の家畜化による恩恵を受けれなかったことも大きい。このあたりは『銃・病原菌・鉄』が詳しい。)
今日、我々はトウモロコシを食べる以外の用途にも使っている。
合成肥料と育種技術により、トウモロコシは太陽と水を他のどんな植物よりも効率よくデンプンに変換できるようになり、人間が食べきれないほどの量を作れるようになったのだ。
そのため、トウモロコシは絵の具から容器まで様々な製品の材料となっている。
チキンナゲットはトウモロコシ尽くしだ。
鶏はトウモロコシを餌に育てられ、ナゲットにはつなぎとしてコーンスターチが使われているし、バターにもコーンフラワーが入っているし、コーンオイルで揚げている。
ナゲットに入っている酵母やレシチン、モノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリド、魅力的な金色にして鮮度を保つためのクエン酸も全てトウモロコシを原料としている。
練り歯磨きや化粧品、使い捨てオムツ、洗剤、段ボール箱、壁張り用材やパテ材、床、接着剤にまでトウモロコシが含まれる。
スーパーマーケットにある商品の4分の1にトウモロコシが入っているといわれている。
有り余るトウモロコシは、今ではエタノールという形で車の燃料にも使われている。
■たくさんありすぎて気づかない
人間は、モノが潤沢なことよりも、稀少なことを理解しやすいようにできている。
なぜなら私達は生存のために、脅威や危険に過度に反応するように進化してきたからだ。
我々の生存戦術の一つに、モノがなくなりそうな危険に注意を向けることがある。
進化の観点から言えば、潤沢にあることは何の問題にもならないが、稀少な場合は奪い合いになる。
トウモロコシの例のように、我々はその一生の間にモノが潤沢になっていくことを実際に経験しても見落としがちだ。
ひとたびモノが潤沢になると、ふだん空気を意識せずに呼吸をしているのと同じで、我々はそれを無視しやすくなるのだ。
経済学が「稀少なものの選択」の科学だと定義されるのはここに理由がある。
潤沢にあるときには選択の必要がないので、それについて考えなくてよいのだ。
中世ヨーロッパでは、海に面していない地域では塩が不足していたので、塩は金と同じように「通貨」として使われた。
現代の塩はどうだろうか?
どの料理もタダ同然で入れられる調味料だ。
安すぎて誰も気にしない。
1900年に、最も基本的な男性用肌着はアメリカでの卸価格が約1ドルだった。
(この価格はインフレ調整前のもので、当時の1ドルは今の25倍、今なら25ドルだ。)
1ドルは高かったので、平均的なアメリカ人はシャツを8枚しか持っていなかった。
しかし、今では使い捨てである。
20世紀における潤沢さの最も身近な例は、プラスチックだろう。
タダに等しく、加工しやすい。
究極の代替商品であるプラスチックは、製造と材料のコストを実質的にゼロにまで下げた。
形も質感も色もお望みのままだ。
第2次世界大戦中に、プラスチックは重要な戦略物資となり、アメリカ政府は10億ドルをかけて合成樹脂製造工場を作った。
戦後、その生産能力はすべて消費者市場に向けられ、この加工しやすい素材はとても安くなった。
プラスチックの第1世代は、使い捨てではなく、優れた素材として売られた。
それは金属よりも望みの形に加工しやすいし、木よりも長持ちする。
ところが、第2世代のプラスチックやビニール、ポリスチレンはとても安くなったので、無造作に捨てられるようになった。
1960年代には、カラフルな使い捨て商品が物不足を克服した工業技術の勝利を告げる社会の象徴となった。
工業製品を使い捨てることは無駄ではなく、進んだ文明の特権だったのだ。
ところが、1970年代に入ると、使い捨て文化が環境に与えるコストが目立つようになり、過剰に溢れるモノに対する姿勢が変わり始めた。
プラスチックはタダ同然の価格だったが、それはたんに適切な価格付けがなされていなかったからだ。
環境に悪影響を与える外部不経済のコストも考えれば、おまけで付いてくるおもちゃを1回遊んだだけで捨ててしまうのは、後ろめたく思うべきなのかもしれない。
■潤沢さは勝利する
20世紀について特筆されるべきは、潤沢さがもたらした大きな社会・経済的変化だ。
自動車は膨大に蓄えられた石油を地下から採掘できるようになったことで実現した。
石油は、稀少な鯨油に代わり、どこでも手に入る液体燃料となった。
巨大コンテナのおかげで、港での積卸に大勢の港湾労働者は必要なくなった。
そのため、船積みの費用は安くなり、余った労働力を他に回せるようになった。
そして、コンピュータは情報を潤沢にした。
水が常に低いところへ流れるように、経済も潤沢な方へと流れた。
あらゆる製品はコモディティ化されて安くなっていき、企業は儲けを求めて新しい希少性を探している。
ここで一つ重要なことは、コモディティ化した商品は安くなるが、その価値はよそに移っていくということだ。
クレイトン・クリステンセンは(『イノベーションのジレンマ』次作の)『イノベーションへの解』の中で、マイケル・E・ポーターのバリューチェーンを産業界全体に拡張した上で、価値がそのバリューチェーンの上を移動していく「魅力的利益保存の法則」を主張している。
価値あるものがコモディティ化して価値が下がり、価値のあるものは、まだコモディティ化していないものへと移る。
知識労働者は希少性を求めてコモディティ化の川をさかのぼっていくが、その線引きは常に動いている。
システムは本質的に動的で複雑なのだ。
潤沢さにもとづく思考は、何が安くなるのかを見つけるだけではなく、価値がどの方向へと移ろうとしていて、その結果、何の価値が上がるのかを探り、利用することでもある。
それは、19世紀はじめにイギリスの経済学者、デイヴィッド・リカードが国同士の比較優位を唱えるずっと前から、成長の原動力となってきた。
これまでの潤沢さは、他国の潤沢な資源や安い労働力による製品で成り立っていたが、今日の潤沢さは、シリコンチップと光ファイバーによる新しい製品によって作られている。
■潤沢さを理解し利用する
ここまで長々と説明してきて、最後はあっさり締めようと思う。
(いや、疲れたんだ・・昨日、知人の結婚式で深夜まで飲んで二日酔いっていうのもあり)
稀少なものと、潤沢なものの管理が重要だ。
いや、正確には、何を稀少なものとして、どういう潤沢さを利用するか、もしくはどういう潤沢さを醸成するかという視点である。
何か望むもののために、価値のあるものを実現しようとする時、その前段で、どういう潤沢さを獲得すべきなのか、ということである。
潤沢さそのものは目的ではないが、目的を達成するために必要なものである。
さらにいえば、潤沢さは目的の達成を保証しない。
だが、潤沢さの勢いは留まることを知らない。
あらゆる業界で潤沢さの波は押し寄せてくる。
しかし、人間は潤沢さには気づけないから、潤沢さを理解しようとしなければ、押し流されてからその波に気づくことになる。
そして潤沢さは勝利するであろう。
「フリー」を武器にできるもできないも、この「潤沢さ」理解し、利用することができるかどうかにかかっている。
如何にして顧客の日常となり得るか ~ 「ゼロの力」とググタスの未来 ~
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/4c9821ec2aceb2416ab5aa3af807c062
AKB48を語るときに知っておきたい「フリー」
http://blog.goo.ne.jp/advanced_future/e/82ed0d579063ea817ff35cfff964832d
今回も参考図書としてクリス・アンダーソン『FREE フリー <無料>からお金を生み出す新戦略』を使います。
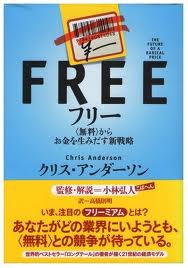
--------------------
■ゼロの歴史
上のリンク先でも述べたのだが、ゼロの歴史は古代バビロニアまで遡る。
古代文明において文字が発明されたのは契約や管理の必要性に迫られたからだとする学説が有力であるが、おそらくゼロにも類似した背景があったと思われる。
(中国の甲骨文字は宗教的背景により生まれたとされている。)
(古代バビロニアは時間を基にした60進法だったので、時間との相性が良い。)
数の数え方を工夫する必要があったのだ。
ただ、多くの文明が記号としてゼロを使っても、「概念としてのゼロ」にはたどり着かなかった。
古代ローマ人はローマ数字でゼロを使わなかったし、古代ギリシャ人ははっきりとゼロを拒絶した。
彼らの数学は幾何学に基づいていたので、数字は長さや角度、面積などの空間を表すものだった。
そのため「ゼロの空間」は意味を成さなかったのだ。
ギリシャの数学を代表するのはピタゴラスとピタゴラス学派で、算数がマイナスの数字や無理数、さらにはゼロを生み出すことを理解していたが、それらは自然の形ではないという理由で否定していた。
■概念としてのゼロ
この視野狭窄もわからないでもない。
数学が現実の物事を表すものだとされる社会では、何もないことを表す数字は必要ない。
それは抽象的な考えであって、抽象的な数学の世界に出てくるものに過ぎない。
イギリスの数学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドは1911年に次のように記した。
ゼロについて大事なことは、日常生活ではそれを使う必要がないことだ。
誰も魚をゼロ匹買いに行かない。
ある意味でゼロは奇数の中で最も洗練された数字で、洗練された思考のために必要となるに過ぎない。
インド人は数字が現実の物事だけを表すものだとは見ずに、概念としても捉えた。
東洋の神秘主義は陰と陽の二重性を通して、有形と無形のモノを両方とも取り込んだ。
シヴァ神は世界の創造者であると同時に破壊者だ。
ニシュカラ・シヴァ神の一側面は、「何もない」、つまり空のシヴァだった。
数字を現実の物質と切り離すことで、インド人は代数学を考え出せたのだ。
数学を発展させていき、9世紀までには、マイナスの数字とゼロなどを論理的に導き出していた。
「zero」の語源はインドにある。
インドでゼロは「空」を意味する「sunya」であり、それがアラビア語の「sifr」に転じて、西洋の学者がラテン語化し「zephirus」として、それから現在の「zero」になったのだ。
■武器となるフリー
「ゼロの概念」を理解することは、「フリー」を考える上で非常に重要だ。
今日、市場に参入する最も破壊的な方法は、既存のビジネスモデルの経済的意味を消滅させることだ。
既存ビジネスが収益源としている商品(商品を規定している重要な要素)をタダ(ゼロ)にするのだ。
すると、その市場の顧客はいっせいにその新規参入者のところへ押しかけるので、そこで別のモノを売りつければよい。
(クレイトン・クリステンセンは既存のビジネスモデルの中で中核となっている要素を無効化するそのようなイノベーションを「破壊的イノベーション」と呼んだ。)
■潤沢な時代
20世紀には、人々がフリーを概念として受け入れはじめただけではなく、そのフリーを現実のものにするための重要な現象も起きた。
それは、モノが潤沢にある時代の到来だ。
それ以前のほとんどの世代は、衣食住の欠乏を常に心配していたが、この50年ほどの間に先進国に生まれた人は、モノが潤沢になることが当たり前になっている。
そして、人間が生きるために最も必要な食料において、この潤沢さは顕著なのだ。
この50年ほどの間に、農業の世界では劇的な変化が起きて、人間は植物を育てるのがとてもうまくなった。
技術革新によって稀少だった農作物が潤沢になったのだ。
そして、この話からは、稀少な主要資源が潤沢に生産されるようになるときに何が起こるかを知る手がかりになる。
■農業革命<緑の革命>
農作物を育てるのに必要な要素は5つである。
太陽、空気、水、土地(栄養)、労働力の5つだ。
太陽と空気はタダだし、農作物を育てる場所の降雨量が多ければ、水もタダになる。
(繁栄した文明は大規模な灌漑施設を作って水の問題を解決していた。)
残るのは土地(肥料)と労働力ということになるが、これはタダではないので、農作物の価格の大半はその費用となる。
産業革命は19世紀になると農業を機械化し、労働コストを大きく下げて、収穫量を増やした。
だが、食糧経済を本当に変えたのは、1960年代に発展途上国で農業の効率化を進め、労働力の削減へと繋がった「緑の革命」だ。
この第2の革命の鍵は、化学にあった。
人類の歴史の大半において、人間が得られる植物の量を決めてきたのは、実は「肥料」である。
農作物の収穫高は、動物と人間の排泄物を中心とした肥料をどれだけ使えるかで決まった。
そして、農地で家畜と作物による栄養サイクルの相乗効果を望むのであれば、両者の使う土地を分けざるを得なかった。
しかし、19世紀の終わりに、植物学者は植物に必要な主栄養が「窒素」と「リン」、「カリウム」であることを解明しはじめたのだ。
20世紀に入ると、一部の化学者がそれらの栄養素を合成する研究にとりかかり、そして飛躍的進歩はBASF社で働くフリッツ・ハーバーの発見によってもたらされた。
空気と天然ガスを高圧・高温下で混ぜることによって、空気の中から窒素をアンモニアの形で取り出すことに成功したのだ。
安価な窒素肥料は1910年代にカール・ボッシュの手で商品化された。
それにより農作物の生産量は大きく増え、マルサス主義的災厄、つまり人口爆発による飢餓という長年危惧されてきた辞退を避けられるようになった。
現在、アンモニアの製造で世界の天然ガスの約5%を消費していて、それは世界のエネルギー消費の2%に当たる。
この窒素肥料は、肥やしに頼っていた農民を解放した。
窒素肥料と化学殺虫剤、化学除草剤によって緑の革命は成し遂げられ、世界の食料生産量を約100倍に増やすことで地球は増加する人口を養えるようになった。
特に、新たに登場した中産階級は食物連鎖の高いレベルにある食べ物を望み、穀物よりも資源集約的な肉を好むようになった。
食料生産量が上がった効果は劇的だった。
先進国の家庭の平均収入に占める食費の割合はかなり低下したのだった。
■潤沢さの象徴:トウモロコシ
農作物の潤沢さを私たちが実感できるものといえば、「トウモロコシ経済」だ。
実にデンプンが詰まったこの特別な植物は、人間が何千年もの間、品種改良により実を大きくしてきたので、1単位面積あたりの生産高は地上のどの作物よりも高い。
歴史家は、米と小麦、トウモロコシという3つの穀物を通して主要な古代文明を見てきた。
米はたんぱく質が豊富だが、育てるのが難しい。
小麦は育てやすいが、たんぱく質が少ない。
トウモロコシだけが育てるのが簡単な上、たんぱく質が豊富なのだ。
それらの穀物が必要とする労働力に対する実に含まれるたんぱく質の量の割合が、その穀物を主食とする文明の進む道に影響を与えた。
その割合が高ければ高いほど、少ない労働で自分たちを養えるので「社会の余剰」が発生する。
それが与える影響は肯定的なものに限らない。
米と小麦を主食とする社会は農耕社会で、内側へ向く文化になりやすい。
おそらく米と小麦を育てる過程で彼らはかなりのエネルギーをとられてしまうからだ。
一方、マヤやアステカなどトウモロコシを主食とする分化は、時間とエネルギーが余っていたので、よく近隣の部族を攻撃したという。
この観点に立てば、アステカ人を好戦的にしたのは潤沢なトウモロコシだったのだ。
(実際の歴史は、このトウモロコシによって支えられた文明は大陸からやってきた侵略者に征服されてしまう。これはトウモロコシの品種改良には非常に長い時間がかかっており、古代文明の食糧生産における優位性は小麦や米のほうに軍配が上がるからだ。また南北アメリカ大陸には大型動物が生息していなかったため、動物の家畜化による恩恵を受けれなかったことも大きい。このあたりは『銃・病原菌・鉄』が詳しい。)
今日、我々はトウモロコシを食べる以外の用途にも使っている。
合成肥料と育種技術により、トウモロコシは太陽と水を他のどんな植物よりも効率よくデンプンに変換できるようになり、人間が食べきれないほどの量を作れるようになったのだ。
そのため、トウモロコシは絵の具から容器まで様々な製品の材料となっている。
チキンナゲットはトウモロコシ尽くしだ。
鶏はトウモロコシを餌に育てられ、ナゲットにはつなぎとしてコーンスターチが使われているし、バターにもコーンフラワーが入っているし、コーンオイルで揚げている。
ナゲットに入っている酵母やレシチン、モノグリセリド、ジグリセリド、トリグリセリド、魅力的な金色にして鮮度を保つためのクエン酸も全てトウモロコシを原料としている。
練り歯磨きや化粧品、使い捨てオムツ、洗剤、段ボール箱、壁張り用材やパテ材、床、接着剤にまでトウモロコシが含まれる。
スーパーマーケットにある商品の4分の1にトウモロコシが入っているといわれている。
有り余るトウモロコシは、今ではエタノールという形で車の燃料にも使われている。
■たくさんありすぎて気づかない
人間は、モノが潤沢なことよりも、稀少なことを理解しやすいようにできている。
なぜなら私達は生存のために、脅威や危険に過度に反応するように進化してきたからだ。
我々の生存戦術の一つに、モノがなくなりそうな危険に注意を向けることがある。
進化の観点から言えば、潤沢にあることは何の問題にもならないが、稀少な場合は奪い合いになる。
トウモロコシの例のように、我々はその一生の間にモノが潤沢になっていくことを実際に経験しても見落としがちだ。
ひとたびモノが潤沢になると、ふだん空気を意識せずに呼吸をしているのと同じで、我々はそれを無視しやすくなるのだ。
経済学が「稀少なものの選択」の科学だと定義されるのはここに理由がある。
潤沢にあるときには選択の必要がないので、それについて考えなくてよいのだ。
中世ヨーロッパでは、海に面していない地域では塩が不足していたので、塩は金と同じように「通貨」として使われた。
現代の塩はどうだろうか?
どの料理もタダ同然で入れられる調味料だ。
安すぎて誰も気にしない。
1900年に、最も基本的な男性用肌着はアメリカでの卸価格が約1ドルだった。
(この価格はインフレ調整前のもので、当時の1ドルは今の25倍、今なら25ドルだ。)
1ドルは高かったので、平均的なアメリカ人はシャツを8枚しか持っていなかった。
しかし、今では使い捨てである。
20世紀における潤沢さの最も身近な例は、プラスチックだろう。
タダに等しく、加工しやすい。
究極の代替商品であるプラスチックは、製造と材料のコストを実質的にゼロにまで下げた。
形も質感も色もお望みのままだ。
第2次世界大戦中に、プラスチックは重要な戦略物資となり、アメリカ政府は10億ドルをかけて合成樹脂製造工場を作った。
戦後、その生産能力はすべて消費者市場に向けられ、この加工しやすい素材はとても安くなった。
プラスチックの第1世代は、使い捨てではなく、優れた素材として売られた。
それは金属よりも望みの形に加工しやすいし、木よりも長持ちする。
ところが、第2世代のプラスチックやビニール、ポリスチレンはとても安くなったので、無造作に捨てられるようになった。
1960年代には、カラフルな使い捨て商品が物不足を克服した工業技術の勝利を告げる社会の象徴となった。
工業製品を使い捨てることは無駄ではなく、進んだ文明の特権だったのだ。
ところが、1970年代に入ると、使い捨て文化が環境に与えるコストが目立つようになり、過剰に溢れるモノに対する姿勢が変わり始めた。
プラスチックはタダ同然の価格だったが、それはたんに適切な価格付けがなされていなかったからだ。
環境に悪影響を与える外部不経済のコストも考えれば、おまけで付いてくるおもちゃを1回遊んだだけで捨ててしまうのは、後ろめたく思うべきなのかもしれない。
■潤沢さは勝利する
20世紀について特筆されるべきは、潤沢さがもたらした大きな社会・経済的変化だ。
自動車は膨大に蓄えられた石油を地下から採掘できるようになったことで実現した。
石油は、稀少な鯨油に代わり、どこでも手に入る液体燃料となった。
巨大コンテナのおかげで、港での積卸に大勢の港湾労働者は必要なくなった。
そのため、船積みの費用は安くなり、余った労働力を他に回せるようになった。
そして、コンピュータは情報を潤沢にした。
水が常に低いところへ流れるように、経済も潤沢な方へと流れた。
あらゆる製品はコモディティ化されて安くなっていき、企業は儲けを求めて新しい希少性を探している。
ここで一つ重要なことは、コモディティ化した商品は安くなるが、その価値はよそに移っていくということだ。
クレイトン・クリステンセンは(『イノベーションのジレンマ』次作の)『イノベーションへの解』の中で、マイケル・E・ポーターのバリューチェーンを産業界全体に拡張した上で、価値がそのバリューチェーンの上を移動していく「魅力的利益保存の法則」を主張している。
価値あるものがコモディティ化して価値が下がり、価値のあるものは、まだコモディティ化していないものへと移る。
知識労働者は希少性を求めてコモディティ化の川をさかのぼっていくが、その線引きは常に動いている。
システムは本質的に動的で複雑なのだ。
潤沢さにもとづく思考は、何が安くなるのかを見つけるだけではなく、価値がどの方向へと移ろうとしていて、その結果、何の価値が上がるのかを探り、利用することでもある。
それは、19世紀はじめにイギリスの経済学者、デイヴィッド・リカードが国同士の比較優位を唱えるずっと前から、成長の原動力となってきた。
これまでの潤沢さは、他国の潤沢な資源や安い労働力による製品で成り立っていたが、今日の潤沢さは、シリコンチップと光ファイバーによる新しい製品によって作られている。
■潤沢さを理解し利用する
ここまで長々と説明してきて、最後はあっさり締めようと思う。
(いや、疲れたんだ・・昨日、知人の結婚式で深夜まで飲んで二日酔いっていうのもあり)
稀少なものと、潤沢なものの管理が重要だ。
いや、正確には、何を稀少なものとして、どういう潤沢さを利用するか、もしくはどういう潤沢さを醸成するかという視点である。
何か望むもののために、価値のあるものを実現しようとする時、その前段で、どういう潤沢さを獲得すべきなのか、ということである。
潤沢さそのものは目的ではないが、目的を達成するために必要なものである。
さらにいえば、潤沢さは目的の達成を保証しない。
だが、潤沢さの勢いは留まることを知らない。
あらゆる業界で潤沢さの波は押し寄せてくる。
しかし、人間は潤沢さには気づけないから、潤沢さを理解しようとしなければ、押し流されてからその波に気づくことになる。
そして潤沢さは勝利するであろう。
「フリー」を武器にできるもできないも、この「潤沢さ」理解し、利用することができるかどうかにかかっている。



















