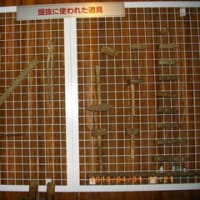庄司和晃は「方言の授業」に続く「コトワザの授業」という教育的な実験の渦中から、前者では何が可能か可能でないかを論じながら、コトワザには言語感覚を養うこととどまらず、「世界観・思想・指針・実践」にさおさす力を養うことを可能する性格が内蔵されていること発見しました。でも、このような性格はあらかじめ本書第Ⅲ部第2章「言語教育の体系化の歩み」の第Ⅰ節「コトワザの教育への展望をもつ」で想定していたことであって、それゆえの「小学校言語学(小学校哲学)」という一連の授業計画に対する命名であったわけです。ですから、ことわざの内蔵する多様な性格は、発見されたというより、教育的な実験の中から「再発見」されたという方が正しいと思います。
では、できることには限界があるという「方言の授業」は、言語感覚を養うための「ことわざ以前」の分野としてだけとどめ置かれたのでしょうか。そうではないようです。庄司は方言と比較することからコトワザの性格を確かめたあと、返す刀で再び「方言教育の可能性」の言及しているのです。それから第一次テキストの目次からうかがえる第三部の「遊びコトバ」の授業(「わたしたちのコトバを見直そう」)はどうなるのか、という問題も気になります。今回は、このあたりを確かめたい。9/15のブログで紹介した「方言の授業では何が可能でないか」の続きから引用します。
≪なお、思想というわけではないが、方言は単なる言語感覚以上のものを伝えるということも忘れてはなるまい。名称が成立するところには、そのものの形態や生態、あるいは比喩や俗信などが関与しているからだ。それらを少しくほりさげることによって、自然観や昔意識(世間観)を高めることにもなるからだ。≫(本書 九八頁)
方言の成立にはその「形態や生態」(あるいは比喩や俗信)が関与しているという言い方が庄司らしさを感じさせますが、そこを少しく掘り下げることによって、自然観や昔意識(世間観)を高めることに寄与できると書いています。その傍証としてか、引用に続いて柳田国男の業績を偲んで書いた臼井吉見の文章の一節を紹介しています。それは、アカトンボという方言の話(「赤とんぼの話」)についての話です。一つの方言の起りや広がりかたについて話をするためには、その言葉を調べるのにどんなに広い学問の背景が必要か、また一つの方言が移り変っていく背後に、どんなに幅の厚い暮しの歴史があるかを語ってくれて、おどろきとおもしろさを覚える、というものです。ここで庄司は、たった一つの方言が変遷していく背景に互いに結びつき積み重なり合っている人々の生活史のありようを方言の「形態や生態」と呼んだわけですが、このような方言に対する見方が世界観の育成に資する可能性を指摘しています。この柳田の「赤とんぼの話」は授業計画では、第一部「方言の授業」でとりあげる予定だった資料です。庄司は、テキスト作成段階で方言が「言語感覚以上のもの」を伝える言葉であることを熟知していた可能性があります。柳田国男を学んできた庄司からすれば当然の発想といえます(私はここを検討せずにきてしまいました)。庄司の「方言の授業」についての見直しはさらに展開していきます。
≪③方言の授業の今後について。
・方言の授業の教材としては、今のところアリジゴクなどは適当といえる。方言集と解説文がかなりな程度に整備されているといえるからだ。ただ、今回使用してみた柳田氏の「蟻地獄と子供」の読み物と馬場氏のアリジゴクについての解説文は、子どもたちがひとりで読めるような形にととのえていかなければならない。読み物や解説文は、語の背景を知る上においてきわめて重要なことだからだ。とくに、方言のように、思想のコトバといえないような語をあつかうときには必要にして不可欠のものといってよいからである。
・世界観教育という面からみると、方言に宿る生活史の厚味をどのようにとらえさせるかに、もう少し意を注いでいく必要がある。読み物が整備されてくれば、この点も多くの解決をみるであろう。
・方言を言語観賞教材としてみたらどうであろう。実用言語というよりは一種の鑑賞言語として教材化すれば、またそれなりの展望が開けてくるかもしれない。≫(本書 九九頁)
一つは、「読み物や解説文は、語の背景を知る上においてきわめて重要」だから、そのような読み物は子供がひとりで読めるような教材に整備する必要があること。二つは、読み物が整備されてくれば、「方言に宿る生活史の厚味」をどう子供にとらえさせるかについて、多くの解決をえるだろうこと。三つは、方言を実用言語というよりも観賞言語として教材化すれば、方言の授業も独自の展開が可能になっていくのではないか、ということ。以上の三つは、方言の授業を単に「コトワザ以前」と位置づけることにとどまらず、その独自性を具体的に追及しようとする意欲の表われと受けとることができます。たいしたことだと思います。
とくに三点目は、方言を観賞言語として教材化しその独自性を追及する授業として位置づけてはどうかという意見です。どういうことか推察してみると、方言を良いコトバの手本として見直すことを意味しているのではないでしょうか。もちろんすべての方言が良いコトバであるはずはないですから、代々の人々が肚で思っていることを素直に表現したコトバとして、したがって聴いてすぐにそれと分かり、おもしろく、覚えやすコトバの手本として学べる授業を構想してみてはどうか、そうすれば良いコトバを選ぶ目ばかりでなく良いコトバを作り出す担い手としての子供を育てることができる。方言の授業の「それなりの展開」とはこのようなことではなかったかと想像します。というのは、庄司はすでに柳田の国語教育論のいくつかを読んでいたと思うからです。(考えすぎかも) さて、「コトワザ以前」への関心は、第一次テキストの目次に予定されていた第三部「わたしたちのコトバを見直そう」(「遊びコトバ」の授業)についても、言及せずには済まないようです。
≪④方言の授業と他への影響について。
・方言の授業が今回以上に格好がついてくれば、いろいろな呼び名・遊びコトバ・ナゾナゾなどの授業への道もついてくるであろう。思想性のない、あるいは思想性にとぼしい言語をどうあつうかということがわかってくるからだ。形式的なものをどう教えるかにもかかわりがある。コトワザなどはそれ自体が教育的効用をもっている。思想的には独立した内容を具備しているといってもいい。どんなコトワザでもすべてそうだとはいいきれないものはあるにせよ、大半はそのように理解してもまちがいではない。だから、ある意味において、コトワザの教育はやりやすい。それ自体が実践への指針をもたらしてくれるからだ。そういう点で、方言などの思想性にとぼしいものは教えにくく、また興味を持続させるには困難さをともなう。文法もそのひとつに数えてよいかもしれない。≫(本書 九九頁)
ここには庄司特有の思考法が表われています。ある事柄についてハッキリそれが何かと言い当てることができないときの発想法、簡単にいえば対象が良く分からないときの考え方です。これまでの記述から見て取れることですが、コトワザというコトバの性格がよく分からなければ、「コトワザ以前」の方言の授業を通して考えます。逆に「方言以後」のコトワザの授業から方言の授業を見直しています。こういう方法をどう呼べばいいか。方言からコトワザへ、コトワザから方言へと眺めていくのですから、<往き帰りの構造>とでも呼んでおきましょう。
また一方で、子供の世界では大きな存在感を示す「いろいろな呼び名・遊びコトバ・ナゾナゾなど」のコトバ群が、方言やコトワザの周辺に存在します。これを「遊びコトバ」群と呼んでおきましょう。これをどう位置づけ、どのように性格を言い当てるか。庄司は「方言の授業」の新たな展開からその答えが見えてくるのではないかと書いています。なぜならば、方言と同じく「遊びコトバ」は思想性のとぼしいコトバ群だから、新たな「方言の授業」の展開が、授業における「遊びコトバ」の扱いを教えてくれるはずだ、というわけです。「遊びコトバ」を授業でどう扱えばよいか、とくに何か分かったわけではないのですが、方言という「思想性のとぼしいコトバ」の周辺に「遊びコトバ」を位置づけて、まだハッキリ掴むことのできない性格をとらえようという手法であることが分かります。これも後年からみれば、庄司和晃らしい思考法(研究法)として浮上してくるのはまずまちがいないことです。名づけて、<「以前以後」と「周辺」から考察する研究法>ではどうでしょうか。その構造はいうまでもなく<往き帰り>にあります。