復本一郎さんが「代表」をつとめる「鬼」の20周年記念会に参席しました。会場は日本工業倶楽部。古い由緒ある会場です。たしか10周年の会にも参席しました。横浜で祝賀会があったと思います。
復本一郎さんとは、2004年に、『三省堂・名歌・名句辞典』という辞典を一緒に作りました。短歌と俳句を一緒にした古典から現代までの、代表的な名歌・名句が引ける辞典です。
近年、残念なことに、歌壇と俳壇の距離が遠くなっています。私が短歌を作りはじめた頃は距離が近く、たとえば高柳重信さん、金子兜太さんといったすぐれた先輩俳人と若い時代に出会う機会がありしました。幸せなことでした。
最近は歌壇・俳壇の距離が遠くなっています。この祝賀会でも、三枝昂之君の顔は見えましたが、歌壇の人は少ししか来ていませんでした。歌人も俳人も、お互いに忙しくなったからでしょう、だんだん付き合いが無くなってしまいました。
『名歌・名句辞典』はそんな現状を少しでも改善したい。そんな願いで編集をしました。そこそこ売れたようです(一度改版し、現在も発売中)。が、歌壇・俳壇の距離の改善には残念ながらほとんど役立ちませんでした。
最近、坪内稔典君と雑誌「短歌」で対談をして、歌壇と俳壇は疎遠になったけれども、俳句と短歌は内容的に似てきている、そんな話をしました。
俳句が「俳」の要素を希薄にして、まじめな文学をめざしはじめたこと。一方、短歌が口語化の波に呑み込まれて、格調の高さより現実との接点に言葉を働かせることに気をつかいがちになったこと。
このため、俳句と短歌は内容的に接近し、差異はわずかに型式、季語の有無ぐらいなってしまった、そんな話をしました。
復本さんは、一貫して「俳の精神」ということをくり返し言って来られました。私は復本さんの『子規のいる風景』『子規のいる街角』など、子規の「俳の精神」を日常性の中で確認する仕事を愛読してきました。
たとえば、「子規の天ぷら談話」という話。子規がしゃべった「天ぷら語源説」を紹介・分析しています。子規の「俳」の精神がきらきらしている話です。
子規が友人に得意になって、なぜ「天ぷら」というようになったか、教えてやろうということで、次のような話をしました。
ある男が店を出そうとして、関西で揚げ物と言っているけど、平凡なので、いい名前を付けて欲しいと山東京伝に頼んだ。すると京伝が、「お前はプラプラしている逐電した浪人」だから、電プラ、天ぷらがいいだろう、と言った、というんです。
いい加減なところが俳的な滑稽ですね。子規はこういう虚実いりまじった、不思議な話、変わった話が大好きだったのです。
復本さんのすごいところは、子規がいつ、どの本を読んでこのエピソードを知ったかを、徹底的に追求するところです。
そして、山東京伝の弟・山東京山の随筆集『蜘蛛糸巻』が、明治25年に刊行されたある随筆集成に収録されているのを突き止める。子規はその本でこのエピソードを知ったというのです。
「俳」「滑稽・戯れ」はいいかげんなものと思われがちですが、復本さんは史実を徹底的に調べて、「俳の精神」を厳密な考証の上に浮かび上がらせる仕事してこられました。
「鬼」20周年は、「俳の精神」を、鮮明な輪郭でふちどる彼の仕事がベースになっているのです。
写真は、当日参席した川本皓嗣、宇田喜代子、太田治子、高橋睦郎、斎藤慎爾、大串章氏ら。



復本一郎さんとは、2004年に、『三省堂・名歌・名句辞典』という辞典を一緒に作りました。短歌と俳句を一緒にした古典から現代までの、代表的な名歌・名句が引ける辞典です。
近年、残念なことに、歌壇と俳壇の距離が遠くなっています。私が短歌を作りはじめた頃は距離が近く、たとえば高柳重信さん、金子兜太さんといったすぐれた先輩俳人と若い時代に出会う機会がありしました。幸せなことでした。
最近は歌壇・俳壇の距離が遠くなっています。この祝賀会でも、三枝昂之君の顔は見えましたが、歌壇の人は少ししか来ていませんでした。歌人も俳人も、お互いに忙しくなったからでしょう、だんだん付き合いが無くなってしまいました。
『名歌・名句辞典』はそんな現状を少しでも改善したい。そんな願いで編集をしました。そこそこ売れたようです(一度改版し、現在も発売中)。が、歌壇・俳壇の距離の改善には残念ながらほとんど役立ちませんでした。
最近、坪内稔典君と雑誌「短歌」で対談をして、歌壇と俳壇は疎遠になったけれども、俳句と短歌は内容的に似てきている、そんな話をしました。
俳句が「俳」の要素を希薄にして、まじめな文学をめざしはじめたこと。一方、短歌が口語化の波に呑み込まれて、格調の高さより現実との接点に言葉を働かせることに気をつかいがちになったこと。
このため、俳句と短歌は内容的に接近し、差異はわずかに型式、季語の有無ぐらいなってしまった、そんな話をしました。
復本さんは、一貫して「俳の精神」ということをくり返し言って来られました。私は復本さんの『子規のいる風景』『子規のいる街角』など、子規の「俳の精神」を日常性の中で確認する仕事を愛読してきました。
たとえば、「子規の天ぷら談話」という話。子規がしゃべった「天ぷら語源説」を紹介・分析しています。子規の「俳」の精神がきらきらしている話です。
子規が友人に得意になって、なぜ「天ぷら」というようになったか、教えてやろうということで、次のような話をしました。
ある男が店を出そうとして、関西で揚げ物と言っているけど、平凡なので、いい名前を付けて欲しいと山東京伝に頼んだ。すると京伝が、「お前はプラプラしている逐電した浪人」だから、電プラ、天ぷらがいいだろう、と言った、というんです。
いい加減なところが俳的な滑稽ですね。子規はこういう虚実いりまじった、不思議な話、変わった話が大好きだったのです。
復本さんのすごいところは、子規がいつ、どの本を読んでこのエピソードを知ったかを、徹底的に追求するところです。
そして、山東京伝の弟・山東京山の随筆集『蜘蛛糸巻』が、明治25年に刊行されたある随筆集成に収録されているのを突き止める。子規はその本でこのエピソードを知ったというのです。
「俳」「滑稽・戯れ」はいいかげんなものと思われがちですが、復本さんは史実を徹底的に調べて、「俳の精神」を厳密な考証の上に浮かび上がらせる仕事してこられました。
「鬼」20周年は、「俳の精神」を、鮮明な輪郭でふちどる彼の仕事がベースになっているのです。
写真は、当日参席した川本皓嗣、宇田喜代子、太田治子、高橋睦郎、斎藤慎爾、大串章氏ら。



















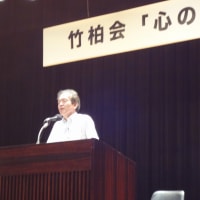


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます