音の遠鳴りについて。
ベルから出てくる音の音量は、いくらでも大きくなる気がする。
けど、マウスピースの振動量は限界があり、ある一定の振動量からはコントロール不能になる。
倍音列がキレイなほど、音の純度は高くなり、
究極は、倍音を含まないというのが一番純度の高い音となる。
けど、楽器の構造上それはあり得ない。
リードが振動すればするほど倍音は増えていく。
硬いリードでは、純度の高い音がでるけど、振動量は少ない。
音圧は、音が空気を振動させる強さで、マウスピースは地震でいうマグニチュードにあたる。
マグニチュードが地表に近ければ、その真上の地面は割れる。
けど、遠くの地表は微妙な揺れであるはず。
大きなマグニチュードの地震が地殻の奥で起これば、遠くの地表にも充分わかるくらいの地震となる。
マウスピースから発生する、音の空気を振動させるエネルギーが強ければ強いほど、
エネルギーは遠くまで波を作る。
アクセントには本来津波のような波が起こるはず。
エネルギーを作るには、ベルに向けてではなく、もっと深い所に震源地を持たなくてはならない。
ベルから出る音量に向けるエネルギーは、遠くまで鳴るエネルギーを優先するとなると、無駄なエネルギーになる。
音とは、周波数。
基音、倍音、それぞれの波がDNAのように複雑に絡み合って音楽を構成する。
つまり、音は細胞。
そこにビブラートをかけると、波が大きく波打つので、目立つ。
純度の高い音があればあるほど、、、、
良くできたオーケストラには、乱れた倍音を持つ音は目立ってしまう。
乱れた倍音列=ノイズ。
逆に、爆音でノイズを出すクラブなどでは、純度の高い音は聴こえない。
つまり、倍音列が綺麗だと、空気を押す波の強さの公倍数が合うので、波を打つ力が強くなる。
かといって、楽器や個人によって、同じ倍音列のバランスを持つ人は一人としていない。
それが、個性であり、音色となる。
あとは、それをどれだけ純度をあげることができるか、となる。
そして、遠鳴りする音は近くで聴いてもうるさくないというのは、迷信ではなく、真実であると思う。
そのかわり、回りがうるさいと聴こえない。笑
力の使い方によって、エネルギーを今流行りの空震に向けることによって音量は小さくなる。
ふくよかな音色は、例外もあるけど、倍音がやたらに多いので近鳴りする。
例外もあるけど(プロ)
遠くで聴いてふくよかな音色はきっと素晴らしい音なんだろうと思う。
音の芯とは、息である。
響きとは出た音が作るものである。
超人的なポテンシャルをもっていない僕らはまぁ、とにかく様々なプロのセッティングやバランスや奏法などをもっと研究しなければならない。
そして、最終的に残る、四色問題のような、原愽巳先生というものを解決しなくてはならない。
ベルから出てくる音の音量は、いくらでも大きくなる気がする。
けど、マウスピースの振動量は限界があり、ある一定の振動量からはコントロール不能になる。
倍音列がキレイなほど、音の純度は高くなり、
究極は、倍音を含まないというのが一番純度の高い音となる。
けど、楽器の構造上それはあり得ない。
リードが振動すればするほど倍音は増えていく。
硬いリードでは、純度の高い音がでるけど、振動量は少ない。
音圧は、音が空気を振動させる強さで、マウスピースは地震でいうマグニチュードにあたる。
マグニチュードが地表に近ければ、その真上の地面は割れる。
けど、遠くの地表は微妙な揺れであるはず。
大きなマグニチュードの地震が地殻の奥で起これば、遠くの地表にも充分わかるくらいの地震となる。
マウスピースから発生する、音の空気を振動させるエネルギーが強ければ強いほど、
エネルギーは遠くまで波を作る。
アクセントには本来津波のような波が起こるはず。
エネルギーを作るには、ベルに向けてではなく、もっと深い所に震源地を持たなくてはならない。
ベルから出る音量に向けるエネルギーは、遠くまで鳴るエネルギーを優先するとなると、無駄なエネルギーになる。
音とは、周波数。
基音、倍音、それぞれの波がDNAのように複雑に絡み合って音楽を構成する。
つまり、音は細胞。
そこにビブラートをかけると、波が大きく波打つので、目立つ。
純度の高い音があればあるほど、、、、
良くできたオーケストラには、乱れた倍音を持つ音は目立ってしまう。
乱れた倍音列=ノイズ。
逆に、爆音でノイズを出すクラブなどでは、純度の高い音は聴こえない。
つまり、倍音列が綺麗だと、空気を押す波の強さの公倍数が合うので、波を打つ力が強くなる。
かといって、楽器や個人によって、同じ倍音列のバランスを持つ人は一人としていない。
それが、個性であり、音色となる。
あとは、それをどれだけ純度をあげることができるか、となる。
そして、遠鳴りする音は近くで聴いてもうるさくないというのは、迷信ではなく、真実であると思う。
そのかわり、回りがうるさいと聴こえない。笑
力の使い方によって、エネルギーを今流行りの空震に向けることによって音量は小さくなる。
ふくよかな音色は、例外もあるけど、倍音がやたらに多いので近鳴りする。
例外もあるけど(プロ)
遠くで聴いてふくよかな音色はきっと素晴らしい音なんだろうと思う。
音の芯とは、息である。
響きとは出た音が作るものである。
超人的なポテンシャルをもっていない僕らはまぁ、とにかく様々なプロのセッティングやバランスや奏法などをもっと研究しなければならない。
そして、最終的に残る、四色問題のような、原愽巳先生というものを解決しなくてはならない。














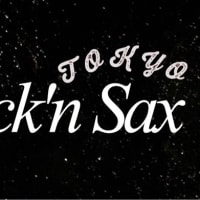





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます