なりますよ!私の2人の子は学びは全てネット+私のレクチャーです。学校の授業では学んでいません!RT @mirai_list: インターネットは発達障害の人が社会経験を積む手段の1つになりうると思います。ネットの罠から自分を守る手段を教わって、身につけた上での話ですが。 #発達障害
@mirai_list 娘は不登校以来知識習得はネットで、更に疑問点は私への質問。息子は小2からネットを始めて、好きな電車を通じて地理も詳しいです。書くことは苦手ですが漢字もかなり読めます。分からないことは質問して来ます。ローマ字入力も全て自力マスターです。自閉症児の力ですね!
@mirai_list 自閉症は基本的に怖がり、用心深いのです。最初は包丁もガスコンロも苦手でした。しかし、或る転機で変わります。言い聞かせて変わる訳では有りません。必要性が彼らを変えます。だから『明日から~する』と自発的に言った時は断固たる有言実行の男ですね(笑)!
→だから、振り回され、溺れ、淫してしまえば、嗜好品はもはや、ちょっとした遊び、生を歓びとするものではなくなってしまう。そもそもが、死を抱え込んでいるからこそ生は織りなされるのであり、わたしたちは、苦痛の最中にあってもなにものかに美を感じることもできるし、→
→理不尽に対して激しい怒りを感じながら、同時に笑いを生み出すことすらできるのだ。それが生きる技術である。必要か不必要かという基準ではなく、健康にいいか悪いかということでもなく、少々の傾きや乱れや歪みを抱えながら、食事とは異なったものを嗜むということ、→
→それに割く時間は、わたしたちが自分の外側との釣り合いを保つための、いわば、綱渡りのときにもつ棒のようなものだろう。※引用は以上。長々と恐縮ですが、雑賀さん独特の言語表現が味わい深く、備忘録的に残しておくことにしました。
@mirai_list 更に言えば自閉症児が劇的に変わるのは絶妙なタイミングでの好奇心の芽生えだと思います。ネットは好奇心の宝庫だから、自閉症児には親和するのだと思います。
今日の臨床心理学の主流は、「症状をとる」とか「認知の障害の特性に応じた訓練」ばかりだ。それはそれで大切だが、こういう傾向「だけ」になることは、臨床心理学をダメにするのだ。この世界に、存在し、想い、思い、感じ、考えて、生きている「私たち」という「不思議」が忘れられているからだ。
セラピストとして誰かの前に立つ時に、生きること、存在することにつきまとう不確かさや不安に想いを巡らせたことがなくて、はたして心理療法家として役に立てるのか(特に、統合失調症の患者さんを前にした時に)?否、と思う。しかし若いセラピストのどれ程の人に、こんな話が通じるのだろうか。
同業者に笑われる覚悟で書く。なぜ、自閉症の人は、これ程までに「人間」を避けなければならないのか?電車にあれ程の関心を向けるのに、どうして人の目を見つめることは避けるのか?そこに臨床家として、何かしらの「恐れ」や「不安」を見ようとしてはいけないのか?「過敏性」で済ますのか?
私はもちろん、自閉症を養育者の関わりに帰すことはない。しかし彼らが、何かの理由で人とつながることが難しいために、我々の手が届かないことが彼らの発達を促し損ねるとは思う。だから、つながれたら何かが動き出すと信じる。それは容易でないとしても。だから、私は彼らのあり方を理解したい。
自閉症ということの中には、存在することの根源に関わる秘密があるのではないか?今日、臨床心理の世界でこんな発言をすることは時代遅れで笑うべきことなのだ。しかし、私は自らに問い続ける。あなたもそんな臨床家であってほしいと、ヴァイジーに話した。教えたいことは、教えられないことなのだ。
私は私の信じる臨床の道を行こうと思う。最新の知見や、神経心理学的視点を軽視したりはしないが、存在するとはあらゆる次元にまたがる、ただならぬことなのだから、そこから目をそらしたりしないでいたいのだ。
そういう私も、理解が届かず、思いめぐらせていることがある。自閉症のことだ。今日、自閉症臨床と言えば「認知の障害」という視点から訓練や刺激の提示の仕方から語られない。私はこれが嫌だ。これでは、「癖のある機械の取扱説明書」で、「人間」を扱っているみたいに見える。
@mirai_listディスレクシア、 ディスグラフィア、ディスカリキュアの人は劣等感、無力感が幼い頃から蓄積されますね!本人の側の障害と考えるか文化・社会・制度の対応能力の障害と考えるかですが…私は後者です。計算は全て自己の流儀。多数派のやり易さと私のやり易さは違う訳です。→
@mirai_list →ディスグラフィア(書字障害)の傾向が強かった私は板書のノート写しをカットして、教科書欄外のメモ方式で大学迄対応しました。それは自己主張を伴いました。私のディスカリキュア(算数障害)は恐らく書字の問題に関連していて、独自の計算方法で乗り切りました。→
@mirai_list →私の場合にはディスレキシアはなくて、読みはかなりの速さ。読字障害はアルファベットなどの横文字の識字に困難が伴うことが知られていますが日本語の場合はどうなのでしょうか?多数派の身体特性に合致した社会・文化・制度の運用上の問題を少数派の認知特性を→
@mirai_list →障害と呼ぶのは疑問です。認知・処理速度が平均以上ならば障害ではないと言うロジックでは、私の計算速度は速いので障害ではなく並み外れた能力と扱うのでしょう。すると平均的な認知処理速度・表記判別可能性がこの種の学習障害の本質で社会・文化・制度の運用の枠組→
@mirai_list →文化・社会・制度の運用上の便宜的な問題に過ぎないこれらの学習障害と呼ばれる人たちの特性に対する配慮、工夫が問われます。僅かな認知特性の人に対する配慮をしていては入試での公平性が担保出来ないと言うのならば私はその多数派の特性に適した入試制度は→
@mirai_list →差別的な制度だと思います!読み、書き、計算は学びの基本ですが、多数派向けの画一的指導方法がどれだけ人の心を傷付けて来たのでしょうか?『書は人なり』『努力に勝る天才なし』などは一面の真実を述べてはいますが…配慮・工夫に恵まれない人には傷付く言葉です。
@gorilabra @mirai_list 私の場合思考速度が書く速度を完全に上回って、キーボードの出現で安定。鉛筆、ペンでの思考は難問をジックリ考える時に向いていて実りある思索を運んできますが…既知の答えを書く時のもどかしさが悪筆に顕れます。書は人なりはトラウマでした(笑)!
@mirai_list さんの呟きを読んで感じるのは成功への見果てぬ夢です。私が20歳の時に訣別した生き方です。 【成功者になるよりも寧ろ価値の有る存在になることが大切です】-アインシュタインユニークで価値の有る人生が寛かです。コミュニケーションなど小さい小さい(笑)!
@mirai_list 誤作動でサブアカウントも同時に呟きましたね(爆笑)!此方は私の呟きのリザーブ用のサブアカウントです。昨日から誤作動しています(笑)!
@mirai_list 私は詩、短歌も嗜むのですが…キーボードでは難渋。難しい問題をジックリ考える時は手の動きと鉛筆の連動が発想を運んで来ます。学生時代の筆記解答は苦手。30年前共通一次の数学を試し解答したら20分で満点でした。何倍もの加点配慮ですよね!入試制度は矛盾だらけ(笑)
@mirai_list 私の数学の授業では学校方式の筆算が苦手で恐らく生徒の倍時間が必要な私が数学を指導する時の計算方法の違いを説明していました。『先生は頭が良いから独自な計算を思い付いた』との生徒の意見に『いや、頭が悪い劣等生だったから創意工夫が必要だった』と答えていました。→










 YOSH @yosh0316
YOSH @yosh0316 伊藤絵美 @emiemi14
伊藤絵美 @emiemi14 風あつめ @kazeatume
風あつめ @kazeatume



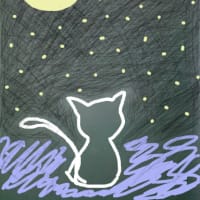
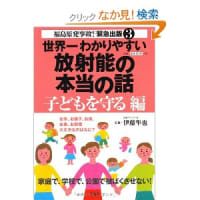
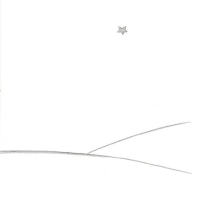
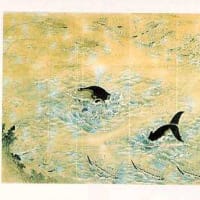

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます