所謂教育関係者と話をしていて、[100人居たら100通りのやり方]と私が話すと[そんなことは無い!多くても数通りで、出来る限り此方の指導に馴染む様に指導して来た!]と反論されて何時も呆れています。当事者の自己決定と並んで問われるの… twitter.com/i/web/status/1…
— YOSH(自閉症研究) (@yosh0316) 2018年7月7日 - 07:58
日本政府が後ろ向きなため子どもの権利条約は「児童の…」と訳されているが、民間団体は「子どもの権利条約」と略して呼んでいる。この条約での子どもは0歳から18歳まで。つまり赤ちゃんの時から権利があり、子どもは親の持ち物ではない。迷った時は、誰が困っていて、誰の問題なのか確認しよう。
— yone (@yone_oki5) 2018年7月7日 - 00:48
どんなことでも100人いたら100通りのやり方があり、その決定権は当事者にある。個々の状況によって援助が必要な場合は、助けてもらい、自分の力を引き出してもらえる相談者・介入者を選ぶ権利も当事者にある。誰かの指示に盲目的に従うことは、失うものが大きい。
— yone (@yone_oki5) 2018年7月7日 - 00:48
不登校に限らず、どのような分野でも立場によって主張が違うのは当たり前であり、考え方が同じになることはない。ただ、虐待被害や子どもの権利や不登校など子どもの人権に関わることは、誤解が生じやすいものでもあるので、確認しておきたい。以下のツイートを読んでいただけると幸いです。
— yone (@yone_oki5) 2018年7月7日 - 00:48














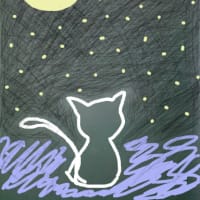
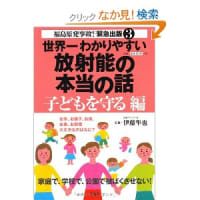
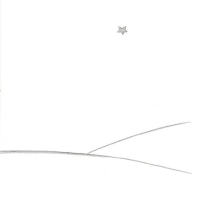
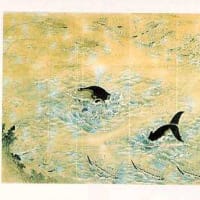

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます