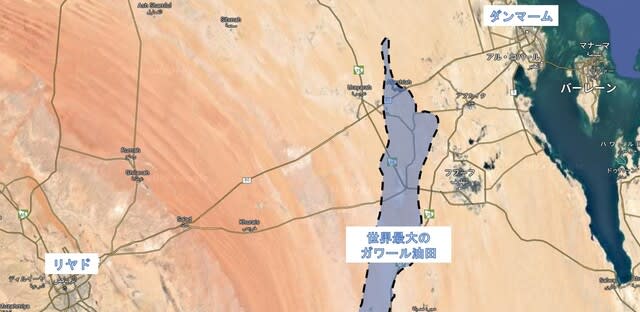スイスに来て、まず驚いたことは物価がすごく高いことです。ホテルは、日本のビジネスホテル程度の広さでありながら、150フラン(1フラン約85円)以上です。昼食では少なくとも15フランは払わなくてはなりません。庶民が利用するスーパーで扱う商品のほとんどが、日本のデパートの地下にあるマーケットより高いです。なぜこんなに高いのでしょうか。それは人件費が高いことだと指摘されていますが、むしろスイス国民が国の安全保障や環境保護にお金を払うことを厭わないからと思います。
スイスは、第1次世界大戦後、食料自給率を上げるため、輸入制限、輸出補助金などの保護政策をとったことは「ジュネーブ便り2」で述べました。それはかなり成功したのですが、しかし1990年代になると、周辺国からスイスの保護政策に対して反発がおき、これらの圧力に妥協せざるを得なくなりました。
そこで1996年には、新しい農業政策への移行のため国民投票が行われました。国民の意思で、保護政策を見直し、さらに環境保全にも重点を置くことになりました。新しい農業政策の柱は、(1)食料の供給、(2)自然生活基盤の維持、(3)農村の景観保全、(4)地域分散居住、です。つまりスイス人は、価格を下げることよりも、安全性、環境保護を優先したのです。将来のための政策ともいえます。
ジュネーブは、バス、トロリーバス、電気で動くトラム、列車といった公共交通が縦横無尽に走り、自動車が無くても暮らせます。バスの専用道路があり、渋滞しません。また改札が無いので、乗り降りがスムーズで、その分早く移動できます。観光客はホテルで配られる無料券で、滞在期間中好きなだけ公共交通を利用することができます。自転車専用道路が整備され、自転車通勤はごく一般的です。これらの政策は自動車を少なくし、環境を守り、観光産業を育てようというものです。

マッターホルンの麓の町ツェルマット(写真)では、環境保護のため、自治体の条例により自動車禁止です。市街地を走るのは電気自動車と観光用の馬車のみ。電気自動車は、エネルギー収支比が低く、エネルギーの観点からは得策でなく、また価格も高いものです。しかし電気自動車の生産地は別なので、ツェルマットへの排気ガスの影響はほとんど無くなります。つまり高くても環境保護を選んだのです。
将来のためにお金を使うスイス人。安い中国産に飛びつく日本人。お金でなんでも買えるかもしれませんが、その使い方によって買えるものが違ってくるのだと思います。スイス人の生き方は、モノを作ると同時に、後始末もするというもので、価格は上がりますが、将来も買えます。それに対し消費至上主義では、モノを安く大量に作ることに専念し、後始末は価格上昇につながるのでほどほどにということで、今は良いのですが、将来は「ケセラセラ」、「なるようになれ」、です。
2011年12月10日に書きました。
スイスは、第1次世界大戦後、食料自給率を上げるため、輸入制限、輸出補助金などの保護政策をとったことは「ジュネーブ便り2」で述べました。それはかなり成功したのですが、しかし1990年代になると、周辺国からスイスの保護政策に対して反発がおき、これらの圧力に妥協せざるを得なくなりました。
そこで1996年には、新しい農業政策への移行のため国民投票が行われました。国民の意思で、保護政策を見直し、さらに環境保全にも重点を置くことになりました。新しい農業政策の柱は、(1)食料の供給、(2)自然生活基盤の維持、(3)農村の景観保全、(4)地域分散居住、です。つまりスイス人は、価格を下げることよりも、安全性、環境保護を優先したのです。将来のための政策ともいえます。
ジュネーブは、バス、トロリーバス、電気で動くトラム、列車といった公共交通が縦横無尽に走り、自動車が無くても暮らせます。バスの専用道路があり、渋滞しません。また改札が無いので、乗り降りがスムーズで、その分早く移動できます。観光客はホテルで配られる無料券で、滞在期間中好きなだけ公共交通を利用することができます。自転車専用道路が整備され、自転車通勤はごく一般的です。これらの政策は自動車を少なくし、環境を守り、観光産業を育てようというものです。

マッターホルンの麓の町ツェルマット(写真)では、環境保護のため、自治体の条例により自動車禁止です。市街地を走るのは電気自動車と観光用の馬車のみ。電気自動車は、エネルギー収支比が低く、エネルギーの観点からは得策でなく、また価格も高いものです。しかし電気自動車の生産地は別なので、ツェルマットへの排気ガスの影響はほとんど無くなります。つまり高くても環境保護を選んだのです。
将来のためにお金を使うスイス人。安い中国産に飛びつく日本人。お金でなんでも買えるかもしれませんが、その使い方によって買えるものが違ってくるのだと思います。スイス人の生き方は、モノを作ると同時に、後始末もするというもので、価格は上がりますが、将来も買えます。それに対し消費至上主義では、モノを安く大量に作ることに専念し、後始末は価格上昇につながるのでほどほどにということで、今は良いのですが、将来は「ケセラセラ」、「なるようになれ」、です。
2011年12月10日に書きました。