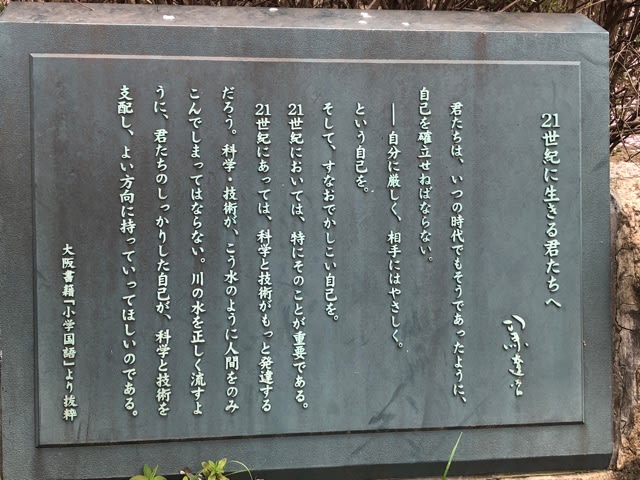
まことに小さな国が開化期を迎えようとしている。小さなといえば、
明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。
産業といえば農業しかなく、
人材といえば三百年の間、
読書階級であった旧士族しかなかった。
明治維新によって、
日本人は初めて近代的な
「国家」というものを持った。
誰もが「国民」になった。
不慣れながら「国民」になった日本人たちは、
日本史上の最初の体験者として
その新鮮さに昂揚した。
この痛々しいばかりの昂揚が分からなければ、
この段階の歴史は分からない。
社会のどういう階層のどういう家の子でも、
ある一定の資格を取るために、
必要な記憶力と根気さえあれば、
博士にも官吏にも軍人にも教師にもなりえた。
この時代の明るさは、
こういう楽天主義から来ている。
今から思えば実に滑稽なことに、
米と絹の他に主要産業のないこの国家の連中が
ヨーロッパ先進国と同じ海軍を持とうとした。
陸軍も同様である。
財政の成り立つはずがない。
が、ともかくも近代国家をつくりあげようというのは、
もともと維新成立の大目的であったし、
維新後の新国民達の少年のような希望であった。
この物語は、その小さな国がヨーロッパにおける
最も古い大国の一つロシアと対決し、
どのように振る舞ったかという物語である。
主人公は、あるいはこの時代の
小さな日本ということになるかもしれない。
ともかくも、我々は
3人の人物のあとを追わねばならない。
四国は伊予松山に、三人の男がいた。
この古い城下町に生まれた秋山真之は、
日露戦争が起こるにあたって
勝利は不可能に近いといわれた
バルチック艦隊を滅ぼすにいたる作戦を立て、
それを実施した。
その兄の秋山好古は、
日本の騎兵を育成し、
史上最強の騎兵といわれる
コサック師団を破るという奇蹟を遂げた。
もう一人は、俳句、短歌といった
日本の古い短詩型に
新風を入れてその中興の祖となった
俳人、正岡子規である。
彼らは明治という時代人の体質で、
前をのみ見つめながら歩く。
登って行く坂の上の青い天に
もし一朶の白い雲が輝いているとすれば、
それのみを見つめて坂を登って行くであろう。










