『ロベスピエール/毛沢東 革命とテロル』 
スラブォイ・ジジェク
長原豊、松本潤一郎/河出書房新書
¥1200
ジジェク氏はスロベニア生まれの先鋭的な革命左翼の思想家。マルクスのみかフロイト・ラカン派の精神分析理論を参照する。立場が違うためだろうが、その論理の大半は難解で、理路を忠実にたどって理解するのは極めて困難である。それでもジジェク氏は面白い。彼の思考の過程や結論に、ときどきハッと気づかされるものを発見して、知的な活性化を促されるからである。
その理由を考えてみると、あるいは、既成の左翼運動をふくめた現代資本主義体制と格闘する独自の視座から、鮮度の高い視点が生まれ出るからかも知れない。いいかえれば、声高に語られ、人心に潜りこんでくるドミナントでお決まりの意見や行動に、私たちはいい加減、うんざりしているのだ。
しかし、ハッとするものに遭遇するためには、難解な理路と付き合う膨大な努力が必要である。ジジェク氏の魅力を知りながら、ついツン読しがちな理由になっている(笑)。
1 毛沢東――無秩序のマルクス主義的君主(p7-61)
・われわれは存在しない物事についてしか語ることができない。(p38)
・われわれは……知らないことを……他者に伝えることができるのである。……失策としての無意識。(p38)
・われわれは、われわれが理解‐思考しないことについて語ることができるだけでなく、究極的には、それらについてのみ、すなわち虚構(イリュージョン)についてのみ、語る。(p39)
・真理は虚構(イリュージョン)の構造を有している(ラカン)。(p39)
※以上4個の文章は人間の認識にたいする精神分析的な箴言であるとも理解できるが、ジジェクの理路は理解が困難である。しかし、日々べらべらと語られる人間の認識内容がイリュージョンだとしたら、どうだろう。われわれは現実のひとコマについて語っているつもりで、ありもしない物語を捏造しているのだとしたら。とくにこの件は、深い悲しみや苦しみを体験しつつある人間にとっては、真実味を帯びてくるだろう。もちろん、ここでは「無意識」をキーワードに理解する必要がある。
・真の勝利(「否定の否定」)は、敵が諸君の言葉を喋りだすまさにその瞬間、起こるのである。この意味で、真の勝利は敗北における勝利である。(p40)
※「敗北における勝利」が、理路にどう組み込まれているかは理解しにくい。しかし、「諸君の言葉」が敵の言葉になった、まさにそのとき、「諸君の言葉」は勝利する。のみかドミナントな公式見解となるのだから、「諸君の言葉」は敵の言説空間に飲み込まれる。そのとき「諸君の言葉」は終焉を迎え、宴の後を経験するだろう。
2 バディウ――政界の論理(p62-109)
・民主的唯物論(バディウ/ブログ主)が猛烈に反撥するのは、諸世界のこの多様性を超える無限の普遍的「真理」が存在し得るという考え方であろう。政治においてそれは、その真理を普遍のものとして課す「全体主義」を意味している[からである]。(p86)
※哲学者のパディウ氏はジジェク氏の友人ということだ。その友人に一項を設け、批判的読解を試みている。この文章はバディウ氏のポストモダンな立場を代理したものだが、普遍的な真理の存在可能性が政治的には「全体主義」の存在可能性につながる、という指摘は驚異的である。いかなる場面でも、わたしたちは暗黙裡に普遍的な真理の存在可能性を仮定しているのだから。
それにしても、新たに「民主的唯物論」と呼ばなくてはならなかったバディウ氏の真意はどこにあるのだろう。引用した文章からは、「ポストモダニズムの唯物論」とでも読み替えられるように思われる。差異と多様性にもとづく「唯物論」であるかのように。
※なお、本文の後尾に独特のカッコでくくられた[からである]が見えるが、読みやすいようにと翻訳者が補った言葉だろう。以降、至るところに見られる。
・今日では、真の敵対はリベラル派の多文化主義と原理主義との間ではなく、そうした対立の領域そのものと[そこから]排除された[それを構成しもし]ている「第三」(急進的な開放的政治)との間に存在しているのである。(p87)
※この文章の読解も難しいが、二項対立への批判として述べられている。すなわち二項対立は、重要な第三項をつねに隠蔽し排除するのだという。これをラカンは「1+1+α」と定式化したらしい。また、『野生の思考』でレヴィ・ストロースが取り出した三つ組の婚姻原理、贈与の原理をも思い出す。いかなる問題も、ただちに正・反(賛成・反対)の二項対立に持ち込まれてしまうドミナントな社会現象を考える上でも、示唆に富む指摘だろう。
なおジジェク氏の文脈で、隠蔽され排除された第三項とは「革命」のことである。
・国家主義的イデオロギーに影響された行為者が、その固有の意思表示(ジェスチャー)を以ってシステム温存的な変革を目指したにもかかわらず、そうした介入の予期せぬ結果がシステムそのものの崩壊を加速的に促進させただけだったとしたら、どうだろう(ジョンストン)。(p94)
※このひとつの例がゴルバチョフのペレストロイカだった、とジジェクは考えている。情報公開という、社会体制を維持するささいな改革だったつもりが、やがてソ連を、その社会体制を、根底から覆す事態に至らせたからだ。こういうことはフランス革命のさなかにも起こったのだという。それが著書のタイトルの一部、『ロベスピエール』にも関連しているのだろう。
・体系(アーキテクチャー)。(p96)
※小さな単語へのルビが面白い。
・「熟成」とは敗北の蓄積に他ならない。(p99)
※失敗は成功のもと、という似たような譬えもある。ここで先鋭左翼のジジェクは、度重なる革命運動の敗北に言及している。日本でも、数々の民主主義的な改革を求める運動が失敗してきたが、この文章もジジェクらしく、失敗しつづける現実の裏面に改革への欲求が(ジジェクの場合には革命への欲求が)、無意識のように凝縮して強く潜在しつづけるのだと読み取れる。
・市場(しょうばい)。(p103)
※これも小さな単語のルビ。市場を「しょうばい」と読ませる著者はジジェクを除いて知らなかった。とくに金融市場は貨幣だけをやり取りする「しょうばい」であるが、それが世界的な不況を蔓延させた元凶なのだから、この世界の成り立ちは何度も再考してみる必要がある。
・本来の意味でドゥルーズ的な逆説は、真に「新たな」何ごとかは反復を通じてのみ出来可能である、という点である。反復が繰り返すことは、過去が「実際にそうであった」そのあり方ではなく、過去に内在し、その過去が現実のものとなることによって露見する、潜在性‐本質(ヴァーチュアリティ)である。この厳密な意味で「新たなもの」の出来‐創発(イマージェンス)は、過去そのものを変化させてしまう。すなわちそれは、・・・・・・過去において現実的だったこと(アクチュアリティ)と潜在的だったこと(ヴァーチュアリティ)の均衡を事後遡及的に変化させるのである。(p107)
・すでにキルケゴールにとっても、反復(受け取りなおし)は・・・・・・前に向かっての運動であって、「古きもの」の再生産ではなく、「新たなもの」の生産だった。・・・・・・反復は「新たなもの」の出来‐創発(が採る諸様式の一つ)であるだけではない。「新たなもの」は反復を通じてのみ出来‐創発するのである。この逆説にとって重要なことは、言うまでもなく、ドゥルーズが「潜在的なこと」と「現実的なこと」との差異として指示したこと――また当然のことだが、それは「精神‐気概(スピリット)」と「文字‐字義(レター)」の差異としても指示される――である。(p107)
※このあたりまで読んできて、もっとも扇情的に受け止めたのは、この「反復」への言及だった。過去と現在(または未来)との関係は、いつも悩みの種だったからだ。ドゥルーズやキルケゴール、ジジェクらによれば、現在(または未来)とは過去の反復であるとすらいえそうである。ただし、過去に潜在したものの反復として。
過去の潜在性が反復されて現在化したとき、過去は事後遡及的に改変される。書き直される、受け取り直される(キルケゴール)。ここに過去の形が、その読みの形が変わっていく秘密があるのだろうが、「新たなもの」は反復を通じてのみ出来‐創発するという指摘はセンセーショナルである。
この論理を演繹し、「精神‐気概(スピリット)」と「文字‐字義(レター)」の差異の指摘としてドゥルーズを引用した点もまたセンセーショナルである。「文字‐字義(レター)」とは、過去に出現した事実、歴史であり、それだけを取り上げて議論を終始させるのは、表面的な歴史的事実以上の何者をも出産禁止に処する行為と同じだろう。ところが日本でも、ある人の過去の発言や過去の文言のみを取り上げ、現在における存在の価値を計ろうとする者もいる。大切なのは、過去の発言や文言に潜在した「精神‐気概(スピリット)」、過去に潜在していた可能性なのだ。
※ここまでジジェクを読んできたが、文章は難解で、ほんとうに疲れる。こりゃまた、このあたりでツン読かもしれないなー(笑)。
3 ロベスピエール――恐怖という「神的暴力」(p110-173)
・人間を抑圧する者たちを罰する。それは慈悲である。彼らを赦すことは野蛮である。暴君たちの厳格はこの厳格だけを唯一の原理とし、共和政府の厳格は慈悲による。(p113)
――ロベスピエールの演説1794年より
※王侯貴族たちだけではなく、つぎつぎと政敵をギロチンにかけたロベスピエールの「狂気」がうかがわれる。こうした「狂気」から先鋭的な革命左翼は何を考えるのか、興味が湧く。
・レヴィナスが曖昧にしているのは隣人の怪物的性質であり、この怪物的性質を理由にラカンは、隣人に・・・・・・「物 Das Ding」を宛てたのである。この言葉に、恐怖小説(ホラー)のすべてを聴き採らねばならない。隣人とは、どんな家庭的な人間面(づら)にも潜在的に潜む、(邪悪な)「物」である。(p123-124)
※ジジェクは倫理的哲学者、レヴィナスの根底を批判する。したがって、われらがネット師匠、内田樹先生の根底も批判にさらされる(笑)。しかしブログ主としては、こうした批判的視点を歓迎する。なぜなら、考えることは信仰とは異なる行為だからである。むしろ信仰は考えの足かせになる。その意味で信仰は思考への不信を表明し、不可知論とも容易に短絡する。考えるとは、いかなる意味でも形而上学とは無縁である。
・レヴィナスが、本来的な意味で弁証法的な逆説において、その名高い「他なること[他者性]」が原因で捉え損なっているのは、あらゆる人間を根底で支える何らかの「同じであること」などではなく、根底的に「非人間的な」「他なること」そのものである。(p124)
※近現代における他者論は、アウシェヴィッツという出来事の理解を直接の動機として展開した。アウシェヴィッツの理解なくして近現代の思想は無力である。愛の哲学者レヴィナスは、それでも「なんじの隣人を愛せ」と隣人愛を説いたが、その根底は人類に共通する同一性の仮説だった。
一方、ラカン=ジジェクは、隣人の異質性=怪物性を他者論の根底に据えた。この一見すると矛盾する他者論の二項対立的な正体は何だろう。ジジェク自身、二項対立に隠蔽される第三項の重要性を指摘していたはずだ。
ここには、現代思想が取り組むべき他者論の重大な「不思議」が存在するのではないか。そして多分、歴史的な反復として、太古の人類に存在していたという「沈黙交易」がヒントになるだろう。「沈黙交易」は、ネット師匠の内田先生がご指摘になって、再び日本で有名な概念になった(笑)。
・アルチュセールとは対照的に、ラカンは理論的人間主義から実践的反人間主義への移行を遂げる。それは、ニーチェが「人間的、あまりにも人間的」と呼んだ次元を踏み越え、人間の非人間的な核心に直面する、倫理への移行だった。この倫理は、人間存在に潜む怪物的性質、日常的には「アウシェヴィッツ」という概念-名前によって覆い隠されている現象で爆発する悪魔的次元をもはや否定することのない倫理であるだけでなく、さらに踏み越えて、こうした悪魔的出来事を断固としてその裡に取り込む倫理であることをも意味している。それをアドルノを以って敷衍すれば、アウシェヴィッツ以降になおも可能な一つの倫理を意味するだろう。ラカンにとってこの非人間的次元は、倫理の究極的な支えなのである。(p125)
※隣人の異質性というより、非人間的次元。もともと「人間」という概念は、特定の共同体における集団幻想である可能性を排除できない。西洋×イスラム、国家×国家、国家×国家内民族など、あいかわらず21世紀にも殺戮をともなう様々な対立があるが、互いが無意識に抱く集団幻想には注目する必要がある。
内田先生によれば、アウシェヴィッツは「あまりにも人間的な」出来事で、神の仕業ではありえず、神への信仰を捨ててはならないとレヴィナスは説いたらしい。こうして神は、人間世界から阻害された。人間世界の真実から神学は無縁になったのだ。とすれば、隣人愛を説く神は人間の真実を超越しているのだから、それは天上の真実になる。夢なのだ。夢ならば、ラカンらが説く怪物的な他者性と二項対立的には矛盾しない。現代思想の重大な「不思議」は、第三項の発見なくして、たちどころに解決された。だから嘘かもしれない(笑)。
・資本主義的不平等(「搾取」)は、「平等という原則に対する非原則的[無節操]な侵害」ではない。それは平等の論理に絶対的に内在しており、その首尾一貫した実現の逆説的な結果なのだ。・・・・・・マルクスの「ブルジョワ」[的な空想]社会主義に対する批判の決定的なコウ捍は、労使間で起きる資本主義的搾取がいかなる類の「不平等[不等価]」交換を含むことも必然としないということにある。この交換は完全に平等で「正しく」、観念的(原理的)には、労働者には自分が売っている商品(彼女の労働力)の価値が完全に支払われているのである。(p137)
※コウ捍・・・「コウ」は手偏に貢、ジジェクは「モメント」とルビを振っている。翻訳者はなぜ難解な漢字を宛てる?
※資本主義の労働力にたいする交換は完全に平等で「正しく」、観念的(原理的)には労働力の価値が完全に支払われている、とは驚異的な指摘だ。マルクスもそう考えているというのだから、賃上げ闘争は左翼の運動ではなく、せいぜい単なる資本主義の改善運動になる。赤いハチマキや腕章をまいて日比谷公園に集まりデモするメーデーは、労使間に必要とされる予定調和的な社会改革運動にすぎない。
こうなると、小刻みな賃上げに労働運動を特化した「連合」の組織率が低下の一方をたどることに不思議はなくなる。すでに労働者は理想的な「平等」を目指して、賃上げ(または賃下げ)のために資本によって組織化されているからだ。この日本に左翼は存在しない。資本と協調する派閥があるだけだ。
・ジャコバン派の急進的「恐怖(テロル」への依拠が、経済秩序の基礎(私的所有など)そのものを撹乱することができないみずからの無力を暴露する、ある種のヒステリックな非抑圧的感情の無意識的な行動化ではないとすれば、他に何と表現することが「できるだろう? そして同様のことが、政治的に粉飾された正しき(PC)のいわゆる「行き過ぎ」にも、当て嵌まらないだろうか? それらは人種差別や性差別の本当の諸原因(経済的な諸原因などの)を撹乱することからの退却を示してもいるのではないか? (p138)
※賃上げに特化された日本の労働運動が資本主義の撹乱になりえないとすれば、ある種のヒステリックな行動が派生する可能性がある。昔の過激な左翼運動がそれだっただろうし、何らかの社会変革を目指したオウム事件も心理的な関係を持っていたかもしれない。長引く不況に苦しんでいる日本に左翼が存在しないとすれば、文化・社会批判に粉飾された奇妙な集団ヒステリーが起こる可能性は高い。大阪の「平成維新」や名古屋の「減税政党」はどうだろう?
また、政治的に粉飾された正しき(PC)のいわゆる「行き過ぎ」の指摘にも意味は広がる。狂信的とも見えるときがある「動物愛護」運動、「反グローバリゼーション」、アグネスらを表に立てた児童虐待への抗議行動、「セクハラ」「パワハラ」など、人がPC的な行動にヒステリックになるのが不思議だった。これらすべて、社会の根底的な変革に触れられないためのヒステリー症状と理解できる。これら不徹底なPC運動は、そのためモグラ叩きの様相を呈するわけだ。
・ある法が人民の集会に提案されるとき、人民に問われていることは、正確には、彼らが提案を承認するか拒絶するかということではなく、それが人民の意志たる一般意志に合致しているかいないか、ということなのである。・・・・・・したがって、私の意見と反対の意見が勝つ場合には、それは、私が思い違いをしていたこと、私が一般意志だと思っていたものがじつはそうではなかったということを、証明しているにすぎない。――『社会契約論』ルソー(p140)
※知る人ぞ知るルソーの『社会契約論』。ジャコバン派の、ひいてはスターリンの恐怖政治が、ルソーを哲学的な系譜にしているとジジェクは批判する。上に引用された投票に対する意見は、現在の日本でも大声で語られるから面白い。たとえば戦後64年にわたって自民党が支持されたのだから、日本人は原発に賛成してきたのだ、とか。菅が首相なのだから、すべての民主党員は菅政権に忠誠を尽くすべきだとか(笑)。これらの意見は、ルソーに哲学的系譜をもった全体主義的恐怖政治であると。
ここでは、投票行為によってはじめて構成される意見を、あらかじめ存在していた「一般意志」と理解する点にルソーのペテンがあるとジジェクは考えている。とすれば、過去の一般意志と現在の一般意志が180度違っていたら、互いに相反する一般意志が複数存在することになる。「一般」と「一般」が一般を争う、特殊な闘争が巻き起こる(笑)。思想家ルソーは、もう当てにならない。
・ここでの「全体主義的」陥穽は事実確認(コンスタティブ)と行為遂行(パフォーマティブ)との短絡である。投票手続きを決断の遂行的行為ではなく、事実確認行為、すなわち一般意志とは何かについての(推測的)・・・・・・意見を表明する行為と理解することによって、ルソーは少数派に留まる人びとの諸権利をめぐる行き詰まりを回避している。・・・・・・彼らは一般意志の本性に関して自分たちが思い違いをしていたということを学ぶというわけである。(p141)
※ルソーの言説によれば、投票行為によって常に少数派の意見と願いは多数派に圧殺されるべきである。そこで投票の前に各種の宣伝を通じて多数派工作が行われるのが、市民や政治家の常態となる。人びとは常に多数派側につこうとする。株式投資と同じ行動パターンである。現代人が見せる、じつに興味深い症状といえる。少数派の圧殺と損失が無慈悲に断行されるので、人びとは恐怖しているのだ。つまり、人びとの「一般意志」を見失わないようにと。こうして「一般意志」は行為遂行的に形成され、株式の価値は、多数派の一致した思惑にしたがって上下する(笑)。ここに実現する「一般意志」を、ジジェクは事実確認と行為遂行との短絡の結果だと批判し、ルソー思想の「全体主義的」陥穽だと理解する。
少数派の意見は誤っているので、少数派は圧殺され多数派に従うべき――少数派を存在していないとする恐ろしい思想は、行為遂行的に形成される決断の結果をつうじて、あたかも投票の前に「一般意志」が存在していかのような錯覚(事実確認行為)に基づく、という指摘は大いに参考になるだろう。この問題は、偶然と必然などとも関係していると思われる。または、過去の偶然を説明するための物語(イリュージョン)。
・一般意志のこうした実体化と予定説という宗教的観念との平行関係には瞠目せざるを得ない。予定説の場合、運命とは過程に先行する決断に実体化されるものでもあって、その結果、諸個人の行動において問題となるのは、彼ら個人の運命を行為遂行的に構成することではなく、先在する彼らの運命を発見(ないし推測)することである。何れの事例においても判然としないのは、偶発性の必然性への弁証法的反転、つまり、偶発的過程の結果が必然性の出現となるそのあり方である。事態が事後遡及的に必然「だったと振り返られることになるだろう」とされる、その方法が問題なのだ。(p141-142)
※とてもロベスピエール的な恐怖政治の理路のなかで読めないが、予定説が諸個人の行動において問題となるのは先在する彼らの運命を発見(ないし推測)することであるという指摘には、日本の若者論、「自分探し」を思い出した。一方で「自分探し」は、個人の運命を行為遂行的に構成することと理解される場合もある。こちら側なら問題はないとジジェクなら答えるだろう。自分を未来に向けて大いに構成していけばいい。
過去の偶発的過程が、「あれは必然だったのだ」と振り返られるその方法は、確かに問題にされるべきである。
・運命(ひつぜん) (p142)
※ちいさなルビ遊び。
・ある出来事が起これば、その出来事はみずからが不可避だったという仮象を創り出す先行的連鎖を[事後遡及的に]創造する。これは、・・・・・・偶発性と必然性に関わるヘーゲル弁証法の提要である。(p142-143)
※現実に起こった出来事は、事後遡及的に不可避だったと思い込む(思い込まされる)ものだ。この精神の態勢が「必然性」と「運命」の概念を産み落とす。この精神は、過去の原因について思索する自然科学を発展させたが、社会や日常の出来事にまで単純に敷衍するのは、はなはだしく危険なのだ。
・自由とは、そのもっとも根源(ラディカル)においては、ある者(物)の「運命」を変える自由なのである。(p143)
※ラカン‐ジジェク的な他者論を参照。こうなると、人間の「自由」すらうっかり主張できない。「自由」の主張は、他者の自由を奪って運命を変えようとする怪物的な主張にもなるからだ。人間の自由すら、軽率に「大文字の他者」とするわけにはいかない。
なおジジェクの文脈そのものは、神学的な予定説と関係している。すなわち、人間の運命は「自由」によって変更可能である、という具合に。

スラブォイ・ジジェク
長原豊、松本潤一郎/河出書房新書
¥1200
ジジェク氏はスロベニア生まれの先鋭的な革命左翼の思想家。マルクスのみかフロイト・ラカン派の精神分析理論を参照する。立場が違うためだろうが、その論理の大半は難解で、理路を忠実にたどって理解するのは極めて困難である。それでもジジェク氏は面白い。彼の思考の過程や結論に、ときどきハッと気づかされるものを発見して、知的な活性化を促されるからである。
その理由を考えてみると、あるいは、既成の左翼運動をふくめた現代資本主義体制と格闘する独自の視座から、鮮度の高い視点が生まれ出るからかも知れない。いいかえれば、声高に語られ、人心に潜りこんでくるドミナントでお決まりの意見や行動に、私たちはいい加減、うんざりしているのだ。
しかし、ハッとするものに遭遇するためには、難解な理路と付き合う膨大な努力が必要である。ジジェク氏の魅力を知りながら、ついツン読しがちな理由になっている(笑)。
1 毛沢東――無秩序のマルクス主義的君主(p7-61)
・われわれは存在しない物事についてしか語ることができない。(p38)
・われわれは……知らないことを……他者に伝えることができるのである。……失策としての無意識。(p38)
・われわれは、われわれが理解‐思考しないことについて語ることができるだけでなく、究極的には、それらについてのみ、すなわち虚構(イリュージョン)についてのみ、語る。(p39)
・真理は虚構(イリュージョン)の構造を有している(ラカン)。(p39)
※以上4個の文章は人間の認識にたいする精神分析的な箴言であるとも理解できるが、ジジェクの理路は理解が困難である。しかし、日々べらべらと語られる人間の認識内容がイリュージョンだとしたら、どうだろう。われわれは現実のひとコマについて語っているつもりで、ありもしない物語を捏造しているのだとしたら。とくにこの件は、深い悲しみや苦しみを体験しつつある人間にとっては、真実味を帯びてくるだろう。もちろん、ここでは「無意識」をキーワードに理解する必要がある。
・真の勝利(「否定の否定」)は、敵が諸君の言葉を喋りだすまさにその瞬間、起こるのである。この意味で、真の勝利は敗北における勝利である。(p40)
※「敗北における勝利」が、理路にどう組み込まれているかは理解しにくい。しかし、「諸君の言葉」が敵の言葉になった、まさにそのとき、「諸君の言葉」は勝利する。のみかドミナントな公式見解となるのだから、「諸君の言葉」は敵の言説空間に飲み込まれる。そのとき「諸君の言葉」は終焉を迎え、宴の後を経験するだろう。
2 バディウ――政界の論理(p62-109)
・民主的唯物論(バディウ/ブログ主)が猛烈に反撥するのは、諸世界のこの多様性を超える無限の普遍的「真理」が存在し得るという考え方であろう。政治においてそれは、その真理を普遍のものとして課す「全体主義」を意味している[からである]。(p86)
※哲学者のパディウ氏はジジェク氏の友人ということだ。その友人に一項を設け、批判的読解を試みている。この文章はバディウ氏のポストモダンな立場を代理したものだが、普遍的な真理の存在可能性が政治的には「全体主義」の存在可能性につながる、という指摘は驚異的である。いかなる場面でも、わたしたちは暗黙裡に普遍的な真理の存在可能性を仮定しているのだから。
それにしても、新たに「民主的唯物論」と呼ばなくてはならなかったバディウ氏の真意はどこにあるのだろう。引用した文章からは、「ポストモダニズムの唯物論」とでも読み替えられるように思われる。差異と多様性にもとづく「唯物論」であるかのように。
※なお、本文の後尾に独特のカッコでくくられた[からである]が見えるが、読みやすいようにと翻訳者が補った言葉だろう。以降、至るところに見られる。
・今日では、真の敵対はリベラル派の多文化主義と原理主義との間ではなく、そうした対立の領域そのものと[そこから]排除された[それを構成しもし]ている「第三」(急進的な開放的政治)との間に存在しているのである。(p87)
※この文章の読解も難しいが、二項対立への批判として述べられている。すなわち二項対立は、重要な第三項をつねに隠蔽し排除するのだという。これをラカンは「1+1+α」と定式化したらしい。また、『野生の思考』でレヴィ・ストロースが取り出した三つ組の婚姻原理、贈与の原理をも思い出す。いかなる問題も、ただちに正・反(賛成・反対)の二項対立に持ち込まれてしまうドミナントな社会現象を考える上でも、示唆に富む指摘だろう。
なおジジェク氏の文脈で、隠蔽され排除された第三項とは「革命」のことである。
・国家主義的イデオロギーに影響された行為者が、その固有の意思表示(ジェスチャー)を以ってシステム温存的な変革を目指したにもかかわらず、そうした介入の予期せぬ結果がシステムそのものの崩壊を加速的に促進させただけだったとしたら、どうだろう(ジョンストン)。(p94)
※このひとつの例がゴルバチョフのペレストロイカだった、とジジェクは考えている。情報公開という、社会体制を維持するささいな改革だったつもりが、やがてソ連を、その社会体制を、根底から覆す事態に至らせたからだ。こういうことはフランス革命のさなかにも起こったのだという。それが著書のタイトルの一部、『ロベスピエール』にも関連しているのだろう。
・体系(アーキテクチャー)。(p96)
※小さな単語へのルビが面白い。
・「熟成」とは敗北の蓄積に他ならない。(p99)
※失敗は成功のもと、という似たような譬えもある。ここで先鋭左翼のジジェクは、度重なる革命運動の敗北に言及している。日本でも、数々の民主主義的な改革を求める運動が失敗してきたが、この文章もジジェクらしく、失敗しつづける現実の裏面に改革への欲求が(ジジェクの場合には革命への欲求が)、無意識のように凝縮して強く潜在しつづけるのだと読み取れる。
・市場(しょうばい)。(p103)
※これも小さな単語のルビ。市場を「しょうばい」と読ませる著者はジジェクを除いて知らなかった。とくに金融市場は貨幣だけをやり取りする「しょうばい」であるが、それが世界的な不況を蔓延させた元凶なのだから、この世界の成り立ちは何度も再考してみる必要がある。
・本来の意味でドゥルーズ的な逆説は、真に「新たな」何ごとかは反復を通じてのみ出来可能である、という点である。反復が繰り返すことは、過去が「実際にそうであった」そのあり方ではなく、過去に内在し、その過去が現実のものとなることによって露見する、潜在性‐本質(ヴァーチュアリティ)である。この厳密な意味で「新たなもの」の出来‐創発(イマージェンス)は、過去そのものを変化させてしまう。すなわちそれは、・・・・・・過去において現実的だったこと(アクチュアリティ)と潜在的だったこと(ヴァーチュアリティ)の均衡を事後遡及的に変化させるのである。(p107)
・すでにキルケゴールにとっても、反復(受け取りなおし)は・・・・・・前に向かっての運動であって、「古きもの」の再生産ではなく、「新たなもの」の生産だった。・・・・・・反復は「新たなもの」の出来‐創発(が採る諸様式の一つ)であるだけではない。「新たなもの」は反復を通じてのみ出来‐創発するのである。この逆説にとって重要なことは、言うまでもなく、ドゥルーズが「潜在的なこと」と「現実的なこと」との差異として指示したこと――また当然のことだが、それは「精神‐気概(スピリット)」と「文字‐字義(レター)」の差異としても指示される――である。(p107)
※このあたりまで読んできて、もっとも扇情的に受け止めたのは、この「反復」への言及だった。過去と現在(または未来)との関係は、いつも悩みの種だったからだ。ドゥルーズやキルケゴール、ジジェクらによれば、現在(または未来)とは過去の反復であるとすらいえそうである。ただし、過去に潜在したものの反復として。
過去の潜在性が反復されて現在化したとき、過去は事後遡及的に改変される。書き直される、受け取り直される(キルケゴール)。ここに過去の形が、その読みの形が変わっていく秘密があるのだろうが、「新たなもの」は反復を通じてのみ出来‐創発するという指摘はセンセーショナルである。
この論理を演繹し、「精神‐気概(スピリット)」と「文字‐字義(レター)」の差異の指摘としてドゥルーズを引用した点もまたセンセーショナルである。「文字‐字義(レター)」とは、過去に出現した事実、歴史であり、それだけを取り上げて議論を終始させるのは、表面的な歴史的事実以上の何者をも出産禁止に処する行為と同じだろう。ところが日本でも、ある人の過去の発言や過去の文言のみを取り上げ、現在における存在の価値を計ろうとする者もいる。大切なのは、過去の発言や文言に潜在した「精神‐気概(スピリット)」、過去に潜在していた可能性なのだ。
※ここまでジジェクを読んできたが、文章は難解で、ほんとうに疲れる。こりゃまた、このあたりでツン読かもしれないなー(笑)。
3 ロベスピエール――恐怖という「神的暴力」(p110-173)
・人間を抑圧する者たちを罰する。それは慈悲である。彼らを赦すことは野蛮である。暴君たちの厳格はこの厳格だけを唯一の原理とし、共和政府の厳格は慈悲による。(p113)
――ロベスピエールの演説1794年より
※王侯貴族たちだけではなく、つぎつぎと政敵をギロチンにかけたロベスピエールの「狂気」がうかがわれる。こうした「狂気」から先鋭的な革命左翼は何を考えるのか、興味が湧く。
・レヴィナスが曖昧にしているのは隣人の怪物的性質であり、この怪物的性質を理由にラカンは、隣人に・・・・・・「物 Das Ding」を宛てたのである。この言葉に、恐怖小説(ホラー)のすべてを聴き採らねばならない。隣人とは、どんな家庭的な人間面(づら)にも潜在的に潜む、(邪悪な)「物」である。(p123-124)
※ジジェクは倫理的哲学者、レヴィナスの根底を批判する。したがって、われらがネット師匠、内田樹先生の根底も批判にさらされる(笑)。しかしブログ主としては、こうした批判的視点を歓迎する。なぜなら、考えることは信仰とは異なる行為だからである。むしろ信仰は考えの足かせになる。その意味で信仰は思考への不信を表明し、不可知論とも容易に短絡する。考えるとは、いかなる意味でも形而上学とは無縁である。
・レヴィナスが、本来的な意味で弁証法的な逆説において、その名高い「他なること[他者性]」が原因で捉え損なっているのは、あらゆる人間を根底で支える何らかの「同じであること」などではなく、根底的に「非人間的な」「他なること」そのものである。(p124)
※近現代における他者論は、アウシェヴィッツという出来事の理解を直接の動機として展開した。アウシェヴィッツの理解なくして近現代の思想は無力である。愛の哲学者レヴィナスは、それでも「なんじの隣人を愛せ」と隣人愛を説いたが、その根底は人類に共通する同一性の仮説だった。
一方、ラカン=ジジェクは、隣人の異質性=怪物性を他者論の根底に据えた。この一見すると矛盾する他者論の二項対立的な正体は何だろう。ジジェク自身、二項対立に隠蔽される第三項の重要性を指摘していたはずだ。
ここには、現代思想が取り組むべき他者論の重大な「不思議」が存在するのではないか。そして多分、歴史的な反復として、太古の人類に存在していたという「沈黙交易」がヒントになるだろう。「沈黙交易」は、ネット師匠の内田先生がご指摘になって、再び日本で有名な概念になった(笑)。
・アルチュセールとは対照的に、ラカンは理論的人間主義から実践的反人間主義への移行を遂げる。それは、ニーチェが「人間的、あまりにも人間的」と呼んだ次元を踏み越え、人間の非人間的な核心に直面する、倫理への移行だった。この倫理は、人間存在に潜む怪物的性質、日常的には「アウシェヴィッツ」という概念-名前によって覆い隠されている現象で爆発する悪魔的次元をもはや否定することのない倫理であるだけでなく、さらに踏み越えて、こうした悪魔的出来事を断固としてその裡に取り込む倫理であることをも意味している。それをアドルノを以って敷衍すれば、アウシェヴィッツ以降になおも可能な一つの倫理を意味するだろう。ラカンにとってこの非人間的次元は、倫理の究極的な支えなのである。(p125)
※隣人の異質性というより、非人間的次元。もともと「人間」という概念は、特定の共同体における集団幻想である可能性を排除できない。西洋×イスラム、国家×国家、国家×国家内民族など、あいかわらず21世紀にも殺戮をともなう様々な対立があるが、互いが無意識に抱く集団幻想には注目する必要がある。
内田先生によれば、アウシェヴィッツは「あまりにも人間的な」出来事で、神の仕業ではありえず、神への信仰を捨ててはならないとレヴィナスは説いたらしい。こうして神は、人間世界から阻害された。人間世界の真実から神学は無縁になったのだ。とすれば、隣人愛を説く神は人間の真実を超越しているのだから、それは天上の真実になる。夢なのだ。夢ならば、ラカンらが説く怪物的な他者性と二項対立的には矛盾しない。現代思想の重大な「不思議」は、第三項の発見なくして、たちどころに解決された。だから嘘かもしれない(笑)。
・資本主義的不平等(「搾取」)は、「平等という原則に対する非原則的[無節操]な侵害」ではない。それは平等の論理に絶対的に内在しており、その首尾一貫した実現の逆説的な結果なのだ。・・・・・・マルクスの「ブルジョワ」[的な空想]社会主義に対する批判の決定的なコウ捍は、労使間で起きる資本主義的搾取がいかなる類の「不平等[不等価]」交換を含むことも必然としないということにある。この交換は完全に平等で「正しく」、観念的(原理的)には、労働者には自分が売っている商品(彼女の労働力)の価値が完全に支払われているのである。(p137)
※コウ捍・・・「コウ」は手偏に貢、ジジェクは「モメント」とルビを振っている。翻訳者はなぜ難解な漢字を宛てる?
※資本主義の労働力にたいする交換は完全に平等で「正しく」、観念的(原理的)には労働力の価値が完全に支払われている、とは驚異的な指摘だ。マルクスもそう考えているというのだから、賃上げ闘争は左翼の運動ではなく、せいぜい単なる資本主義の改善運動になる。赤いハチマキや腕章をまいて日比谷公園に集まりデモするメーデーは、労使間に必要とされる予定調和的な社会改革運動にすぎない。
こうなると、小刻みな賃上げに労働運動を特化した「連合」の組織率が低下の一方をたどることに不思議はなくなる。すでに労働者は理想的な「平等」を目指して、賃上げ(または賃下げ)のために資本によって組織化されているからだ。この日本に左翼は存在しない。資本と協調する派閥があるだけだ。
・ジャコバン派の急進的「恐怖(テロル」への依拠が、経済秩序の基礎(私的所有など)そのものを撹乱することができないみずからの無力を暴露する、ある種のヒステリックな非抑圧的感情の無意識的な行動化ではないとすれば、他に何と表現することが「できるだろう? そして同様のことが、政治的に粉飾された正しき(PC)のいわゆる「行き過ぎ」にも、当て嵌まらないだろうか? それらは人種差別や性差別の本当の諸原因(経済的な諸原因などの)を撹乱することからの退却を示してもいるのではないか? (p138)
※賃上げに特化された日本の労働運動が資本主義の撹乱になりえないとすれば、ある種のヒステリックな行動が派生する可能性がある。昔の過激な左翼運動がそれだっただろうし、何らかの社会変革を目指したオウム事件も心理的な関係を持っていたかもしれない。長引く不況に苦しんでいる日本に左翼が存在しないとすれば、文化・社会批判に粉飾された奇妙な集団ヒステリーが起こる可能性は高い。大阪の「平成維新」や名古屋の「減税政党」はどうだろう?
また、政治的に粉飾された正しき(PC)のいわゆる「行き過ぎ」の指摘にも意味は広がる。狂信的とも見えるときがある「動物愛護」運動、「反グローバリゼーション」、アグネスらを表に立てた児童虐待への抗議行動、「セクハラ」「パワハラ」など、人がPC的な行動にヒステリックになるのが不思議だった。これらすべて、社会の根底的な変革に触れられないためのヒステリー症状と理解できる。これら不徹底なPC運動は、そのためモグラ叩きの様相を呈するわけだ。
・ある法が人民の集会に提案されるとき、人民に問われていることは、正確には、彼らが提案を承認するか拒絶するかということではなく、それが人民の意志たる一般意志に合致しているかいないか、ということなのである。・・・・・・したがって、私の意見と反対の意見が勝つ場合には、それは、私が思い違いをしていたこと、私が一般意志だと思っていたものがじつはそうではなかったということを、証明しているにすぎない。――『社会契約論』ルソー(p140)
※知る人ぞ知るルソーの『社会契約論』。ジャコバン派の、ひいてはスターリンの恐怖政治が、ルソーを哲学的な系譜にしているとジジェクは批判する。上に引用された投票に対する意見は、現在の日本でも大声で語られるから面白い。たとえば戦後64年にわたって自民党が支持されたのだから、日本人は原発に賛成してきたのだ、とか。菅が首相なのだから、すべての民主党員は菅政権に忠誠を尽くすべきだとか(笑)。これらの意見は、ルソーに哲学的系譜をもった全体主義的恐怖政治であると。
ここでは、投票行為によってはじめて構成される意見を、あらかじめ存在していた「一般意志」と理解する点にルソーのペテンがあるとジジェクは考えている。とすれば、過去の一般意志と現在の一般意志が180度違っていたら、互いに相反する一般意志が複数存在することになる。「一般」と「一般」が一般を争う、特殊な闘争が巻き起こる(笑)。思想家ルソーは、もう当てにならない。
・ここでの「全体主義的」陥穽は事実確認(コンスタティブ)と行為遂行(パフォーマティブ)との短絡である。投票手続きを決断の遂行的行為ではなく、事実確認行為、すなわち一般意志とは何かについての(推測的)・・・・・・意見を表明する行為と理解することによって、ルソーは少数派に留まる人びとの諸権利をめぐる行き詰まりを回避している。・・・・・・彼らは一般意志の本性に関して自分たちが思い違いをしていたということを学ぶというわけである。(p141)
※ルソーの言説によれば、投票行為によって常に少数派の意見と願いは多数派に圧殺されるべきである。そこで投票の前に各種の宣伝を通じて多数派工作が行われるのが、市民や政治家の常態となる。人びとは常に多数派側につこうとする。株式投資と同じ行動パターンである。現代人が見せる、じつに興味深い症状といえる。少数派の圧殺と損失が無慈悲に断行されるので、人びとは恐怖しているのだ。つまり、人びとの「一般意志」を見失わないようにと。こうして「一般意志」は行為遂行的に形成され、株式の価値は、多数派の一致した思惑にしたがって上下する(笑)。ここに実現する「一般意志」を、ジジェクは事実確認と行為遂行との短絡の結果だと批判し、ルソー思想の「全体主義的」陥穽だと理解する。
少数派の意見は誤っているので、少数派は圧殺され多数派に従うべき――少数派を存在していないとする恐ろしい思想は、行為遂行的に形成される決断の結果をつうじて、あたかも投票の前に「一般意志」が存在していかのような錯覚(事実確認行為)に基づく、という指摘は大いに参考になるだろう。この問題は、偶然と必然などとも関係していると思われる。または、過去の偶然を説明するための物語(イリュージョン)。
・一般意志のこうした実体化と予定説という宗教的観念との平行関係には瞠目せざるを得ない。予定説の場合、運命とは過程に先行する決断に実体化されるものでもあって、その結果、諸個人の行動において問題となるのは、彼ら個人の運命を行為遂行的に構成することではなく、先在する彼らの運命を発見(ないし推測)することである。何れの事例においても判然としないのは、偶発性の必然性への弁証法的反転、つまり、偶発的過程の結果が必然性の出現となるそのあり方である。事態が事後遡及的に必然「だったと振り返られることになるだろう」とされる、その方法が問題なのだ。(p141-142)
※とてもロベスピエール的な恐怖政治の理路のなかで読めないが、予定説が諸個人の行動において問題となるのは先在する彼らの運命を発見(ないし推測)することであるという指摘には、日本の若者論、「自分探し」を思い出した。一方で「自分探し」は、個人の運命を行為遂行的に構成することと理解される場合もある。こちら側なら問題はないとジジェクなら答えるだろう。自分を未来に向けて大いに構成していけばいい。
過去の偶発的過程が、「あれは必然だったのだ」と振り返られるその方法は、確かに問題にされるべきである。
・運命(ひつぜん) (p142)
※ちいさなルビ遊び。
・ある出来事が起これば、その出来事はみずからが不可避だったという仮象を創り出す先行的連鎖を[事後遡及的に]創造する。これは、・・・・・・偶発性と必然性に関わるヘーゲル弁証法の提要である。(p142-143)
※現実に起こった出来事は、事後遡及的に不可避だったと思い込む(思い込まされる)ものだ。この精神の態勢が「必然性」と「運命」の概念を産み落とす。この精神は、過去の原因について思索する自然科学を発展させたが、社会や日常の出来事にまで単純に敷衍するのは、はなはだしく危険なのだ。
・自由とは、そのもっとも根源(ラディカル)においては、ある者(物)の「運命」を変える自由なのである。(p143)
※ラカン‐ジジェク的な他者論を参照。こうなると、人間の「自由」すらうっかり主張できない。「自由」の主張は、他者の自由を奪って運命を変えようとする怪物的な主張にもなるからだ。人間の自由すら、軽率に「大文字の他者」とするわけにはいかない。
なおジジェクの文脈そのものは、神学的な予定説と関係している。すなわち、人間の運命は「自由」によって変更可能である、という具合に。












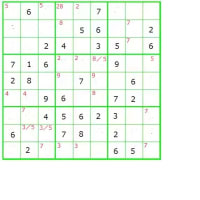
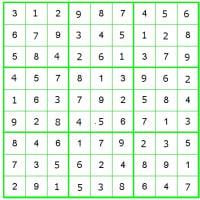
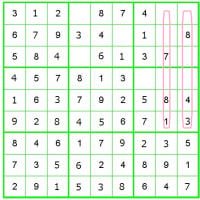
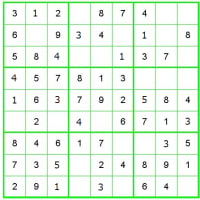
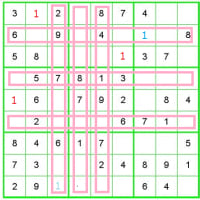
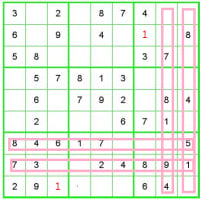
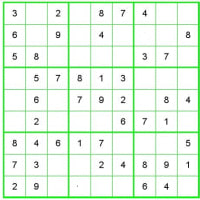

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます