現在、仕事場籠もり中です。
写真はあとでまた上げようと思います。
ストーブで部屋を暖めるのに午前中一杯くらいかかってしまいます。
暖かくないと接着が出来ないのです。
人間は平気でも、水は凍るのですね。
そのまま暖房し続けると深夜過ぎても暖かいのです。
よって、仕事がどうしても夜型になってしまうのです。
あと数日で、希少な戦前の国産ハーモニウムの修復が終わる予定です。
これは面白いです。
大手メーカー製ですが、特別生産品のようで、量産部品を手加工で改変しています。
リード(音源)は1列。
フォルテ(スウェルと共用、シャッターの開閉で音量をコントロールする仕組み)とトレモロが付いています。
エクスプレッションという、ハーモニウムのアイデンティティのようなストップが無いのは残念です。
まあ、後付で追加も出来ますけど。
このあたりは、その時代、その環境(国)の楽器製作の思想と音楽性の関係なので、後からいじるのは憚られるところではあります。
僕は既に2台のハーモニウムのピッチ変更をしています。
a=435Hzからa=442Hzへの変更です。
これにより、そのハーモニウムは当時(19世紀末から20世紀初頭)のピリオド楽器(時代楽器)としての価値を失いますが、現代の実用楽器になります。
これは、非常にデリケートな問題で、所有者様の理解と覚悟があ必要なのです。
こんな(バチ当たりかもしれない)ことをやっているのは、世界的に見ても僕くらいかも。
さて、寝るか。















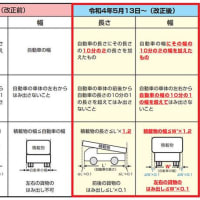




ひろにゃん様の車も新しくなってしまったのに、うちの車は相変わらずレトロです。夏に電磁クラッチを交換しました。
ところで、Aの音って・・・独奏のみなら良いんでしょうけれど・・・やつぱり周りと合わないとダメですよね。
うちにある楽器は、おおよそA=440Hzで・・・まぁ昭和の楽器ですから仕方がないし、「電子楽器」の類が「440Hz」なので、シーケンサー(or電子音源)に合わせて練習するには、ちょうど良いのです。
アコーディオンサークルの仲間の楽器はどうも442Hzのものが多く、一緒に弾くと「ミュセット」 (笑) になってしまいます。
でも、今でも電子楽器は440hzの様ですし、ポピュラー音楽界も440Hzという話を聞きますが・・・・
世界的には、どちらが優勢なのでしょうね。
幸い、年末に小型のアコ一台格安で譲ってもらったのが、442Hzなのでそれ使おうと思うのですが、・・ボタン式なので、ゼロから練習しなくては(涙)。
まさかJIS とか ISOで決める訳にはいかないでしょうから。
弦とか管なら、その場で調律変更可能でしょうけれど、「リード」となると、削らなくてはならないので、困りますね。
返事が遅くなりました。
現在ではポピュラー音楽はa=440Hz、クラシックはa=442Hzというのが一般的なようですね。
市民ホールのピアノなんか、演歌コンサートで440その後のクラシックコンサートのために442に調律変えなんてこともやっています。
あんまり頻繁なピッチ変更は良くないんですけどね。
ピッチと調律法を標準化したり共有したり出来るようになったのは、楽器の歴史に於いてごく最近の出来事です。
でも、合奏ということ自体は非常に長い歴史があるわけです。
そこにはきっと色々な工夫や努力があったのでしょうね。