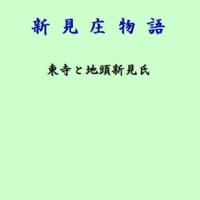1P~ 7P ユリノキの特徴 & CO2 吸収量・炭素C 固定量
8P~22P ユリノキの育苗・育樹体験記
1.ユリノキの特徴
ユリノキは北米中部原産の広葉落葉樹で、ユリの花に似た大輪を咲かせるので百合の木の和名がついています。又西洋では花がチューリップに似るとして(英名) American tulip treeと呼ばれます。
最大の特徴は葉形にあり、葉先が尖らず平らで直線(切形)であり “半纏” 、“軍配“ あるいは “Tシャツ”に似ています。この葉形で容易にユリノキと同定できます。
早生樹には広葉落葉樹のユリノキ、センダン、常緑針葉樹のコウヨウザン(広葉杉)等があります。
ユリノキは側枝が太くならず、幹が真っ直ぐ伸びる通直性を有し、自然樹形のままで通直で優良な材が得られます。幹を真っ直ぐに伸ばすための密植栽培あるいは間伐、枝打ち作業という伝統的林業形態からの解放が期待できます。
林業では、植樹後5回以上(年1回)の夏季下草刈り作業が不可欠ですが、重労働であるため林業の後継者不足やコスト高による不採算化の要因になっています。
ユリノキは成長が速いので下草刈りの回数は少なくて済みます。なお現在では樹高30cm~50cmに育てたコンテナ苗木の植樹と生分解性防草シートの活用により下草刈りからの解放が可能となっています。
コンテナ苗木とは露地育成苗木に代わる苗木生産方法で、コンテナ容器で育成して根鉢を形成させ、植樹の効率化と活着率の向上を図るものです。
1
スギ・ヒノキは植樹から伐採収穫期までおよそ50~60年を要し、自分の代に植林して収穫は子、孫の代になります。
これに比べ、ユリノキは約20年で成木に成長し収穫することができます。又、スギ・ヒノキ等常緑針葉樹は伐採後、切り株に萌芽しないので、伐採したら新たに苗木を植え付けなければなりません。
ユリノキはクヌギやコナラと同様に旺盛な萌芽力があり伐採株に多数萌芽します。1本だけ選択して残してやると再び成木に生長します(萌芽更新)。こうして一度苗木を植樹すると、自分の代で1~2,3回の収穫が期待できます。果樹栽培も同様ですが植樹から収穫期までの期間が短いことは、一代の間に”果実“を収穫できることであり、これは大きな魅力です。
ユリノキの魅力 蜜源 (アボック社flower museumより)
植樹後10年ほどで花を咲かせるようになり、樹齢20年になると1本の木で3kg~4kg の蜜を分泌します。この半量をミツバチが採蜜するとして1.5kg~2kg の量になります。30本の成木があれば、ミツバチの一群(西洋蜜蜂-3万~3.5万匹)は 45kg~60kg の蜂蜜を集めます。
花は蕾が順次開花していくので樹全体の花期は20日以上と長い。
2
2.ユリノキの温暖化抑制効果―CO2吸収と炭素C固定
A. ユリノキのCO2吸収力と炭素C固定力を検証します。
a. 成長速度
ユリノキ 樹齢20年で胸高直径40cm~50cm に成長
杉 樹齢20年で胸高直径 17cm 樹齢50年で胸高直径 30cm
檜 樹齢20年で胸高直径 14cm 樹齢65年で胸高直径 40cm
(標高、斜面の向き、土質、固体等により差が出る)
b. ユリノキの CO2 吸収量および 炭素C 固定量を算出
植樹して20 年後(樹齢20年)に、直径 40cm~50cm 長さ4mの材木を収穫すると仮定して、CO2 吸収量および 炭素C 固定量を算出してみます。計算式は略式で結果は概数になります。なお枝や端材は生物資源(バイオマス bio mass)として利活用するので CO2 は循環します。葉や根は分解して腐葉土となり地力・保水力に寄与します。
収穫材木の容積 = (断面積 )×長さ
= π ×0.2×0.2×4=0.5~0.8㎥ 平均0.65㎥/本
20年間の炭素C固定量 (容積密度、炭素割合は概数)
= 容積×容積密度(0.35)×炭素含有割合(0.5)
= 0.65㎥×0.35t/㎥ ×0.5=0.11t →110kg/本
20年間の CO2吸収量(CO2:C=44:12 として)
= 110kg×44/12 = 403kg → 400kg/本
年間炭素C固定量=110kg/20年= 5.5kg/本/年
年間1ha/1000本当たり炭素C 固定量=5.5 t /ha/年
(年間の CO2 吸収量 = 400kg/20年= 20 kg/本/年)
年間1 ha/1000本当たり CO2 吸収量 = 20 t /ha/年
3
c. スギの CO2 吸収量および 炭素C 固定量を算出
<林野庁の発表データとは若干差があります>
植樹50年後(樹齢50年)に直径30cm、長さ4mの材木を収穫すると仮定し算出。(容積密度、炭素含有割合は同じとみなす)
収穫材木の容積 =π × 0.15×0.15×4m =0.28㎥/本
50年間の 炭素C 固定量
= 容積×容積密度(0.35)×炭素含有割合(0.5)
= 0.28㎥×0.35t/㎥×0.5 = 0.05t/本→50kg/本
50年間の CO2 吸収量=50kg/本×44/12=180kg/本
年間の炭素C固定量=50kg/本 /50年=1kg/本/年
年間1ha1000本当たり 炭素C 固定量= 1 t /ha/年
年間の CO2 吸収量=180kg/本 /50年=3.6kg/本/年
年間1ha1000本当たり CO2 吸収量= 3.6 t/ha/年
ユリノキとスギの1ヘクタール当たり1年間の 炭素C 固定量およびCO2 吸収量 を比較する。
ユリノキ 炭素 C固定量 5.5 t /ha/年 CO2 吸収量 20.0 t /ha/年
スギ 炭素 C固定量 1 t /ha/年 CO2 吸収量 3.6 t /ha/年
CO2 吸収量の差 16.4 t/ha/年[20t/3.6t=5.5倍]
4
d. CO2 排出量 の規制 (パリ協定2020年~目標)
日本は20年のパリ協定で CO2 排出量を2030年に3.4億t削減することを公約しています。その内人工林による CO2 吸収を2600万t/年 (7.6%) と目論んでいます。
日本の森林面積は国土の 67%の2500万haで、その4割の1000万haが人工林ですが、安価な外材の輸入政策により林業経営は成り立たず、放置・荒廃化が進んでいます。
2019年度の国産材供給量2200万㎥の内、71%の1570万㎥がスギ・ヒノキ(スギ:ヒノキ=81:19)です。
今後も年間1570万㎥のスギ・ヒノキ材の供給を維持するには、人工林1000万ha の内、毎年5.6万haのスギ・ヒノキを伐採し、その跡に毎年再植林して森林を更新することが求められます。
1haの収穫材容積=0.28㎥/本×千本/ha=280㎥/ha
1570万㎥/280㎥/ha = 5.6万ha
3.スギ・ヒノキから早生樹への樹種転換
スギ・ヒノキの伐採跡地への植林樹種を CO2 吸収量の大きい早生樹 (ユリノキ・センダン、コウヨウザン等) に置き換えるとどうなるでしょうか。ユリノキで計算します。
毎年5.6万ha のスギ・ヒノキの人工林が早生樹人工林に置き換わるとすると、20年でおよそ現在の人工林面積1千万haの1割が早生樹林に置き換わります。(5.6万ha/年×20年=112万ha)
これによる CO2吸収量 の変化を見てみます。
ユリノキとスギの CO2 吸収量の差は年間16.4 t/ha でしたので、20年後の年間 CO2吸収量 は1800万t/年 増となります。
(16.4t/ha/年×112万ha ≒ 1800万t/年)
20年後の2040年には人工林の CO2 吸収を2600万tから1800万t増の4400万t/年に引き上げることができます。
20年後の2040年には人工林の CO2 吸収を2600万tから1800万t増の4400万t/年に引き上げることができます。
5
[参考:我が国のCO2 1人当たり排出量と総排出量]
2019年(概数)1人当たり9.0t×1.26億人≒ 11億t排出
2013年(概数)は13.11億tでした。
2020年のパリ協定で日本は2030年に2013年比で26%・3.4億t減の9.7億tに抑えることを公約。
この内人工林(伐採・植樹)により2600万t (13.11億t×2%)を吸収すると目算している。
日本の森林は国土の67%・2500haあり、その内6割が天然林、4割1000haが人工林となっている。
天然林は CO2 の吸収と排出が循環するだけなので、炭素固定による温室効果ガス削減に算入することができません。
この人工林1000haを放置・荒廃から守るには林業経営が成り立つ森林政策の転換・導入が必要です。
魅力のある林業に転換していくためには、短期間で収穫期を迎え、かつ CO2 吸収量が大きな早生樹(ユリノキ・センダン・コウヨウザン等)の導入が有効になります。
6
e.林業の現状と課題
日本は森林国でありながら、木材の自給率は安価な外材(天然林の伐採)の輸入政策により20%以下にまでに落ち込みました。戦後、植林したスギ・ヒノキ等が収穫を迎えていますが、伐採・搬出に高い費用がかかって赤字になるから、伐採されず放置されています。台風による倒木被害痕も随処に見られ、多くは荒廃したままです。
戦後の日本経済の成長は棄農政策によって支えられてきました。稲作農家を犠牲にして、輸出産業に偏重した経済施策を推し進めてきたのです。米作付面積を減らすと補助金を出すというような農業政策が続いた結果、小規模化と耕作放棄による荒田化が進み、日本の食料自給率は38%にまで落ち込んでしまいました。温暖化による災害等で米・豪・カナダ等の食糧生産に異常が発生すると、中国をはじめ国際間の食糧争奪競争が起り、日本は必要な食糧を確保できず1億2千万人が飢餓に陥るのです。既にその兆候が随処に顕在化しています。
林業についても国産材から輸入材に頼って来た結果、木材自給率は20%にまで低下し、森林は荒廃し林業従事者は激減してきました。
2000年代になると外国産天然材の枯渇化により、輸入外材価格が高騰した結果、国産材の供給量が増えてきています。しかし、これらは戦後植林した樹木の伐採によるもので、伐採に見合う植林がなければほどなく枯渇してしまいます。エネルギー・食糧・木材・希少金属・半導体あらゆる資源について、他国に依存するだけの政策を改めるべき時にきています。
7

8

9

10

11

12
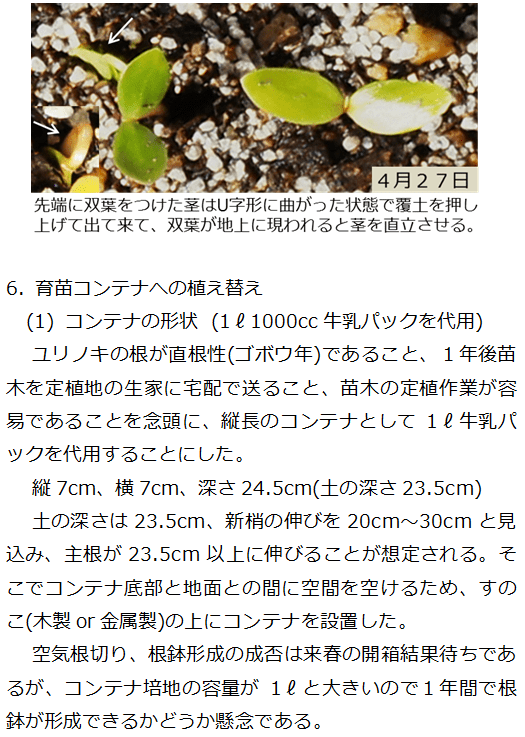
13

14

15

16

17

18
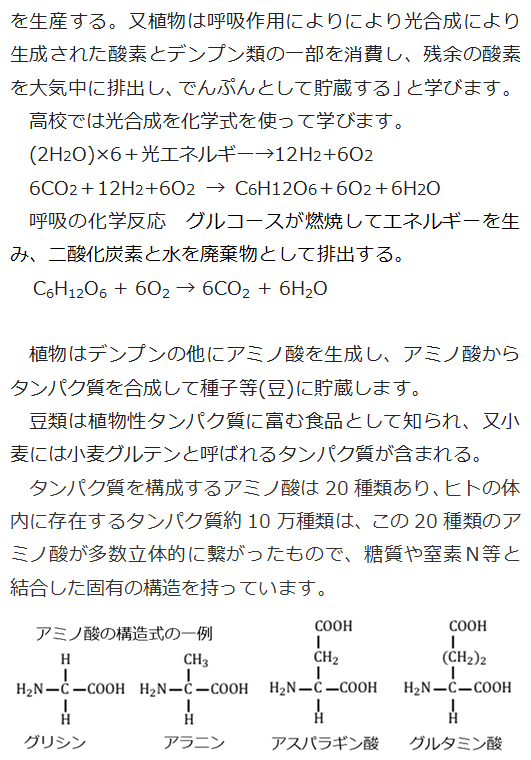
19

20

21

22