と昨日の夕食時に恵子が言った。
不自由な右手で箸を使い食べ物を口に持ってはいくものの、健常者からみたらかなりあぶなっかしい格好だ。
それでも、嬉しそうにそう見せてくれるのもきっと昼間行った病院でのコンサートのせいかもしれない。
昨日10日の午後、フルムスのメンバー4人(クラリネット、ヴァイオリン、コントラバス、ピアノ)と私で恵子の入院する病院で患者さん向けのコンサートを行った。
きっと無理矢理一番前に座らされたのだろう、恵子が恥ずかしそうに一番前の席に同室の方と並んで座っていた。
いつも見舞いに来ている家族の方々の顔も見えるし、もちろん患者さんたち、看護士さん、療法士さんたちの顔がずらっと並んでいた。
とはいえ、ちょうどこの日にお見舞いに来ていた家族の方たちも大勢いらっしゃった(コンサートを狙って来てくれたのなら有り難いことだが)。
病棟の2階と3階でそれぞれ50人以上は並んでいたので計百人以上の方に聞いていただけたはずだ。
それは、この1ヶ月以上ほぼ毎日のように病室やリハビリ室をうろつき回っている得体の知れないのオヤジの正体が皆に知れ渡った日でもあった。
「ああ、そうなんだ、この人は音楽をやる人なんだ」と認知していただけたらそれだけで十分ではある。
この日コンサートがあることを知ってわざわざお見舞いに来てくれた人たちもいた(いちどきにいろんな人のお見舞いを受けて恵子はビックリしていなかったかナ?)。
演奏メンバーやお見舞い客が帰られた後二人で食事をしている時(この病院は家族がいる時は病室で食べなくてもよい決まりになっている)、冒頭のセリフが恵子の口から飛び出したのだ。
きっと「音楽を聞いたからこんなに軽い動きができるようになったよ」と言いたかったのだと思う。
音楽家である私への精一杯の配慮だろう。
とても嬉しいと同時にこんなにも気を使わせているのかとすまない気持ちにもなった。
二人で「明るいリハビリ」を頑張ろうと毎日戦っているのだが、お互いに気持ちの浮き沈みはあるので、この心づかいにちょっと泣けてしまった。
その翌日である今日は、介護施設にまた別のフルムスメンバー8人を連れての演奏に行った。
演奏というよりは、私が長年考えてきた介護と音楽のあるべき姿を試す意味でのトライアルだ。
私は、音楽は絶対に一方的な作業ではいけないと思っている。
「音楽はコミュニケーション」。そう位置づけてきたし、おそらく人類史の中でも音楽の基本的な姿はそういうものだろうと思っている。
だからこそ、音楽が人の気持ちをほぐし、癒し、そしていわゆる人と人との「絆」を深めることができるのだろうとも思っている。
だとしたら、音楽が医療や介護や看護の現場で役にたたないはずがないとずっと思い続けてきた。
それをきちんとした形で世の中に示していきたいというのが私の考え方だ(もちろんそこにお金を払って買っていただきたいのだ)。
今の介護施設での音楽のあり方は絶対に間違っている。
そう思ってきたからこそのこうした介護施設を経営する企業へのアプローチを昨年からずっと根気よく続けてきた。
今度の震災でもそう確信したが、人が大事な仕事を行う時ボランティアをアテにしていては絶対にダメだということ。
これは確信を持って言える。
ボランティアには「責任」がないのだからいつでも「や~めた」と逃げることができるしそれを強制もできないのだ。
人には「悪意」も「善意」も両方備わっている。
だからこそ、どちらかだけをアテにはできないのだ(人間が善意だけの存在ならアテにしても良いのかもしれないが)
介護のような「大事な」仕事にボランティアをアテにするような風潮がここ何年も続いていることを私はもっての他だと思っている。
大事な仕事をやるためにこそ「プロ」が必要なわけで、それを担うにはそれなりの覚悟と献身と技術がいる。
しかもそれは高いレベルでの技術や覚悟だ。
それを見せるために行った今日の施設でのトライアル演奏だったのだが、これが成功したかどうかを決めるのはこの施設に暮らしている人たちだと思う。
具体的には企業がそのサービスを「買ってくれる」ことが「成功した」としたということの証にはなるのだが、このサービスがこれからの介護にとって絶対に必要だという確信を持っている私としてはこれからもやり続けていくしかない(仮にこの企業が買ってくれなければ新たなクライアントをとことん探していくまでだ)
音楽の必要性は介護だけでなくリハビリにもある。
それはいつも言っていること。
問題はそれにいつ誰が気づいてくれるかだ。
気づいてくれるまで「やり続ける」しかないだろう。
不自由な右手で箸を使い食べ物を口に持ってはいくものの、健常者からみたらかなりあぶなっかしい格好だ。
それでも、嬉しそうにそう見せてくれるのもきっと昼間行った病院でのコンサートのせいかもしれない。
昨日10日の午後、フルムスのメンバー4人(クラリネット、ヴァイオリン、コントラバス、ピアノ)と私で恵子の入院する病院で患者さん向けのコンサートを行った。
きっと無理矢理一番前に座らされたのだろう、恵子が恥ずかしそうに一番前の席に同室の方と並んで座っていた。
いつも見舞いに来ている家族の方々の顔も見えるし、もちろん患者さんたち、看護士さん、療法士さんたちの顔がずらっと並んでいた。
とはいえ、ちょうどこの日にお見舞いに来ていた家族の方たちも大勢いらっしゃった(コンサートを狙って来てくれたのなら有り難いことだが)。
病棟の2階と3階でそれぞれ50人以上は並んでいたので計百人以上の方に聞いていただけたはずだ。
それは、この1ヶ月以上ほぼ毎日のように病室やリハビリ室をうろつき回っている得体の知れないのオヤジの正体が皆に知れ渡った日でもあった。
「ああ、そうなんだ、この人は音楽をやる人なんだ」と認知していただけたらそれだけで十分ではある。
この日コンサートがあることを知ってわざわざお見舞いに来てくれた人たちもいた(いちどきにいろんな人のお見舞いを受けて恵子はビックリしていなかったかナ?)。
演奏メンバーやお見舞い客が帰られた後二人で食事をしている時(この病院は家族がいる時は病室で食べなくてもよい決まりになっている)、冒頭のセリフが恵子の口から飛び出したのだ。
きっと「音楽を聞いたからこんなに軽い動きができるようになったよ」と言いたかったのだと思う。
音楽家である私への精一杯の配慮だろう。
とても嬉しいと同時にこんなにも気を使わせているのかとすまない気持ちにもなった。
二人で「明るいリハビリ」を頑張ろうと毎日戦っているのだが、お互いに気持ちの浮き沈みはあるので、この心づかいにちょっと泣けてしまった。
その翌日である今日は、介護施設にまた別のフルムスメンバー8人を連れての演奏に行った。
演奏というよりは、私が長年考えてきた介護と音楽のあるべき姿を試す意味でのトライアルだ。
私は、音楽は絶対に一方的な作業ではいけないと思っている。
「音楽はコミュニケーション」。そう位置づけてきたし、おそらく人類史の中でも音楽の基本的な姿はそういうものだろうと思っている。
だからこそ、音楽が人の気持ちをほぐし、癒し、そしていわゆる人と人との「絆」を深めることができるのだろうとも思っている。
だとしたら、音楽が医療や介護や看護の現場で役にたたないはずがないとずっと思い続けてきた。
それをきちんとした形で世の中に示していきたいというのが私の考え方だ(もちろんそこにお金を払って買っていただきたいのだ)。
今の介護施設での音楽のあり方は絶対に間違っている。
そう思ってきたからこそのこうした介護施設を経営する企業へのアプローチを昨年からずっと根気よく続けてきた。
今度の震災でもそう確信したが、人が大事な仕事を行う時ボランティアをアテにしていては絶対にダメだということ。
これは確信を持って言える。
ボランティアには「責任」がないのだからいつでも「や~めた」と逃げることができるしそれを強制もできないのだ。
人には「悪意」も「善意」も両方備わっている。
だからこそ、どちらかだけをアテにはできないのだ(人間が善意だけの存在ならアテにしても良いのかもしれないが)
介護のような「大事な」仕事にボランティアをアテにするような風潮がここ何年も続いていることを私はもっての他だと思っている。
大事な仕事をやるためにこそ「プロ」が必要なわけで、それを担うにはそれなりの覚悟と献身と技術がいる。
しかもそれは高いレベルでの技術や覚悟だ。
それを見せるために行った今日の施設でのトライアル演奏だったのだが、これが成功したかどうかを決めるのはこの施設に暮らしている人たちだと思う。
具体的には企業がそのサービスを「買ってくれる」ことが「成功した」としたということの証にはなるのだが、このサービスがこれからの介護にとって絶対に必要だという確信を持っている私としてはこれからもやり続けていくしかない(仮にこの企業が買ってくれなければ新たなクライアントをとことん探していくまでだ)
音楽の必要性は介護だけでなくリハビリにもある。
それはいつも言っていること。
問題はそれにいつ誰が気づいてくれるかだ。
気づいてくれるまで「やり続ける」しかないだろう。















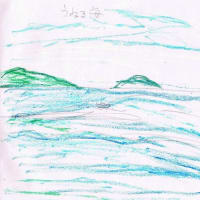


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます