
北海道紋別沖で回収された違法設置のカニかご=7月(水産庁提供)
http://www.sankei.com/economy/photos/141012/ecn1410120007-p1.html
敦賀カニ市長の話しでは無いが、「カニの話し」。
記事参照
2014.10.12 17:58
オホーツクの海に何が? ロシア船カニ密漁急増 背景に取り締まり厳格化
北海道紋別沖のオホーツク海の排他的経済水域(EEZ)内でロシア船が違法に設置したとみられるカニ漁用の漁具が急増している。
水産庁が今夏に押収したカニかごは、前年比で約5・5倍、かごの中のズワイガニの押収量も約4・8倍に増加。ロシア船が日本海域に越境してまで密漁する背景には、ロシア海域で厳格化する取り締まりがあるとみられる。
違法カニかごが押収されたのは、「北見大和堆」と呼ばれるカニ漁場。
水産庁は7~8月の2回で、かご291個、ズワイガニ約2500キロ(6439匹)を回収した。
いずれも2012年7月の回収開始以降で最多だった。
水産庁によると、近年、ロシア国境警備局の密漁取り締まりが厳格化しており、日露両政府は12年9月、密漁されたカニの取引を排除するためにカニの輸出に関する二国間協定に署名。
ロシアからのカニ輸入にはロシア側の証明書提出を義務付け、日本側の税関で確認する内容で、ことし12月に発効予定だ。
関連ニュース
マツダ車のエンジン生産へ ロシア合弁企業がウラジオストクで
ロシア、外相会談を拒否 追加制裁受け硬化
「制裁の修正、解除もある」 対ロシアで岸田外相が談話
政府が対ロシア追加制裁を発表
ロシア艦2隻が宗谷海峡を通過 大規模演習参加か
舛添都知事、ロシア・トムスクに到着 アジネット総会出席へ
http://www.sankei.com/economy/news/141012/ecn1410120007-n1.html
*上記の話しは「ズワイガニ」だが、最近、北欧のノルウェーで、「タラバガニ」が大繁殖しているようだ!。
現地では外来種として駆除の対象になっているようだ。
最近ではフィヨルド内湾にまで繁殖地を広げており、元々の生態系が脅かされているようだ。
この話し、「駆逐名目の漁獲」と言う事で、日本の業者はビジネスチャンスと言う事が言える。
価格を安くし、流通量を多くしてもらいたい。
それが消費者の考え、希望、と言う事が言える。
流通量を従来の2.5倍にし、店頭価格を半額にしても、回転出来ると思うので、店屋業者の収益は確実にアップ出来る。
重要な点は、消費者にとって、「いかに買いやすくなるように出来るか?!」と言うところにある。
焦点:信金・信組の道険しい「本業回帰」、届かないアベノミクスの恩恵
2013年 09月 6日 07:09 JST

[go to article]
9月6日、信用金庫や信用組合などの地方の中小金融機関が、融資拡大という「本業回帰」への壁に直面している。写真は2011年4月、都内で撮影(2013年 ロイター/Yuriko Nakao)
http://jp.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=JPTYE9840AB20130905
あすの視点
情報BOX:G20要人発言一覧
焦点:海外勢の日本株売り加速、足並みそろわぬ政府・日銀を不安視
焦点:消費増税で企業間格差が鮮明に、商品力・価格決定力で明暗
アングル:9月活況も米年末商戦は苦戦か、賃金伸び悩みがネック
[稚内 6日 ロイター] - 信用金庫や信用組合などの地方の中小金融機関が、融資拡大という「本業回帰」への壁に直面している。
安倍政権が推進する景気浮揚策の恩恵が届かないまま、地方での資金需要が停滞しているためだ。
国債など有価証券投資に依存する経営が続く中、アベノミクスの負の効果ともいえる金利上昇のリスクも現実味を帯び始めた。
地域金融機関が新たな再編の波に直面する可能性も消えていない。
「前向きな資金需要、新しい事業や設備投資といったのものはほとんどない」──。
日本最北端の町、北海道稚内市を基盤とする稚内信用金庫(稚内市中央)の増田雅俊理事長は、地元経済の厳しい現状にため息をつく。
同信金の預金残高は2013年3月末時点で3791億円。
しかし、このうち貸出できているのは865億円にとどまり、残る預金の大半は地方債や国債で運用している。
稚内市における同信金の貸出金シェアは5割を超えているのに、預貸率は22.8と低迷しているのが実情だ。
増田理事長は、貸出需要そのものがなくなっていることを理解して欲しい、と強調する。
かつてタラバガニやスケトウダラ漁の拠点として潤った同市はいま、地元産業衰退という窮状に直面している。
1977年、旧ソビエト連邦(当時)による200海里漁業専管地域の設定で、同市を拠点とする底びき網漁などの水揚げ量は激減、現在は40年前の7分の1に落ち込んだ。
住民の流出にも歯止めがかからず、現在の人口は約3.8万人。
頼みの綱は観光業だが、道内には札幌、函館、旭川などトップクラスの観光地が目白押し。
1日に2本の羽田からの直行便があるものの、稚内まで足を延ばす来訪客の数は過去10年でおよそ半減した。
地場経済の縮小と貸出ニーズの長期的な減少が続く中、同信金は早々と運用先を国債、共同発行市場公募地方債などリスクウェートの低い有価証券にシフトさせた。
同理事長は、金利上昇の懸念について、運用益の増加につながるため、経営の直接のハードルではない、と自信を見せる。
<企業に潤沢な自己資金、借入拡大は期待薄>
資金需要が盛り上がらず融資拡大ができない、という稚内信金の現状は、国内の信金・信組の多くが同様に抱える問題だ。
日銀の貸出・資金動向によると銀行の貸出は7月に前年同月比2.3%増と、今年に入り回復の兆しを見せているが、信金の貸出はわずかながらではあるが前年同月比マイナスに沈んだままだ。
昨年末の第二次安倍政権の発足は、地方の中小金融機関にとって現状打開の後押しになるはずだった。
「アベノミクス」の大きな柱として、日銀は新規に発行される国債の約7割にあたる量を買い取り、市中に資金を供給する異次元の金融緩和策を発表。
企業の資金需要が高まれば、稚内信金のような地域金融機関や地銀、大手行にとっては、預金を国債運用ではなく貸出業務に回す、という本業回帰の経営シナリオが描ける。
しかし、中小企業を主要な貸出先とする信金・信組の多くは、アベノミクスの恩恵を全く実感していない。
農林中金総合研究所の理事研究員、渡部喜智氏は「企業の資金需要の増大には限界がある。余資運用は増やすことはできても、減らせる展望は開けにくい」と、引き続き運用に頼らざるを得ない現状を指摘する。国内の事業法人(金融機関を除く)は、バランスシートに225兆円という潤沢な現預金を抱えている。借入れが本格的に拡大すると予想するのは少数派だ。
例外がないわけではない。今年4月の信用金庫法の施行令改正により、信金は取引先の海外子会社に対し直接融資をできるようになった。
規制緩和を活かし、浜松信用金庫(静岡県浜松市)は9月、古山精機のインドネシア現法に国際協力銀行(JBIC)と計1億円の協調融資を実施。取引先の海外事業の拡大をJBICと共同で後押しするのは信金として初の事例となった。
しかし、こうしたビジネス拡大を後押しする政策支援の枠組みがあるにもかかわらず、浜松信金のような取り組みは全国的な広がりをみせていない。
融資対象の中小企業に海外進出のニーズが少ないという事情と同時に、長期のデフレ経済下で防衛的な経営姿勢が定着し、融資リスクを積極的に取れなくなった信金・信組の企業体質も背景にある。
一方で、4月の日銀による大規模緩和で国債マーケットのボラティリティ―が一時的に急上昇し、一部の信金は国債頼みの運用のもろさを痛感した。
「期初に予定していた国債の購入を半分にせざるを得なかった」と首都圏の信金の企画担当者は打ち明ける。
最近は金利の動きも落ち着いてきたものの、「金利が低いならば低いままで安定してくれればいいが、一方で日銀は(物価安定上昇率)2%と言っているし、わからない」(同担当者)。
多くの金融機関が「安全弁」としてきた国債運用の先行きに不安が生じてきたことは否定できない。
今年3月末までの過去10年間、全国の信金の国債保有残高は69%増の10.6兆円に膨らんだほか、社債の保有残高は50%増の16.2兆円に膨らんだ。三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)、みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)、三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)の3メガにいたっては、13年3月期に国債運用で3社合算で業務純益の24%にあたる約6660億円を稼ぎ出した。それほどまで国債依存が進んでいたことの証でもある。
<高まる業界再編へのプレッシャー>
金融機関に求められるのは、企業に事業展開の血液となる資金を円滑に補給することだ。
この役割を果たさず、国債運用に偏重している現状について、批判は絶えない。
「5割以下の預貸率なんて銀行と言えるのか。彼らは努力をしなくても、国債を買っていれば自動的に収益を得られているのだ」──。
自民党の金融通と知られ、アベノミクスの推進役である山本幸三・衆院議員(自民)はこう切り捨てる。
そして、預貸率に目標を設定させ、一定量の貸し出しを促す政策を国として打ち出す必要があると訴える。
都市銀行は1980年代に20行あったが、小泉政権の下で強行した不良債権処理をきっかけに、現行の3メガバンク体制に落ち着いた。
一方、信金・信組は1990年代に計400超あったが、この22年間でおよそ半減した。
しかし、体力が小さい地域金融機関にとって、将来の経営拡大や生き残りをかけた提携や買収・合併という大胆な選択を迫られる状況はなお続いている。
八千代銀行8409.Tと東京都民銀行8339.Tは2014年の経営統合を視野に交渉を開始した。
融資拡大という本業の立て直しが進まなければ、これに続く再編の動きがさらに広がる可能性も否定できない。
(浦中大我 取材協力:江本恵美 編集:北松克朗)
ゥ Thomson Reuters 2014 All rights reserved.| Learn more about Reuters
http://jp.reuters.com/article/JPshiten/idJPTYE9840AB20130905?sp=true
中小企業は信用金庫が重要だ。
安倍氏や政権関係者らは大企業の事しか目に入っていないので、零細小中企業には「アベノミクスの恩恵」など皆無と言う状況だ。
政権は、完全に近視眼になっていると言う事が言える。
安倍氏や安倍政権経済担当関係者らは、「日本の経済の中で、小中零細の状況、農林水産の状況が分かっていない」、と言う事が「バターの品切れ問題」を考えれば、顕著に表れていると言う事が言える。
日本経済と政治は「目先の利益追求」に傾けば、「日本としての本来の底力」は、失われがちになると言う事が言える。
失われた部分の「補充が出来るか?、出来ないか?」で、自ずと結果は異なってくると言う事だ。
その部分について、そもそも「気が付いているのか?」と言う事も重要だ。
http://www.sankei.com/economy/photos/141012/ecn1410120007-p1.html
敦賀カニ市長の話しでは無いが、「カニの話し」。
記事参照
2014.10.12 17:58
オホーツクの海に何が? ロシア船カニ密漁急増 背景に取り締まり厳格化
北海道紋別沖のオホーツク海の排他的経済水域(EEZ)内でロシア船が違法に設置したとみられるカニ漁用の漁具が急増している。
水産庁が今夏に押収したカニかごは、前年比で約5・5倍、かごの中のズワイガニの押収量も約4・8倍に増加。ロシア船が日本海域に越境してまで密漁する背景には、ロシア海域で厳格化する取り締まりがあるとみられる。
違法カニかごが押収されたのは、「北見大和堆」と呼ばれるカニ漁場。
水産庁は7~8月の2回で、かご291個、ズワイガニ約2500キロ(6439匹)を回収した。
いずれも2012年7月の回収開始以降で最多だった。
水産庁によると、近年、ロシア国境警備局の密漁取り締まりが厳格化しており、日露両政府は12年9月、密漁されたカニの取引を排除するためにカニの輸出に関する二国間協定に署名。
ロシアからのカニ輸入にはロシア側の証明書提出を義務付け、日本側の税関で確認する内容で、ことし12月に発効予定だ。
関連ニュース
マツダ車のエンジン生産へ ロシア合弁企業がウラジオストクで
ロシア、外相会談を拒否 追加制裁受け硬化
「制裁の修正、解除もある」 対ロシアで岸田外相が談話
政府が対ロシア追加制裁を発表
ロシア艦2隻が宗谷海峡を通過 大規模演習参加か
舛添都知事、ロシア・トムスクに到着 アジネット総会出席へ
http://www.sankei.com/economy/news/141012/ecn1410120007-n1.html
*上記の話しは「ズワイガニ」だが、最近、北欧のノルウェーで、「タラバガニ」が大繁殖しているようだ!。
現地では外来種として駆除の対象になっているようだ。
最近ではフィヨルド内湾にまで繁殖地を広げており、元々の生態系が脅かされているようだ。
この話し、「駆逐名目の漁獲」と言う事で、日本の業者はビジネスチャンスと言う事が言える。
価格を安くし、流通量を多くしてもらいたい。
それが消費者の考え、希望、と言う事が言える。
流通量を従来の2.5倍にし、店頭価格を半額にしても、回転出来ると思うので、店屋業者の収益は確実にアップ出来る。
重要な点は、消費者にとって、「いかに買いやすくなるように出来るか?!」と言うところにある。
焦点:信金・信組の道険しい「本業回帰」、届かないアベノミクスの恩恵
2013年 09月 6日 07:09 JST

[go to article]
9月6日、信用金庫や信用組合などの地方の中小金融機関が、融資拡大という「本業回帰」への壁に直面している。写真は2011年4月、都内で撮影(2013年 ロイター/Yuriko Nakao)
http://jp.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=JPTYE9840AB20130905
あすの視点
情報BOX:G20要人発言一覧
焦点:海外勢の日本株売り加速、足並みそろわぬ政府・日銀を不安視
焦点:消費増税で企業間格差が鮮明に、商品力・価格決定力で明暗
アングル:9月活況も米年末商戦は苦戦か、賃金伸び悩みがネック
[稚内 6日 ロイター] - 信用金庫や信用組合などの地方の中小金融機関が、融資拡大という「本業回帰」への壁に直面している。
安倍政権が推進する景気浮揚策の恩恵が届かないまま、地方での資金需要が停滞しているためだ。
国債など有価証券投資に依存する経営が続く中、アベノミクスの負の効果ともいえる金利上昇のリスクも現実味を帯び始めた。
地域金融機関が新たな再編の波に直面する可能性も消えていない。
「前向きな資金需要、新しい事業や設備投資といったのものはほとんどない」──。
日本最北端の町、北海道稚内市を基盤とする稚内信用金庫(稚内市中央)の増田雅俊理事長は、地元経済の厳しい現状にため息をつく。
同信金の預金残高は2013年3月末時点で3791億円。
しかし、このうち貸出できているのは865億円にとどまり、残る預金の大半は地方債や国債で運用している。
稚内市における同信金の貸出金シェアは5割を超えているのに、預貸率は22.8と低迷しているのが実情だ。
増田理事長は、貸出需要そのものがなくなっていることを理解して欲しい、と強調する。
かつてタラバガニやスケトウダラ漁の拠点として潤った同市はいま、地元産業衰退という窮状に直面している。
1977年、旧ソビエト連邦(当時)による200海里漁業専管地域の設定で、同市を拠点とする底びき網漁などの水揚げ量は激減、現在は40年前の7分の1に落ち込んだ。
住民の流出にも歯止めがかからず、現在の人口は約3.8万人。
頼みの綱は観光業だが、道内には札幌、函館、旭川などトップクラスの観光地が目白押し。
1日に2本の羽田からの直行便があるものの、稚内まで足を延ばす来訪客の数は過去10年でおよそ半減した。
地場経済の縮小と貸出ニーズの長期的な減少が続く中、同信金は早々と運用先を国債、共同発行市場公募地方債などリスクウェートの低い有価証券にシフトさせた。
同理事長は、金利上昇の懸念について、運用益の増加につながるため、経営の直接のハードルではない、と自信を見せる。
<企業に潤沢な自己資金、借入拡大は期待薄>
資金需要が盛り上がらず融資拡大ができない、という稚内信金の現状は、国内の信金・信組の多くが同様に抱える問題だ。
日銀の貸出・資金動向によると銀行の貸出は7月に前年同月比2.3%増と、今年に入り回復の兆しを見せているが、信金の貸出はわずかながらではあるが前年同月比マイナスに沈んだままだ。
昨年末の第二次安倍政権の発足は、地方の中小金融機関にとって現状打開の後押しになるはずだった。
「アベノミクス」の大きな柱として、日銀は新規に発行される国債の約7割にあたる量を買い取り、市中に資金を供給する異次元の金融緩和策を発表。
企業の資金需要が高まれば、稚内信金のような地域金融機関や地銀、大手行にとっては、預金を国債運用ではなく貸出業務に回す、という本業回帰の経営シナリオが描ける。
しかし、中小企業を主要な貸出先とする信金・信組の多くは、アベノミクスの恩恵を全く実感していない。
農林中金総合研究所の理事研究員、渡部喜智氏は「企業の資金需要の増大には限界がある。余資運用は増やすことはできても、減らせる展望は開けにくい」と、引き続き運用に頼らざるを得ない現状を指摘する。国内の事業法人(金融機関を除く)は、バランスシートに225兆円という潤沢な現預金を抱えている。借入れが本格的に拡大すると予想するのは少数派だ。
例外がないわけではない。今年4月の信用金庫法の施行令改正により、信金は取引先の海外子会社に対し直接融資をできるようになった。
規制緩和を活かし、浜松信用金庫(静岡県浜松市)は9月、古山精機のインドネシア現法に国際協力銀行(JBIC)と計1億円の協調融資を実施。取引先の海外事業の拡大をJBICと共同で後押しするのは信金として初の事例となった。
しかし、こうしたビジネス拡大を後押しする政策支援の枠組みがあるにもかかわらず、浜松信金のような取り組みは全国的な広がりをみせていない。
融資対象の中小企業に海外進出のニーズが少ないという事情と同時に、長期のデフレ経済下で防衛的な経営姿勢が定着し、融資リスクを積極的に取れなくなった信金・信組の企業体質も背景にある。
一方で、4月の日銀による大規模緩和で国債マーケットのボラティリティ―が一時的に急上昇し、一部の信金は国債頼みの運用のもろさを痛感した。
「期初に予定していた国債の購入を半分にせざるを得なかった」と首都圏の信金の企画担当者は打ち明ける。
最近は金利の動きも落ち着いてきたものの、「金利が低いならば低いままで安定してくれればいいが、一方で日銀は(物価安定上昇率)2%と言っているし、わからない」(同担当者)。
多くの金融機関が「安全弁」としてきた国債運用の先行きに不安が生じてきたことは否定できない。
今年3月末までの過去10年間、全国の信金の国債保有残高は69%増の10.6兆円に膨らんだほか、社債の保有残高は50%増の16.2兆円に膨らんだ。三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)、みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)、三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)の3メガにいたっては、13年3月期に国債運用で3社合算で業務純益の24%にあたる約6660億円を稼ぎ出した。それほどまで国債依存が進んでいたことの証でもある。
<高まる業界再編へのプレッシャー>
金融機関に求められるのは、企業に事業展開の血液となる資金を円滑に補給することだ。
この役割を果たさず、国債運用に偏重している現状について、批判は絶えない。
「5割以下の預貸率なんて銀行と言えるのか。彼らは努力をしなくても、国債を買っていれば自動的に収益を得られているのだ」──。
自民党の金融通と知られ、アベノミクスの推進役である山本幸三・衆院議員(自民)はこう切り捨てる。
そして、預貸率に目標を設定させ、一定量の貸し出しを促す政策を国として打ち出す必要があると訴える。
都市銀行は1980年代に20行あったが、小泉政権の下で強行した不良債権処理をきっかけに、現行の3メガバンク体制に落ち着いた。
一方、信金・信組は1990年代に計400超あったが、この22年間でおよそ半減した。
しかし、体力が小さい地域金融機関にとって、将来の経営拡大や生き残りをかけた提携や買収・合併という大胆な選択を迫られる状況はなお続いている。
八千代銀行8409.Tと東京都民銀行8339.Tは2014年の経営統合を視野に交渉を開始した。
融資拡大という本業の立て直しが進まなければ、これに続く再編の動きがさらに広がる可能性も否定できない。
(浦中大我 取材協力:江本恵美 編集:北松克朗)
ゥ Thomson Reuters 2014 All rights reserved.| Learn more about Reuters
http://jp.reuters.com/article/JPshiten/idJPTYE9840AB20130905?sp=true
中小企業は信用金庫が重要だ。
安倍氏や政権関係者らは大企業の事しか目に入っていないので、零細小中企業には「アベノミクスの恩恵」など皆無と言う状況だ。
政権は、完全に近視眼になっていると言う事が言える。
安倍氏や安倍政権経済担当関係者らは、「日本の経済の中で、小中零細の状況、農林水産の状況が分かっていない」、と言う事が「バターの品切れ問題」を考えれば、顕著に表れていると言う事が言える。
日本経済と政治は「目先の利益追求」に傾けば、「日本としての本来の底力」は、失われがちになると言う事が言える。
失われた部分の「補充が出来るか?、出来ないか?」で、自ずと結果は異なってくると言う事だ。
その部分について、そもそも「気が付いているのか?」と言う事も重要だ。













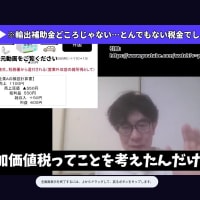
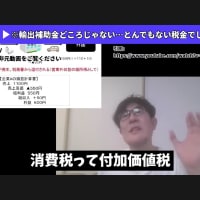
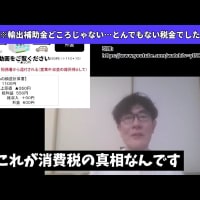

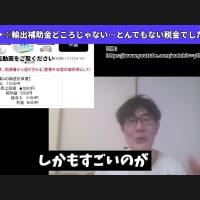

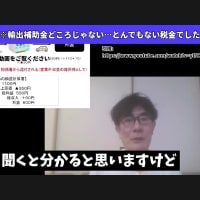





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます