ふとしたことから生まれる、すれ違いや行き違い。お互いの「違い」から生じる「ズレ」。だけど、それは決して悪いことではありません。
群馬県で2日から開かれた第57回全国保育団体合同研究集会(保育合研)。白梅学園大学の五十嵐元子さんの語りです。大切なのは「ズレ」を違和感で終わらせないこと。なぜそうなのか知ろうとすることが「重なり」となり、新たな関係への入り口となります。
横浜市立大学名誉教授の中西新太郎さんは、多様な大人が子どもに関わることが、やわらかさや趣の深さを生むと話しました。違っているから実は面白い。保育園を、多彩な関わりが行き交う場にしようと呼びかけました。
こうした大人たちの姿を、子どもたちはじっと見つめ続けています。「人と関わるって、こういうことなんだ!」と気づいて、「ズレ」を楽しみ、関係をつむいでいくことができるのか。それとも「違い」を排除して溝をつくり、さらに深くして、人と人との間を断ち切ってしまうのか。
オンライン視聴を含めて7200人を超える保育者、保護者、研究者らが3日間、さまざまな場で学び、語り合い、笑い、涙しました。9日には、18の分科会と特別分科会をオンラインで開催予定。全体会や保育・子育て講座、保育制度講座の録画配信も、これから予定しています。
酷暑の夏が続きますが、多彩な学びの場も用意されています。私たちはそこでどんな「ズレ」と出合い、「重なり」にどれだけ気づくことができるでしょうか。















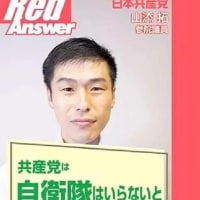




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます