廃止を含め根本的な見直しを
機能性表示食品の成分データの開示をめぐる裁判で、最高裁判所が消費者勝訴の判決を出しました。
食品表示は食の安全にとって極めて重要です。「LDL(悪玉)コレステロールを下げる機能がある」など、医薬品のような効能を売りにした食品ではなおさらです。
最高裁判決(6月6日)は、行政の事務に支障を及ぼすおそれがあるという消費者庁の主張に沿って情報の一部を不開示とした高裁判決を全員一致で破棄し、東京高裁に審理を差し戻しました。
裁判長の宇賀克也裁判官は補足意見で、情報開示は事業者全般にメリットが大きく、行政コストを軽減し、食品分析の専門家や国民一般にとっても食品行政の透明性が向上し信頼を高める、と開示の利益を指摘しました。
■不十分な情報開示
機能性表示食品制度は、財界の強い要求を受けた安倍晋三政権が規制緩和策として2015年に導入しました。それまで特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品に限っていた“効能の表示”を一般の健康食品にも認めました。
効果や安全性の科学的根拠を国が1点ごとに審査し許可するトクホと違い、国の事前の審査はなく、企業が所定の書類を届け出るだけの“手軽さ”から届け出が急増し(25年8月15日現在、9937件)、20年にはトクホの売り上げを超えました。
国は制度の実態を検証する調査を実施しました。しかし、公開されたのは商品名やメーカー名がない、どの商品に問題があるか消費者にはわからない「概要」だけでした。製品の安全性に懸念を抱き、詳しい情報の開示を請求した市民に提示されたのは、ほとんど黒く塗りつぶされた報告書でした。
18年、「公開は消費者の権利確保の大前提」だとして市民が検証資料の公開を求めて提訴、7年がかりで今回の最高裁判決にこぎつけました。
■発生した重い被害
現在の制度では、大きな健康被害が起きなければ商品の危険性が判明しません。
日本共産党は制度導入前から危険性を指摘してきました。穀田恵二議員(当時)は14年の衆院消費者問題特別委員会で「命にかかわる問題だ。起こってからでは遅い。私は危ないと言い、あなた(森雅子担当相、当時)は危険はないと言う。でも、いまの事態は安全性を保証しない」と導入に反対しました。
裁判が続いていた24年3月、懸念は現実となりました。機能性表示食品として販売された小林製薬の紅麹(べにこうじ)サプリメントによる腎疾患で、多数の死者や重篤者を出す深刻な健康被害が発生しました。
事件を受けて、政府は健康被害情報の報告義務化などの予防措置を打ち出しましたが、実効性は疑問視されています。国民が強く求めている被害情報の公開義務付けはされておらず、事後検査の情報公開も不十分です。
消費者にもわかりやすく、十分な情報公開は必須です。しかし、一部修正しても、商品の安全性保証は企業まかせという根本は変わりません。機能性表示食品は廃止を含め根本的に見直すべきです。















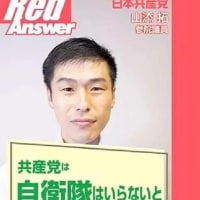




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます