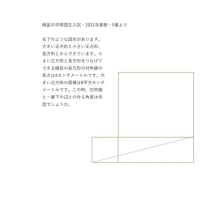ここではチャート自体を表記するのが難しいので、式のみでの説明となってしまいます。
(問い1)にも(問い2)にも使えるように、初めのA、B、Cの袋に入れた個数をそれぞれ〔A〕〔B〕〔C〕とします。
また(2)の操作でAの袋からBの袋に移す個数を【1】とします。
それぞれの袋の個数の変化を示します。
Aの袋
〔A〕
↓(2)の操作で【1】がAからBへ移る。
〔A〕-【1】
↓(4)の操作で【4】がCからAへ移る。
〔A〕+【3】
Bの袋
〔B〕
↓(2)の操作で【1】がAからBへ移る。
〔B〕+【1】
↓(3)の操作で【2】がBからCへ移る。
〔B〕-【1】
Cの袋
〔C〕
↓(3)の操作で【2】がBからCへ移る。
〔C〕+【2】
↓(4)の操作で【4】がCからAへ移る
〔C〕-【2】
各袋の最後の個数は次の通りです。
Aの袋→〔A〕+【3】
Bの袋→〔B〕-【1】
Cの袋→〔C〕-【2】
それではまず(問い1)について考えましょう。
初めの個数は同じ(〔A〕=〔B〕=〔C〕)ですから、差がもっとも大きくなる場合はAの袋とCの袋の差がもっとも大きくなる場合です。
そのときの差は【5】です。
もっとも少なくなるCの最後の個数を0としてみます。
もっとも多くなるAの最後の個数をなるべく大きくするためには〔A〕を最大にします。
〔A〕=〔B〕=〔C〕を忘れないでください。
200÷3=66余り2ですから、〔A〕=66となります。
このとき〔C〕-【2】=0としてありますから、【2】=66
つまり
【1】=33となります。
これを各袋の変化にあてはめてみると次のようになります。
Aの袋
66
↓
33
↓
165
Bの袋
66
↓
99
↓
33
Cの袋
66
↓
132
↓
0
どこにもおかしな数字が出てきませんからこれが個数の差がもっとも大きくなる場合と考えられます。
(答え)165個
今度は(問い2)について考えます。
最後の個数が同じなので次の式が成り立ちます。
〔A〕+【3】=〔B〕-【1】=〔C〕-【2】
〔B〕をもっとも大きくしたいのですから、最後の個数を、考えられる最大の数の66としてみます。
つまり〔A〕+【3】=66
ここで最小となる〔A〕は【1】以上でないといけないので
66÷4=16余り2を計算します。
この結果〔A〕は16以上の数と分かります。
(この式の意味は線分図を使うと分かりやすいです。)
ここで、【3】は明らかに3の倍数ですし、66も3の倍数ですから、〔A〕も3の倍数です。
また〔B〕-【1】=66より
〔B〕=66+【1】なので
〔B〕をもっとも大きくするためには【1】をなるべく大きくした方がよいと分かります。
以上をまとめると
〔A〕=18
【1】=16
となります。
これにより、〔B〕=66+16=82と分かります。
(答え)82個
(問い1)にも(問い2)にも使えるように、初めのA、B、Cの袋に入れた個数をそれぞれ〔A〕〔B〕〔C〕とします。
また(2)の操作でAの袋からBの袋に移す個数を【1】とします。
それぞれの袋の個数の変化を示します。
Aの袋
〔A〕
↓(2)の操作で【1】がAからBへ移る。
〔A〕-【1】
↓(4)の操作で【4】がCからAへ移る。
〔A〕+【3】
Bの袋
〔B〕
↓(2)の操作で【1】がAからBへ移る。
〔B〕+【1】
↓(3)の操作で【2】がBからCへ移る。
〔B〕-【1】
Cの袋
〔C〕
↓(3)の操作で【2】がBからCへ移る。
〔C〕+【2】
↓(4)の操作で【4】がCからAへ移る
〔C〕-【2】
各袋の最後の個数は次の通りです。
Aの袋→〔A〕+【3】
Bの袋→〔B〕-【1】
Cの袋→〔C〕-【2】
それではまず(問い1)について考えましょう。
初めの個数は同じ(〔A〕=〔B〕=〔C〕)ですから、差がもっとも大きくなる場合はAの袋とCの袋の差がもっとも大きくなる場合です。
そのときの差は【5】です。
もっとも少なくなるCの最後の個数を0としてみます。
もっとも多くなるAの最後の個数をなるべく大きくするためには〔A〕を最大にします。
〔A〕=〔B〕=〔C〕を忘れないでください。
200÷3=66余り2ですから、〔A〕=66となります。
このとき〔C〕-【2】=0としてありますから、【2】=66
つまり
【1】=33となります。
これを各袋の変化にあてはめてみると次のようになります。
Aの袋
66
↓
33
↓
165
Bの袋
66
↓
99
↓
33
Cの袋
66
↓
132
↓
0
どこにもおかしな数字が出てきませんからこれが個数の差がもっとも大きくなる場合と考えられます。
(答え)165個
今度は(問い2)について考えます。
最後の個数が同じなので次の式が成り立ちます。
〔A〕+【3】=〔B〕-【1】=〔C〕-【2】
〔B〕をもっとも大きくしたいのですから、最後の個数を、考えられる最大の数の66としてみます。
つまり〔A〕+【3】=66
ここで最小となる〔A〕は【1】以上でないといけないので
66÷4=16余り2を計算します。
この結果〔A〕は16以上の数と分かります。
(この式の意味は線分図を使うと分かりやすいです。)
ここで、【3】は明らかに3の倍数ですし、66も3の倍数ですから、〔A〕も3の倍数です。
また〔B〕-【1】=66より
〔B〕=66+【1】なので
〔B〕をもっとも大きくするためには【1】をなるべく大きくした方がよいと分かります。
以上をまとめると
〔A〕=18
【1】=16
となります。
これにより、〔B〕=66+16=82と分かります。
(答え)82個