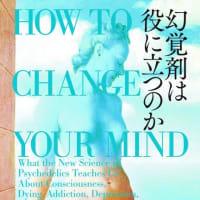【47】の前文の続きの洗濯のことでも良かったのですが……今回は「時間」のことについて言い訳してみようかなと思いました
いえ、書きはじめた頃は「大体鐘の音で寝起きしたり、働きはじめたり仕事の作業をやめたり……」といったような中世の農村的イメージだったのですが、その後やっぱり「時間がはっきりしないと困るなあ 」といった出来事が出てきまして――まあ結局のところ、「朝の八時ごろ」とか、そんな表現がでてくる結果となりました(^^;)
」といった出来事が出てきまして――まあ結局のところ、「朝の八時ごろ」とか、そんな表現がでてくる結果となりました(^^;)
ただ、日暮れとともにそこから数えて一時、二時……と数える方法であるとか、修道院における時間の計測法のほうがたぶん、いかにも異世界っぽいという「ぽさ」はあるにしても、わたしの中では「単にややこしいだけやんけ☆ 」としか思わなかったというのがあって、そうした時間の計測方法は取ろうと思えなかったというか。
」としか思わなかったというのがあって、そうした時間の計測方法は取ろうと思えなかったというか。
でも、「図解・中世の生活」によりますと、「機械式時計は14世紀以降に誕生した」ということでして、その前までは昼は日時計、夜は砂時計やろうそく、水時計で大体のところの時間をはかっていたということらしく、また教会や修道院から鳴る鐘、これを基準にして人々は生活していた……それで、この修道院の生活においては、「朝課(真夜中)」、「讃課(午前三時)」、「1時課(午前6時)」、「3時課(午前9時)」、「9時課(午後3時)」、「晩課(午後6時)」、「終課(午後9時)」――という、こうしたサイクルについては、他のファンタジー作品などでも見たり読んだりしたことのある方は多いと思います
そんで、「シェイクスピアの時代のイギリス生活百科」によると、こちらはルネサンス時代ですから、すでに1時間は60分であるといったように認識され、上流階級の人々だけが文字盤付きの時計を持っていたといったことらしく。。。
>>時間。
田舎の広大な領地で野山を歩いていると、領主館の礼拝堂の鐘が働く人々に時を告げるのが聞こえるだろう。多くの人にとって、これだけが彼らの知る時の規則である。町では教会の鐘の音が時を定める。複数の教会がある場合は、ひとつの教会が他の教会のために時を定める。それゆえ町の人々が「時計の時間」ではなく「鐘の時間」を口にする場面を見かけることもあるだろう。だが、このような非公式なやり方の裏に、重要な変化が隠れている。
エリザベスの時代に時間は標準化された。昼間と夜間を十二等分する中世の方式では、夏の昼の一時間は冬の倍の長さになったが、このような方法はすでに過去のものだ。エリザベス朝の人々は私たちと同じように一日の時間を数えた。すなわち、真夜中と正午から十二時間ずつで、一時間は60分である。
町の住民は、市場を開ける時間、閉める時間を知らせる鐘、すべての旅人が外出禁止になるとき、町の門が閉められるときに鳴る晩鐘を聞き逃さないよう耳を澄ませる。農村部の教区に住む人々は、礼拝の時刻や荘園裁判所の開廷を告げる教会の鐘に耳をかたむける。
文字盤のある時計は通常、針がひとつしかなく、何時であるかを示している。分を数えるときはふつうの時計ではなく砂時計を用いる。もっとも、船乗り、錬金術師、占星術師、自然哲学者、聖職者を除けば、使う者はほとんどいない。なぜ聖職者が使うのかとお思いだろうか。優秀な聖職者は一回に二時間、あるいは三時間も説教を続けるつもりでいるものだ。
鐘の音で知らされるため、エリザベス朝において時間はまさに公共のものだった。上流階級だけが「寝室用の小型の目覚まし時計」を持っている。「文字盤つきの時計」は、1580年代にはたぶん五ポンドはするだろう。ダイヤモンドをちりばめた、銀の鎖つきのエリザベスの時計のようなものを持っている人はさらに少ない。外出時は、ほとんどの人は昔ながらのやり方で、すなわち太陽の位置で時計を推しはかるか、日時計の指輪を使う。これは真鍮の輪の形をした日時計で、指にはめることができる。時刻を知りたいときは、日付を合わせ(そのためにスライドする輪がついているものもある)、てっぺんの穴から射しこみ、指輪の内側に刻まれた目盛りに当たる日の光を確認する。もっとも精巧なリング型の日時計には、カレンダー、キリスト教の祝祭日一覧、主なヨーロッパの都市の緯度もついており、海外でも使用できる。このような精巧な時計がほしければ、最高の品をつくっているロンドンのハンフリー・コールの店で尋ねるといい。
(「シェイクスピアの時代のイギリス生活百科」イアン・モーティマーさん著、市川恵里・樋口幸子先生訳/河出書房新社より)
まあ、「時間などというものはそもそも存在しない」という超科学的(?)な考え方もあったりするわけですが、あらためて「時とは何か? 」などと聞かれると、一瞬答えに詰まってしまうものですよね(^^;)
」などと聞かれると、一瞬答えに詰まってしまうものですよね(^^;)
それではまた~!!
惑星シェイクスピア。-【50】-
(ふう~ん。とはいえ、何故こんな童話のような建国神話を、今もこの州の人々は呑気に信じていられるのかねえ)
カドールは聖ウルスラ神殿からやや南西に下った場所にある聖ウルスラ大聖堂にて、大修道院長がやって来られるのを待つ間――ハムレットやタイスとともに、壁に描かれたメレアガンス州に古くから伝わる建国神話のレリーフ、あるいはタペストリーなどを順に眺めていた。
(それに、一見これで「めでたし、めでたし……」となったように見えるかもしれないが、引きとられていった先の家でウルスラは家事万能の主婦よろしくこき使われ、そこから騎士との結婚によって逆転勝利した――ということについては、俺はある種の疑問を感じるな。まあ、俺も結局はそうした女と結婚しようとするに違いないが、メレアガンス州で育った女性は二言目にはすぐ、「聖女ウルスラさまを見習って」料理が上手くなるよう、掃除が出来るよう、手芸が上手くなるようやかましく言われて育つらしいからな……)
「それにしても素晴らしい大聖堂ですね」
タイスは修道院、と聞いていたので、もっと質素な礼拝堂を想像していたのだが、聖ウルスラ大聖堂(ここと聖ウルスラ神殿とはまったく別の独立した建物である)とその大聖堂に付属した修道院とは、貧乏僧が日夜祈りを捧げている……といったイメージとはまったくかけ離れた、壮麗な礼拝堂を有ていたからである。
天井といい壁といい、どこもかしこも絵画やタペストリーが飾られているか、浮き彫りが施されているかのいずれかで、そのレリーフにしても細かいところまでうるさいほどに彫刻がされており、もし礼拝堂であると最初に聞かされていなかったすれば、心静かに祈るよりもこれら芸術品ひとつひとつを鑑賞するのに忙しく、本来の目的を忘れ去ってしまうかもしれぬほどだった。
「ここメルガレスでは、神官というのは元老院にて結構な力を持っているそうですよ」
「つまり……?」
カドールが含みのある顔の表情をして見せたため、タイスはその先を促した。彼がこうした顔をしている時は、大抵が思うところを隠している場合が多いからだ。
「つまり、元老院は約三百名ほどで構成されていて、内百人が貴族、神官が五十名、騎士やその家系の者が五十名、残りの約百名が民間の有力者から選抜されているわけですよ。また、聖ウルスラ神殿の巫女姫や巫女たちは政治に直接関わってはいないが、非常に強い影響力を持っているとか……」
「ということは、聖ウルスラ神殿の巫女たちは、ただ神殿にこもって平和を願い、民の幸福を祈ってばかりいるわけではない、ということですか?」
大聖堂には、一番奥に祭壇があり、そこには惑星神ゴドゥノフと星母神ゴドゥノワがこの宇宙と世界を形作ったという創世神話の描かれた三連の大祭壇画が正面を飾っている。そして、祭壇前には右に大盾を手にした聖ウルスラが、そして左に剣を構えた騎士エドワールの彫刻が台座の上に安置されていた。
民たちは、自由にここへ来て捧げ物をしたり、捧げる物を持たなかったとしても、ただ静かに祈るために木製の長い椅子に腰かけ、誰でも祈ることが出来た。付属した建物の修道院は女人禁制であるが、大聖堂のほうは夜間を除き、一般に開放されている。また、聖ウルスラ神殿においても、人々は男女問わず神殿で捧げ物をして祈ることが許されているが、神殿の奥の巫女たちの住居のほうは当然男子禁制であった。
ハムレットは座席の一番後ろの席で、熱心に祈る人々の背中を見つつ、自分もまた神に祈りを捧げていたが、自分の後ろにいるタイスとカドールの会話にもこの時耳を澄ませていたわけである。
「俺も、ここへそう長く滞在していたわけではないので、どちらかというと人の噂話に近いかもしれないのだがな」と、カドールは小声で続けた。「巫女さま方というのは、ただ神殿にこもって祈っていればいいというのではなく、民の幸福のためには具体的に行動する必要があると、そんなふうにお考えになるそうだ。そこで、機会を捉えては外へ出ていき、政治的影響力のある貴族と接触したり、騎士に嘆願したり、神官らと話しあったりと、なかなか行動的だという話だったな。簡単にいえば、聖ウルスラ神殿の巫女姫にはある種の否決権があるということさ。元老院で話しあって決めた政府の方針についてでも、「星母神さまに祈ったところ、こうせよと仰せられたのです」と最後に巫女姫がおっしゃれば……議会でどんなに長い時間をかけ紛糾しつつ、最終的にまとめあげた案件についてでも、巫女姫にはやめさせることの出来る最終決定権があるというわけだ」
「鶴の一声ならぬ神の一声というわけですね。それは、巫女たちが熱心に活動することにもなるわけだ……」
タイスとカドールの間では、それ以上のことは語られなかったが、ハムレットにもその理由が説明されずともわかっていた。元老院で取り決めたことを巫女姫から「待った」をかけられず通すためには、当然事前の打ち合わせといったものが必要になるだろう。また、ずっと神殿にこもっているということは、世事に疎くもなるだろうから、その政治方針で本当に正しいのかどうか精査するためにも――有能な巫女たちが忙しく働き、巫女姫にそのあたりのことを申し伝える必要があるに違いない。
「ですが、それはある意味危険なシステムですね」
「まったくそのとおりだ」と、カドールが頷いてみせる。「過去には、領主であるメレアガンス伯爵と時の聖ウルスラ神殿の巫女姫とが仲が悪く対立していた……なんていう例もある。元老院の最高権威者は当然伯爵だからな。そこで、お互いに相手を自分の言うなりにさせたいとなったら――元老院議員である有力貴族や神官や騎士、それに富裕な民の権力者らを、一体何人自分の側の味方につけるかという、水面下の醜い争いに繋がる可能性だってあるだろう。今のところ、危なっかしいながらもそれなりに上手く機能しているということなんだろうが、もし万一、知恵の足りない間抜けな領主が誕生し、その下には姑息なおべっか使いしか存在しないとなった場合は……まあ、聖ウルスラ神殿の巫女姫側が自然と力を持つことになり、私腹を肥やす神官が巫女姫を傀儡のように扱おうとした時代には、有力貴族や騎士らが結束して伯爵側に味方したりといったような具合でバランスが取られてきたのだろうな」
「こうした場所で、あまり大きな声で言っていいことでありませんが……」と、タイスは多少周囲を気にして、礼拝堂のほうを振り返った。「この大聖堂ひとつ取って見てもわかる気がします。修道院のほうからあまり外へ出ることなく、祈りに専心している僧であれば別として、元老院で議員を兼ねているような神官らは、かなりのところ裕福な暮らしをしているのではないですか?違いますか」
「そのとおりだ。聖ウルスラ神殿とここ、聖ウルスラ大聖堂のある丘を下っていった麓に、そうした神官たちの住まう豪邸が並んでいる。屋敷のあちこちに、ここの大聖堂と同じく聖女ウルスラの彫像やら、宗教的シンボルがあちこちに配されているとはいえ……とにかく物凄く金がかかっていると一目でわかる絵画やら家具やらが競うかのように並んでいるわけだ。庶民らはそうした神官のことを『世俗的神官』と揶揄して呼ぶこともあるようだが、神学や哲学に通じているという意味では、確かに人々から敬われてもいるし、この大聖堂でもなかなかに感動的なお説教をぶつこともあるという、そうした存在らしいな」
タイスとカドールが暇潰しにそんな話をしていると――ギベルネスが着ているのにも似た、茶の質素な僧服を着た老人が、誰か人を探すような仕種をして、入口のほうに姿を現していた。カドールはこの人物、オド=オスティリアス大修道院長と面識はなかったが、その仕種で彼なのだろうと認識していたし、それは彼のほうでも同じだったようである。
「お待たせして、大変申し訳ありませんでした。羊が一匹行方不明になっておりましてな……まあ、ちょっとした大捕り物ですよ。長く行方不明になっておって、突然ふらっと戻ってきたかと思えば、今度はこちらに捕まえられたくなかったらしいのですな。羊の毛を刈り込まれるのが嫌さに、去年の春、その直前でいなくなったのですよ。あなた方、一年以上毛を刈られなかった羊がどんな様子をしてるか知っておりますかな?」
「いえ……」とタイスとカドールがほぼ同時に答えると、髪も口髭もすっかり白くなっているオドは、快活に笑っていた。
「いやいや、もうモッコモッコのフッサフッサですわ。普通、毛のほうは自然と抜けて生えかわるものなんですがな、自分でもこのままではどうも何かがうまくない……人間は嫌いだが、ここはひとつ妥協して昔の古巣へ戻ろうと、そう思ったのかどうか。捕まえて毛を刈るのがその羊のためというせいもあり、朝から修道院中が久しぶりに大騒ぎでしての。そんなわけで、僧侶ともあろう者がお客人をお待たせしてしまって大変申し訳ない」
「こちらこそ、お忙しいところ、お時間をいただき申し訳ありません」
そう言ったのは、礼拝堂の座席から立ち上がったハムレットだった。途端、オドの灰色の瞳は驚きに見開かれた。聡明な顔立ちをしているだけでなく、その前まで祈りの姿勢をずっと取っていたことから――(なかなかに見所のある若者のようだわい)と、そのように見て取っていたからである。
(とはいえ、まさか我が修道院に入りたいという希望があるというわけではなかろうな)
そのように思いつつ、オドはこの三人の客人たちを、大聖堂の中にある応接室のほうへ通した。ここ、聖ウルスラ大聖堂には、聖ウルスラ神殿にないものとして、貴族でも庶民でも誰でもが利用できる相談室がある。相談に当たるのは修道院の僧たちで、仕切りのあるそのいくつもの個室で語られたことは、決して外部に洩れることはないと言われている。そこで人々は罪の告白をしたり、人生の問題に関して神の導きを求めたりするわけだが、応接室のほうはそれら懺悔室と呼ばれる場所を通り過ぎた奥のほうにあった。
また、そこへやって来るまでの間に、何人もの信者らと廊下で通りすがったのだが、誰もがみなオド=オスティリアスに対し敬礼したり、深い尊敬の滲みでた態度で挨拶したり、さっと脇へ寄り廊下の中央を空けたりと――彼がこの町の人々誰からも慕われる人物であることがわかったものである。そのうちの中のひとりに、赤ん坊が生まれ、洗礼を授けてもらったばかりの夫婦がおり、おくるみに包んだ赤子を奥方が抱いていたため、オドは彼らと少しばかり話すと、最後にその赤ん坊を祝福してからその場をあとにする……そのような一場面まであった。
「いやいや、すみませんな。あの赤ん坊は生まれてくる時、危うく母子とも命を落とすところだったもので……母親だけでなく、赤ちゃんのほうも元気でまったく嬉しい限りですわい」
こちらへどうぞ、とオドが案内した応接室は、重厚な樫の扉も樹木の葉や果実が細かく彫刻されていたが、やはり室内のほうも聖人や聖騎士らの彫刻、それに神話に纏わる絵画、他に壁を飾るものとしては本棚に並ぶ貴重な神学や哲学、法典などの分厚い本が所狭しと並んでいたものである。
ハムレットとタイスとカドールは、こちらもやはり精緻な刺繍の施された豪奢なソファに腰かけ、螺鈿細工のテーブルを挟み、オスティリアス大修道院長と相対した。
「して、一体どのようなご用向きでしたかな?」
オドは使者から、「ローゼンクランツ騎士団の騎士殿が面会を申し出ておられる」といったようにしか聞いていなかった。また、似たような形で彼と会いたがる貴族・騎士・神官・巫女・富裕な商人・庶民……といったものは、数え切れないほどいるわけだったが、他州の騎士団の騎士とあっては会わぬわけにゆかぬとオドにしても考えたわけである。
「こちらにおられる方は、ハムレット王子です。今は亡きエリオディアス王の忘れ形見の……」
カドールが思い切ってそう申し出たことには理由があった。修道院の僧たちには、何がしかの相談に来た者に対して守秘義務があり、特に懺悔室で語られたことについては俗世の人に洩らしたことがわかった場合は破門と定められているほどである。また、オド=オスティリアスの高名については噂で聞き及んでいたものの――彼の人柄を直に目にして、(この人物であれば信頼できる)と判断したということがあった。
「ですが、エリオディアス王の御子息は……」
そう独り言のように呟きかけて、オドはハッとした。ハムレットは旅装束に身を包んでおり、そのいでたちは決して華美なものではなく、むしろ質素そのものだった。飾り気のない青灰色のチュニックに、薄汚れた細長い白のズボン。靴にしても、長く旅してきたのだろうことがわかる、擦り切れた足首までの革靴である。その上に灰色の薄い外套(マント)を羽織っていたが、それもまたむしろ着ないほうがいいくらいのものだったのである。
それでいて、ハムレットには一目見て誰もがもう一度目を留めたくなるほどの、ある種の気品が備わっていた。白い肌に憂いを帯びたような深く青い瞳、それにブロンドの髪は短かったが、毛先がまるで女性の髪のように自然とカールしていた。
「では、あなた様方はもしや……」
「そうです」と、タイスが言った。この英邁なる大修道院長がすでに何かを察したのだろうと見て取ってのことだった。「ハムレットと俺とは、ヴィンゲン寺院からここまで、長く旅をしてきました。ローゼンクランツとライオネスとギルデンスターンの砂漠の三領地はすでに我々に味方してくださるとの約束があります。そこで、メレアガンス伯爵の意向としてはいかがなものかと考えまして……」
「そのこと、ここメルガレス城砦へ到着なさってから、他に知っている者はございますか?」
先ほどまで、孫を見る翁のように柔和な顔をしていたオドの顔つきが、一瞬にして変わった。それはまるで軍部の参謀が、少ない将兵でいかに敵国に勝つかと算段する時のような厳しい顔つきだったと言える。
「いえ、我々はこちらへ来てから、今後のことを相談する第一の人選として、あなたさまを選んだのです」と、カドールはほっとして言った。どうやらオド=オスティアスという男は単に人が好いのみならず、相当な切れ者に違いないとわかったからである。「他に、俺の騎士仲間が今、聖ウルスラ騎士団のラウール・フォン・モントーヴァン殿を訪ねておりますが、彼は信頼のおける高潔な人物ですので、何も心配しておりません」
「そうでしたか……」
このあと、オドは三人に果実茶を振るまってくれた。うっすらレモンやオレンジの味がする紅茶で、驚いたことにはとても冷たくて美味しかった。客人の来る頃合を見計らって、他の僧が気を利かせ準備していたのだという。他に、ドライフルーツがたっぷりのカステラまであった。
「みなさま方はこの部屋、いかがお感じになりますかな?これは私が想像してみますのに、ヴィンゲン寺院などではきっと、考えられないくらい贅沢で、僧の暮らしには似つかわしくないとお考えになられてたとしても無理はありません。もっとも、修道院自体のほうは飾り気もなく質素そのものですが、何分、聖ウルスラ神殿のほうには多額の寄付金が集まりますのでな……聖女ウルスラさまの名を冠した大聖堂が貧乏くさいのではどうにも堪らないというわけで、このようにたっぷりお金のかかった豪華な造りになっとるわけでして。また、我々修道院の僧侶は、元老院のメンバーともなっている神官方には自然と逆らえぬ上下関係が存在するのです。メレアガンス伯爵に何か圧力をかけるといった形で物を申し上げられるのも、こちらの神官方というわけなのですよ」
「オレは……オド=オスティリアス大修道院長殿の忌憚ない御意見をお聞きしたくて来たんです」と、ハムレットは、信頼の置けそうなオドにすっかり好感を持って言った。「どうなのでしょうか。メレアガンス伯爵はオレに手を貸してくださると思いますか?」
「そうですな。残念ながら私には、領主さまに何かを申し上げて強く働きかけるような力はございませんが……」と、前置きしてオドは言った。「ハムレット王子がメレアガンス伯爵とお会い出来る機会というのは、おそらくラウール・フォン・モントーヴァン殿がお作りになってくださるだろうと想像します。というのも、ラウールさまは長くメレアガンスさまの狩猟友達であられた方ですし、その他車輪競馬など、共通の趣味も持っておいでで……ですが、そのモントーヴァンさまを持ってしても、クローディアス王の命で砂漠の三州をロットバルト伯爵とともに食い止めよと言われた場合、どちらに味方するのが自分にとって得策なのかと秤にかけた場合――ハムレット王子に味方し、王権を獲れればその後メレアガンス州は安泰でしょう。ですが万一敗れれば、伯爵さま御自身のみならず奥方さまも一人息子のエレアガンスさまも、他に一族全員が酷い拷問ののちに死ぬことになるわけです。優柔不断なメレアガンスさまのこと、どちらとも決めかねるでしょうし、何より油断ならない臣下の誰かにハムレット王子の存在は嗅ぎつけられ、間者から王都テセウスのクローディアス王の耳に必ずやそのこと入ってしまうことでしょう。メレアガンスさまが断固たる態度で腹を決めてのちであればともかく、まだ何もない状態でハムレット王子のことをメレアガンスさまのお耳に入れるのは、それだけでも相当危険なこととお覚悟なさっておいたほうがいい」
「では、ロットバルト州はどのようなものでしょうか」
(やはりそうか)と落胆しつつ、カドールはオスティリアス大修道院長にそう聞いた。大きな溜息が洩れそうになる。
「そうですね……ロドリゴ=ロットバルト伯がハムレット王子に間違いなく味方なさると、そのような密約が結ばれてのちであれば、メレアガンスさまも頷かれることでしょうな。とはいえ、それもなかなか難しいことです」
「何故ですか?」と、タイスが聞いた。カドールに聞いたところによると、ロドリゴ=ロットバルト伯の人となりというのは、好戦的で自由気ままなギャンブル好き、ということだったからである。
「ロットバルト伯爵は、王都でなくとも、他の内苑州それぞれと、昔から複雑な姻戚関係を結んでいる方ですからな。ロットバルトが叛旗を翻したとなると、ロットバルト州出身の方々は、内苑州のそれぞれが住む場所において片身の狭い思いをするのみならず、拷問ののちに処刑が待っているやもしれませぬ。とはいえ、ロットバルト伯は奸智に長けるのみならず、なかなかしたたかな方でもありますから……事の運びようによってはハムレット王子に味方してくださる可能性というのは、少なくとも保守的なメレアガンスさまよりは高いやもしれませぬ」
「そもそもは、ロットバルト州の利益のために嫁がせた親類縁者が処刑されたとしても……のちに自分に帰ってくる利益のほうが大きいと判断すれば、オレたちに味方するかもしれないと?」
(そんな人物、本当に信用できるのだろうか?)と、ハムレットの顰めた眉と青い瞳には、この時はっきりと深い不審の色が浮かんだ。
「どう言ったらいいか……ロドリゴ=ロットバルト伯爵は、ようするにギャンブル好きな性格をしておられるのです。海や風のように制することの出来ぬ御気性ながら、かといって海や風が本当の意味で嫌いだという人間はいない……まあ、そのようなお方ですね。また、好き嫌いのはっきりした御性格であられるので、第一印象にはお気をつけになったほうがいいかもしれません。ロットバルト伯爵は一度あるものや人が好きとなったらとことんつけ狙い、嫌いとなったらとことん嫌うという、そのようなご気性のお方なのですな。それと、王都がやたら重税を課してくるので、なかなか新しく船団を造って出航できないと、そのことには大変ご不満を持っておられるようです。ただそれだけのことのためにも、自分の首を賭けて内乱に加担する方であり、逆にハムレット王子のことが気に入らないとなったら……喜んで王都のクローディアス王に身柄を引き渡すような人物でもあると、そこのところはよく見極められたほうがいいかと存じます」
「どちらにしても、大変なお方のようだ」
タイスが溜息を着いてそう言った。彼らの手の内には、ローゼンクランツ公爵の公爵印、ライオネス伯爵の伯爵印、ギルデンスターン侯爵の侯爵印の捺された親書があるが、それらは神々の託宣により大義が語られ、クローディアス王がそもそも兄王を謀殺し、さらにはその子息であるハムレット王子のことも殺害しようとしたこと、そのことを知った忠臣ユリウスがヴィンゲン寺院へハムレット王子を連れて逃げたこと、彼が真実エリオディアス王の息子であることはヴィンゲン寺院の僧たちが証しすること、クローディアス王の統治のやり方に対する疑問や重税に対する民の負担の軽減……翻ってハムレット王子が王になった場合の恩恵についてなど――ふたりの伯爵にこの親書を渡した時点で、これが反逆の証拠にもなるであろうことが書かれているのである。
「そういえば、メレアガンス州のほうでは、民たちに課された重税に対する不満というのはどの程度のものなのですか?」
カドールがそう聞いた。彼がここメルガレス城砦を見る限りにおいて、城砦に住む人々自体は活気があり、税に圧しひしがれて苦しんでいる――といった印象は今のところ薄かったからである。
「なかなか難しいところでしょうな……」
聖職者といったものは税を課されずに済む存在ではあったが、彼は一般庶民の暮らしというものが楽でないことは、よくよく承知していた。いや、知り抜いていたといっていい。
「今から約四年ほど前に戦争がありましたわな……戦費がかかったこともあり、直後はここメルガレス城砦も経済のほうが相当冷え込みました。また、税率のほうは上がりこそすれ下がることはありませんでしたので、連日法務院のほうでは同じような裁判が繰り返されていたものです。つまり、税の支払えない分を誰かしらから借りたものの返せないといったような訴えです。そこで、財務長官であるカンブレー卿が一計を案じ、こう進言したのですよ。住民が支払えなかった税については、一旦州のほうで負担し、王都へ納める分はメレアガンス州のほうで立て替えるといったような形ですね。簡単にいえば、支払える時に少しずつでもいいから支払えという……州内の他の城壁町や村落などでも、同じようにしているはずです。その地方をそれぞれ治める貴族の責任者が税を取り立てているわけですが、まずは自分が一旦立て替えているわけですよ。支払えなければ牢屋行きだというのは誰もがわかっていることですからね、地方貴族の温情に感謝しつつ、少しずつ税を納めるといった、そうした形なわけですが……今でギリギリどうにか黒字といった財政ですから、内乱に加担すれば、それはもう後戻りは出来ないということを意味しています」
「なるほど……実は俺は、自分の主君にこう言われていたのですよ。砂漠の三州には他のどこの州にもない貴重な香辛料といった特産品が、いくらでも産出が可能であるのに対して――メレアガンス州とロットバルト州は財政的にもっと苦しいのではないかと。クローディアス王が税率を下げてくださればいいが、王都というのは、他の州から巻き上げた税金によって成り立っているわけですからね。そこに住む特権階級の貴族らは、外苑州の庶民の苦しさについてなど、考えてみたこともないでしょう。だったら打ってみるべきだ、ということにもなるのではないですか?今でどうにかギリギリ黒字であるなら、いずれそれは赤字に転じるということになるでしょうから……そして、そのあたりの事情のほうはロットバルト州でも似たり寄ったりでしょう。財務長官のカンブレー卿というのは、どのようなお方ですか?」
カドールは、ようやく心に少しばかり余裕が生まれ、ドライフルーツ入りカステラをひとつ頂戴することにした。
「あくまでもこれは私の見たところ、ということですが……財務長官のカンブレー卿と法務長官のヴォーモン卿とは、信頼のおける人物と見ていいと思います。ともに貴族の元老院議員でもあるのですが、このふたりの言うことであればメレアガンス伯爵も耳をお傾けになることでしょう。そういえば、ヴォーモン卿は弟君が、そしてカンブレー卿は息子さんのひとりが聖ウルスラ騎士団の騎士だったと記憶しております。私は普段、このようなことは口にしないのですが、今、聖ウルスラ騎士団のほうも何かと大変なようですね。中には悪事に加担したことを後悔し、ここの懺悔室を訪れる者が何人となくいるようです」
「懺悔室で語られたことは、決して僧侶たちのほうで口外することはないとわかってはいるのですが……」と、カドールが聞いた。彼は同じ騎士として、悪事、と聞いては放っておくことが出来なかったのである。「騎士には守らねばならぬ十戒があることは、オスティリアスさまのほうでもよくご存知でしょう。まさかとは思いますが、弱い立場の民から金品を巻き上げる、あるいはあろうことか婦女子に乱暴するといったことがあったわけではないでしょうね?」
「私の口からはなんとも申し上げられませぬ。ですが、私自身もそれがどういった種類の悩みであるかは懺悔室にて直接聞きましたし、他の修道僧にしてもそうです。彼らは、騎士たちの悩みにどう答えるべきか自身も思い悩むあまり、私に相談しにきたのですよ。私たち僧には守秘義務がありますが、それでも自分の手に余ると感じた相談事については、私や他の僧との間で話しあいの場を持つことがありますからな……何より、ラウールさまの元へ向かわれた他のお仲間の方がおられるのであれば、そちらの事情についてはいずれ明らかとなることでしょう」
「では、オレもここでオスティリアスさまに人生相談しても構いませんか?」
出し抜けにハムレットがそう申し出たため、オドは少しばかり驚いた様子だった。口許まで持っていった紅茶茶碗を、一度受け皿へ戻している。
「ええ、もちろんですよ。もしそれが何か個人的なことであれば……懺悔室のほうへ移動いたしますか?」
「いや、いいんだ。それは、ここにいるタイスもカドールもよく知っていることだから……オレはここへやって来るまでの間、随分不思議な体験をしたのですよ。そうでもなければとても、現王権を倒して自分が王になるべきだなどとは、そんな恐れおおいことは考えられもしなかったに違いない」
ここでハムレットは、ヴィンゲン寺院にて受けた託宣のこと、三女神と出会ったのは自分だけではないこと、その後、言われたとおり<神の人>を探しに行ってみると、確かにその人物――今旅を共にしているギベルネという方がいたこと、他にキャメロン州やアヴァロン州であったことなどをなるべく短くつづめて、大まかに語った。
「ハムレットさま、では、もしやその剣というのが……」
「そうなんだ。今こうして見る限りにおいては、大して人目を惹くこともない、どうということもない剣なのに……時折、なんともいえない光と輝きを放つことがある。オレにしても、もしそうした不思議なことがなかったとしたら……今ごろはヴィンゲン寺院であったことは夢だったんじゃないか、オレはやはり王になる器などではないに違いないと苦悩していたと思います。けれど、同じく三女神から託宣を受ける現場にいた友のタイスが一緒にいてくれることで……また、ギベルネ先生が何かと助けてくださることでも、やはり出来るだけの努力をしなければならないと思い直すことが出来るのです」
「その<神の人>と呼ばれる方には、是非とも私としてもお会いしてみたいですが……ハムレットさま、大変恐縮ながら、その剣、私にも見せていただけませぬか。いえ、握らせてください、などと恐れおおい申し出をしているわけではないのです。ただもし、剣の柄か鞘にでも――竜の刻印でもあるのではないかと、そう思いまして……」
オドは実をいうと、この時点ですでにもう目に見えぬ王冠がハムレットの頭上に輝いているのを見て取っていた。このことは彼にとっては決して理屈ではなく、目の前にどのような困難が横たわっていようとも、最終的にこの方がクローディアスを倒し、間違いなく王位に就かれるだろうと予感したのである。
「すまないが、オスティリアスさま……」と、ハムレットは腰帯から鞘ごと剣を取ると、申し訳なさそうに言った。「確かに、この剣が光り輝く時、竜の紋章のようなものが剣の刃の表面に幻の如く現れることがあります。ですが、いつもとは限らぬゆえ……」
この時、ハムレットは(おそらく何も起きないだろう)と思っていた。だが、そのように自信のない彼がうっすらオパールに輝く鞘から剣を抜いた瞬間のことだった。そこには、今までハムレット自身ですら目にしたこともない強い輝きによって、剣の刃の表面に光の竜が浮き出ていたのである。しかもその光は、オドに向かって一瞬にして激しく伸びていき――彼に向かい、襲いかかっていったのである!!
「あなたこそ王です、あなたこそ王です、ハムレット王子よ!!」
オドは驚愕すると同時、椅子から立ち上がった。テーブルの紅茶茶碗がガチャリと揺れ、床に落ちて割れる。オドはその場に跪くと、ハムレットのことをその場で王として拝謁していた。
「不信仰な私をどうかお許しくださいませ……おお、ハムレットさま!!なんという運命の巡りあわせであることか。実は巫女さま方のおられる聖ウルスラ神殿には、代々守ってきたある秘宝があるのでございます。それは、聖女ウルスラが竜を倒すために星母神からいただいたという鎧冑であり、また、聖ウルスラ騎士団が守ってきたものと致しましては、竜の火を打ち消すことが出来るという大盾がございます。それらはすべて、竜の剣の所有者が持つべきものと定められております。なんとなれば、聖ウルスラ外典にそのように書き記されておりますれば……」
ハムレットが鞘に剣を収めると、大きな光の竜は消えた。光の竜の出現については、タイスもカドールも、ハムレット自身ですらが驚かされたが、それ以上に震えおののき頭を床につけたままでいるオド=オスティリアスこそが――長く修道院という場所で神に仕えていながらも、その神の力の片鱗に束の間触れただけで、まるで竜の逆鱗に触れたが如く、心底悔恨したような様子を見せていた。
実をいうと、のちにハムレットのこの旅の過程が書き記されることになる段には、ここで彼は次のように言うことになるらしい。『剣の竜という証拠を見たからそなたは信じたのか。だが、証拠を見ずして神を信じる者こそ、真の信仰者ぞ』と……けれど実際にはハムレットは、この敬虔な修道院長のほうに身を屈め、申し訳なさそうにこう言ったのである。
「どうか、お顔を上げてください、オスティリアス修道院長。実をいうとオレは女王ニムエにこう言われたのですよ。この剣の鞘と刃と、どちらが美しいと思うか、と……オレは光の竜の浮き出た刃のほうも美しいと思いましたが、もっと素晴らしいと感じたのは鞘のほうでした。すると、女王ニムエはこう言ったのです。『よく見たものだ。刃よりもそれを包む鞘を選んだということは、そちの治世は平和なものとなるだろう』と。逆に、もしオレが刃のほうを選んでいたとすれば、オレの治めることになる国は、戦乱の絶えない国になるだろうと、そういうことらしかったのです」
「では、では……やはりあなたさまがこの国の王となるべきお方ということ。ですが、この老いぼれにはなんの力もない。とはいえ、そうとわかった以上は、この命に代えても、出来ること何もかもせずにはおられませぬ。ああ、なんということだ!ハムレットさま、今こそ私の目は覚めましたぞ。私はおそらくいつしか、『あれこそ民の心のわかる、相談に足る人物、聖ウルスラ大修道院長さまぞ』と言われることにすっかり慣れてしまい、少しばかり慢心するところがあったようですわい。おお、なんたる不信心者か!このような者が大修道院長さまとは、まったく笑わせる!!」
ハムレットはオドが床に座したまま、自分の膝を容赦なく何度も打ち据える姿を見て胸を痛めた。また、タイスには彼の気持ちがよくわかる気がしていた。(俺にしても、ヴィンゲン寺院で三女神の顕現ということを経験した時、神を信じているはずの僧でありながら、実はいかに自分がひどい不信仰者であったかを思い知らされていたのだからな)と……。
「違います、大修道院長さま」と、ハムレットはオドに向かって身を屈めたまま、彼の両手を取って言った。「オレにはわかっています。あの光の竜は、オドさまの信仰心が強ければこそ反応したのです。でなければ、竜は姿を現すことさえなかったことでしょう。また、そのようにもしオドさまがメレアガンス伯爵を説得なさろうとしたところで難しいことが今はオレにもよくわかっている……聖ウルスラ騎士団のラウール殿にはランスロットたちが会いに行ってますから、オレたちはこれからどうすべきかについて、よくよく話しあわねばなりません。オドさまにおかれましては、今後、もしここの大聖堂で祈りをあげる時には――オレたちの旅の安寧と、この国の平和について是非とも祈っていただきたい。そして、そのような味方こそ、オレたちがもっとも必要とするものです」
「おお、ハムレットさま……!!」
この時、オド=オスティリアスはある種の信仰的感激が極まったかのように、最後には泣きだしてさえいた。このことには、普段ギベルネに対し(本当に<神の人>なのだろうか?)と疑ってきたカドールですらも心に感動するものを覚えていた。むしろ状況としては、メレアガンス伯爵もロットバルト伯爵も味方になってくれる公算は低いようにさえ思われるにも関わらず――今、礼拝堂という神のおられる御膝元において、この場にいる四人にはある見えているひとつのヴィジョンがあった。
それが「どのようにしてなされるか」はわからないし、その見通しも暗いようにさえ思われるにも関わらず……おそらくは最終的に運命は落ち着くべきところに落ち着くだろうという、それは未来図だった。それも、神の導きによってそのことは間違いなく成就されるだろうことを――彼らは不思議と一致して信じきることが出来たのである。
>>続く。