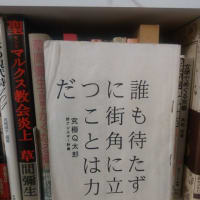中学二年の国語の授業の時のこと。その日の授業は、四〇人ほどいるクラスの生徒を六つほどに班分けし、各班ひとりずつ順番に黒板の前に出て行って立ち、女性教師がクイズ形式で出す問題の答えを一人で考えて黒板に書いて戻ってくるというものだった。ひどい劣等生だった私はこの授業形態のときは大抵正解できずに恥ずかしい思いをした。それだけでなく、班ごとに正解数を競うものだから、簡単な問題を間違えると同じ班の人間に罵られたりするので、それもまた憂鬱だった。
その日も順番が回ってきて仕方なく黒板の前に立った。教師が問題を言う。「それでは問題です。ふるさとの、『何』なつかし停車場の、ひとごみの中に、そを聴きに行く…、はい、この短歌の『何』の部分にはどんな言葉が入るでしょうか?」それを聞いて私はほっとした。その『何』のところに入る言葉は「訛」であることを私は知っていた。ちなみにこのクイズ形式で出される問題は、授業でやったやらない関係なく出されるので、本当にクイズのように答えを予測するしかない問題が出されることが多く、このときも最近石川啄木の短歌を授業でやったわけではなかった。でもとりあえず簡単な問題だったのでよかった。今日は恥を掻いたり責められたりしないで済む、と思いつつ私は黒板に「なまり」と書いて(漢字では書けなかった)席に戻った。すると同じ班の人たちは何かぽかんとしたような苦笑いのような、微妙な表情で戻ってきた私を見ていた。黒板を見ると、「なまり」と書いているのは私一人で、他の者は別の言葉を書いているか、なにも書いていなかった。クラス全体を見廻してみると、やはり皆一様に微妙な表情をしていた。
教師が手を叩いて注意を促した。「はい、全員席に戻りましたね。はい、それでは正解の発表です。ここには、な、ま、り、という言葉が入ります。ふるさとの、訛懐かし停車場の、ひとごみの中に、そを聴きに行く、というのが正解です。ということで正解は…小林くん(私の本名)ひとりだけですね。素晴らしいー、はい拍手」クラス中から「おー」というどよめきがあがって拍手が起こり、ひとしきり騒ぎになった。どうやら「訛」という答えを知っていたのはクラスの中でもごく少数か、あるいは私ひとりのようだった。拍手や歓声を浴びて半笑いになりながら、私は狐につままれたような気持ちになっていた。私は劣等生であり、それはもう本当に劣等生だった。テストでも50点より上を取ることが滅多にないくらい本物の劣等生だった。授業なんて国語だろうが数学だろうがなんだろうが、いつだって空想に浸っているか外をぼんやり見るかしていて全く聞いていなかった。そんな私がなぜかこの句は知っていた。(石川啄木の短歌ということまでは知らなかった)というか、馬鹿の私が知っているくらいなのだから、誰もが当然知っているものだと思っていた。ではなぜ私はこの短歌を知っていたのか。以前に授業でやったのならば、ほかにも答えられるひとはいただろうし、クラスがどよめくようなこともなかっただろう。では授業以外でその短歌を知ったのか。上野駅に歌碑があるほど有名な句だから、確かにテレビなどで見ることもあったかもしれない。
当時の私の脳味噌にはバスケットボールとロックミュージックといくつかの漫画以外はほぼ何も記録されていなかった。そこにいつの間にか啄木の短歌の一節が知らぬ間に紛れ込んでいて、それなりに定着していた。バスケットやロックに比べて地味すぎるその歌がなぜ私に定着したのかははっきりしない。詩言語が持つ言葉の響きというものを、私はその頃から無意識に気に入っていたのかもしれない。あるいはそれらの言葉が音楽的な響きを持っていることが気に入ったのかもしれない。授業で聞いたにしろ、日常生活で聞いたにしろ、注意散漫な私の頭に強い印象を持って残っていたのだから、それは私にとって特別なもの、あるいは必要なものだったのだろう。
しかし私はふうんと思っただけで、それきり詩や短歌のことを考えることなく、また浅はかな中学生の日常に戻っていった。詩歌の持つ魅力は私の無意識に留められはしたが、そのことを認識すらできずに忘れてしまった。それから二十年が経ち、啄木とは全く関係ないあるきっかけでようやく私は詩のようなものを書き始める。そしてそれから十五年。この間書いてきたものといえば比較的わかりやすい言葉を使った行分け詩が大半だ。短歌に興味はほとんどないが、啄木のあの歌のあの響きが、いまの私が持つ詩の価値観に根強く影響していないとは言えない。そして私はその価値観から抜け出してやろうなどとはちっとも思わずに詩を書いてきた。そしてこれからも十代の頃に焼きつけられたものに手を伸ばしながら詩を書き続けていくのだろう。それは表現者として、いいことではないのかもしれないけれど。
その日も順番が回ってきて仕方なく黒板の前に立った。教師が問題を言う。「それでは問題です。ふるさとの、『何』なつかし停車場の、ひとごみの中に、そを聴きに行く…、はい、この短歌の『何』の部分にはどんな言葉が入るでしょうか?」それを聞いて私はほっとした。その『何』のところに入る言葉は「訛」であることを私は知っていた。ちなみにこのクイズ形式で出される問題は、授業でやったやらない関係なく出されるので、本当にクイズのように答えを予測するしかない問題が出されることが多く、このときも最近石川啄木の短歌を授業でやったわけではなかった。でもとりあえず簡単な問題だったのでよかった。今日は恥を掻いたり責められたりしないで済む、と思いつつ私は黒板に「なまり」と書いて(漢字では書けなかった)席に戻った。すると同じ班の人たちは何かぽかんとしたような苦笑いのような、微妙な表情で戻ってきた私を見ていた。黒板を見ると、「なまり」と書いているのは私一人で、他の者は別の言葉を書いているか、なにも書いていなかった。クラス全体を見廻してみると、やはり皆一様に微妙な表情をしていた。
教師が手を叩いて注意を促した。「はい、全員席に戻りましたね。はい、それでは正解の発表です。ここには、な、ま、り、という言葉が入ります。ふるさとの、訛懐かし停車場の、ひとごみの中に、そを聴きに行く、というのが正解です。ということで正解は…小林くん(私の本名)ひとりだけですね。素晴らしいー、はい拍手」クラス中から「おー」というどよめきがあがって拍手が起こり、ひとしきり騒ぎになった。どうやら「訛」という答えを知っていたのはクラスの中でもごく少数か、あるいは私ひとりのようだった。拍手や歓声を浴びて半笑いになりながら、私は狐につままれたような気持ちになっていた。私は劣等生であり、それはもう本当に劣等生だった。テストでも50点より上を取ることが滅多にないくらい本物の劣等生だった。授業なんて国語だろうが数学だろうがなんだろうが、いつだって空想に浸っているか外をぼんやり見るかしていて全く聞いていなかった。そんな私がなぜかこの句は知っていた。(石川啄木の短歌ということまでは知らなかった)というか、馬鹿の私が知っているくらいなのだから、誰もが当然知っているものだと思っていた。ではなぜ私はこの短歌を知っていたのか。以前に授業でやったのならば、ほかにも答えられるひとはいただろうし、クラスがどよめくようなこともなかっただろう。では授業以外でその短歌を知ったのか。上野駅に歌碑があるほど有名な句だから、確かにテレビなどで見ることもあったかもしれない。
当時の私の脳味噌にはバスケットボールとロックミュージックといくつかの漫画以外はほぼ何も記録されていなかった。そこにいつの間にか啄木の短歌の一節が知らぬ間に紛れ込んでいて、それなりに定着していた。バスケットやロックに比べて地味すぎるその歌がなぜ私に定着したのかははっきりしない。詩言語が持つ言葉の響きというものを、私はその頃から無意識に気に入っていたのかもしれない。あるいはそれらの言葉が音楽的な響きを持っていることが気に入ったのかもしれない。授業で聞いたにしろ、日常生活で聞いたにしろ、注意散漫な私の頭に強い印象を持って残っていたのだから、それは私にとって特別なもの、あるいは必要なものだったのだろう。
しかし私はふうんと思っただけで、それきり詩や短歌のことを考えることなく、また浅はかな中学生の日常に戻っていった。詩歌の持つ魅力は私の無意識に留められはしたが、そのことを認識すらできずに忘れてしまった。それから二十年が経ち、啄木とは全く関係ないあるきっかけでようやく私は詩のようなものを書き始める。そしてそれから十五年。この間書いてきたものといえば比較的わかりやすい言葉を使った行分け詩が大半だ。短歌に興味はほとんどないが、啄木のあの歌のあの響きが、いまの私が持つ詩の価値観に根強く影響していないとは言えない。そして私はその価値観から抜け出してやろうなどとはちっとも思わずに詩を書いてきた。そしてこれからも十代の頃に焼きつけられたものに手を伸ばしながら詩を書き続けていくのだろう。それは表現者として、いいことではないのかもしれないけれど。