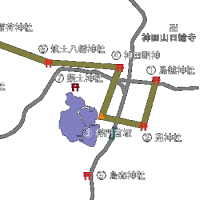はい、今回はご好評につき、『歴史のからくり』シリーズ第2段を書いてみましょうか。前回ご紹介いたしました4人の歴史上の人物、これに2人加えまして6人にしてみました。幕末の坂本龍馬と、飛鳥の聖徳太子です。作り直した表をご覧ください。
これ眺めてみると壮観ですね。「これ全部お前の過去世なのかよ」とか言われちゃうと困るのですが、『カルマ関係者』であることは確かみたいです。ここで『過去世』という言葉をもう一度検証してみましょう。6人揃ったところで当てはめることができる、面白い理論があるんですね。それは魂の『本体と分身』理論です。
ひとつの魂の構造は、1人の本体と5人の分身によって成り立ち、同じ傾向性を保ちながら、順番に地上に生まれ変わって魂修行をしているというお話し。その際、それぞれの人の経験は、6人チームで共有されるということなのです。(幸福の科学出版『太陽の法』第2章参照)
この理論を私のカルマ関係者に当てはめて見ますと、とりあえず一番格が高そうなのが聖徳太子なので『本体』とします。そうしますとほかの5人が『分身』ということになりまして、共通の目的意識である『国造り』という仕事のために、順番にカルマバランスを取りながら、個性化して色々な花を咲かせている、『にゃんこ』な人たちと言うことができます。名づけて『国造りにゃんこチーム』です。
この人たちは、理論的に言いますと、6回に1回しか生まれ変わることができないので、この6人の人たちの本当の過去世は、もう一巡遡らないと出てこない、ということになるんですね。ですから大体1400年に1回の転生という計算になるでしょうか。とてもアバウトなのですが・・。もうね、この前の人として3人くらい目星を付けてあるんですがね、その人たちは一巡先の人の人生にシンクロして似ています。本当の過去世ってそういう感じになると思います。生き様が似てくるんですね。
たとえば『日蓮聖人』ですが、この方の過去世はあの『マルティン・ルター』だと言われています。「法華経のみが正しい」と言った日蓮聖人と、「聖書のみをもって義とすべし」と言ったマルティン・ルターは、よくシンクロしているように見えます。権威に反逆して罰せられるところも似ていますし、他宗派を激烈に攻撃するようなところも似ています。こういうふうなシンクロ状態が確認できるのが、どうやら本当の過去世ということらしいですね。
パウロと親鸞聖人も、『罪』という意識が深いのがよくシンクロしているのですが、これ結構問題なんですね。原始キリスト教の教会を作ったのはパウロとペテロなのですが、パウロは回心する前、熱心なキリスト信者『ステファノ』を殺しました。それからペテロはイエスが十字架にかかろうとしている目の前で、「この人のことは知らない」と3回言ったんですね。このことで2人とも、とても深い罪悪感があるのですが、この2人が教会を立ち上げたところに後世キリスト教に『罪』の意識が深く入り込む原因があったという説があります。私もなんだかそんな気がいたしますね。『おとぼけにゃんこ』がキリスト者本来の信仰存在様式なのであるならば、『罪』の意識はなくなって自由になっているはずです。その自由で楽しい雰囲気がなくなっているのであるならば、もはや病的と言わざるを得ないでしょう。過程に苦悩のドラマがあったとしても、ゴールは楽しいはずなのです。ま、これは『にゃんこ王国』の補足なのですが・・。
さて、ここまでお話しできればすごい予測ができるんですねぇ、面白いです。それはこの『にゃんこチーム』6人の次に生まれてくる人です。その人は、順番からいきますと、『聖徳太子の再来』ということになります。ご本体の登場なんですね。そして陽のキャラクターの坂本龍馬が果たせなかった何らかのコンセプト、忘れものを拾って大輪の花を咲かせるという使命を持っているはずです。聖徳太子の再来・・、なんだか考えただけでワクワクしてこないでしょうか・・・。
それにしてもあれですね、坂本龍馬の忘れものってなんだったのでしょう。常識的には明治新政府が坂本龍馬のビジョンを実現したもののように見えるのですが・・、この『忘れもの』がなんだかわかる方いらっしゃるでしょうか・・・。
ひょっとして龍馬はアセンションまで見越していたのか・・・。
続く・・
<あとがき>
ま、あくまでも理論的に導き出した結果ですので、神託のように受け取れれても困るのですが、本当にそうなら自然にかたちになっていくのでしょう。
ということで、坂本龍馬と聖徳太子の情報や、ほかの法則を発見したという方等、いろいろご意見をお寄せいただいて盛り上げていったら面白いかと思います。宜しくお願いいたします。

/文:シュバン/平将門関連書籍/将門奉賛会/
これ眺めてみると壮観ですね。「これ全部お前の過去世なのかよ」とか言われちゃうと困るのですが、『カルマ関係者』であることは確かみたいです。ここで『過去世』という言葉をもう一度検証してみましょう。6人揃ったところで当てはめることができる、面白い理論があるんですね。それは魂の『本体と分身』理論です。
ひとつの魂の構造は、1人の本体と5人の分身によって成り立ち、同じ傾向性を保ちながら、順番に地上に生まれ変わって魂修行をしているというお話し。その際、それぞれの人の経験は、6人チームで共有されるということなのです。(幸福の科学出版『太陽の法』第2章参照)
この理論を私のカルマ関係者に当てはめて見ますと、とりあえず一番格が高そうなのが聖徳太子なので『本体』とします。そうしますとほかの5人が『分身』ということになりまして、共通の目的意識である『国造り』という仕事のために、順番にカルマバランスを取りながら、個性化して色々な花を咲かせている、『にゃんこ』な人たちと言うことができます。名づけて『国造りにゃんこチーム』です。
この人たちは、理論的に言いますと、6回に1回しか生まれ変わることができないので、この6人の人たちの本当の過去世は、もう一巡遡らないと出てこない、ということになるんですね。ですから大体1400年に1回の転生という計算になるでしょうか。とてもアバウトなのですが・・。もうね、この前の人として3人くらい目星を付けてあるんですがね、その人たちは一巡先の人の人生にシンクロして似ています。本当の過去世ってそういう感じになると思います。生き様が似てくるんですね。
たとえば『日蓮聖人』ですが、この方の過去世はあの『マルティン・ルター』だと言われています。「法華経のみが正しい」と言った日蓮聖人と、「聖書のみをもって義とすべし」と言ったマルティン・ルターは、よくシンクロしているように見えます。権威に反逆して罰せられるところも似ていますし、他宗派を激烈に攻撃するようなところも似ています。こういうふうなシンクロ状態が確認できるのが、どうやら本当の過去世ということらしいですね。
パウロと親鸞聖人も、『罪』という意識が深いのがよくシンクロしているのですが、これ結構問題なんですね。原始キリスト教の教会を作ったのはパウロとペテロなのですが、パウロは回心する前、熱心なキリスト信者『ステファノ』を殺しました。それからペテロはイエスが十字架にかかろうとしている目の前で、「この人のことは知らない」と3回言ったんですね。このことで2人とも、とても深い罪悪感があるのですが、この2人が教会を立ち上げたところに後世キリスト教に『罪』の意識が深く入り込む原因があったという説があります。私もなんだかそんな気がいたしますね。『おとぼけにゃんこ』がキリスト者本来の信仰存在様式なのであるならば、『罪』の意識はなくなって自由になっているはずです。その自由で楽しい雰囲気がなくなっているのであるならば、もはや病的と言わざるを得ないでしょう。過程に苦悩のドラマがあったとしても、ゴールは楽しいはずなのです。ま、これは『にゃんこ王国』の補足なのですが・・。
さて、ここまでお話しできればすごい予測ができるんですねぇ、面白いです。それはこの『にゃんこチーム』6人の次に生まれてくる人です。その人は、順番からいきますと、『聖徳太子の再来』ということになります。ご本体の登場なんですね。そして陽のキャラクターの坂本龍馬が果たせなかった何らかのコンセプト、忘れものを拾って大輪の花を咲かせるという使命を持っているはずです。聖徳太子の再来・・、なんだか考えただけでワクワクしてこないでしょうか・・・。
それにしてもあれですね、坂本龍馬の忘れものってなんだったのでしょう。常識的には明治新政府が坂本龍馬のビジョンを実現したもののように見えるのですが・・、この『忘れもの』がなんだかわかる方いらっしゃるでしょうか・・・。
ひょっとして龍馬はアセンションまで見越していたのか・・・。
続く・・
<あとがき>
ま、あくまでも理論的に導き出した結果ですので、神託のように受け取れれても困るのですが、本当にそうなら自然にかたちになっていくのでしょう。
ということで、坂本龍馬と聖徳太子の情報や、ほかの法則を発見したという方等、いろいろご意見をお寄せいただいて盛り上げていったら面白いかと思います。宜しくお願いいたします。
/文:シュバン/平将門関連書籍/将門奉賛会/