
2024/10/02 wed
前回の章
一本の縄で繋がれたまま地下へ向かう階段を降りる。
よく覚えておこう。
いつか自分の手でこの事を作品として書くまでは……。
数名の警官と俺ら罪人たちしか通らない通路を黙々と歩きながら、地下の集合場所へ向かう。
薄暗い中を進み、何度か左右に曲がる。
一列縦隊で指示されながらだから、ただ黙って歩くのみ。
「池袋方面、総員二十三名、到着」
いつもの集合場所へ行くと、俺たちはベンチに座らされ、自分の名前を呼ばれるまで大人しく待つ。
「巣鴨、岩上」
「はい」
呼ばれた時だけ立ち上がり、返事をする。
それからまた硬い木のベンチがある檻の中へ振り分けられた。
どのように区別されているのか知らないが、ここでは別々の者同士が適当に振り分けられているような気がする。
「あれ、久しぶりです」
檻のベンチに腰掛けた瞬間、小声で隣の奴が話し掛けてきた。
見ると一番街通りのゲーム屋ワールドワンで、俺が店長をしていた頃よく来てくれた客だった。
千人近くいる場所で、奇遇にもこうして顔を合わせるなんてすごい偶然である。
「ああ、お久しぶりです。元気でしたか?」
「元気と言うか…、まあ退屈ですよね。知り合いに会うと思いませんでしたが」
「それは俺もです。何をして捕まったんです?」
「自分はシャブです。店長は? ゲーム屋で?」
「いえいえ、ビデオだから猥褻図画ですね」
「ワールドワン時代、『俺は絶対に捕まらない』とか言ってたじゃないですか」
「しょうがないですよ。捕まっちゃったんだから」
俺たちは顔を見合わせて大笑いすると、すぐに警察官がすっ飛んできて「喋ってんじゃねえぞ、おまえら」と怒鳴りつけてきた。
すると向かいに座る男が立ち上がり、牢屋に近づく。
「看守さん…、紙を」
非常に嫌な予感がする。
案の定、男は片手錠になり、トイレットペーパーを両腕でクルクルと巻き出した。
レッツ、ショータイム。
これから異臭漂うウンコタイムの始まりだ。
他人がクソをしている空間にただ黙って座っているのは、拷問以外の何ものでもない。
それでも文句一つ言う権利すらない俺たち。
堅い木のベンチが尻に食い込んで痛い。
はあ…、毎度の事ながら、ここへ来る度悪い事はしちゃいけないって反省する。
ブリッ…、ブリリ……。
ゲッ…、あの野郎、ひょっとして下痢かよ……。
ブリッ…、ブリュリュ……。プー……。
もう!
クソしたら早く水で流せよ、この馬鹿っ!
そうやって怒鳴りつけたいが、それさえも禁じられている俺ら。
部屋の中にいる全員が手錠を掛けた両腕を上げ、黙って鼻をつまんでいた。
最後の最後でとんだ味噌がついたもんだ。
「巣鴨、岩上」
「はーい」
ようやく俺の番が来たようだ。
ここに着いてからどのぐらい時間が経ったんだ?
今日で釈放なんだから、もうちょっと早く呼べばいいのに。
警察官二人に挟まれるような形で、黙々と細長い通路を歩く。
コンコン……。
軽くドアをノックする警察官。
少ししてから「失礼します」とドアを開ける。
中にはいつもの検事と秘書の女二人が座っていた。
「……」
このバカボンパパ似の検事が接見禁止を解かないから、俺は誰とも面会できなかったのだ。
本当にこの馬鹿はムカつく。
向かいの椅子に座らされると、手錠についた青い縄を解かれ、そのまま背もたれと一緒にグルグル体ごと巻かれる。
これは犯罪者が暴れたり、逃げようとしたりしないような処置なのだろう。
手錠は外されているので、このぐらいは当たり前か。
再び「失礼します」と頭を下げ、二人の警察官は部屋を出て行く。
これでこの中は俺と検事と秘書の三人だけになる。
このブサイクな秘書とブ男検事は、プライベートでやっちゃったりしているのかね?
そんなどうでもいい事を考えていると、検事が口をようやく開いた。
「岩上智一郎…、罪名、猥褻図画販売目的所持。今回に限り初犯という考慮をして…、ば…、罰金五十万」
とても悔しそうに言う検事。
不起訴確定の瞬間だった。
しかし表向きは裏DVDを売る仕事をして四回目というだけで、五十万円も罰金を取ろうとしているのだ。
普通に考えてみればおかしい話。調書上では一日一万二千円しかもらえていないと伝えてある。金額にすれば四万八千円しか給料をもらっていない計算なのである。いや、四回目の途中で捕まっている設定だから、三万六千円か。
どちらにしても、簡単にその金額を決められる検事。
こんな奴が国を動かした気でいるから世の中おかしくなっているんだろう。
どうせこれで釈放だ。
ならば一つぐらいリアクションをしておこう。
「五十万? ずいぶんと高いな。こっちはたった数万しかもらっていないのによ」
「何だ、キサマ……」
検事の目が鋭くなる。
「キサマ? そっちこそその言い方って何だよ? 俺だってちゃんとした一人の人間だ。確かに検事さんは人間を裁く立場かもしれない。でもな、もうちょっと人間の痛みってもんを知っといたほうがいい」
「何だと、この若造が……」
昔から猛勉強をしていい大学へ入り、こうした立場の仕事につく。
世間一般で見れば、エリートコースだろう。
だが、こんな社会経験ゼロの男が自己判断で人を裁く。
本当にそれでいいのかよ。
罰金の五十万は組織がすぐ用意してくれるので、俺は別段痛くない。
それでもひと言自分の気持ちをこうして言ってやりたかった。
「あんたが俺を不起訴に決めたんだ。俺は今日で釈放。これもあんたが決めた」
「だから何だ?」
「悔しいだろ? 俺を起訴できなくて」
「くっ……」
絶対に起訴をさせないという俺の持論が、国の法律に勝ったのだ。
食いたいものも自由に食えず、女も抱けない退屈で苦痛の二十二日間。
俺はそれに耐え抜き、持論を押し通した。
本当はこんな裏稼業の世界で幅を利かせるのではなく、リングの上で戦っていたかった。
ずっと今回はプロレスの試合で想定すれば、相手の技をひたすら受けて耐えている状況である。
だから最後にこっちの必殺技をお見舞いしなきゃいけない。
プロレスってそういうものだから。
「いいか……」
俺は縄で括りつけられた椅子ごと立ち上がる。
「な、何だ、キサマ!」
一瞬怯む検事。
「安心しろって、何もしねえよ。俺の調書にプロレスと総合格闘技って書いてあったろ?」
「だ、だから何だ?」
「せっかくだし、対戦相手が気に食わない時、どうやってパフォーマンスをするか見せておこうかなと思ってね」
ゆっくりと天井を見上げ、それから目線だけ下に向け検事を見据える。
右の拳を真正面に突き出してから、ピンと親指だけを伸ばす。
その状態のまま時間を掛けて肘を曲げ、左頬下の首まで右手を持っていく。
「……」
検事は黙って俺の行動を睨んでいた。
目を見開きながら舌を出し、スローモーションに真横へ腕を動かす。
首を掻っ切るポーズを終えると、上から見下ろすようにして検事を睨みつける。
「俺は少なくてもこうやって対戦相手を威嚇するんだ」
「ふ、ふざけるなっ!」
真っ赤な顔をして怒る検事だが、もう遅い。
俺はこれで釈放。
ようやく娑婆の空気を自由に吸えるのだ。
「検事さん…、別にふざけてなんかいねえよ。大真面目だ」
そう言って俺は不敵に笑った。
地下鉄に乗って池袋駅まで向かう。
まずは百合子に連絡を入れないと。
返してもらった携帯電話を取り出し電話を掛けようとすると、いきなり着信が入る。
知らない番号だった。
末尾が一一〇なんで、どこかの警察署というだけは分かる。
釈放されたばかりなのに何故?
これ以上やましい事などないので、電話に出た。
「あ、こちら川越警察署です」
「は?」
「川越警察署なんですが。岩上智一郎さんですよね?」
「はあ、何でしょうか?」
「ご家族の方から捜索願いが出てまして、それで電話をしてみたところなんです」
なるほど、俺が捕まってから二十二日間経つ。
大方弟の徹也辺りが心配して警察にって事も考えられる。
それにしてもついさっきまで巣鴨警察署にいたのに、何もこいつら分からないのか。
「そうなんですか。ちょいと仕事で大阪のほうへ行ってましてね。それで出発する前知人のところに泊めてもらったんですが、その時携帯を忘れてしまったんですよ」
よくもまあ俺もこう嘘がポンポンと出てくるもんだ。
「ああ、そうですか」
「まあ、そんな訳なんで捜索願いは取り消しといて下さい」
「かしこまりました」
「お騒がせして申し訳ないですね。お疲れさまです」
電話を切ると、百合子にメールを打ってみた。
《心配掛けてすまなかったな。無事出て来れたぞ。今仕事中だろうからメールにしといた。このあと歌舞伎町へ行ってオーナーたちと会うから、そのあとゆっくり会おう。 岩上》
あとはどうするか?
とりあえず歌舞伎町へ向かうとして、家でも大騒ぎになっている可能性がある。
徹也に電話を入れておくか。
「あ、兄貴?」
「おう、久しぶりだな」
「何をやってたんだよ? ずっと連絡つかないからさ、家じゃ大騒ぎだよ」
「悪かったよ。仕事で大阪へ行っててさ、携帯こっちに忘れてしまったんだ」
「家じゃ兄貴宛てに俺々詐欺の電話あってさ」
「はあ、俺々詐欺? 何だそりゃ?」
「パートの緑さんいるじゃん」
「ああ、で?」
「緑さんが電話を取ったらいきなり兄貴が事故ったって。それで親父に『智ちゃんが事故ちゃったー!』って大袈裟に言うもんだから親父も焦って出てさ」
「うん、それで?」
「相手が急いでいるところいきなり突っ込まれ、それで家に電話をしたとね。で、親父もパニくっているからさ、俺が代わったの。まず状況を聞こうと思ってさ」
「ああ」
「そしたら知り合いの車屋に見せたら結構いっちゃってるから、とりあえず百万円を振り込んでくれって」
「へえ」
「で、俺も車屋だから、どこにそんな事故したばかりで査定を出せるところがあるの?って聞いてさ。そんな車屋があるなら逆に紹介してほしいって。それで話にならないから兄貴を出して下さいって言ったんだ」
「うん」
「そしたらおまえの兄貴はブルブル震えちゃって電話で話せる状況じゃないなんて言うからさ。ああ、じゃあそれ兄貴じゃないっすねって。元々嘘だと思ってたから色々つっ込んだら、相手、何も言えなくなっちゃってね。向こうから電話を切っちゃったんだ。で、俺々詐欺なんだって分かって。でもそういえば兄貴を見た人間が誰もいないって話になってさ、どっかで無茶してさらわれて監禁されてんじゃねえのって捜索願いを出したんだよ」
「馬鹿か…。俺が何で無茶をしなきゃいけねえんだよ。今さっき川越警察から電話あったから取り下げといたよ」
「でもさ、連絡ぐらいつけるようにしといてくれよ。兄貴の仲がいい先輩の坊主さんや神田さんとかに聞いても分からないって言うしさ。大騒ぎだったんだぜ?」
「悪かったよ。一本電話をしときゃよかったな」
「坊主さんとかも心配してたから連絡しといたほうがいいよ」
「ああ、すぐするよ」
電話を切って坊主さんや神田さんへ掛ける。
みんな、俺がもう殺されたんじゃないかって大騒ぎだったらしい。
弟の徹也に本当の事を言えなかったのは、おじいちゃんの耳に入ると困るからだ。
警察のご厄介になんて外聞悪いだろうし、いらぬ心配を掛けてしまう。
なので仕事で大阪にという線は崩せない。
坊主さんらには真実を伝え安心させた。
そういえば中に入っている時、百合子に榊先生へ連絡しとけってメールしていたけどうまく言い訳できたかな?
電話をしてみると、タイミング良く先生が出てくれた。
事情を話すと、「何だ、この野郎…。まあ、これはうちの女房や由香には言えないなあ。俺とおまえの話だけにしとこう。いきなりおまえの彼女から電話あったから、何かと思ったよ」とブツブツ文句を言っていた。
久しぶりの歌舞伎町。
靖国通りを渡り、歌舞伎町へ向かう。
道を歩いていると顔見知りの人間とすれ違い、俺の顔を見ると「お疲れさまでした」と声を掛けてくれる。
さくら通りをゆっくり歩くと知り合いがまるで俺の帰りを待っていたように左右に並び、みんな笑顔で「お疲れさま」と言ってくれた。
この街に生き、この街を愛してきた。
わずか二十二日間だったがずいぶんと昔の事のように思える。
ここが俺にとって居場所。
また戻ってきたんだ、この街に……。
奥でオーナーの高山、金子、村川の姿が見える。
照れ臭そうに会釈をすると、「辛い思いさせてすまんかったなあ」と肩を叩いてきた。
「松本さんは?」
「今、野方警察署にいる」
「そうですか……」
「とりあえず喉渇いてるやろ? ラーセン行こう」
コマ劇場裏手にあるビデオ村。
その近くにある喫茶店のラーセン。
初老マスターが一人で細々と営んでいるレトロな店である。
マスターは俺の顔を見ると、嬉しそうに「お疲れさん」と声を掛けてくる。
アイスコーヒーを注文し、留置所の話をひと通りした。
オーナーたちは財布を取り出し、「少ないけど取っておいてくれ」と一人二十万円ずつテーブルの上に置く。全部で六十万。
「しばらく女抱いてないだろ? バルボアにでも行こうか」
バルボア…、歌舞伎町で一番高級なソープランドである。
百合子の存在がなければ喜んで行くところだ。
「いえ、お気持ちだけで…。一番始めに抱かなきゃいけない女がいますんで」
「そうか。じゃあ、これは気持ちや。取っとき」
さらに高山が五万円をテーブルの上へ置いてくる。続いて金子と村川も同じ額を置く。
「いえ、こんなにもらったら……」
「気持ちや、気持ち。うまいものぎょうさん食って、ゆっくりしてきたらええ。本当にお疲れさん」
二十二日間の留置所生活。
組織の為というよりも、俺は純粋にあの空間を楽しんだだけ。
それなのに手元に七十五万円の金が入ってきた。
「他の店は? 『ビビット』と『らっきょ』は無事ですか?」
「ああ、今のところ大丈夫」
「良かった……」
「しばらくゆっくりしてきな。店の事は考えんでもええ」
もう少し話していたいが、百合子の奴、首を長くして待っているだろう。
深々とお辞儀をしてラーセンをあとにした。
まずは肉だ。
肉を食いたい。
パンパンに膨らんだ財布をスーツの内ポケットに入れ、俺は西武新宿駅へ向かった。
特急小江戸号が本川越駅に到着する。
改札を出て駅前のロータリーへ走った。
白い軽自動車に寄り掛かるようにして百合子は俺を見ていた。
「し、心配掛けたな」
満面の笑みを浮かべ近づくと、いきなり顔面にパンチをされる。
「馬鹿馬鹿……」
好きなだけ殴らせてやった。
「よし、とりあえず肉を食うぞ。ステーキだ。あそこの駅前のところ行こう」
一人前七千円のステーキを注文し食べる。
こんな高級肉など滅多に食べないが、出てきたのが冷凍肉だったせいもあり感動はいまいちだった。
腹が満腹になると、そのままホテルへ向かう。
「ほら、取っておけ」
オーナーから七十五万円をもらったので、三十万円をあげた。
百合子は何度も断ったが、半ば強引に渡した。
バックから『キン肉マン超人大全集』を取り出し、笑いながらパラパラとページをめくる。
よくもまあこんな本を警察に差し入れようとしたもんだ。
「いつも『俺は大丈夫だ』なんて偉そうに言っていたくせに、いきなり警察に捕まっちゃうんだもん……」
「悪かったよ。もうこんな事ないから安心してくれ」
「大変だったんだからね。大塚駅まで重いトランクを引っ張ってやっとの思いで到着したのに、靴下とその本しか受け取ってくれないんだもの」
「しょうがない。接見禁止だったんだから。文句は検事に言ってくれ」
「馬鹿…、反省が足りないぞ」
「……。すみません……」
「キスして」
「ああ……」
その日何度も百合子を思う存分抱く。
この二十二日間、こいつは待ってくれるという不思議な自信があった。
いや、信頼という表現が適切だろうか。
「これからどうするの?」
「数日ゆっくりして、それから考える。一応組織にもまだ顔出すようだろうし」
「そう」
「何かして欲しい事あるか?」
全身汗だくになりながら聞くと、百合子はジッと俺の顔を見ているだけだった。
「どうした?」
何かを言いたそうな表情の百合子。
しばらく無言でセックスに没頭した。
「中に欲しい。中にちょうだい……」
大きな喘ぎ声を出しながら、百合子は言った。
「……」
百合子の覚悟。
ずっと俺を待っていたのか。
自分が子供を作るなんて、これまで考えた事などなかった……。
ヒステリックなお袋。
肩身の狭かった学生時代。
同じ学校へ通う従兄弟の宇津木裕子からは、「あいつの家はよってたかってお母さんを追い出したんだよ」と陰で言われ続けられた。
担任の一倉先生までが裕子の話を鵜呑みにし、俺に出て行った母親と会わせようと当時したぐらいだ。
勉強がいくらできたって、強くならないと殺されちゃう……。
力無き子供の頃、心の底からそう感じた。
理不尽な暴力による虐待。
左まぶたの上についた二つの傷跡。
未だ消えやしない。
一つ目の傷がついた発端は、俺が塾をサボったから。
当時住み込みで働いていたせっちゃんは、八つの塾へ強制的に通わされ休む日がない俺を見て、哀れに感じたのだろう。
近所の喫茶店へ連れて行ってくれ、ピザトーストをご馳走してくれた。
母親に見つかるとは考えていなかったんだよな……。
「……」
部屋に着くなり、お袋は俺をソファの上に投げつける。
テレビを見ていたまだ幼稚園児の弟の徹也は、その急展開にビックリしたようで部屋の隅に行きビクビク震えていた。
まだ小さい貴彦は何も知らず寝ている。
僕は泣きながら何度も頭を地面にこすりつけ、必死に懇願した。
容赦なく手当たり次第叩くお袋。
塾を一つさぼる事が、ここまで悪い事だなんて全然思ってもみなかった。
「まったく舐めた真似してくれたね。このガキは……」
いつもより感情が高ぶり、お袋は高音で怒鳴っていた。
その声を聞いているだけで、心に冷たいものが通過する。
髪の毛をつかんで強引に立たされ振り回された。
当時の俺には泣く事ぐらいしかできない。
視界がグルグル回り、様々な角度を映している。
自分が今、どのような目に遭っているのかすら分からなかった。
突然、ガラスのテーブルが目の前に迫ってくる。
俺は瞬間的に目を閉じた。
ガチャンという音と共に、激しい痛みが襲う。
気がつくと、僕は床の上で倒れていた。
ズキッとした痛みを左まぶた辺りに感じる。
そっと手を触れてみた。
ぬるっとした嫌な感触。
左手の指先を見ると、人差し指に赤い血がついていた。
そう…、これが初めて振るわれた暴力だった。
一つ目の傷がついたあの出来事……。
二つ目の傷の発端は、ひもじさから来たものである。
原因は一階のおじいちゃんとおばあちゃんのところへ、弟たちを連れてご飯を食べさせたから。
いつも夜になると出掛けてしまう両親。
腹が減ったとまだ幼稚園の徹也と、赤ちゃんだった貴彦は泣き続けた。
だから他に方法がなく…、仕方なく下へ連れて行ったのだ。
帰ってきてそれを目撃した母親は、感情的になり長男の俺へ怒りをぶつける。
あの時は本当に殺されると思ったっけなあ……。
ドアの隙間から睨みつけるお袋と視線が合う。
「……!」
一瞬、心臓が止まったかと感じる。
俺は扉の少し開いた隙間を見て、ご飯の茶碗をテーブルに落としてしまった。
「ちゃんとしっかり持たないと駄目だよ、智一郎」
おばあちゃんが注意をしても、俺の耳には届かなかった。
全神経は、僅かに開いた扉の隙間に注がれていた。
隙間から見える暗闇。
真っ暗な部分に白い目が、一つだけ見えたのだ。
その目は怒りを表しているかのように釣り上がっている。
幼いながら俺は、それがお袋だと直感的に分かった。
全身がガクガク震えだす。
もっと早めに食べ終わり、すぐに二階の部屋に戻るべきだったのだ。
あれほど、注意していたはずなのに……。
誰も扉の向こうにいる存在に気がつかない。
俺だけがそれを知っているのだ。
隙間から白い手が見え、ゆっくりと手招きしている。
俺は操られるかのように立ち上がってしまう。
「どうした、智一郎」
「も、もう…、お腹いっぱい……」
それだけ言うのが精一杯だった。
おじいちゃんたちに、扉の向こうにいる存在を知られたくなかった。
俺は黙って扉のほうへ、歩いていく。
誰か俺をとめて……。
お願いだから、誰か気付いて……。
いくら心の中で必死に叫んだって、誰にも聞こえやしない。
居間を出る際、一瞬だけ振り向く。徹也がおばさんのピーちやんと楽しそうにはしゃいでいるのが見える。
羨ましかった。
その瞬間腕を強く引かれ、俺は廊下に引っ張り出される。
思った通りお袋がもの凄い形相で立っていた。
足元から震えだす俺など一切気にせずに、お袋は強引に階段へ連れていく。
一歩一歩階段を上るたびに尻を叩かれる俺。
今、声を出すとおじいちゃんたちに心配させてしまう。
そんな思いが頭をよぎり、懸命に涙を堪えた。
途中の踊り場まで到着すると、髪をつかまれた。
「何で帰ってくるまで待てなかったんだ?」
俺だけに聞こえるぐらいの声で、お袋はそう言った。
「ご、ごめんなさい……」
「何回、同じ事を言わせるんだよ?」
すごい勢いで尻を叩かれた。
髪の毛を握るお袋の手が無言で、上にあがれと言っていた。
足が震えてうまく階段を上れない。
するとまた尻に痛みが走った。
部屋に到着すると、床に放り出される。
俺はそこで初めて泣いた。
泣けば恐ろしいお袋の顔が、涙で滲んで見えなくなる。
「何度、言ったら分かるんだよ」
頬に痛みが走る。
俺は両腕で顔を隠した。
痛みは色々なところから感じた。
容赦なく無差別に攻撃を繰り出すお袋。
俺は泣くしか方法がない。
「これを持ってろ」
俺におもちゃ電話の受話器の部分を右手に持たせる。
電話機の本体を持ち、一歩一歩ゆっくりと後ろに下がっていくお袋。
幼いながらも、これからどうなるのかが理解できた。
分かっていながら怖くて離せなかった。
受話器を……。
手を離したら、そのあと何をされるかを想像してしまう。
まだ幼い俺には、その想像のほうが怖かった……。
どんどん伸びていくコード。
それでも俺は電話の本体を震えながら持っている。
恐ろしかったのだ。
抵抗して、これ以上殴られるのが嫌だった。
おもちゃの電話機の本体と、俺の右手にある受話器を繋げているゴム製のコードが伸びきったと思った瞬間、お袋の手元から離れていた。
「……!」
いきなり目の前が真っ暗になり、火花が散る。
思わずその場にうずくまってしまう。
目の上が焼けるような痛みを発している。
「ハハハ…、馬鹿だねー。あんた、何やってんの?」
逃げようと立ち上がり、後退した。
その時おもちゃのブロックを踏んでしまい、足の裏に痛みが走る。
胸を押され、床に倒れ込む。
「何、勝手に転んでんだ。立て!」
俺は言われるまま立ち上がる。
足元にはおもちゃのブロックが散乱していた。
ママはいくつかのブロックを拾っている。
「動くなよ。きょうつけして目をつぶってろ!」
「はい……」
これから何をされるのか。
身体を震わせながら、目を少しだけうっすら開けた。
お袋がブロックを投げつける途中だった。
青色のブロックが俺の頭に命中する。
俺は再び倒れた。
「何、大袈裟に倒れてんだ!」
起き上がれば、また同じ目に遭う。
分かっていながら立ち上がった。
そうするしかないのだ。
何度もお袋は、俺にブロックを投げつけた。
俺はこのまま殺されるのかな。
素直にそう感じた。
その時、部屋のドアが勢いよく開く。
「おまえは何をやってんだ!」
おじいちゃんだった。
今まで見た事のないような厳しい目でお袋を見ていた。
二階の騒ぎを聞ききつけ、助けに来てくれたんだ。
真っ暗闇な中、一筋の光明が見えたような気がした。
必死にその光ある方向へと向かう。
「おじいちゃん……」
自然とその方向に駆け寄ろうとした時、背中に激しい痛みを感じた。
床に倒れ込む際、スローモーションのように映し出される。
そして、目の前に割れた白いブロックの破片が見えた。
「わぁっ……」
俺は目を押さえながら、床に転がった。
「……」
目を閉じればいつだって鮮明に…、昨日の出来事のように思い出す。

この二つの傷だけじゃない。ペットとして可愛がっていた猫のみゃうを小便したというだけで、ダンボール箱へ閉じ込め、川へ捨てに連れて行かれた。
どんなにやめてと懇願しても、母親は容赦なかった。
両肩に爪を食い込まされ、いくら泣いてもやめてくれなかった事もある。
顔と心にたくさんの傷を負わせ、母親は小学二年生の冬、俺ら三兄弟を残して家を出て行った……。
なかなか過去のトラウマから抜け出せない俺。
だからこそ、処女作『新宿クレッシェンド』の主人公には、幼き俺の虐待のエピソードをプレゼントしたんじゃないのか?
この忌々しい傷跡がついた部分を作り話に加える事で、作品はよりリアルさを増す。
書いていて本当に辛かった。
心の中をエグられるような感覚。
それを歌舞伎町の一角にあるビルの地下で、ひっそり書き続けたのだ。
右手でそっと傷跡を撫でてみる。
そのあとでゆっくりと百合子を見つめた。
身勝手な親父。
家の金を好きなように使い、近所では英雄気取り。
昔から真面目に働かず、ただおじいちゃんの築き上げた財産を盗んでは使ってきただけ。
絵に描いたような道楽息子とは、親父のような人間を指すのだろう。
家の中ではおばさんのピーちゃんの鼻の骨を折るぐらい、容赦なく理不尽な暴力を振るい続け、外では百八十度変わり、誰からも「本当にいい人ね」と笑顔で言われるほどだった。
「情けねえ野郎だ」
常に俺の顔を見ると、そう言って殴りつけてきた親父。
台所に立ち、料理をしようとしただけで「女みてえな真似しやがって」と理不尽に殴られる。
きっとこんな部分があるなんて。近所の人には分からないのだろうと思った。
小学校四年生だった俺を配達と偽って、当時付き合っていた人妻の家へ連れて行かれ、そこで初めて見た加藤皐月。
この女は多くの災いを俺にもたらせてきた。
親父の女遊びは人妻が多い。
高校生になった頃、加藤はそんな親父をストーカーするように毎日家のすぐ近くに車を停め、俺が学校やアルバイトから帰る度に「お父さんは?」と聞かれた。
非常に迷惑だったが、それでも加藤は世間体などまるで気にしない。
その間、親父はいつも逃げ回っていた。
高三になって、加藤皐月とうちで働くパートの緑さん、そして知らない女三人で、強引に家へ上がり込んできた事がある。
結果、全員親父が抱いた人妻だった。
まさか緑さんまでそうだったなんて当時は知らない俺。
人間不信になるようなショックを受ける。
身体の中で、何かが壊れた気がした。
人の家に来るぐらいだから、三人共相当な覚悟があっただろう。
しかしその中でも加藤は群を抜いて強かった。
この一件を境に、俺は決めた事がある。
それは出て行った親父と母親を離婚させようというもの。
家族の誰にも相談せず、自分自身で勝手に決めた。
何故なら家の近くで他の男性と住み、商売を始めた母親に対し、誰一人関わろうともせず、無視をしていたからだ。
何で誰一人文句を言えないのだろう?
当時は不思議でしょうがなかった。
そして親父の傍若無人な行動を止められる人間もいない。
だからこそ俺が離婚させようと動いた。
高校を卒業したらと……。
すぐ働きたかった。
大学へ行こうなんて高校へ入学した時から考えていない。
親父が学費を出した事など一度もなく、おじいちゃんがそういったものをすべて肩代わりしていたからだ。
高校卒業後、小学二年生以来、俺は自分の意思で初めて母親の下へ行く。
敬語で冷静に話し、離婚を承諾させた俺に待っていたのは、酷い現実だった。
「おまえはお母さんが恋しいのか?」
そう家族から言われ続け、俺の真意など誰も理解してくれない。
恋しい?
恋しいはずないじゃないか。
母親…、本来なら親父と呼んでいるのだから、お袋と言う呼び方が正しい。
しかしあえて区別する為に俺は母親という言葉を使い分けているほどなのだ。
根底にある感情は憎悪…、それしかない。
誰にも言い訳などしなかった。
それだけショックだったのだろう。
家族から忌み嫌われ、常に厄介者扱いだった俺。
おばさんのピーちゃんが俺の食事を用意する事なんて、社会人になってからまずない。
そんな二人の呪われた両親の血を受け継ぐ俺は、子孫など作らないほうがいいと、ずっと思っていた。
俺がこんな人生を歩んでいるのも結局のところ自分の責任である。
だが俺だけが巻き起こした訳じゃないものに、巻き込まれ滅茶苦茶にされるのは何故だ?
ジャンボ鶴田師匠が亡くなった二十九歳の総合格闘技出場。
試合前日だというのに、加藤皐月は深夜俺の部屋まで来て「お父さんに私捨てられちゃう、どうしたらいい?」と大騒ぎ。
そこへ親父が当時相手をしていた看護婦を家に連れて帰ってきたものだから、一気に修羅場と化した。
俺はまったく眠れず徹夜で、生命のやり取りをする誓約書まで書いて臨んだ試合へ行ったのだ。
全日本プロレスのプロテスト受かった合宿前だってそうだ。
同級生の大沢が酒乱で大暴れをして、共に警察の厄介になり全日本プロレスは取り消しになった。
ここぞという時に邪魔が入る。
神様がいるんだとしたら、わざと意地悪しているとしか思えなかった。
よく分からないが、俺は業が深いのだろう。
いつしかそんな風に捉えていた。
俺はこの呪われた身体に流れるを血をすべて吐き出したかったのだ。
再び百合子を見つめる。
彼女も俺の目をジッと眺めていた。
まだ付き合い始めて数ヶ月。
それでも警察にパクられた俺を待っていてくれた。
ずっと人間ってものを信じられなかった。
別に人間が嫌いって訳じゃない。
ただ、俺は常に寂しかったのだ……。
信用できる人間…、そばに寄り添ってくれる女を求めていた。
こいつなら、いいか……。
新しい家庭を作る。
心の奥底でずっと待ち望んでいたのかもしれない。
もうそろそろ裏稼業なんて引退するようかな……。
真面目に働いて普通に生きる。
そんな生活も悪くない。
ゆっくり目を閉じる。
俺は百合子の中に、何度も連続で射精した。












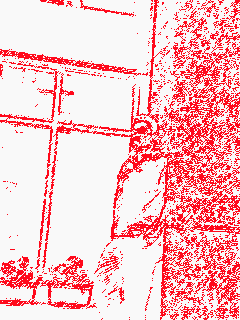






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます