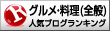サックスプレーヤーとバンドをやった事のある方なら一度はこの質問をぶつけられた事があるのではないでしょうか。今日はそんな時その状況をどう捉えどう対処すれば良いのかお困りの方に向けて筆をとってみました。
<一番大切な事>
それは正直に答える事です。
質問者はあなたがサックスに関して含蓄のある人物とは思っていません。
あくまで客観的な感想を求めています。
ですが良い機会だからといってあなたが普段からその人に感じているサックスの音の不満は間違えても伝えてはいけません。理不尽かもしれませんが「そんな事聞いてないんだよ!」と喧嘩になる事請け合いです。それは別の時間にお茶の席でも設けてじっくり話しましょう。
他に例外もありますがそれは後半に書きます。
<相手はどんな状態なのか>
サックスに限らず管楽器というものは骨振動の所為で人間の肉声のように主観的音色と客観的な音色に差異が存在します。これは自分の声を録音して聞くと思ってたのと全然違うというのと同じ状況です。
また、ベルが奏者の前にある為に野外や音の反響がデッドな練習スタジオ等では吹いている本人が感じている音は実際に鳴っている音量の半分以下でその音色も『ブシュー』だとか『パスー』と聞こえています。
そんな状況の中で質問者があなたに求める答えとは
- 外音は艶やかになっているのか等の最低限の音色の情報
- バンド演奏の中で自分の音が埋もれていないかと謂う音量の情報
この二つの場合がほとんどです。
演奏経験の豊富なサックスプレーヤーの場合は骨振動や息の通り具合、楽器の振動などから自分に聞こえなくても外音がどんな感じかを予測することができます。そんな上級者がこの質問をする時というのは
- 初めて演奏する音響空間で判別できない(畳敷きの和室やチャペルなど天井がとても高い空間など)
- 共演者又はバンドリーダーであるあなたの楽曲や音楽性にそぐわない音ではないかを確認している。
等理由は様々です。
<何をしてあげられるのか>
この質問をするサックスプレーヤー達の大半はリードを別のスペアに交換するのかどうかを検討しているだけなので解決案を提案する必要もありません。正直に答えて放っておいてあげましょう。
ただし、あなたにしてあげられる事が全くない訳ではありません。あなたが思いやりのある優しい人なのであれば担当楽器の音量をサックスプレーヤーに合わせて抑えてあげましょう。あなた一人のほんの少しの思いやりだけでサックスプレーヤーの不安要素の大半を和らげてあげることができます。
経験の豊富なサックスプレーヤーの場合は先ず
「そんな質問をするなんて一体どうしたんだい?」
と理由を聞いてから正直に答えてあげましょう。そしてそっとしておいてあげてください。サックスプレーヤーはあなたの正直な感想を聞き勝手に判断し対策を練ります。
<質問者がやけにご機嫌な時は>
これまではサックスプレーヤーが不安を抱えている事を前提にして書いて来ました。しかし不思議なことに「サックスの音どう?」という質問をとても上機嫌な調子で訪ねてくる時があります。この最も罪深く対処が面倒臭いケースでは一体どうしたら良いのでしょうか。
面倒臭いとは言いましたがこの場合も質問者はあなたに含蓄のある感想なんて求めていません。サックスプレーヤーはサックスのことに関する深い議論はサックスプレーヤー同士でしか出来ない事は百も承知だからです。なので気軽にと言いたいところですが的外れな返答をしてご機嫌を損ねるよりは「おっ!この人わかってる!」みたいな感じに思わせたいですよね?
なので先ずは上機嫌の理由を知りたいところですがすぐに見抜けない時は「そんなにご機嫌で良い事でもあったのかい?」と直接テンポよく聞き出すのが最善策かと思います。
ほとんどの場合は
- 楽器を新調した
- マウスピースを新調した
- 高性能なストラップを新調した
などの理由、酷いものになると
- リガチャー(マウスピースにリードを固定する締め金)を新調した
- サックスのネジを貴金属性に変えた…etc
などの理由になってきます。
リガチャーやネジに関しては黒縁メガネを使っていた人が青縁に新調して「どう?どこか変わったかわかるよね!?」と聞いてくるぐらい罪深いと思います。サックスプレーヤー同士ならその日着ているシャツを褒め合う程度の話題ですがサックスプレーヤー以外の人が感想を述べるにはハードルが高いように思われます。
でもちょっと待って欲しいw
先ほども述べましたが「サックスのことに関する深い議論はサックスプレーヤー同士でしか出来ない事は百も承知」なんです。
色や材質に形状を褒めたりするだけでOKそれで満足します。
ちなみに筆者がうまい答え方だと思ったのは
A「へー、これ買ったんだぁ、いくらしたの?」
S「…万円です。」
A「うわぁこんな只の締め金がそんなにするんだ凄いなー」
というやり取りを耳に挟んだ時でした。
参考まで。。
<あなたが疲れている時は>
自分の演奏の準備で忙しかったり疲れていてまともに相手をするのが面倒臭いなと思ったら
「えー、、ちょっと分かんないよ。。」
「へー、そうなんだすごいね、、」
と軽く流してあげましょう。興味を持たれないことも理解されないことにも慣れっこなのでサックスプレーヤーがあなたに対して悪感情を持つ事はたまにいるかもだけどほぼないです。そもそもご機嫌をとる必要は全くなくそんな事が原因でバンドの音が悪くなるとかはちょっと無いなって僕は思います。
<このサックスの音どうかなぁ?>
この質問をしても満足のいく答えが得られない事に対して大半のサックスプレーヤー達はもはや諦観の境地にいるのでぶっちゃけなんと返答しても問題にはなりません。ですがサックスプレーヤーは人に吐露する人も決して人に相談しない人も皆々この疑問と常に向かい合っていることを知って欲しいです。
あと、もしもサックスプレーヤーさんがこの記事を読んでいたら肝に命じてください。
自分の出音の感想を聞く時は先に相手に理由を伝えましょう