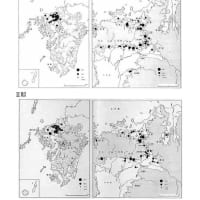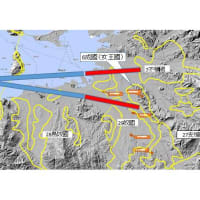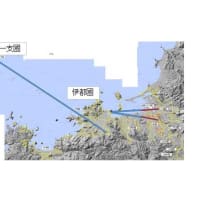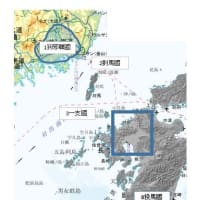2300トヨウツガモノナタマチル[充因美積母萌延成垂増育活 tou you u tu xau mou nou na ta mau tiu ru]
【原本訳】豊かに生み育てる母なるもの(それは次に示す通り)、生育完成、余剰から増加へこの一元の力の流れである。
【一音訳】[充]充分に[因]原因・世[美]生まれる[積]積み上げる[母]母体[萌]目に見えて物質が増加[延]秩序立て[成]物事が完成した[垂]力が溢れ出る[増]物質増加の最大の姿[育]力の流れ[活]~している
【文節訳】[充因]豊か。充分な原因があるということは豊ということ[美積]生み育てる[母]生命を生む母体[萌延]生物[成]物事が完成した[垂増育]溢れて増加する力の流れ[活]~ている。
[充因美積母]次々生み育てる母[萌延成]生物が完成する[垂増育活]余剰から増加への力が流れている
【解釈訳】この場合の母体とは母なる大地のことだろう。ウツ、生み積み上げるとはこの場合生み育てる、生み出すの意味。モノとは生物。この節では植物、穀物の事だろう。弥生時代の特徴である米作を当てはめると理解しやすい。
【古事記】豐宇氣毘賣(とようけびめ)の神。宇迦之御魂(うかのみたま)の神。
【祭神】伊勢神宮の外宮の祭神豊受大御神(とようけおおみかみ)。伏見稲荷大社の宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)
【意訳】豊かに次々と生み育てる母なる大地には、生物を完成させ、溢れさせ、増やす力の流れがある。(第2章第3節節題)
2301ノピレ[延霊゜舞 nou piu rai]
【原本訳】秩序を生み出す霊力。
【一音訳】[延]秩序が進行中である[霊゜]自然の意志と力の一単位[舞]集中動作
【文節訳】[延]秩序[霊゜舞]命のもと
【解釈訳】ピとは自然の意志と力の一単位である。ピ[霊゜]の集団をパ[晴゜]といい、[霊゜]が発動するのをプ[震゜]、消滅するのをペ[放゜]という。ピとは生命構成する見えない最小の単位といってよい。ピが集中すると熱が発生する。生命を維持するには熱が必要だ。よって、ピレは熱の力であり、命の素(もと)と言える。
【意訳】植物の秩序を生み出す命の素の力。
2302パモガ[晴゜萌狩 pa mou xa]
【原本訳】自然力を捕捉し活性化する。
【一音訳】[晴゜]大自然の持つ意志とその力が張り出して行く。生命力[萌]目に見えて物質が増加して行く[狩]獲得する。刈る
【解釈訳】熱によって温められると、生命力が増加し、溢れる生命力を獲得する。パモガのパからパル[晴゜活]春の言葉が派生して出来たと考えられる。
【意訳】暖かくなると植物は活性化する。
2303ズピレ[澄゛霊゜舞 zu piu rai]
【原本訳】水という媒体の霊力。
【一音訳】[澄゛]どんどん吸い取る。水。[霊゜]自然の意志と力の一単位[舞]集中動作
【文節訳】[澄゛]水[霊゜舞]命のもとの熱。
【解釈訳】水は熱を溜め込むから、生命にはどうしても必要である。
【意訳】命の素をため込む水の力。
2304スグナ[澄哈成 su xu na]
【原本訳】秩序体を捕えわが物とする。
【一音訳】[澄]自然の意志と力を吸い込む[哈]食う[成]物事が完成した
【解釈訳】生物は総て水を吸い込むようになっている。生物は水を吸って食って完成するということだろう。スグナのナから夏という言葉は派生したと考えられる。魚をすくう、漁(スナドリ)などの言葉が残っている。
【古事記】少名毘古那(すくなびこな)の神。少彦名の神、漁師のえべっさん。
【意訳】水は植物の生育に欠かせない。
2305タピレ[垂霊゜舞ta piu rai]
【原本訳】余分の力を生み出す霊力。
【文節訳】[垂]力が溢れ出る[霊゜舞]命のもと。熱の力。
【解釈訳】生物が吸収した命の素が溢れ出る。一粒の米が命の素の熱と力を吸収し溢れると、たくさんの米が出来る。生命を分化、分割するためには熱をどんどん吸収することが必要である。
【意訳】命の素の余剰をつくる力。
2306ポギヂュ[穂゜飯集゛po xiu jiu]
【原本訳】意志を分化、籠らせ、寄せ集める。
【一音訳】[穂゜]自然の持つ意志と力が分派、独立したもの。分霊。[飯]五穀そのもの[集゛]物質の無秩序な群がり
【解釈訳】分派独立した穀物の群がり。例としてたわわに実った米などの穀物等。ポギジュのギ。xiuは喉音であって、ヒともキとも聞こえる音。私は独自にⅹ行をガ行として索引仮名として扱っているので、xiuはギとしている。ポギヂュのギ(キ)から派生して秋が出来たと考えられる。
【意訳】余剰をつくる力で植物は分化したわわに稔る。
2307[マピレ増霊゜舞 mau piu rai]
【原本訳】分体を造り出す霊力。
【文節訳】[増]増加する[霊゜舞]現象の命の素。熱と力。
【解釈訳】命の素が増える。命のもとを子孫につなぐ。命のもとを移動させる。生命を維持し子孫を増やして行くためには、自らの熱力を増していかねばならない。
【意訳】命の素の分体をつくる力。
2308トミゴ[充実子 tou miu xou]
【原本訳】充実するとその雛形を分離する。
【一音訳】[充]充分に[実]物質[子]母体から生まれた二世。雛形。
【解釈訳】[子xou]は喉音であり、ホともコとも聞こえる音。私は索引仮名としてx行はガ行で表すことにしている。自ら充実し、雛型、種子を作る。子孫を作る。春夏秋と来て、冬。冬になると山の動物は冬ごもり。大地からは緑が消える。新しい生命の始まりとなる春までの充電期間。トミゴ(ホ)の語感からふゆにつながる語を考えるのは難しいが、冬は「殖ゆ(ふゆ)」が語源という説もあり、増える、子孫を残すという意味合いを考えると成り立つかも知れない。
【意訳】充実した実は子孫を残す。
次へ
【原本訳】豊かに生み育てる母なるもの(それは次に示す通り)、生育完成、余剰から増加へこの一元の力の流れである。
【一音訳】[充]充分に[因]原因・世[美]生まれる[積]積み上げる[母]母体[萌]目に見えて物質が増加[延]秩序立て[成]物事が完成した[垂]力が溢れ出る[増]物質増加の最大の姿[育]力の流れ[活]~している
【文節訳】[充因]豊か。充分な原因があるということは豊ということ[美積]生み育てる[母]生命を生む母体[萌延]生物[成]物事が完成した[垂増育]溢れて増加する力の流れ[活]~ている。
[充因美積母]次々生み育てる母[萌延成]生物が完成する[垂増育活]余剰から増加への力が流れている
【解釈訳】この場合の母体とは母なる大地のことだろう。ウツ、生み積み上げるとはこの場合生み育てる、生み出すの意味。モノとは生物。この節では植物、穀物の事だろう。弥生時代の特徴である米作を当てはめると理解しやすい。
【古事記】豐宇氣毘賣(とようけびめ)の神。宇迦之御魂(うかのみたま)の神。
【祭神】伊勢神宮の外宮の祭神豊受大御神(とようけおおみかみ)。伏見稲荷大社の宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)
【意訳】豊かに次々と生み育てる母なる大地には、生物を完成させ、溢れさせ、増やす力の流れがある。(第2章第3節節題)
2301ノピレ[延霊゜舞 nou piu rai]
【原本訳】秩序を生み出す霊力。
【一音訳】[延]秩序が進行中である[霊゜]自然の意志と力の一単位[舞]集中動作
【文節訳】[延]秩序[霊゜舞]命のもと
【解釈訳】ピとは自然の意志と力の一単位である。ピ[霊゜]の集団をパ[晴゜]といい、[霊゜]が発動するのをプ[震゜]、消滅するのをペ[放゜]という。ピとは生命構成する見えない最小の単位といってよい。ピが集中すると熱が発生する。生命を維持するには熱が必要だ。よって、ピレは熱の力であり、命の素(もと)と言える。
【意訳】植物の秩序を生み出す命の素の力。
2302パモガ[晴゜萌狩 pa mou xa]
【原本訳】自然力を捕捉し活性化する。
【一音訳】[晴゜]大自然の持つ意志とその力が張り出して行く。生命力[萌]目に見えて物質が増加して行く[狩]獲得する。刈る
【解釈訳】熱によって温められると、生命力が増加し、溢れる生命力を獲得する。パモガのパからパル[晴゜活]春の言葉が派生して出来たと考えられる。
【意訳】暖かくなると植物は活性化する。
2303ズピレ[澄゛霊゜舞 zu piu rai]
【原本訳】水という媒体の霊力。
【一音訳】[澄゛]どんどん吸い取る。水。[霊゜]自然の意志と力の一単位[舞]集中動作
【文節訳】[澄゛]水[霊゜舞]命のもとの熱。
【解釈訳】水は熱を溜め込むから、生命にはどうしても必要である。
【意訳】命の素をため込む水の力。
2304スグナ[澄哈成 su xu na]
【原本訳】秩序体を捕えわが物とする。
【一音訳】[澄]自然の意志と力を吸い込む[哈]食う[成]物事が完成した
【解釈訳】生物は総て水を吸い込むようになっている。生物は水を吸って食って完成するということだろう。スグナのナから夏という言葉は派生したと考えられる。魚をすくう、漁(スナドリ)などの言葉が残っている。
【古事記】少名毘古那(すくなびこな)の神。少彦名の神、漁師のえべっさん。
【意訳】水は植物の生育に欠かせない。
2305タピレ[垂霊゜舞ta piu rai]
【原本訳】余分の力を生み出す霊力。
【文節訳】[垂]力が溢れ出る[霊゜舞]命のもと。熱の力。
【解釈訳】生物が吸収した命の素が溢れ出る。一粒の米が命の素の熱と力を吸収し溢れると、たくさんの米が出来る。生命を分化、分割するためには熱をどんどん吸収することが必要である。
【意訳】命の素の余剰をつくる力。
2306ポギヂュ[穂゜飯集゛po xiu jiu]
【原本訳】意志を分化、籠らせ、寄せ集める。
【一音訳】[穂゜]自然の持つ意志と力が分派、独立したもの。分霊。[飯]五穀そのもの[集゛]物質の無秩序な群がり
【解釈訳】分派独立した穀物の群がり。例としてたわわに実った米などの穀物等。ポギジュのギ。xiuは喉音であって、ヒともキとも聞こえる音。私は独自にⅹ行をガ行として索引仮名として扱っているので、xiuはギとしている。ポギヂュのギ(キ)から派生して秋が出来たと考えられる。
【意訳】余剰をつくる力で植物は分化したわわに稔る。
2307[マピレ増霊゜舞 mau piu rai]
【原本訳】分体を造り出す霊力。
【文節訳】[増]増加する[霊゜舞]現象の命の素。熱と力。
【解釈訳】命の素が増える。命のもとを子孫につなぐ。命のもとを移動させる。生命を維持し子孫を増やして行くためには、自らの熱力を増していかねばならない。
【意訳】命の素の分体をつくる力。
2308トミゴ[充実子 tou miu xou]
【原本訳】充実するとその雛形を分離する。
【一音訳】[充]充分に[実]物質[子]母体から生まれた二世。雛形。
【解釈訳】[子xou]は喉音であり、ホともコとも聞こえる音。私は索引仮名としてx行はガ行で表すことにしている。自ら充実し、雛型、種子を作る。子孫を作る。春夏秋と来て、冬。冬になると山の動物は冬ごもり。大地からは緑が消える。新しい生命の始まりとなる春までの充電期間。トミゴ(ホ)の語感からふゆにつながる語を考えるのは難しいが、冬は「殖ゆ(ふゆ)」が語源という説もあり、増える、子孫を残すという意味合いを考えると成り立つかも知れない。
【意訳】充実した実は子孫を残す。
次へ