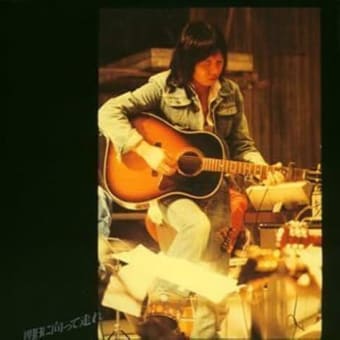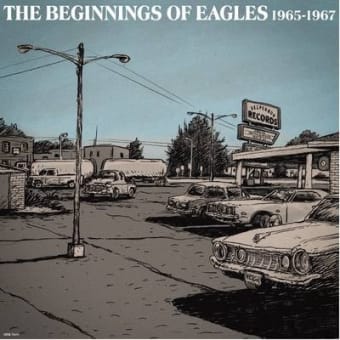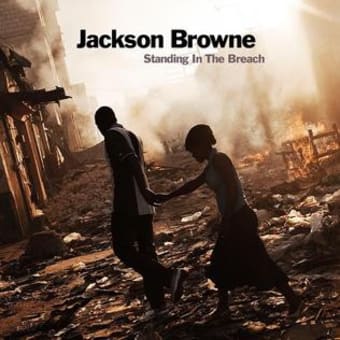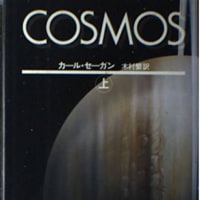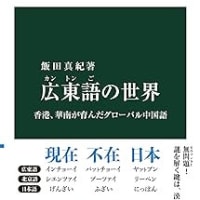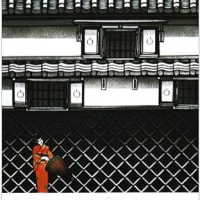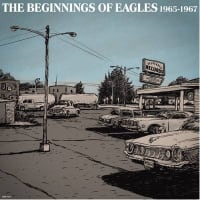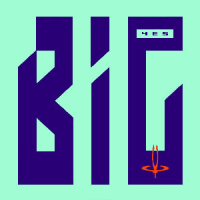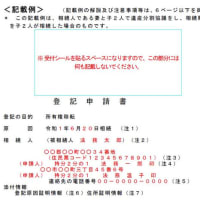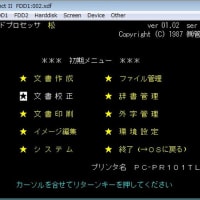<1970年代>
週刊朝日を読み始めたのは1970年代の半ば。高校の部活を引退し、受験勉強にはまだ早かったので学校の図書室でよく時間を潰していた。そのときに手に取ったのが週刊朝日。家ではずっと朝日新聞を取っていたから何の抵抗もなかったが、お堅い朝日新聞に比べて、くだけた内容でニュースや世相をわかりやすく伝えてくれたのが新鮮だった。五木寛之と野坂昭如の連載エッセイは面白かったし、「スヌーピーの英語教室」を読んで一所懸命英語力を身に付けようとしたのも懐かしい。身に付かなかったけれど。
毎週買って読むようになったのは大学に通うために上京してから。住んだ下宿では新聞の購読もできなかったので、新聞代わりに買い始めたのだが、ちょうど表紙を篠山紀信が担当し始めてずいぶん垢抜けた印象になった。山藤章二の「ブラックアングル」もその少し前から連載していたし、しばらくしてから巷の小ネタを面白おかしく取り上げる「デキゴトロジー」も始まった。ここら辺りからだんだん誌面が充実していった感がある。
この頃の週刊朝日の良さって、新聞のように正面から攻めるのではなく斜に構えて世の中を切り取って、それが多少スキャンダラスな事象であっても闇雲にのめり込まずセンス良くまとめる知性を感じさせた点にあった。老若男女を読者層のターゲットにしながらも、知的な大人が読む雑誌、だったのだ。
<1980年代>
1980年代に入っても週刊朝日の快進撃は続く。紀信の表紙の女子大生シリーズ第一回を飾った宮崎美子は一躍スターとなり、以後、この企画は芸能界への登竜門となった。立花隆や田原総一朗の連載ルポも読み応えがあったし、野村克也がプロ野球の戦況を解説する連載も面白かった。「ブラックアングル」が好調だった山藤章二が、更に「似顔絵塾」を開講したのもこの頃。地味な連載であったが、明治から昭和までの物の値段の推移と、それに纏わる思い出が語られる「値段の風俗史」も忘れ難い。
80年代半ばでは「デキゴトロジー」が絶好調。下ネタやサブカルっぽいネタも満載で、よくもまあこんなネタを拾ってくるものだと感心したし、夏目房之介や大川清介のとぼけたイラストも好きだった。「MMK(モテてモテて困る)おばさん」や「典奴」なんかを取り上げていたのはこの頃ではなかったかな。80年代後半は「フォーカス」に始まる写真週刊誌の隆盛を受けて、ニュースグラビアにも力を入れていた時期でもあった。休刊まで続いた東海林さだおの連載食べものエッセイも始まった。そして、昭和が終わる。
<1990年代>
1980年代末から1990年代初め(つまり昭和末期から平成初め)にかけて週刊朝日を取り巻く環境に大きな変化があった。ひとつはAERAの創刊。その少し前にニューズウイーク日本版が創刊されて、AERAは体裁からしてニューズウイークの朝日版といった趣きだった。もうひとつは朝日ジャーナルの休刊。朝日ジャーナルは左翼イデオロギー色の強い雑誌だったから、ソ連の崩壊によって存在意義が薄れてしまったのは当然と言えば当然だが、それによって朝日新聞が発行する総合週刊誌が週刊朝日とAERAの二つになってしまい、棲み分けが微妙になったのは否めまい。
自分にとって面白くて刺激を受けた週刊朝日はここら辺りまでだったな。相変わらず紀信の表紙やブラックアングル等は続いていたけれど、そろそろマンネリ化してたかも。語り草になったナンシー関のエッセイは良かったけれど、評判が良かったという「恨ミシュラン」なんかは好きじゃなかったな。神足裕司の文章はともかく、西原理恵子のイラストは体が受け付けなかった。週刊朝日は知的なスタンスが好きだったので、あまり知性の感じられないストレートすぎる表現に違和感を感じたのだ。どうやらそのような路線変更は当時の編集長の方針で、1993年には突然「71年間ご愛読ありがとうございました」の表紙で、何事かと思ったら「週刊朝日」のロゴをポップな字体に変えただけで、あまりに薄っぺらい虚仮おどしに腹が立ったのを覚えている。ロゴだけじゃなく誌面も全体的に軽薄になって、週刊朝日の凋落の道を最初に作った戦犯はこの編集長だ。
この頃から並行して週刊文春をわりと買うようになった。現在の週刊文春はスクープ連発の文春砲で有名になってしまったが、そういう記事よりも充実した連載陣に惹かれたのだ。リベラルな朝日だけじゃなくコンサバな文春も読んでバランスを取ろう、という意図もあった。やがて週刊文春を読む比率が高まるに従って、週刊朝日を読む比率も徐々に下がって、毎週買うのを止めてしまったのもたしかこの頃。
その後、揺り戻しがあってロゴの字体も戻ったけど、かつての勢いはもう戻らなかった。司馬遼太郎が亡くなって「街道をゆく」もぷっつんと終わってしまったし(でも休刊まで「街道をゆく」ネタを強引に引っ張り続けたのは些か痛々しかった)、紀信の表紙も終了。「デキゴトロジー」は一度終わって、その後再開したけどパワー不足でずいぶん小粒になった。週刊朝日はゆっくり衰退しながら20世紀が終わる。
<2000年代>
もうこの頃になると週刊文春と週刊朝日を買う比率は逆転して、週刊文春を買うほうが多くなった。週刊朝日は大事件が起きたときか、新聞広告か電車の宙吊りを見て気になる記事があったときに買うスタイル。だから今記事を読み返しても記憶が薄い。休刊まで続いた林真理子の対談もの、田原総一朗と内館牧子の連載エッセイ、山科けいすけの連載漫画は、もうこの頃既に始まっていたのにはちょっと驚いた。表紙はまた人物のポートレートに戻っていたが、男性スターが起用されることが度々あって、ちょっとしたカルチャーショックと言うか時代の変遷を感じた。
2000年代後半に香港に赴任したのだが、日本の雑誌を定期的に航空便で送ってもらう有料サービスがあって、それを利用する際に朝日か文春か迷った末に週刊文春を購読することにした。自分にとって週刊朝日はもう毎週読むほどのものではなくなっていた訳だが、それでもこの頃はまだ「本命は週刊朝日、週刊文春は一時の浮気」のつもりでいた。
<2010年代~休刊まで>
日本に帰国してまた週刊朝日とのお付合いが始まった(赴任中も一時帰国時等に読んでいたが)。2010年代前半あたりまではまだ薄ぼんやりとした停滞の時代だったと思うが、それ以降は明らかに誌面が劣化したと感じる。まず、この頃から大学合格者ランキングの記事がボリュームアップしていった。いや、大学合格者数の記事自体は昔からあったけれど、年々内容がゴージャスになり長期間に亘って掲載されるようになったのだ。表紙は女性よりも男性の比率がだんだん高くなっていって、そのこと自体は問題ではないが、休刊までの数年間なんてジャニーズ系ばっかりになったのには参った。表紙とタイアップしたジャニタレのヨイショ記事など読みたくもない。そして政治ネタの記事が減っていったのは、2012年に起きた「ハシシタ事件」の影響だけではあるまい。やがて介護だの年金だの終活だのの高齢者向け記事、すなわちあまり手間暇かけずに作れる安直な記事ばかりが目立つようになっていった。
かつての週刊朝日は、大家・新鋭取り混ぜて多彩な執筆者が新しい世界や知見を教えてくれた。週刊朝日を読んで興味を持って著作に接したことも数多かった。この頃にはそのようなことは殆どなくなり、その役割は週刊文春が担ってくれた。週刊文春は近年スクープ力が凄いけれど、そういう面も充実しており、昔の週刊朝日のような勢いを感じる。
結局、休刊時点での週刊朝日の目玉は、男性アイドルの表紙と、大学合格者ランキングの記事と、高齢者向けの記事の三本柱だったようだ。かつて老若男女を読者層のターゲットにしながらも知的な大人が読む雑誌であった週刊朝日が、こんな情けない雑誌になって終焉してしまったのは実に残念だ。しかも上記の三本柱の読者層って、アイドル好きの女性と、受験生の家庭と、高齢者であって全部バラバラじゃないか。読者層のターゲットも絞り切れないなんて、一体どんな戦略を持って雑誌を作っていたのか。
もちろん、雑誌全体の売上げが落ちているのは世の中の抗えない流れだ。出版元(現在は本社から切り離されて朝日新聞出版)としても週刊朝日とAERAという同じような総合週刊誌を二種類も維持できなくなって、苦渋の選択で週刊朝日を切り捨てたのだろう。伝統ある週刊朝日よりも新興のAERAを選択したのは意外ではあったけれど、ここ数年の週刊朝日の体たらくを見れば仕方なかったのかも知れない。もっともAERAが金を払って読む価値のある雑誌とはあまり思えない。それなら週刊朝日に梯子を外されて孤軍奮闘を強いられてしまったサンデー毎日を応援したいな。
(かみ)
最新の画像もっと見る
最近の「Book Review」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事