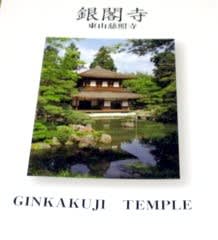萩

松陰神社
明治40年(1907)の創建で吉田松陰を祭神とする神社。

松下村塾
吉田松陰が主宰した私塾。
高杉晋作や久坂玄瑞に伊藤博文、山縣有朋などが通っており後の倒幕そして新政府設立の原動力となっている。

講義室
内部は八畳。

本殿
現在の社殿は、昭和30年に完成。

吉田松陰幽囚ノ旧宅
伊豆下田沖で海外渡航を試みたが失敗、江戸伝馬町の牢獄、次いで萩の野山獄に入れられた。
その後は実家である杉家旧宅で預かりの身となった。

茶室

内部は全体四畳半で一畳を床とする

床
床柱は皮付丸太となっています。

幽囚室
松陰が謹慎生活を送った部屋。
松陰はここで孟子や武教全書などを講じ、次第に多くの若者が集まるようになり、のちに松下村塾での教育が始まりました。

松陰神社宝物殿 至誠館
松陰神社に伝わる松陰の遺墨・遺品類を展示している。

茶室「花月楼」
萩藩7代藩主・毛利重就が、安永5年(1776)に三田尻御茶屋に建てたもの。
川上不白から献上された図面を以て造立しているが、不白の自邸にあった広間茶室「花月楼」が基となっている。
下部に写っている「花月楼」の額は品川弥二郎が明治20(1887)年に揮毫したもの。

文化2年(1805)茶堂・竹田休和が萩の平安古の屋敷に移し、更に明治20年(1887)品川弥二郎が萩の旧宅に移築した。
吉田松陰没後100年にあたる昭和34年(1959)にこの場所へ移されている。

内部は主室八畳に四畳の上段の二方に入側が矩折に廻る。
入側の建具を外すと二十畳敷の大広間として使える。

上段には床、棚、付書院を備える。

七事式の根本である花月之式を催すことができるよう設計された席で興味深かったです。

松陰だんごを食して次の場所へ

松陰神社
明治40年(1907)の創建で吉田松陰を祭神とする神社。

松下村塾
吉田松陰が主宰した私塾。
高杉晋作や久坂玄瑞に伊藤博文、山縣有朋などが通っており後の倒幕そして新政府設立の原動力となっている。

講義室
内部は八畳。

本殿
現在の社殿は、昭和30年に完成。

吉田松陰幽囚ノ旧宅
伊豆下田沖で海外渡航を試みたが失敗、江戸伝馬町の牢獄、次いで萩の野山獄に入れられた。
その後は実家である杉家旧宅で預かりの身となった。

茶室

内部は全体四畳半で一畳を床とする

床
床柱は皮付丸太となっています。

幽囚室
松陰が謹慎生活を送った部屋。
松陰はここで孟子や武教全書などを講じ、次第に多くの若者が集まるようになり、のちに松下村塾での教育が始まりました。

松陰神社宝物殿 至誠館
松陰神社に伝わる松陰の遺墨・遺品類を展示している。

茶室「花月楼」
萩藩7代藩主・毛利重就が、安永5年(1776)に三田尻御茶屋に建てたもの。
川上不白から献上された図面を以て造立しているが、不白の自邸にあった広間茶室「花月楼」が基となっている。
下部に写っている「花月楼」の額は品川弥二郎が明治20(1887)年に揮毫したもの。

文化2年(1805)茶堂・竹田休和が萩の平安古の屋敷に移し、更に明治20年(1887)品川弥二郎が萩の旧宅に移築した。
吉田松陰没後100年にあたる昭和34年(1959)にこの場所へ移されている。

内部は主室八畳に四畳の上段の二方に入側が矩折に廻る。
入側の建具を外すと二十畳敷の大広間として使える。

上段には床、棚、付書院を備える。

七事式の根本である花月之式を催すことができるよう設計された席で興味深かったです。

松陰だんごを食して次の場所へ