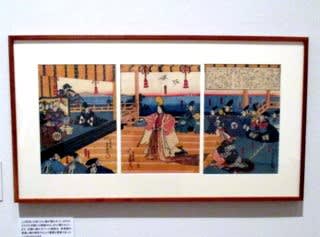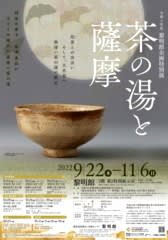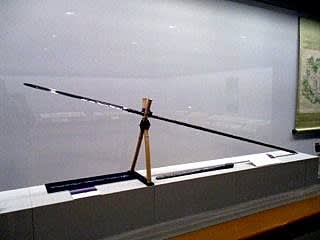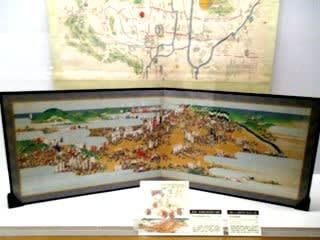京都大原

宝泉院
額縁庭園や血天井で有名な寺院。こちらには大阪茨木市から移築された茶室があります。

茶室「日新庵」
茨木市の太田家住宅にあった裏千家十三代・圓能斎が造った茶室。

最初は露地。奥に手水鉢と灯籠があります。

茶室の躙口と待合。

内部は四畳半

床と床脇
床脇は地板を敷き、正面に大下地窓を開ける。銅鑼が吊ってあることも併せて裏千家の茶室「咄々斎」を模している。

水屋
お次は

広間
内部は十畳。


こちらでお抹茶をいただきました。

床
赤壁が印象的

障子には山水画が描かれています。
侘びた小間と豪華な広間のコントラストが楽しい茶室でした。

宝泉院
額縁庭園や血天井で有名な寺院。こちらには大阪茨木市から移築された茶室があります。

茶室「日新庵」
茨木市の太田家住宅にあった裏千家十三代・圓能斎が造った茶室。

最初は露地。奥に手水鉢と灯籠があります。

茶室の躙口と待合。

内部は四畳半

床と床脇
床脇は地板を敷き、正面に大下地窓を開ける。銅鑼が吊ってあることも併せて裏千家の茶室「咄々斎」を模している。

水屋
お次は

広間
内部は十畳。


こちらでお抹茶をいただきました。

床
赤壁が印象的

障子には山水画が描かれています。
侘びた小間と豪華な広間のコントラストが楽しい茶室でした。