こんばんは。
今回は、正負両電源についてつらつらと書いていきたいと思います。
片電源の場合、個人的には、スイッチング AC アダプタで十分だと感じています。
勿論、それが非常にノイジーであるなら、ノイズフィルタなどの対策は必要としても、電源回路を筐体の外に出せるというのは、大きな利点であることに変わりは無いからです。
だってそうですよね、高級なアンプだと電源筐体が別になっているのは珍しくも何ともない。
主要なノイズ源である電源部を別筐体にすれば、アンプ回路の配置自由度は格段に増すわけです。
更に言えば、電源部の熱や振動も、別筐体ならアンプ部に影響を与えることがないわけです。
なので、片電源であるならば、トランスで変圧した後、整流して、レギュレータ回路を通す、なんて面倒なことをしなくても良いと考えるわけです。
秋月電子の安い AC アダプタでも、高出力のものもありますからね、必要十分なものを買えばよろしい。
ところがです、やっぱりオペアンプを使いたい場面がどうしても出てきますよね。
ディスクリートで作るにしても、負電源があると便利な場面は多いです。
そうなると、何かしらの方法で両電源を用意しなければならないわけです。
片電源であるスイッチング AC アダプタから正負両電源を作るには、仮想 GND や、レールスプリッタというのがキーワードになってきます。
単純なことを言えば、抵抗分圧回路です。そこにオペアンプを付けたりして、精度を上げる、というのが多いですね。
或いは、 Texas Instruments TLE2426CP などの専用 IC を使う。電流は 20mA と少ないですが、オペアンプ一つ動かす回路なら問題ないでしょう。
※ 中身は抵抗分圧とオペアンプみたいなものです。
これまで数多製作してきた経験から言えば、仮想 GND では良い音になりません。
仮想 GND を追求していくと、結局、回路規模が大きくなっていきます。
そうなると、センタタップ付きトランスと整流回路で作った正負両電源と大差無くなります。
整流後のレギュレータ回路は、三端子レギュレータが楽ですけれども、ディスクリートでもそれほど難しいわけではないですね。
三端子レギュレータは内部に負帰還回路があって、電流を安定化させています。
何か拘りがあって負帰還回路を使いたくないなら、簡単なシリーズレギュレータを組めばよろしいですね。
※ ツェナーで作ったシリーズレギュレータより、三端子レギュレータの方がローノイズで、かつ正確な電圧になります。
とまあ、色々と書いてきましたけれども、結論を言えば次のようです。
① 片電源なら、スイッチング AC アダプタを買うのが良い。電源を別筐体にできるし、ノイズ対策も容易。
② 正負両電源なら、センタタップ付きトランスと整流回路を使う。三端子レギュレータで十分だし、ディスクリート化も容易。
ちなみに、ピュアオーディオ界隈では、三端子レギュレータ=音悪い説があります。
そんなことないです。電源のノイズ対策が極めて簡便ですし、電圧精度も高いし、電流も十分。
トランス電源でヘッドフォンアンプを作る時、これほど頼りになる IC もありませんよ。
ただ、拘りとして、できるだけ負帰還回路を使いたくない派からすると、避けたい気持ちもわかる、という程度の話です。
※ 作ると分かりますが、ヘッドフォンアンプのようなノイズにシビアなものでも、ツェナーで作ったシリーズレギュレータで十分実用です。
さて、結論を書いておいて、ここからは少し別のお話。
仮想 GND の問題は、結局は抵抗分圧から逃れられない、そして、 GND の取り扱いが難しいです。
電源の GND をケース GND とショートさせてしまうと、仮想 GND と繋げられない、とかね。
ヘッドフォンアンプなら、出力先は他と絶縁されたヘッドフォンしかないので、仮想 GND でも大した問題にはなりませんが、相手がパワーアンプならそうも行きませんよね。
なので、簡単なプリアンプを作りたいな、という人向けに、絶縁型の両電源 DCDC コンバータを紹介します。
これを使えば、電源側をスイッチング AC アダプタにしたまま、簡単に両電源を作ることができますし、電源の GND と出力側の GND をショートさせても問題がありません。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06529/
両電源の DCDC コンバータの一例です。秋月には他にも沢山あるので、探してみてください。
当然ですが、これはヘッドフォンアンプにも使えます。
±12VDC が作れるなら、電圧の余裕があるので、回路設計も容易でしょう。
無理して、低電圧で余裕のない回路を作る必要が無くなります。
例えば、定電流回路に、カレントミラーを使って2石、なんてことを避けて、 CRD 1 本でも、電圧の損失は大して問題になりません。
回路規模の縮小に大きく貢献することでしょう。
以上。
今回は、正負両電源についてつらつらと書いていきたいと思います。
片電源の場合、個人的には、スイッチング AC アダプタで十分だと感じています。
勿論、それが非常にノイジーであるなら、ノイズフィルタなどの対策は必要としても、電源回路を筐体の外に出せるというのは、大きな利点であることに変わりは無いからです。
だってそうですよね、高級なアンプだと電源筐体が別になっているのは珍しくも何ともない。
主要なノイズ源である電源部を別筐体にすれば、アンプ回路の配置自由度は格段に増すわけです。
更に言えば、電源部の熱や振動も、別筐体ならアンプ部に影響を与えることがないわけです。
なので、片電源であるならば、トランスで変圧した後、整流して、レギュレータ回路を通す、なんて面倒なことをしなくても良いと考えるわけです。
秋月電子の安い AC アダプタでも、高出力のものもありますからね、必要十分なものを買えばよろしい。
ところがです、やっぱりオペアンプを使いたい場面がどうしても出てきますよね。
ディスクリートで作るにしても、負電源があると便利な場面は多いです。
そうなると、何かしらの方法で両電源を用意しなければならないわけです。
片電源であるスイッチング AC アダプタから正負両電源を作るには、仮想 GND や、レールスプリッタというのがキーワードになってきます。
単純なことを言えば、抵抗分圧回路です。そこにオペアンプを付けたりして、精度を上げる、というのが多いですね。
或いは、 Texas Instruments TLE2426CP などの専用 IC を使う。電流は 20mA と少ないですが、オペアンプ一つ動かす回路なら問題ないでしょう。
※ 中身は抵抗分圧とオペアンプみたいなものです。
これまで数多製作してきた経験から言えば、仮想 GND では良い音になりません。
仮想 GND を追求していくと、結局、回路規模が大きくなっていきます。
そうなると、センタタップ付きトランスと整流回路で作った正負両電源と大差無くなります。
整流後のレギュレータ回路は、三端子レギュレータが楽ですけれども、ディスクリートでもそれほど難しいわけではないですね。
三端子レギュレータは内部に負帰還回路があって、電流を安定化させています。
何か拘りがあって負帰還回路を使いたくないなら、簡単なシリーズレギュレータを組めばよろしいですね。
※ ツェナーで作ったシリーズレギュレータより、三端子レギュレータの方がローノイズで、かつ正確な電圧になります。
とまあ、色々と書いてきましたけれども、結論を言えば次のようです。
① 片電源なら、スイッチング AC アダプタを買うのが良い。電源を別筐体にできるし、ノイズ対策も容易。
② 正負両電源なら、センタタップ付きトランスと整流回路を使う。三端子レギュレータで十分だし、ディスクリート化も容易。
ちなみに、ピュアオーディオ界隈では、三端子レギュレータ=音悪い説があります。
そんなことないです。電源のノイズ対策が極めて簡便ですし、電圧精度も高いし、電流も十分。
トランス電源でヘッドフォンアンプを作る時、これほど頼りになる IC もありませんよ。
ただ、拘りとして、できるだけ負帰還回路を使いたくない派からすると、避けたい気持ちもわかる、という程度の話です。
※ 作ると分かりますが、ヘッドフォンアンプのようなノイズにシビアなものでも、ツェナーで作ったシリーズレギュレータで十分実用です。
さて、結論を書いておいて、ここからは少し別のお話。
仮想 GND の問題は、結局は抵抗分圧から逃れられない、そして、 GND の取り扱いが難しいです。
電源の GND をケース GND とショートさせてしまうと、仮想 GND と繋げられない、とかね。
ヘッドフォンアンプなら、出力先は他と絶縁されたヘッドフォンしかないので、仮想 GND でも大した問題にはなりませんが、相手がパワーアンプならそうも行きませんよね。
なので、簡単なプリアンプを作りたいな、という人向けに、絶縁型の両電源 DCDC コンバータを紹介します。
これを使えば、電源側をスイッチング AC アダプタにしたまま、簡単に両電源を作ることができますし、電源の GND と出力側の GND をショートさせても問題がありません。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06529/
両電源の DCDC コンバータの一例です。秋月には他にも沢山あるので、探してみてください。
当然ですが、これはヘッドフォンアンプにも使えます。
±12VDC が作れるなら、電圧の余裕があるので、回路設計も容易でしょう。
無理して、低電圧で余裕のない回路を作る必要が無くなります。
例えば、定電流回路に、カレントミラーを使って2石、なんてことを避けて、 CRD 1 本でも、電圧の損失は大して問題になりません。
回路規模の縮小に大きく貢献することでしょう。
以上。











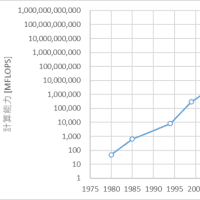













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます