友人と話していて、「執事といえばセバスチャン。」という話題が出た。それって、ルーツはどこなんだ?何か有名な小説とかあるの?
思い起こせば大学時代にバイト先で、趣味が全く被らない人に(つまり、英国史にはまるで興味ない)
「psyさんちの執事の名前は、セバスチャンだよな?」
「・・・うちの執事は斎藤ですが?」
「うっそ、ダメだよ。執事はセバスチャンじゃなきゃ。俺はセバスチャンって呼んでいい?」
「どうぞ。」
と言われたこともあった。(その後しばらく執事ネタは続いた)つまり、かなりユニバーサルな認識だと思うんだけど。
昨今、例のカフェ・ブーム(多分、ヴィクトリアンかリージェンシーのメイド・イメージ)だそうだが、メイドとバトラーがセットなイメージが広がっている気がするな。でも、対義語としては、
Butler(執事) ⇔ Housekeeper(家政婦)
Valet(従僕)⇔ Maid(侍女)
だろうと思うのだが。
Housekeeperというと日本では、「家政婦は見た!」なイメージがあるからダメなんだろうか。家政婦が、家庭内の内向きのこと、執事が表向きの事を司るのかと。執事は今でも養成学校があり、執事・家政婦は認証制だか登録制だったはずだ。英国で家政婦をして働いている人の本が何冊か出ている。英国に対して美しいイメージを保っていたい、という人にはお薦めできないが、私は共感できる部分も多く、面白かった。
ついでにリージェンシーからヴィクトリアンに掛けて、ご主人様に付くのはバレット、奥方様に付くのがメイドだと思うんだけど。バレットはまあ、ご主人様のクラバット(後のネクタイ、スカーフに近い)を結んで差し上げたり、へシアンブーツをシャンペン入りの靴墨で磨いたり(あほか)、寝酒(輸入高級品のポートワインとかブランディ)の準備をして差し上げたりする。
基本的に、貴族の家では主人一家に対面できる使用人は、使用人の中ではアッパーとされる。だけど、英国人の知人(アッパー・・・っぽかった)がいうには、奇妙な捩れ現象が生じる職種もあって、かのショーン・ビーンが演じたGamekeeper(狩番)なんだそうだ。私が英国にいた頃に、狐狩りの全面廃止の法案を巡って揉めていて、反対派の理由の一つが社会の下層にいるゲームキーパーの失職問題があったのだ。使用人の中でも低い身分のゲームキーパーは、場合によっては最も主近くに位置し、紳士の嗜みを紳士以上に卓越した腕前でこなす、contradictな存在なんだそうだ。彼の個人的見解かもしれないけど。その辺も踏まえると、メラーズの台詞もより面白いかなーと思う。
執事に相当する言葉は、"Butler""Chamberlain""Steward"(宗教上の執事は除く)などがある。バトラーは多分中産階級にも使うが、チェンバレンは貴族にしか使わない。英国貴族は、荘園領主として自分の所領に本邸を持ち、これはCountry House、Manor Houseと呼ばれる。その他に政治家として(貴族院に議席を持つので)真面目に仕事している人は議会の会期中、それ以外の人も"The season"と呼ばれる社交シーズンにロンドンに出てくるためにロンドンに別宅を持ち、これをTown Houseと呼ぶ。で、タウンハウスとマナーハウスにそれぞれ執事がいたりするようなんだが、マナーハウスの場合土地の差配もしなければならないので、執事というより家令とか家宰とかいう訳語の方があっている気がする。(土地差配人が別個にいる場合もある)このマナーハウスにいるのが、スチュワード、と呼ばれているような気がするけど、全くの私見なので根拠はない(言い切るな)。
因みに、「執政」と呼ばれるゴンドールのフーリン家のあのお方たちは、原語では"Steward"もしくは、"Ruling Steward"である。スチュワードって言うから、私はてっきり王家の私的なサーバントなんだと思い込み、例えば宰相とか議会の長であったとかの、公的な地位や権限ゆえに王権を代行するようになったわけではなく、王への忠義のみが彼らが王国を裁量する権力をもち続けることの裏付けというか、周囲に認知させる唯一の正当性だと思っていたのだけど、実は英国には「王国執事」という職掌が存在したのだ。
原語では"Lord Steward"もしくは、 "Lord Steward of the Household"で、公的な君主の家裁で、彼らは常に政府の一員であり、(爵位もちの)貴族であり、枢密顧問官であったようだ。ヘンリー八世以降には別名、グランド・マスターとも呼ばれたとのこと。君主と個人的に面会し、その委任された権限と権威の象徴として白の杖を常に携えていたとか。公的な地位の割には、王の私的な晩餐とかも司っていたみたいで、良くわからないポジションだけど。
ついでに、Lord Chamberlain が"above stairs"の事に責を負うというのに対して、Lord Steward は"below stairs"の事に責を負うのだそうだ。この単語を見た瞬間、件の映画のなんとも微妙な階段が不意に思い起こされたのは言うまでもない。いくこむしじゃないけど、あれに何百年も座っていたら性格も歪むって。
あー。そういえば、本国にはバレット・カフェがあったなあ。あれ?バトラー・カフェだったっけ?どっちにしろアダルティーな店だったから、行った事はないけど。
思い起こせば大学時代にバイト先で、趣味が全く被らない人に(つまり、英国史にはまるで興味ない)
「psyさんちの執事の名前は、セバスチャンだよな?」
「・・・うちの執事は斎藤ですが?」
「うっそ、ダメだよ。執事はセバスチャンじゃなきゃ。俺はセバスチャンって呼んでいい?」
「どうぞ。」
と言われたこともあった。(その後しばらく執事ネタは続いた)つまり、かなりユニバーサルな認識だと思うんだけど。
昨今、例のカフェ・ブーム(多分、ヴィクトリアンかリージェンシーのメイド・イメージ)だそうだが、メイドとバトラーがセットなイメージが広がっている気がするな。でも、対義語としては、
Butler(執事) ⇔ Housekeeper(家政婦)
Valet(従僕)⇔ Maid(侍女)
だろうと思うのだが。
Housekeeperというと日本では、「家政婦は見た!」なイメージがあるからダメなんだろうか。家政婦が、家庭内の内向きのこと、執事が表向きの事を司るのかと。執事は今でも養成学校があり、執事・家政婦は認証制だか登録制だったはずだ。英国で家政婦をして働いている人の本が何冊か出ている。英国に対して美しいイメージを保っていたい、という人にはお薦めできないが、私は共感できる部分も多く、面白かった。
ついでにリージェンシーからヴィクトリアンに掛けて、ご主人様に付くのはバレット、奥方様に付くのがメイドだと思うんだけど。バレットはまあ、ご主人様のクラバット(後のネクタイ、スカーフに近い)を結んで差し上げたり、へシアンブーツをシャンペン入りの靴墨で磨いたり(あほか)、寝酒(輸入高級品のポートワインとかブランディ)の準備をして差し上げたりする。
基本的に、貴族の家では主人一家に対面できる使用人は、使用人の中ではアッパーとされる。だけど、英国人の知人(アッパー・・・っぽかった)がいうには、奇妙な捩れ現象が生じる職種もあって、かのショーン・ビーンが演じたGamekeeper(狩番)なんだそうだ。私が英国にいた頃に、狐狩りの全面廃止の法案を巡って揉めていて、反対派の理由の一つが社会の下層にいるゲームキーパーの失職問題があったのだ。使用人の中でも低い身分のゲームキーパーは、場合によっては最も主近くに位置し、紳士の嗜みを紳士以上に卓越した腕前でこなす、contradictな存在なんだそうだ。彼の個人的見解かもしれないけど。その辺も踏まえると、メラーズの台詞もより面白いかなーと思う。
執事に相当する言葉は、"Butler""Chamberlain""Steward"(宗教上の執事は除く)などがある。バトラーは多分中産階級にも使うが、チェンバレンは貴族にしか使わない。英国貴族は、荘園領主として自分の所領に本邸を持ち、これはCountry House、Manor Houseと呼ばれる。その他に政治家として(貴族院に議席を持つので)真面目に仕事している人は議会の会期中、それ以外の人も"The season"と呼ばれる社交シーズンにロンドンに出てくるためにロンドンに別宅を持ち、これをTown Houseと呼ぶ。で、タウンハウスとマナーハウスにそれぞれ執事がいたりするようなんだが、マナーハウスの場合土地の差配もしなければならないので、執事というより家令とか家宰とかいう訳語の方があっている気がする。(土地差配人が別個にいる場合もある)このマナーハウスにいるのが、スチュワード、と呼ばれているような気がするけど、全くの私見なので根拠はない(言い切るな)。
因みに、「執政」と呼ばれるゴンドールのフーリン家のあのお方たちは、原語では"Steward"もしくは、"Ruling Steward"である。スチュワードって言うから、私はてっきり王家の私的なサーバントなんだと思い込み、例えば宰相とか議会の長であったとかの、公的な地位や権限ゆえに王権を代行するようになったわけではなく、王への忠義のみが彼らが王国を裁量する権力をもち続けることの裏付けというか、周囲に認知させる唯一の正当性だと思っていたのだけど、実は英国には「王国執事」という職掌が存在したのだ。
原語では"Lord Steward"もしくは、 "Lord Steward of the Household"で、公的な君主の家裁で、彼らは常に政府の一員であり、(爵位もちの)貴族であり、枢密顧問官であったようだ。ヘンリー八世以降には別名、グランド・マスターとも呼ばれたとのこと。君主と個人的に面会し、その委任された権限と権威の象徴として白の杖を常に携えていたとか。公的な地位の割には、王の私的な晩餐とかも司っていたみたいで、良くわからないポジションだけど。
ついでに、Lord Chamberlain が"above stairs"の事に責を負うというのに対して、Lord Steward は"below stairs"の事に責を負うのだそうだ。この単語を見た瞬間、件の映画のなんとも微妙な階段が不意に思い起こされたのは言うまでもない。いくこむしじゃないけど、あれに何百年も座っていたら性格も歪むって。
あー。そういえば、本国にはバレット・カフェがあったなあ。あれ?バトラー・カフェだったっけ?どっちにしろアダルティーな店だったから、行った事はないけど。










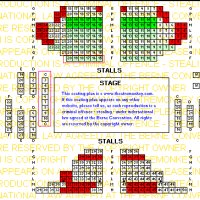















ja.wikipedia.org/wiki/セバスチャン
何か、アニメでは、執事というよりは召使いっぽかったでございますが。ロッテンマイヤーさんに、いいように扱われていたし(笑)
日本では、執事ってどうも虚構の世界っぽいでございますよね。
番頭さんとかのほうが、真実味がございます。
そういえば、うちの親父は幼き頃、実母よりねえやに懐いていたなどという伝説がございます。ねえやが一緒じゃないと、文房具屋さんに消しゴムも買いに行けなかったとか(絶句)
http://q.hatena.ne.jp/1088091944
私ぜんっぜん覚えてませんでした。
>Butler⇔Housekeeper
対義語、というのは目から鱗でした。どうもHousekeeperのポジションが分かりにくかったのですが、内向きの仕事をする使用人のトップ、という感じでよろしいんですよね?日本語で「家政婦」というと大分イメージが違ってしまう気がします。
>Lord ChamberlainとLord Steward
む、難しゅうございます…
>お父様
幼少期って、何歳ぐらいまででございましょう・・・。そう言えば、お元気でいらっしゃいますか?
>ハウスキーパー
内向きの、且つ、女性使用人のトップだと思います。厨房のトップは、それはそれで権力をもっているようですが(料理べたを自覚している英国人があえてフレンチ・シェフを雇っていたりするので、ちょっと特殊な空間なのかも)、一応厨房とかも込みで内向きトップだと思われます。
家政婦って、なんか語感が悪いですよね・・・。市原悦子氏のせいでしょうかね・・・。何だか貧乏臭いようなイメージが。
>Lord ChamberlainとLord Steward
ええ、私も良くわかっていません。でも、イメージ的にはエドワードIVに対するヘイスティングス卿が、王国執事な感じです。
ボルトン夫人は、家長であるチャタレイ氏だけではなく、コニーとも接するからこそ使用人の中では(元は看護婦だけど)位が上なんですね。
使用人の中でも最下層のメラーズがコニーを寝取るのが、当時としてはいかにすごいタブーだったかが伺えます。
>タブー
体の関係を持つだけだったら、多分タブーじゃないと思うんです。タブーだったのはコニーが本気になったことだったと思います。
「言え!森の中では俺のものだと!」とかいう台詞があったように思うのですけど、上記↑エゲレス人が言うように、森の中では(紳士のスポーツとされる狩猟においては)自分こそがLordなのだという自負の現れ、のような気がします。