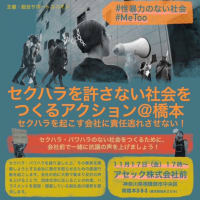前回は、イギリス社会におけるブリットポップそのものの果たしたアイデンティティとしての役割について述べたが、今回はこの音楽を利用することによって利益を得た政治―労働党の第三の道とブリットポップについて書いてみたい。
■ブリットポップと労働党
96年。UK最大の音楽授賞式、ブリット・アウォード。ベストバンド、ベストアルバムで表彰を受けたオアシスのノエルギャラガーは、スピーチの壇上に上がると、「この国の若者にささやかな希望を与えてくれる人」として、オアシスメンバー5人と、所属レーベルであるクリエイションのアラン・マッギーの名を上げ、そして最後の一人の名前を口にした。
「トニー・ブレア。彼こそ男の中の男だ! パワー・トゥー・ザ・ピープル!」
トニー・ブレア、いわずとしれた労働党の党首である(当時)。
彼は、まさにブリットポップとともに現れた。94年、弱冠41歳にして党首にのし上がると、その年のQアウォード授賞式へ出席し、「ロックンロールは私たちの文化と生活の大切な一部であり、この国の大切な産業」とスピーチし、ビートルズ、ストーンズ、キンクスを自分のフェイバリットとして上げた。そもそも彼自身もオックスフォード大学在学時代、アグリールーマーズというバンドを組んでおり、ボーカルを務めていた。
その後もオアシスやブラーとも交流したり、ギターを弾くブレアの写真や、音楽以外にも、流行のアーティストやコメディアン、スポーツ選手などとおさまった写真や映像が幅広く流布された。
ブレアの労働党は、来るべき97年の総選挙で、保守党を政権の座から引きずり下ろすため、イメージアップにブリットポップなどの若者文化にすり寄っていったのだ。(この辺の話は、04年の映画『リヴ・フォーエヴァー』に詳しい。)

そして選挙直前、ブレアは、ブリットポップに火をつけた、かのロック雑誌『セレクト』の表紙を飾る。
そして97年の総選挙。ブレア政権が地滑り的勝利を収めた。659席中、419席が労働党という党史上最大の得票だった。
勝利を祝い、ブレアは首相官邸にノエル・ギャラガーなどスターを招いてお茶会を開いた。手を握るノエルとブレア。
やがて「クール・ブリタニア」のかけ声と共に、イギリスの音楽を国家戦略として積極的に打ち出していくことになる。(ブリットポップ自体は97年に衰退を迎えるのだが…)
しかし、労働党もまた、保守党と同じ、ネオリベラリズム政党だった。強固な労働組合を支持基盤とした一方、万年野党と化していた労働党は、政権を握るためにグローバル企業の味方についたのである。94年に生産手段の国有化という綱領を削除し、それまでの社会民主主義路線から、大きく舵を切った。
ただし、サッチャーとの差異化を図るため、ある程度の福祉を実現させたのも事実だ。とはいえ、それはネオリベラリズムの中で就労意識があり、働く意欲を持つ者にのみ厳選して福祉を与えるという限定的なものだった。(これの日本版が「再チャレンジ」政策というわけだが…)
誰にでも与えられる福祉ではなく、競争社会への能動的な参加と引き替えに、初めて得られる福祉。つまりは、生活を保障する人間を選別するという、修正されたネオリベラリズムに他ならなかった。
ブレアのブリットポップ戦略は、そのなかで民衆の指示を得るための工作に過ぎなかったのだ。
■なぜブレアはUKロックを召還したのか? 労働党による「自由」の「奪還」
前回、ブリットポップが呼び起こすイギリスのナショナリズム、労働者の生活観について書いた。
確かにこうしたブリットポップを労働党が政権奪回のために利用するのは非常に有効だと判断されたのだろう。
しかし、ここでちょっとした疑念がわく。単にナショナルで庶民的な記憶を、何百年にも渡るイギリスの歴史の中から呼び起こすだけなら、その媒体がそもそもロックである必要はなかったはず。なぜ、ここ底の浅い数十年程度の歴史の中から、あえてロックが召還されることになったのだろう。単に若者文化であるという以上の意味があるのではないだろうか。そしてまた、逆になぜ人々からあれほど労働党が支持されたのだろうか。検討してみたい。
それには、サッチャーの行ったネオリベラリズム改革の起源にさかのぼる必要がある。
そもそも、ネオリベラリズムは、60年代に隆盛を極めた若者の運動や、ロックのような文化に象徴されるような、若者の求めた「自由」を、企業や国家の側が乗っ取った思想であったと言える
1960年代、学生運動に象徴される、自由を求めた社会運動が世界中で勃発した。
それはいわば、国家や企業が一元的に社会の隅々に侵入し、自分たちを支配することに対しての抵抗だった。
確かに、当時は経済的に行き詰まりがあったわけではなかった。イギリスに至っては、労働党率いる労働組合運動が実現した国家産業、そして行き届いた福祉政策が、人々の生活を安定させていた。
しかし、一方では、国家や官僚、政治家によって上意下達で一元的に自分たちのライフスタイルや生活が管理され、陰鬱さ、凡庸さに覆い尽くされることに対する不安と敵対感が蔓延していった。
こうしたフラストレーションから、既存の体制に対抗して、多様で自由な表現やライフスタイルが流行し、誰かの命令をただ忠実に実行するのではない、若者自身の能動的な活動がもてはやされた。イギリスでも管理教育に反対する学生運動が各地で頻発し、モッズを始め、スウィンギング・ロンドンと呼ばれる時代の最先端を行く音楽、ファッションのスタイルが若者の間で全盛を極める。(もちろん、前回記したように、以降も80年代に至るまで、そうした自由な音楽のスタイルが生まれていくことになる。ちなみにグラストンベリー・フェスの誕生は70年代であり、60年代末に広まったヒッピー的な思想を受け継いでいるようだ。)
また、この頃には、「自由」を求める運動のみならず、世界的にベトナム戦争反対運動、アメリカの公民権運動やフェミニズム運動など、それまでの労働運動や福祉国家の対象から漏れていた社会的マイノリティや第三世界の人々に対する社会的な不平等に対して、社会的公正を要求する運動もあった。
この自由と社会的公正への欲求こそが、60年代の運動の大きなテーマだったのだ。
こうした運動は、従来の社会体制を大きく揺るがし、国家や企業、管理や金儲けにとらわれないような社会が模索された。
しかし、多様性や自由なライフスタイルの欲求は、少品種大量生産のフォーディズムから、多品種少量生産のポストフォーディズムへの生産体制の移行に伴い、多様化された商品を企業が生みだし、人々に買わせることによって回収されていくこととなる。ロックなどのカウンターカルチャーも、ハード・ロックやプログレッシヴ・ロックのように、多様な商品の一形態へと矮小化されていく。
そして、イギリスは70年代に経済的な行き詰まりを迎える。福祉への高額な出費による財政赤字、国家の規制によって停滞する経済活動への不満が、労働党の牽引してきた福祉国家に対して浴びせられた。労働党は、そうした社会に対する対抗策を打ち出すことができなかった。だが保守党は違った。労働者の保護を建前に企業活動の「自由」を妨害する頑迷で強固な労働組合を敵対視し、経済的活動における「自由」を賞賛するキャンペーンが、メディアや知識人などを動員して行われた。そして、自分たちのネオリベラリズムこそが、60年代に求められていた「自由」を実現する存在だとアピールされた。その結果が、79年の保守党サッチャー政権の誕生に結実する。
つまり、自由を求める運動が、社会的公正を求める運動から切り離され、国家や企業の側に絡めとられてしまったのだ。
しかもその「自由」は、金儲けを基軸とした個人的「自由」であり、コミュニティに貢献することなく、他の人たちを食い物にすることで一握りの人間が膨大な利益を手にすることができる「自由」へと変換されてしまっていた。企業の活動を「自由」にするために、労働条件や社会福祉は切り捨てられ、人々の生活はより困窮した。そして、金で消費することでしか実現しない「自由」で多様なライフスタイルが賞賛されていた。

とはいえ、さすがに、いくら「自由」を標榜したところで、その露骨な格差への敵対感が、80年代、90年代を通して、人々の間に広がっていった。しかし、その怒りは、代替する労働党への支持には結びつかなかった。
公正を求める労働運動の側が、自由を求める運動を取り入れることができなかったのだ。確かに、労働党の標榜する「公正」の実現を求めて、ダサイながらも労働党はある程度の支持を集めていた。ブリット・ポップ期にも活躍することになるポール・ウェラーが80年代に結成していたスタイル・カウンシルなど、支援するアーティストもいた。
しかし、画一的で文化的には至って保守的で退屈で、経済的にも赤字を膨らませるばかりの労働党は、文化的にも経済的にも自由を体現する存在とはとても期待されず、万年野党としか認識されないようになっていた。
しかし、ブレア党首の登場により、自由を求める運動に、社会的公正を求める労働運動の側がついに追いついた…ように人々の目には映った。
自由な文化や表現からはほど遠く、年老いたイメージの労働党が、かつてロックバンドの元ボーカルの経験もある、40歳そこそこの若々しい党首を抱き、「社会的公正」を訴え、さらには経済的な企業活動の「自由」も肯定しながら、政権闘争の舞台に颯爽と躍り出た。そして彼らは、積極的にロックを支持した。
もちろん、ブレア政権は本質的にグローバル企業の利益を代弁するサッチャリズムの、手の込んだ修正版でしかなく、根本的には何も変わっていなかった。
しかし、ブリットポップというナショナリスティックかつ庶民的な、そしてまたそもそもロックという「自由」の記憶を召還することで、人々の興奮と熱狂的な支持を集めることに成功した。
自由という理念を、単なる金もうけの哲学にしてしまった保守党の手から、民衆の側が奪還した。そしてついに、「公正」が抜け落ちた「自由」でもない、「自由」の制限される「公正」でもない、「第三の道」の時代が来た―そう思われた、はずだった。
■ブリットポップ・アイデンティティの限界
こうして、ナショナリスティックで労働者の生活観を反映した文化であり、かつ「自由」や多様性を体現した文化として、ブレアはブリットポップを、政治にロックを取りこんだ。
しかし、いくらイメージアップのためとはいえ、ラディカルな音楽を取り込むことにはリスクが高いはずだった。
アーティストだってそう簡単には政治家に取り込まれることを潔しとはしないだろうし、取り込んだはずが内部から批判されるなどの危険もある。ブリットポップの労働者アイデンティティがラディカルに機能すれば、結局はネオリベでしかない第三の道だって批判されるに違いない。
しかし、そこには、ブリットポップ・アイデンティティの限界があったのだ。二点指摘してみたい。
まず一点目は、イギリスというナショナリズムの限界だ。ブリットポップは、前述のように「俺たちイギリス人」というナショナリズム、アメリカ文化への敵対心を通じて、格差社会における人々の統合をしていた。
確かに、労働者という意識が形成されていることは、上流階級への敵対心を形成し、社会変革へと連なるリスクがある。しかし、企業の活動が以前にもましてグローバル化するなかで、イギリス人労働者のみで労働者の環境を変えていくのには限界がある。ブリットポップがまとめ上げた一体感は、あくまでもイギリス人(移民は排除されると思うが)の労働者だけのものであり、世界的に共有されるようなものではなかった。ある意味でアメリカのネオリベラリズムの矛盾を体現していたグランジやヒップホップとは、全く連携することはなかった。前述のスタイル・カウンシルだって「Internationalists!」とベタベタに歌っていたのに、だ。
そして、もう一点が、労働者階級の本質主義化ともいうべき現象である。
前述したように、ブレア政権がとった福祉政策が福祉の対象とした労働者は、無害化され、ネオリベラリズムに文句をはさむような「危険な」労働者からは区別された、就労意欲のある労働者であった。彼らは、そうした条件付きで初めて生きることを肯定されるのだ。
ここで、ブリットポップが果たした大きな役割がある。ブリットポップにおいて、普通の人々、とりわけ労働者階級は、生まれつきで選択不能な、そして変化することのない本質主義的なアイデンティティとされていることが多い。
これまでのUKロックの中でも、社会的公正や自由を求める、労働者や社会的なマイノリティというアイデンティティが機能してきた。ただ、パンクやレイヴカルチャーは、いずれも既存社会の根本的な変化や、そこからの離脱を志向していた。貧困や社会との違和感は、固定されたアイデンティティや個性としていつまでもあるものではなく、克服していくための一時的なもののはずなのだった。格差をなくして、若者が生きられるようにするためにこそ、パンクスは「俺たちは貧乏だ」と絶望を共有して集まった。
しかし、ブリットポップからは、現実社会を変えていくような要素はすっかり抜け落ちている。貧困の中にいる労働者そのものを本質主義的に変わることのないアイデンティティにしてしまうという転倒が起きている。
そのおかげで、ブリットポップは、ネオリベによって解体されたコミュニティに成り代わって、メディアや音楽業界が、ノスタルジーを引き合いに出しながら「労働者」を商品にして仕掛けた、単なるお祭りとして成立した。
更に言えば、メジャーな音楽のなかでは無視されてきた貧困が、ついにメインカルチャーで語られるようになったわけなのだが、それは、商業主義によって(政治的には)漂白されることで、ネオリベラリズムの社会のなかに包摂されてしまった。
そこには、酒、セックス、ドラッグ、下層の生活の生々しさなどの過激さやパワーはあるが、社会運動としては無害化され、メディアや音楽業界の利益が率先した「イギリスの労働者」という新手のブランドとして商品化されたのだ。

ノエル・ギャラガー映画『リヴ・フォーエヴァー』(右写真は公式HPより)で語る。
「階級は選択肢じゃねえ。」「爪に入った泥は勲章だ。」
さらに、もっと極端なのが、弟のリアムだろう。彼はどこかでこんな調子のことを言っていた。
「仕事が終わってうまいビールを飲んで良い音楽を聴く、それが本当の労働者だ。政治がどうとか言ってるやつは本当の労働者階級じゃねえ。」
ブリットポップが、「生まれつきで変わることのない」アイデンティティであり、社会を根本的に変革したり、労働者階級の置かれている存在そのものを変えていくような側面をそぎ落とされたロックだったからこそ、ブレアは利用することができた。
ブリットポップ爆発の年、94年。まだ保守党政権だったちょうどこの年、社会から積極的に逸脱していくレイヴ・カルチャーのムーブメントに法的にとどめを刺すため、クリミナル・ジャスティス法が成立した。これは、10人以上が屋外で集まって反復するビートを持つ音楽をかけると逮捕されるという異様な法律である。
しかし、ブレア政権成立以降も、依然としてこの法律は残されたままだ。結局、ブレアにとって、労働者や社会的弱者の声はどうでも良いものであり、あくまでも無害なブリットポップだったからこそ、あれだけ利用できたのだった。
さて、ここまでブレアの第三の道とブリットポップの関係について見てきた。
ある意味、ロックの自由を政治に売り渡したとも言えるブリットポップ。
その対局にある現象が、グラストンベリー・フェスなのかもしれない。
そんなわけで、次回はそのブリットポップの衰退と、グラストンベリー・フェスにおける、自由な表現の試みについて見てみたい。(つづく)
(るヒ)