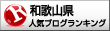:刑法172条 虚偽告訴罪(コロビ転び公務執行妨害罪と言い掛かり逮捕)
:実例:大阪府警南署福田恭弘刑事が取調室で行き成り「さがれ、下がれ、お前 頭突きするのか!?虚偽告訴!」
手錠などの拘束は連続3時間、署長巡視は1日1回以上 警察庁が指示
板倉大地2023年12月1日 20時44分 朝日新聞デジタル記事
愛知県警岡崎署で勾留中だった男性が死亡した事件を受け、警察庁は1日、留置管理についての再発防止策を全国の警察に指示した。
警察庁によると、勾留中に暴れた際に手錠と捕縄を使って行う拘束は、最大で連続3時間と定める。解除後に暴れた場合はまた拘束することもある。拘束中に食事時間が来た場合は、解除時に食事を提供する。これまでは手錠などの使用時間に上限がなかった。
拘束道具を使用する際は警察本部に事前に報告することも指示。これまでは署の判断で可能だった。緊急時でも使用後の速やかな報告を求める。
留置場の巡視では、勾留中に自殺や逃走を図る恐れがある人の場合、署長が1日1回以上、巡視するよう定める。内規では、巡視の回数は定められていなかった。岡崎署では男性が逮捕されてから死亡するまでの10日間、署長が一度も巡視していなかった。
体調を崩していたり、精神に障害があったりする場合には、速やかに救急搬送や入院などの対応を取るよう指示した。
警察庁は今後、留置場の居室にセンサーを設置し、勾留された人の服の動きから呼吸の状況を感知して知らせる仕組みについて、導入を検討するという。(板倉大地)
〈岡崎署勾留死事件〉 昨年12月、愛知県警岡崎署で勾留中だった男性(当時43)が脱水症状による腎不全で死亡した。精神疾患があり、留置場で大声を出すなどしたため保護室に隔離され、「戒具」と呼ばれるベルト手錠や捕縄で手足を拘束されていた。亡くなるまでの5日間は食事ができず、水分も十分に補給できていなかった。県警は同月、署を家宅捜索。一連の対応に法令違反の疑いがあるとみて、調査・捜査してきた。
:実例:大阪府警南署福田恭弘刑事が取調室で行き成り「さがれ、下がれ、お前 頭突きするのか!?虚偽告訴!」
手錠などの拘束は連続3時間、署長巡視は1日1回以上 警察庁が指示
板倉大地2023年12月1日 20時44分 朝日新聞デジタル記事
愛知県警岡崎署で勾留中だった男性が死亡した事件を受け、警察庁は1日、留置管理についての再発防止策を全国の警察に指示した。
警察庁によると、勾留中に暴れた際に手錠と捕縄を使って行う拘束は、最大で連続3時間と定める。解除後に暴れた場合はまた拘束することもある。拘束中に食事時間が来た場合は、解除時に食事を提供する。これまでは手錠などの使用時間に上限がなかった。
拘束道具を使用する際は警察本部に事前に報告することも指示。これまでは署の判断で可能だった。緊急時でも使用後の速やかな報告を求める。
留置場の巡視では、勾留中に自殺や逃走を図る恐れがある人の場合、署長が1日1回以上、巡視するよう定める。内規では、巡視の回数は定められていなかった。岡崎署では男性が逮捕されてから死亡するまでの10日間、署長が一度も巡視していなかった。
体調を崩していたり、精神に障害があったりする場合には、速やかに救急搬送や入院などの対応を取るよう指示した。
警察庁は今後、留置場の居室にセンサーを設置し、勾留された人の服の動きから呼吸の状況を感知して知らせる仕組みについて、導入を検討するという。(板倉大地)
〈岡崎署勾留死事件〉 昨年12月、愛知県警岡崎署で勾留中だった男性(当時43)が脱水症状による腎不全で死亡した。精神疾患があり、留置場で大声を出すなどしたため保護室に隔離され、「戒具」と呼ばれるベルト手錠や捕縄で手足を拘束されていた。亡くなるまでの5日間は食事ができず、水分も十分に補給できていなかった。県警は同月、署を家宅捜索。一連の対応に法令違反の疑いがあるとみて、調査・捜査してきた。