山梨百名山:雁ヶ腹摺山 小金沢山 大蔵高丸
登った山:雁ヶ腹摺山(1874m) 赤岩ノ丸(1792m) 川胡桃沢ノ頭(1965m) 牛奥ノ雁ヶ腹摺山(1985m)
小金沢山(2014.4m)三等三角点 点名:雨沢 黒岳(2010m)一等三角点 点名:小金沢山 白谷ノ丸(1920m)
大蔵高丸(1781m)
平成30年12月1日(土) 天候:晴 メンバー:単独 所要時間:9時間47分 距離:GPS計測=20.6km
-------------------------------------------------------------
①大峠05:40---②雁ヶ腹摺山06:21---①大峠07:03~07:15---③赤岩ノ丸07:42---④黒岳分岐点08:18
---⑤川胡桃沢ノ頭08:40---⑥牛奥ノ雁ヶ腹摺山09:02---⑦小金沢山09:46---④黒岳分岐点---⑧黒岳11:25
⑨白谷ノ丸11:43---⑩湯ノ沢峠12:10---⑪湯ノ沢峠避難小屋---⑫大蔵高丸12:45---⑨白谷ノ丸14:01---
⑧黒岳14:37---④黒岳分岐点14:39---①大峠15:27
-------------------------------------------------------------

2018/12/1(土)のログ
三つの「雁ヶ腹摺山」と付く山名に興味を抱き歩いてきました。

昨夜、大峠に着きそのまま車中泊し翌早朝05:40出発し途中の登山道から南南西側に見えた富士山

で、雲取山山行で見た「雁ヶ腹摺山」に40分ほどで到着
既に1名の登山者が富士山に三脚を向けていました。

東側から06:24 陽が昇り始めて

4分ほどで陽が顔を出してきました。

06:34富士山の光景
ここから見る富士山は、旧500円札に印刷されていた富士山の撮影場所なんだそうです。
ちなみに雲取山山行の時、七ッ石小屋から見た雁ヶ腹摺山

大月市では、秀麗富嶽十二景が選定されており大月市域の山頂から望む美しい富士山を市のシンボルとし自然を
そのまま後世に伝える目的で選定したそうです。

山頂を後にし西側に広がる山稜が見えだしてきました。

登山道は良く整備されています。

大峠から数分の場所には水場もあります。

大峠に戻り

朝食を済ませ、次なる「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を目指します。
大峠の駐車場から見た富士山です。

先ずは黒岳方向を目指し いていきます。
いていきます。

途中「赤岩ノ丸」1792mピークを通過して行きます。
この周辺には「丸」なるピークがいくつもあることを発見 しました。
しました。
で、雁ヶ腹摺山もそうなんですが「丸」にも探求心が湧いてきま~したよ 。
。

黒岳の④分岐を通過し⑤川胡桃沢ノ頭へ、霜 が降りていました。
が降りていました。

目の前に目指す牛奥ノ雁ヶ腹摺山が見えてきました。

で、牛奥ノ雁ヶ腹摺山に09:02着、ここは山梨百名山では無いようですが日本で一番長い山名らしいです。

その山頂から見える富士山です。

さらに北上し 小金沢山を目指して
小金沢山を目指して

牛奥ノ雁ヶ腹摺山から44分ほどで小金沢山に到着です。
小金沢山は山梨百名山になっていました 。
。

山頂からは雲取山(左側ピーク)が見えています。

パノラマで撮影です。
富士山と雲が素敵です。

小金沢山から→牛奥ノ雁ヶ腹摺山→川胡桃沢ノ頭と戻り④黒岳分岐点から数分ほどで黒岳山頂に到着です。
黒岳(2010m)山頂には一等三角点 点名:小金沢山が設置されていました。
で、変ですね。黒岳の点名が小金沢山だなんて?
先ほど登ってきた小金沢山(2014.4m)は三等三角点で点名が雨沢なんですよ。変ですね~
こんなことが良く見うけられますが点名はどうやって付けているのでしょうかね。

黒岳から南に下った見晴らしの良いピーク名は「白谷ノ丸」の山名板が設置されていました。
大峠から登ったピークの「赤岩ノ丸」といい「白谷ノ丸」の「丸」興味津々であります 。
。

白谷ノ丸から270mほど急降下し湯ノ沢峠へ下ってきました。

この峠には、湯ノ沢峠避難小屋があるんですが小屋裏は林道日川線の終着でトイレが整備されていました。

時間がまだあるので湯ノ沢峠からさらに南下し山梨百名山の「大蔵高丸」の山頂へ到着し
三つ目の「丸」の頂きに到着しましたよ。
で、帰宅後「丸」について調べてみました。
その結果、「山梨百名山」によれば「丸」は古い朝鮮語の「山」である「モリ」が語源ではないかと。
奈良時代ごろ大月周辺には多くの百済人が渡来した記録があるそうなんです。
で、「丸」の山も極めてみたいな~と思ったのでした。

さ~大峠へ向けていざ出発だ
目の前に見えるピークである白谷ノ丸まで270m登り返していくのですが気持は こんな感じ・・・
こんな感じ・・・

この周辺はお花畑だそうで広範囲にフェンスが張られ獣の侵入を防止しています。

ふ~ふ~いいながら白谷ノ丸を通過して行きます。
黒岳分岐から赤岩ノ丸への登山道は風倒木が連続して横たわっているので注意が必要です。

風倒木を跨ぎ迂回して無事大峠へ到着しました。
明日、三つ目の笹子ノ雁ヶ腹摺山と本社ヶ丸(ほんじゃがまる)を目指すべく「道の駅つる」へと下っていきます。
2日目に続く


















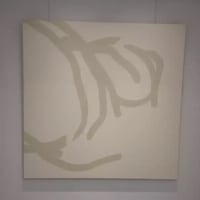
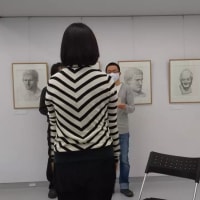








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます