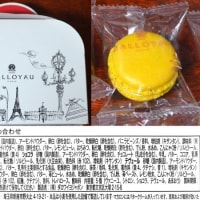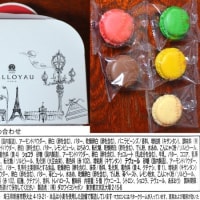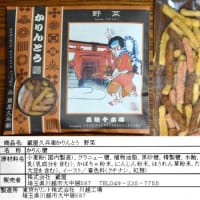この時期あたりになると、
「日本には八百万(やおよろず)の神さまがうんぬん」という
話が聞かれるようになるものですが、
実は「やおよろずの神」というのは、
たくさんの神様、いろいろな種類の神様を表す言葉ではない、
というのをご存知でしょうか。
改めてすこし考えればわかることですが、
たくさんの、千種の神様のことを表すなら、「万(よろず)の神」と
言えばいいだけのことです。
日本語の用法として、全体を現す単語の前に何か単語を置くというのは……
『限定化用法』ともいうべきもので、範囲を狭めるものなのです。
たとえば、宇宙会議に『全国』の指導者が集まった、と言えば
それは世界の全部の国のことをあらわします。
一方で、宇宙会議に『日本全国』の指導者が集まった、と言えば
なぜか日本なにかの区分の指導者が集まったということになります。
『万(よろず)』もそれと同じ。
『万(よろず)』で全部をあらわすのですから、
その頭に限定語をあえてつけるというのは、
意味を広げるのではなく、意味を狭めるのです。
たとえば、『よろずの神』で全部の神様をあらわすのに対し、
『四国よろずの神』と言えば、四国の種々の神様を表します。
日本語の誤用ではなく、古い神道の正しい言葉では、
八百万の神は、そういう限定系統の神様をあらわす言葉なのです。
なぜこんな誤用が広まってしまったかといえば、
古文解釈者が古文を誤訳したからです。
加えて、八百屋がいろんな種類の野菜を売っていることと
概念を混ぜてしまったこともあるのでしょう。
でも、その八百屋も本来の語源は別の場所にあり――
古文を読んで行くのはとても楽しいですが、
どれだけ解読してもまともに取り合ってもらえる場所がないのが残念です。
古文を読める人と語り合ってみたいものです。
わたしの研究も資料も残せるものなら残したかったです。