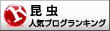2010/7/16 大雪山系・雲ノ平にて
7月に入り、エゾ梅雨のようなジメジメした天候が続いていた。
本日は天候も良く、大雪山系の黒岳と雲ノ平を歩いてみた。思い起こせば、この時期は大雪山系の他の山域を歩くことから、はじめて歩いた黒岳・・・笑
ロープウェイとリフトを利用して黒岳の7合目まで観光客と一緒に到着してしまうけど、リフトから見下ろす花々と高山蝶の数々は別世界のようだ~♪ リフトから撮影したら転び落ちるかも知れないので、自粛しましたが・・・。
黒岳への登山道は短時間で登れることから、観光客や初心者の登山客も多いが、垂直分布ゆえ高山植物の変化は驚くばかり。いつも、下山に利用することから、この素晴らしさに気が付いてなかった。
さて、この日は、チシマツガザクラが標高2000m付近の大地で満開♪
2010/6/26 十勝岳連峰・雲の平にて
【出典:Wikipedia】
ギンザンマシコ(銀山猿子)は、動物界脊索動物門鳥綱スズメ目アトリ科に分類される鳥類の一種である。
アメリカ合衆国、カザフスタン、カナダ、スウェーデン、中華人民共和国北部、日本、ノルウェー、フィンランド、モンゴル、ラトビア、ロシアスカンジナビア半島北部からロシア極東地域に至るユーラシア大陸の亜寒帯と、アラスカ、カナダ北部、ロッキー山脈で繁殖し、一部の個体は冬季に南方へ渡る。
日本では、北海道の高山(大雪山系など)で少数が繁殖するほか、冬鳥として北海道の各地に渡来する。本州では冬季まれに観察される。
全長20-22cm。腹部の羽毛は灰色。翼や尾羽の羽毛は黒褐色で、羽縁は淡色。オスは全身が赤い羽毛で覆われる。メスは全身が黄褐色の羽毛で覆われる。
高山帯や針葉樹林に生息する。冬季になると標高の低い場所へ移動し、小規模の群れを形成する。冬季には市街地の街路樹でも見られる。食性は雑食で昆虫類、木の葉、果実(ナナカマド、ハイマツ、ハンノキ)等を食べる。地上でも樹上でも採食を行う。
2010/7/3 手稲山にて
意識して見つけた、ヒカゲチョウ・・・・ところが
帰宅して調べたら、ヒカゲチョウは北海道以外が生息域、クロヒカゲは日本全土が生息となっていたので、ヒカゲチョウは見ること出来ないことに気がついた。
だけど、ヒカゲチョウによく似てるなぁ~
2010/6/27 十勝岳連峰・富良野岳にて
初めて、国の天然記念物の「ウスバキチョウ」の滑空写真に挑戦しました。かなり遠距離でしたが、見える程度には撮影できました!
実は、富良野岳はコマクサは少なく、殆ど期待してなかったのですが、ウスバキチョウが飛び交っていることで、付近を観察してみるとコマクサが数年前よりも増えていることに気がつき、二重の感激でした。
2007/7/15 白雲岳頂上付近にて
我が国における分布は、北海道の大雪山系・十勝岳連峰の標高1,700m以上の高山帯のみに限定され、日本国指定の天然記念物である。アゲハチョウ科の中でも原始的なグループに属する種類。局地的な分布や個体数の減少により、日本からの絶滅も危ぶまれている。
我が国での幼虫の食草は、同じく天然記念物であるコマクサであるため、両者の個体数のバランスを保つことが課題とされる。
《出典:Wikipedia》
果たして今年は撮影が許されるだろうか・・・・楽しみな存在である。