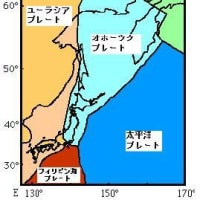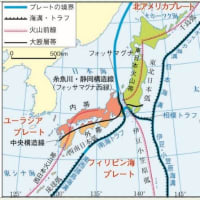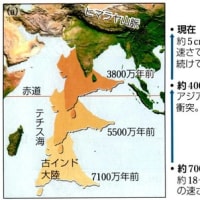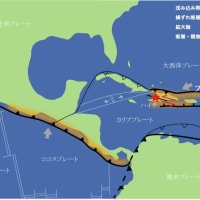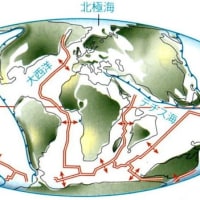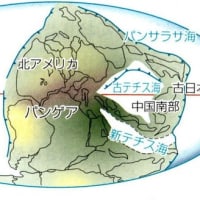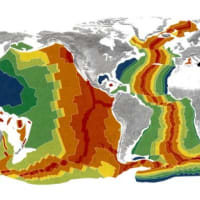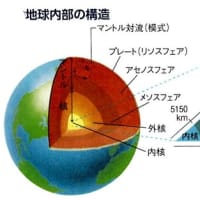宮城県仙台市の折立団地の場合



自動車が積雪あるいは凍結の冬道を、スリップせずに安全に走行するためには、スパイクタイヤが有効であった。しかし、雪も氷もない舗装道路を走行すると、スパイクタイヤは路面を削り、主要道路周辺ではアスファルト粉塵が舞い上がり、冬の空気を吸い込むと、喘息になることもあった。スパイクタイヤは粉塵公害の元凶であった。
地元新聞社が、1980年からスパイクタイヤの追放のために一大キャンペーンを展開した。宮城県議会は全国に先駆けて、1985年12月25日 にスパイクタイヤ対策条例を公布した。スパイクタイヤの使用禁止が県レベルで決められ、やがて、全国的に禁止された。
しかし、ピンのない冬タイヤ(スタッドレスタイヤ)では、自動車のスリップ事故などが増えて危険なため、仙台市は折立団地を除雪・融雪モデル地区に指定した。


スパイクタイヤは積雪道路でも凍結道路でも、スリップをせず、積雪地域の自動車には不可欠であった。しかし、スパイクタイヤに打ち込まれた特殊ピンが、雪のない道のコンクリート舗装道路を削り、粉塵をまきあげた。仙台市・札幌市市街地では、スパイクタイヤの粉塵による健康被害が大きかった。
折立団地は1970年代に宮城県住宅供給公社の造成した住宅団地であり、北斜面の日当たりの悪い斜面で、なかなか売れなかった団地でもあった。この陽当たりの悪い団地で、スパイクタイヤからスタッドレスタイヤに転換できれば、スパイクタイヤを全国から追放できる契機になるはずであった。
折立団地には1cmの積雪があれば、大型除雪車が即座に出動、さらにその後ろからは散水車が融雪剤入りの水をまいた。モデル地区としての除雪・融雪を徹底した。道路には雪も氷もないのだから、当然、夏タイヤ同然の当時のスタッドレスタイヤでも、有効性は明らかであった。
除雪車・融雪車の重機が、団地外周の谷を埋めた狭い道路を走り回れば、谷を埋めた砂礫は圧縮されて、団地外周道路は沈下した。このことは関係者が事前に恐れていたことだが、スパイクタイヤ追放キャンペーンの声の大きさに負けたのであった。
結局、沈下予防の薬品注入やパイルの打ち込みをせず、除雪・融雪の重機を走らせた。重機の重さで舗装道路には小さな割れ目ができ、そこからは融雪水が侵入して、コンクリート直下で凍ったり融けたりして、地下にひび割れができ、それが次第に拡大、空洞化が進んだ。
地震のたびに、離れた割目がつながり、3月11日の東日本大震災では、団地内外の道路が崩壊した。そこに面した住宅では土台が崩れ、大きな被害を出した。
仙台市ではこの事態を予想していたのか、いないのか、知っていても黙っていたのか、それとも財政難が理由かは分からないが、とにかく、仙台市内の多くの団地では、大型重機による除雪・融雪を、2000年前後から、できる限り、しないようにしている。
団地内の除雪は、団地住民の手作業にまかされた。塩分の多い融雪剤は健康に悪いため、融雪剤の散布を減らした。
団地住民の手作業による除雪作業が多くなった。高齢化した団地住民には重労働であり、朝の通勤時刻までには除雪・融雪は終わらない。そのため積雪時の自家用自動車通勤が減り、チェーン装着の市営バス利用者が増えた。
陽の当たらない坂道の団地では、冬の積雪量が多い。その融けた水が舗装道路の下の土中にたまって凍結し、舗装道路を下から損傷することがある。やがて、その空洞が自然にあるいは小さな地震でも突然崩れ、道路・住宅が大きな被害を受けることが目立つようになる。
住宅は南側斜面の方がよいようである。
仙台市の冬は暖かく、日中は雨で、夜間に雪になる。早朝からの除雪・融雪作業が、重機から、団地住民の手作業に転換された。日中には道端に積み上げられた雪からの融水が舗装道路下に流れ込んで、重機の使用時と同様、舗装道路は下から痛めつけられる。
特に、折立団地のように、陽当たりの悪い北向き斜面では、積雪つまり融雪水が多いので、坂道に面した住宅を建てる場合、冬の積雪・融雪が道路を痛める恐れがあるかどうか、よく検討しなくてはならない。団地の端は景色がよいものだが、崖と道路と自宅の位置関係に注意し、宅地を選ぶことが重要である。折立団地の特殊例ではない。どこの住宅団地でも起こる危険がある。
ただし、北海道のように、積雪を道に残さず、海・川・排雪溝・指定集積地に運ぶ場合はコンクリート下の空洞化は進みにくい。



自動車が積雪あるいは凍結の冬道を、スリップせずに安全に走行するためには、スパイクタイヤが有効であった。しかし、雪も氷もない舗装道路を走行すると、スパイクタイヤは路面を削り、主要道路周辺ではアスファルト粉塵が舞い上がり、冬の空気を吸い込むと、喘息になることもあった。スパイクタイヤは粉塵公害の元凶であった。
地元新聞社が、1980年からスパイクタイヤの追放のために一大キャンペーンを展開した。宮城県議会は全国に先駆けて、1985年12月25日 にスパイクタイヤ対策条例を公布した。スパイクタイヤの使用禁止が県レベルで決められ、やがて、全国的に禁止された。
しかし、ピンのない冬タイヤ(スタッドレスタイヤ)では、自動車のスリップ事故などが増えて危険なため、仙台市は折立団地を除雪・融雪モデル地区に指定した。


スパイクタイヤは積雪道路でも凍結道路でも、スリップをせず、積雪地域の自動車には不可欠であった。しかし、スパイクタイヤに打ち込まれた特殊ピンが、雪のない道のコンクリート舗装道路を削り、粉塵をまきあげた。仙台市・札幌市市街地では、スパイクタイヤの粉塵による健康被害が大きかった。
折立団地は1970年代に宮城県住宅供給公社の造成した住宅団地であり、北斜面の日当たりの悪い斜面で、なかなか売れなかった団地でもあった。この陽当たりの悪い団地で、スパイクタイヤからスタッドレスタイヤに転換できれば、スパイクタイヤを全国から追放できる契機になるはずであった。
折立団地には1cmの積雪があれば、大型除雪車が即座に出動、さらにその後ろからは散水車が融雪剤入りの水をまいた。モデル地区としての除雪・融雪を徹底した。道路には雪も氷もないのだから、当然、夏タイヤ同然の当時のスタッドレスタイヤでも、有効性は明らかであった。
除雪車・融雪車の重機が、団地外周の谷を埋めた狭い道路を走り回れば、谷を埋めた砂礫は圧縮されて、団地外周道路は沈下した。このことは関係者が事前に恐れていたことだが、スパイクタイヤ追放キャンペーンの声の大きさに負けたのであった。
結局、沈下予防の薬品注入やパイルの打ち込みをせず、除雪・融雪の重機を走らせた。重機の重さで舗装道路には小さな割れ目ができ、そこからは融雪水が侵入して、コンクリート直下で凍ったり融けたりして、地下にひび割れができ、それが次第に拡大、空洞化が進んだ。
地震のたびに、離れた割目がつながり、3月11日の東日本大震災では、団地内外の道路が崩壊した。そこに面した住宅では土台が崩れ、大きな被害を出した。
仙台市ではこの事態を予想していたのか、いないのか、知っていても黙っていたのか、それとも財政難が理由かは分からないが、とにかく、仙台市内の多くの団地では、大型重機による除雪・融雪を、2000年前後から、できる限り、しないようにしている。
団地内の除雪は、団地住民の手作業にまかされた。塩分の多い融雪剤は健康に悪いため、融雪剤の散布を減らした。
団地住民の手作業による除雪作業が多くなった。高齢化した団地住民には重労働であり、朝の通勤時刻までには除雪・融雪は終わらない。そのため積雪時の自家用自動車通勤が減り、チェーン装着の市営バス利用者が増えた。
陽の当たらない坂道の団地では、冬の積雪量が多い。その融けた水が舗装道路の下の土中にたまって凍結し、舗装道路を下から損傷することがある。やがて、その空洞が自然にあるいは小さな地震でも突然崩れ、道路・住宅が大きな被害を受けることが目立つようになる。
住宅は南側斜面の方がよいようである。
仙台市の冬は暖かく、日中は雨で、夜間に雪になる。早朝からの除雪・融雪作業が、重機から、団地住民の手作業に転換された。日中には道端に積み上げられた雪からの融水が舗装道路下に流れ込んで、重機の使用時と同様、舗装道路は下から痛めつけられる。
特に、折立団地のように、陽当たりの悪い北向き斜面では、積雪つまり融雪水が多いので、坂道に面した住宅を建てる場合、冬の積雪・融雪が道路を痛める恐れがあるかどうか、よく検討しなくてはならない。団地の端は景色がよいものだが、崖と道路と自宅の位置関係に注意し、宅地を選ぶことが重要である。折立団地の特殊例ではない。どこの住宅団地でも起こる危険がある。
ただし、北海道のように、積雪を道に残さず、海・川・排雪溝・指定集積地に運ぶ場合はコンクリート下の空洞化は進みにくい。