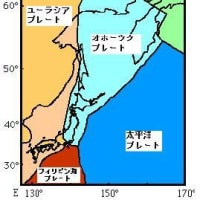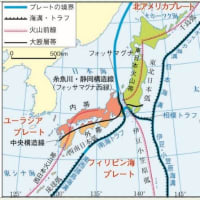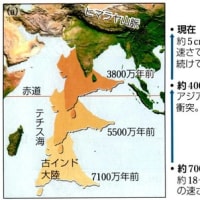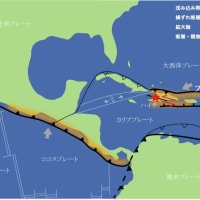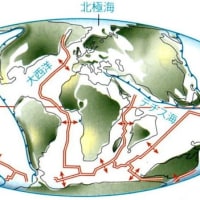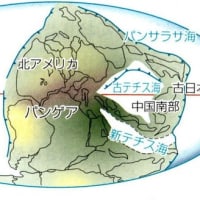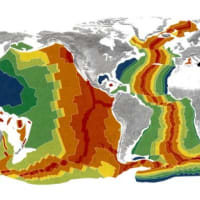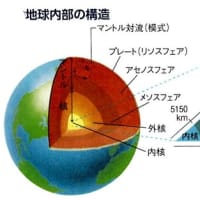河川争奪
野坂山地では石田川の流域が広く、大量の雨水・砂礫を西方向に運搬していた。
しかし、fm(マキノ断層)の活動で、西側が隆起、相対的に東側が沈降した。
この断層運動により、石田川の断層東部分は、沈降した百瀬川に流れを変えた(河川争奪)。
その結果、石田川上流域の砂礫と水は百瀬川に流入することになった。
百瀬川にとっては適正量を超える砂礫・水量を得たことになった。
百瀬川は、野坂山地の出口から下流方向に扇状地を形成した。
百瀬川扇状地の堆積物は、百瀬川の侵食分に石田川の侵食分が、加わったものである。
百瀬川の洪水が起こりやすくなったため、山中にも扇状地にも多数のせき(砂防ダム)をつくった。
さらに、百瀬川に石田川の水量の加わるので、百瀬川に葉堤防と遊水池の建設が必要になった。
百瀬川の天井川は、石田川からの増量分を考慮すれば、天井川解消も急務であった。
地形図のfs酒波断層は、琵琶湖西岸断層の一部で琵琶湖側が沈降して扇状地が多数できる。

百瀬川上流~中流
百瀬川は野坂山地の谷を侵食し、その砂礫を堆積して扇状地を形成した。
かつて流路が安定せず、洪水が頻発した。扇央の水田部分も、百瀬川の旧流路である。
百瀬川の洪水被害対策として、
� 百瀬川の流路を、現流路に堤防で固定した。
� 百瀬川扇頂に水門をつくり、百瀬川の流量と農業用水の流量の配分を可能にした。
� 百瀬川本流に多数の砂防ダム(せき)を建設、砂礫の流出をおさえている。

(1975年)
百瀬川中流~下流
百瀬川が運搬堆積した砂礫で、河床を上昇させて、天井川になった。
県道335号は、百瀬川との交差では、河床の下を通る、天井川である。
しかし、生来川との交差では河床の上を通り、生来川は天井川ではない。
百瀬川は天井川で洪水の危険があり、低位置の生来川に流水を落とす工事を続けてきた。
生来川は低位置にあり、天井川の百瀬川の水を琵琶湖に流す。その目的で生来川の拡幅工事がなされた。

(1975年)
百瀬川の天井川の終点1
下流(八反田地区)で百瀬川の天井川は終わり、低位置を流れる生来川に流された。
しかし、現在、百瀬川の天井川部分は埋め立てられて、右岸・左岸の堤防がつながった。
かつての天井川は、現在は農道として使われている。

(2003年)
百瀬川天井川の終点2
湖北バイパスの手前で、百瀬川の洪水は生来川に落とされる。
終点2の先には百瀬川の流路はない。
百瀬川の水が、この終点2から流れ落ちることは、梅雨・台風の大雨の時だけである。
ふだんは水が流れず、鉄板を組み合わせてつくった、仮の水路である。

(2003年)
落差工の工事開始
百瀬川は高い位置の天井川であり、低い位置につくられた生来川に洪水が流される。
百瀬川の堤防を切り取り、そこから生来川に向かう落差工建設が始まった。
生来川は琵琶湖に注ぐ小川であったが、百瀬川の洪水を流すために掘削・拡幅された。
また、落差工の頂上部分の堤防は、百瀬川の堤防ではなく、百瀬川遊水地の堤防である。

(2004年)
落差工だけ完成(2007年)
高さ20mの落差工本体は完成した。しかし、まだ使うことはできない。
落差工上部の百瀬川遊水地が未完成であり、遊水地と落差工とがつながっていない。
落差工下部は雨水がたまっているが、生来川とつながり、完成している。
落差工本体は完成したが、遊水地からの水路がなく、使用できないのである。

遊水池(遊水地)
遊水地は、百瀬川の洪水をいったん貯め、放水量を調整しながら、落差工から生来川へ計画的に流すことを目的とする。ダムと同じものである。
しかし、2010年現在、百瀬川から遊水地に入る流路が建設されていない。
また、遊水地から落差工への流路(放水路)も建設されていない。
落差工は、遊水地が完成しない限り、使用できない。
しかし、遊水地の工事は、予算の都合だろうが、停滞したままである。
落差工はムダのままだが、遊水地は雨水がたまって野鳥の楽園になっている。

(2010年)
人・車はトンネル
県道335号は、百瀬川の下を通る。トンネルの南は335号、トンネルの北は287号である。
百瀬川は天井川の典型だが、トンネルの上を水が流れるのは、洪水時のみで、年5、6回である。
それでも洪水の危険を避けるため、百瀬川の流れを北の生来川に流す工事が進行中である。
トンネルは狭くて自動車のすれ違いができない。生活道路で西近江路の名称がある。
大型トラックの通行できる湖北道路(県道161号)が建設された。

最新の画像[もっと見る]