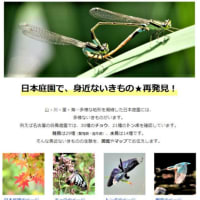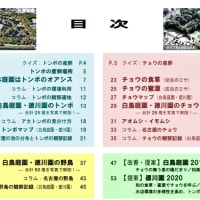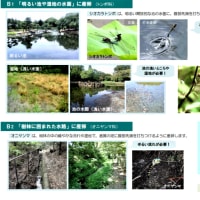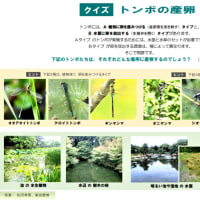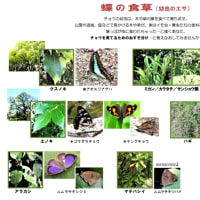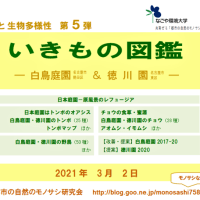アコウの木(推定樹齢175年)
鹿児島県肝属郡根占町山本の宮田小学校に生えていたアコウの木。
故あって伐採を迫られていましたが、デザイン博白鳥会場に移植され、オアシス広場でやさしい木陰を提供してくれました。
25年後の今も、国際会議場南の公園でユニークな存在感を見せています。
2014年10月31日
世界デザイン博覧会から25年
デザイン博が変えたもの、残したもの
【主催】 熱田生涯学習センター・熱田区役所・名古屋学院大学
【会場】 名古屋学院大学白鳥学舎 翼館4階クラインホール
【講師】 元(財)世界デザイン博覧会協会事務局・加藤正嗣
今回は、1989年に開催された世界デザイン博覧会の話題(講演会記録)です。
デザイン博の「志」を改めて振り返り、決して一筋縄では行かない「都市の緑」に取り組むヒントが得られればと思います。
◆デ博は、名古屋の文化革命!
当時、日本全体が「重厚長大から軽薄短小へ」と舵を切ろうとしていました。
名古屋もまた、戦後の都市計画による「整然とした均質で機能的なまちづくり」から、「潤いや個性、感性を感じさせるまちづくり」への脱皮を模索していました。
「モノづくりの伝統を生かしながら、21世紀に向けてもう一皮むけるにはどうすれば良いか?」、そんな問題意識も広がり始めていました。
そんなとき、「デザイン」 というキイワードにたどりついたのです。
◆デザイン博は、ムーブメント!
今ではその重要性を誰も疑わないデザインですが、当時はまだ、市民生活には縁遠いものという受け止め方が一般的でした。
おまけに名古屋は、ダサい、エビフリャ~などとバラエティ番組で笑いをとるためのスケープゴートにもされていました。
そんな状況を変えるための「ムーブメント」を起こそう!
デザイン博は、単なるお祭りやエンタメではなく、名古屋が21世紀に向けて脱皮するムーブメントだ!
そう呼びかけたのが、デザイン博でした。
ムーブメントという言葉(思想)を、日本で最初に公式に使ったのもデザイン博でした。
◆制約を個性に変える!
「郊外型・開発型」が一般的だった博覧会を、「都市型・既存ストック活用型」に転換したのも、
会場には一般車駐車場を設けず、「パーク&シャトル方式」へと大胆に転換したのも、
「分散会場+まちじゅうが博覧会」方式によって、多様な参加を実現させるモデルを開発したのも、
元祖「キモカワ」といえるデポちゃんブームも、
・・・・
今では当たり前になっている多くのことが、デザイン博から始まりました。
そしてそれは、様々な不利な条件を何とか克服したい! しかし理想は曲げたくない!
そんな悩みの末のブレイクスルーだったのです。
◆デ博がまいた種
堀川をにぎわいと潤いの都市軸に変える取り組みはもとより、
ごみ非常事態宣言、愛・地球博、COP10、・・・多くの取り組みに際して、デザイン博の経験が生かされました。
1989年から25年たった今、改めて、「デザイン博が変えたもの、残したもの」を振り返ってみたいと思います。
■ 講演スライドの一括ダウンロードは → 【PDF】
□ FM-DEPO をもう一度聞きたい方は
→ 開局時の放送(1989.7.1)
→ 閉幕日の放送(1989.11.26)
デ博閉幕後も放送継続を望む声が殺到し、Zip FMの開局につながりました。
また愛・地球博のFM LOVEARTHにも引き継がれました。
■ 分割してダウンロードしたいときは
第1部 開幕までの歩みと背景 → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
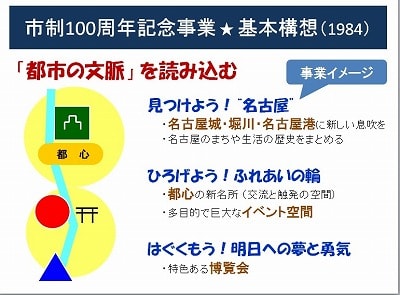
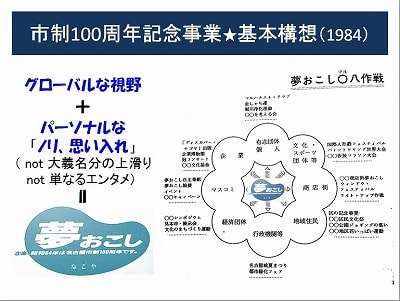 ほか
ほか戦前の名古屋は、南北軸(堀川、本町通)に沿って発展しました。戦後は一転して、東西軸(広小路、地下鉄東山線)が主役になりました。
市制100周年事業では、南北軸の再生(名古屋城・堀川・名古屋港に新しい息吹を)が図られました。
当時は、一村一品運動など町おこしの創世紀でした。
我々も当然に名古屋の町おこしをねらったわけですが…、
しかし同時に、「200万都市の名古屋が、名古屋を興すだけで良いのか? もっと普遍的な何かをめざす必要があるのでは?」という思いや、
「大義名分の上滑りではなく、個の思い入れやノリを大切にしたい」 という思いがありました。
そうだ 「夢」 だ! 夢を興そう!
これなら、「グローバルな目線とパーソナルな思い入れ」を統合できる!
こうして、「夢おこし」 というキャッチフレーズが生まれ、デザイナーの山内瞬葉さんがユニークなマークにしてくれました。
第2部 デザイン博はムーブメント! → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
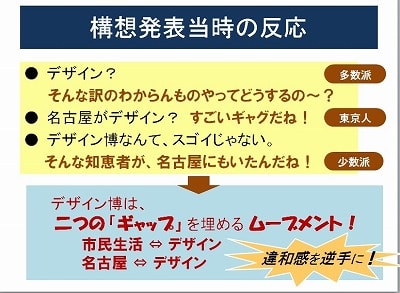
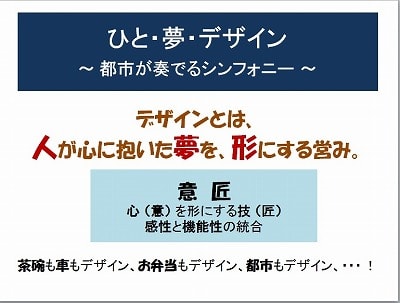 ほか
ほか「博覧会はエンタテイメント」という割り切りが世間で横行する中で、「博覧会はムーブメント!」という 「青臭い志」 を貫きました。
そこには、「ムーブメントにしない限り、二つのギャップを埋められない!」というリアルで切実な認識がありました。
協会職員はもとより、デザイン関係者、出展企業、参加した市民団体、…関係者のだれもがデザインの4文字と格闘しました。
第3部 3会場の個性化 → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
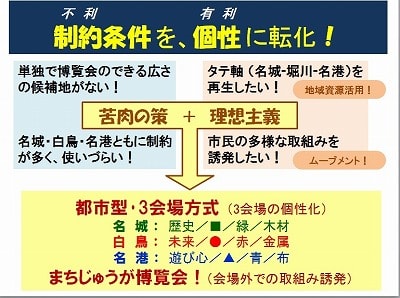

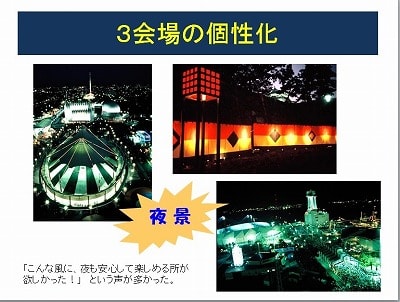 ほか、懐かしい風景の数々…
ほか、懐かしい風景の数々…「当初に思い描いた夢のうち半分くらいしか形にできなかったけど、でも、思いもかけなかったことがたくさん実現しましたね」
… そんな泉眞也さん(総合プロデューサー)の言葉のように、
大手企業のパビリオンだけでなく、多様な主体による多様な表現が花開きました。 ムーブメントの醍醐味!です。
第4部 元祖★ネットワーク型博覧会 → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
 ほか
ほか「窮すれば通ず」のことわざ通り、苦肉の策から新しいスタイルが生まれました。
第5部 元祖★キモカワ → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
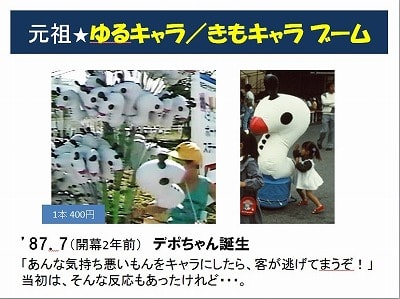
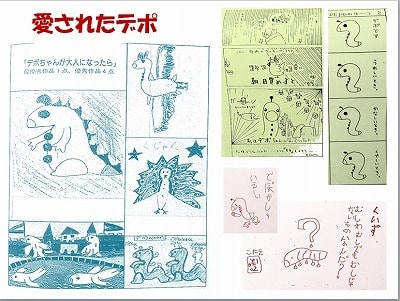 ほか
ほか博覧会協会職員の勝手連「デポちゃんクラブ」も大暴れしました。
ノーベル賞輩出の名古屋大学のように、「現場の自由な発想と行動が許される雰囲気」が、当時の博覧会協会にはありました。
これも、デザイン博の貴重な財産でした。
第6部 デ博の播いた種 → 【PDF】
*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)
 ほか
ほかスライドには書き洩らしましたが、名古屋市立大学芸術工学部の誕生(1996)も、デザイン博の成果です。
このほかにも、継承すべきものがたくさんあると思います。
ご意見を、お寄せください。