
〈訂正〉「その4」で、モンターグの台詞を「(主遣いの)照屋さんと高橋さんが同時に言った」としたのは誤りで、正しくは「(クラリス役の)佐藤さんと高橋さんが同時に言った」でした。
「その4」の本文はすでに直しています。ストーンマン、フェルプス夫人を演じた田川陽香さん、ご指摘ありがとうございました。
脚本・演出
客席で観る限り、脚本家と演出家の仕事を見分けることは難しいので、とくに分けずに論じます。
脚本 佃典彦さん
演出 小林加弥子・中村孝男
★
原作
アメリカのSF作家レイ・ブラッドベリの原作(1953年)。
「火星年代記」とともに代表作とされ、州によっては現在、ハイスクールの副読本に指定されているらしい。
反対に、あまり評価しない声があるのも事実。
魅力も多い作品だが、ドラマの原作として見ると、難しいところは多い。
〇主人公の「物語の始まり」時点での位置とエンディング時点での立ち位置の落差が少ない。(結局、おなじところをぐるぐるしている。モンターグはこの物語が始まる前から、本を持ち帰り自宅に隠している。つまり、昇火士の仕事と本の価値について、現状に疑問を感じている)
〇フェーバーや昇火隊長ベイティーの理屈っぽい長広舌。
〇モンターグ、ベイティー、フェーバー、そしてラストに出てくる学者たちの関心と思考形態が似通っていること。
〇物語が、登場人物間の葛藤によってカタストロフを迎えるのではなく、「隣国による都市への攻撃」という外力によって終わること。(この隣国は、詳しく描写されないが、ロシア=ソビエトの影が濃い)
などなど。
これは、執筆当時、実際に行われた「アカ狩り」や「危険文書の焼却」「思想統制」に、ブラッドベリが切迫した危機感を抱いていたから、なのだろう。当時、マッカーシズムによって多くの学者・文化人などが、スパイ容疑や陰謀罪などで逮捕された。
構成の不備や作品の完成度を置いても、「伝えたい」「伝えねばならない」中身があった、破綻するほど追い詰められた熱情がブラッドベリには、あった。
この熱情は、作中、モンターグの一見突発的な訳の分からない暴力的な衝動に反映されても、いる。
思想統制と同時に、TV、ラジオ、コミックなどの、軽薄になりがちな新しい大衆文化への危機感も、この作品には反映されている。搾取と侵略によって経済的に繁栄しながら、文化としては頽廃していく自国の白人中心社会への批判も、あったのだろう。引いては、「言論・創作活動や自由な社会活動の未来」に対する(フェーバーのような)無力感のさえ、感じていたと思われる。
★
構図としては、
〇人々の思考・思想の多様さを高め、豊かな感情・感覚を育てる「本」を、焼きつくして、一般大衆の「考え、感じ、表現する心」を奪う立場の行政(昇火所長ベイティーに代表される)。
〇対立項として、規制システムにスポイルされ、都市を逃れる学者たち、グレンジャー、シモンズ博士など。また。隠遁しながらテロのような反撃を狙う非力なフェーバー、社会システムから自由で〈自分自身〉として自然に生きる少女、クラリス。
〇行政の思い通りにコントロールされ、疑問を感じず享楽にふける妻ミルドレッドとその友人たち。(当時の中産階級以上の家庭によく見られた「利己的で、暇を持て余し快楽ばかり追求するお気楽な」典型的マダムたち)
〇自分たちの職務にひたすら忠実で「善良」な昇火士仲間ブラック・ストーンマン。
で、これらの中で悩み、考え、行動し、暴れ、模索する主人公モンターグ。
以上で、構成される。
★★★
脚本・演出
冒頭、ミリーの血液入れ替え手術は、原作では自宅で行われる。これを「真空移動装置によって瞬時に病院に運ばれた」としたのは良いアイデアだと思う。よりSFらしくなるし舞台処理としてもすっきりする。スクリーンにプロジェクターでモノクロの影絵を投映したのも、効果的だった。
他の場面でも影絵は使われていたが、どことなく古風な絵柄で「1950年代のSF」の雰囲気がよく出ていた。
★
昇火隊の出動を、サバイバル番組の実況仕立てにしていた。これも、うまい。第一部のテンポの良さは、このアイデア=仕掛けによるところが大きい。
スリルが増すし分かり易い。それに、昇火隊の活動の「ウソくささ」がうまく強調される。ベイティーが視聴率に拘っているのが皮肉っぽい。マスコミの大衆迎合的誘導も表される。
★
ミリーと二人の女友達のホームパーティー風場面で、原作には「3面の壁全体がスクリーンになった」ラウンジという映像装置が登場する。この装置は、原作では「大衆を無知化する軽薄な垂れ流し文化」の象徴のように扱われる。
ひとみ座の舞台では、これをゴーグル式の映像装置としていた。
これによって、人形たちは動きを制約されず、「その場に存在しながら現実を見ず、外界とは関係ない世界の享楽に浸っている」感が出ていた。演者たちの好演で、この場面はとても面白かった。
★
原作には、ところどころ、ブラッドベリらしい美しい情景描写が出てくる。
舞台では、これをラスト近くの「川と月」の場面だけに集約していた。それも、布と照明だけを使ってシンプルに。これは第一部の少女クラリスの自然愛や感性・詩情を、思い出させるものでもある。
炎の赤に対してのディープブルーの絵柄は、緊迫した場面が続く中で、印象的なシーンだった。
★
芝居の大筋を「ベイティーとモンターグの対峙」「ミリーを代表とする、享楽的人々との齟齬」に絞って、ややもすれば饒舌になりがちな原作を、うまくまとめている。
また原作で、学者、ベイティー、フェーバーらがたびたび口にする「古典作品からの引用」は、ほぽ、捨象され、すっきりしていた。
★
原作では、
ベイティーらを殺してからモンターグは線路沿いに都市を逃れ、同じく都市を脱出中の「彷徨える学者たち」と出会う。(原作では男ばかりで女性は居ない。脚本で新たにウエスト夫人を登場させたのは、やや男性偏重である原作を修正したかったものか、あるいはキャスティングのバランスの都合か)
隣国の空爆によって、自分たちの居た都市が焼かれるのが遠く見える、その街の現状は分からない。
モンターグと学者たちは、踵を返し、都市に向かう。そこで小説は終わっている。
舞台では、
学者たちとの出会いのあと、いったん終幕のような雰囲気になり、その後突然巨大な炎幕が降りてエンディングとなった。炎幕は舞台全体を覆ったのだから、あるいは世界全体が昇火されたのかもしれない。
まあ、それは、観客ひとりひとりの受け取り方次第、ということなのだろう。
★
プロローグに「彷徨える学者たち」を登場させ全体の方向を指し示していたが、これには「ネタばれ」を指摘する声もあった。
観客が原作の内容を知っているかどうか、で受け取り方は違うと思うが、まあ、あった方が親切かな、と私は思いました。
★
「主遣いの照屋さんではなくクラリス役の佐藤さんです」と、Xのメッセージで、今回出演されていた田川陽香さんが指摘してくれた場面。
それまで台詞を担当していた高橋和久さんの声に重ねて、女性の声が同じセリフを喋った。
主遣いの声だとしたら、単に「モンターグの心の二重性を表している」と受け取れる。
しかしもし、「少女クラリスの声である」設定なら、もっと別の意味が加わることになる。
この場面、とても印象に残り、効果のある演出だったが、小林加弥子さんの意図はどちらだったのだろう。











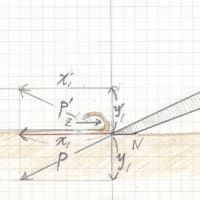




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます