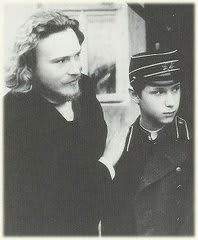
小説を読むというのは単なる娯楽だろうか。人生において何の役にも立たないのだろうか?
会社で文学の趣味があるのはどうやら僕一人のようで、変人扱いをされている。「趣味の本もいいが、ビジネス関係の本も読んだらどうだ」と上司に言われる。僕の仕事ぶりからは、顧客への心遣いが感じられない、というお叱りを受けてる最中にそう言われた。本で顧客への心遣いとかビジネスマナーが身につくなら苦労はしないと思う。実際、僕は仕事に関して非常に勉強不足なので反論はしにくいが、どこか論理がつながらない気がする。少なくとも趣味を否定される筋合いはない。
僕は現代小説は嫌いだ。エンターテインメントというか、どギツイ内容で話題になるだけの現代小説を軽蔑している。読むことで読者の思想に何かしらの良い影響を与えるのが「良い本」だと思う。
僕がサラリーマンしながら世界の名作を読み漁ったり、歴史を学んだり、芸術を味わったり、俳句にハマったり(これに関してはまた機会があれば書きたい)するのは一種の実験だ。このような一見役に立たないような教養を身に着けた人間が、社会においてどんな立場になるのか?教養がどれほど自分を助けてくれるのか?文学は人を救うのか、殺すのか??
優れた文学には、人間の心とはどういう性質のものか書かれている。人間の強さも弱さも描かれている。だから名作文学の素養がある人は、人の痛みがわかるようになると思う。僕はそんな文学から人間の心を学び、いつか人を指導する立場になった時、決して目下の人を無神経に傷つけたりしない上司になりたい。上司にならなくとも、周りの人の痛みを知り、悩みに共感し、そして自分の意見をわかりやすく説く人間でありたい。人間的魅力は、きっと教養の有る無しで変わる。短い人生の味わいも変わるはずだ。
名作文学「カラマーゾフの兄弟」をレビューしたい。本にかけられている帯によると、「東大教師が新入生にすすめる本、第一位!」だそうだ。この帯が利いたのか海外名作文学では異例の売れ行きを見せているらしい。
ドストエフスキーは読むと人生観が変わると聞いていたので、いよいよ手を出してみようと思いカラ兄全3巻を購入した。これで東大生レベルの文学的教養が手に入るならチョロいもんだ。
読んでみて思うのは、まず「ロシア文学」「ドストエフスキー」というものへの世間一般の偏見は罪だということだ。「暗い、難解、救いが無い」というイメージである。まあ「イメージのみ」で考えると間違ってはいないが、重要なのはこの小説に含まれる問題提起であり、作者の思想の独自性だ。自分はカラ兄を読む前に、ドストエフスキーのライバルであるロシア文学者トルストイの短編を読んでいたのでこのような偏見はかなり弱まっていた。その短編は神と人間を題材にしているが、非常に温かみがあり希望の持てる内容だった。
今回読んだカラ兄は訳が良いためもあろうが、読みやすい(原卓也 訳)。内容はおぞましいシーンもあるが、人間の美しさを描く箇所もあり決して絶望的な話ではない。声を出して笑える冗談こそ書かれていないが、皮肉やパロディのようなウィットな笑いは感じられる。
ただ、聖書やキリスト教がとことん遠慮無しに語られるのでそこらへんに興味が無いとキツイ。また当時のロシア農村の生活は貧困に喘いでおり、読んでて非常に寒くなる。僕はロシア人の日常やロシア正教にも興味があったので面白かった。
本作はドストエフスキーの死の直前に書かれた作品で、作者の全人生の思索の結果がぎっしり詰まっている。作者の哲学が登場人物の台詞を通して語られる。
登場人物は主にカラマーゾフ家の家族4名。父フョードル、長男ドミートリイ(通称ミーチャ)、次男イワン、三男アリョーシャ。他にフョードルの私生児スメルジャコフ、修道院のゾシマ長老、ミーチャの恋人(というかやや微妙な立場の)カテリーナ、高級売春婦グルーシェニカなど、非常にキャラ立ちした面々だ。
登場人物の性格とそのキャラクターを象徴する台詞を紹介しながら、内容をざっとつまみ食いしてみよう。
醜い外見を持つ物欲と色欲の権化、フョードル=カラマーゾフ。修道院にてゾシマ長老との会話の中で。
「私はいつも、人様の前に出るたびに、俺は誰よりも下劣なんだ、みんなが俺を道化と思い込んでるんだ、という気がするもんですから、そこでつい『それならいっそ、本当に道化を演じてやれ、お前らの意見など屁でもねえや、お前らなんぞ一人残らず俺より下劣なんだからな!』と思ってしまうんです。」
フョードルは中盤で殺されてしまうのだが、愚かで醜いキャラクターながら、売春婦グルーシェニカを妻にするために金で釣ろうと必死になったり、神聖なる修道院で無礼狼藉を働いたりと、まさに作中でおどけるピエロって感じで個人的には好きだ。
カラマーゾフ兄弟の長男にして最も乱暴で激情家、ドミートリイ。コニャックで泥酔しながら修道僧である弟アリョーシャへ語る。
「俺が我慢できないのは、高潔な魂と高い知性とを備えた人間が、聖母マリアの理想から出発しながら、最後はソドムの理想に堕してしまうことなんだ。(中略)いや、人間は広いよ、広すぎるくらいだ、俺ならもっと縮めたいね。なにがどうなんだか、わかりゃしない。そうなんだよ!」
知性家としては次男イワンが勝るものの、ドミートリイの哲学も恐ろしいほど深く複雑だ。カテリーナに借りた金を返す返さないで悩むのだが、「俺は卑怯だ、愚劣だ」という彼の苦悩はこの小説の重要なテーマの一つだ。
その知性故にやがて精神を病み破滅するインテリ、次男イワン。アリョーシャに向かって現在のロシアの言論について。
「ロシアの小僧っ子たちが今までどんな活動をしてきていると思う?(中略)飲み屋でのわずかな時間をとらえて、いったい何を論じあうと思う?ほかでもない、神はあるかとか、不死は存在するかといった、世界的な問題なのさ。」
1878年に書かれた本作だが、当時のロシアの学生の論争は「神はあるか」といった問題だったという。すごいレベルが高くないか?「我が愛する偉大なるロシア」みたいな愛国的台詞もちょくちょく出てくるし、けっこう熱い時代だったようだ。
三男アリョーシャはカラマーゾフとは思えないほど純粋で可愛いキャラだ。ロシア正教一本の生活からやがて心変わりして修道院を出る。その心の変化が興味深い。
他に個人的に好きなのはカラマーゾフ家のコック、スメルジャコフだ。フョードルが知恵遅れとみられる乞食の少女を犯して出来たという、悲しい出自を持つ。ひねくれているが非常に頭が良く、独自の無神論を展開し他の登場人物を困惑させる。髪を櫛でなでつけ、外国製のシャツを着、ピカピカに磨いた革靴を履く伊達男でもある。影がある男の生き様、カッコいい!
ゾシマ長老の若い頃の話などは、人間の善の部分を切り取った心洗われるような挿話である。ロシア文学は決して暗いだけではないのだ。
作中に強烈な無神論が登場するのでキリスト教の信者は読みにくいかもしれない。だが登場人物が醜く争い、悩む姿は人間の本性を正しく描いている。「神と人間」、「善と悪」、「罪と罰」を読者に激しく問うてくる。
本作をもしも東大の全新入生が読んだら、どうなるだろう?東大生はやがて政治家や官僚や企業の幹部になるので、社会に与える影響は大きいはずだ。善と悪を深く考えさせれば、汚職や天下りは少しは減るのだろうか?
僕が考えるに、この小説は全国の高校2、3年生にムリヤリ読ませて欲しい。本当は義務教育で読ませて欲しいが内容がキツすぎてPTAが許さないだろう。
世の中には、精神が成熟しないまま大人になった人間が多すぎる。善と悪について深く考えたことがないから、恥知らずな行動ができてしまう。人生で一度でもこういう思索をした経験があれば、ホームレスを集団暴行したり、子供を車に置き去りにしてパチンコに興じたりできないと思う。教養無き人間は悪いことをしている最中に罪の意識にさいなまれることも無い。
道徳教育にとって小説は有効だ。優れた小説は人生を仮想体験させる。読者の心に強力な楔を打ち込むことができる。やがて読書で得た知識が、価値判断の基準になったりする。
高校生の段階で、一度人生や善悪の基準について、徹底的に考えさせる必要がある。世の中には素晴らしい先生もいて、生徒の人生を良い方向に導いたりするらしいが、そんな先生はごく一部だ。大抵の人間は手本となる大人を見つけられないまま、善悪の曖昧なまま大人になる。
全ての高校生がカラ兄を読んで、成熟した大人への一歩を踏み出してほしい。
今後もっと知りたいのは解説に書いてあったドストエフスキーが西欧文明に幻滅したという話だ。ドストエフスキーがヨーロッパ巡りに出かけて、西欧文明の実態を目の当たりにしてショックを受け、完全に幻滅したらしい。日本はその頃に明治維新が起こり、当時の西欧の物真似をして現在までひたすら西欧化してきたわけだが。
こう考えると、ドストエフスキーの作品は現代日本にまだまだ示唆を与え続ける物凄い本だとわかる。
(写真は映画「少年たち」、HP:本嫌いさんの読書感想文よりお借りしました。)
追記:本嫌いさんの読書感想文 このページはカラ兄の楽しみ方を面白く紹介していておすすめだ。
少し前に紹介した「坂の上の雲」は日露戦争の話で時代も近く、ロシア側からも描いているので時代背景などを知る手がかりになった。
また、評論家の小林秀雄もドストエフスキーについて書いているので、その評論文を読んで理解が深まったらまた何か書きたいと思う。
会社で文学の趣味があるのはどうやら僕一人のようで、変人扱いをされている。「趣味の本もいいが、ビジネス関係の本も読んだらどうだ」と上司に言われる。僕の仕事ぶりからは、顧客への心遣いが感じられない、というお叱りを受けてる最中にそう言われた。本で顧客への心遣いとかビジネスマナーが身につくなら苦労はしないと思う。実際、僕は仕事に関して非常に勉強不足なので反論はしにくいが、どこか論理がつながらない気がする。少なくとも趣味を否定される筋合いはない。
僕は現代小説は嫌いだ。エンターテインメントというか、どギツイ内容で話題になるだけの現代小説を軽蔑している。読むことで読者の思想に何かしらの良い影響を与えるのが「良い本」だと思う。
僕がサラリーマンしながら世界の名作を読み漁ったり、歴史を学んだり、芸術を味わったり、俳句にハマったり(これに関してはまた機会があれば書きたい)するのは一種の実験だ。このような一見役に立たないような教養を身に着けた人間が、社会においてどんな立場になるのか?教養がどれほど自分を助けてくれるのか?文学は人を救うのか、殺すのか??
優れた文学には、人間の心とはどういう性質のものか書かれている。人間の強さも弱さも描かれている。だから名作文学の素養がある人は、人の痛みがわかるようになると思う。僕はそんな文学から人間の心を学び、いつか人を指導する立場になった時、決して目下の人を無神経に傷つけたりしない上司になりたい。上司にならなくとも、周りの人の痛みを知り、悩みに共感し、そして自分の意見をわかりやすく説く人間でありたい。人間的魅力は、きっと教養の有る無しで変わる。短い人生の味わいも変わるはずだ。
名作文学「カラマーゾフの兄弟」をレビューしたい。本にかけられている帯によると、「東大教師が新入生にすすめる本、第一位!」だそうだ。この帯が利いたのか海外名作文学では異例の売れ行きを見せているらしい。
ドストエフスキーは読むと人生観が変わると聞いていたので、いよいよ手を出してみようと思いカラ兄全3巻を購入した。これで東大生レベルの文学的教養が手に入るならチョロいもんだ。
読んでみて思うのは、まず「ロシア文学」「ドストエフスキー」というものへの世間一般の偏見は罪だということだ。「暗い、難解、救いが無い」というイメージである。まあ「イメージのみ」で考えると間違ってはいないが、重要なのはこの小説に含まれる問題提起であり、作者の思想の独自性だ。自分はカラ兄を読む前に、ドストエフスキーのライバルであるロシア文学者トルストイの短編を読んでいたのでこのような偏見はかなり弱まっていた。その短編は神と人間を題材にしているが、非常に温かみがあり希望の持てる内容だった。
今回読んだカラ兄は訳が良いためもあろうが、読みやすい(原卓也 訳)。内容はおぞましいシーンもあるが、人間の美しさを描く箇所もあり決して絶望的な話ではない。声を出して笑える冗談こそ書かれていないが、皮肉やパロディのようなウィットな笑いは感じられる。
ただ、聖書やキリスト教がとことん遠慮無しに語られるのでそこらへんに興味が無いとキツイ。また当時のロシア農村の生活は貧困に喘いでおり、読んでて非常に寒くなる。僕はロシア人の日常やロシア正教にも興味があったので面白かった。
本作はドストエフスキーの死の直前に書かれた作品で、作者の全人生の思索の結果がぎっしり詰まっている。作者の哲学が登場人物の台詞を通して語られる。
登場人物は主にカラマーゾフ家の家族4名。父フョードル、長男ドミートリイ(通称ミーチャ)、次男イワン、三男アリョーシャ。他にフョードルの私生児スメルジャコフ、修道院のゾシマ長老、ミーチャの恋人(というかやや微妙な立場の)カテリーナ、高級売春婦グルーシェニカなど、非常にキャラ立ちした面々だ。
登場人物の性格とそのキャラクターを象徴する台詞を紹介しながら、内容をざっとつまみ食いしてみよう。
醜い外見を持つ物欲と色欲の権化、フョードル=カラマーゾフ。修道院にてゾシマ長老との会話の中で。
「私はいつも、人様の前に出るたびに、俺は誰よりも下劣なんだ、みんなが俺を道化と思い込んでるんだ、という気がするもんですから、そこでつい『それならいっそ、本当に道化を演じてやれ、お前らの意見など屁でもねえや、お前らなんぞ一人残らず俺より下劣なんだからな!』と思ってしまうんです。」
フョードルは中盤で殺されてしまうのだが、愚かで醜いキャラクターながら、売春婦グルーシェニカを妻にするために金で釣ろうと必死になったり、神聖なる修道院で無礼狼藉を働いたりと、まさに作中でおどけるピエロって感じで個人的には好きだ。
カラマーゾフ兄弟の長男にして最も乱暴で激情家、ドミートリイ。コニャックで泥酔しながら修道僧である弟アリョーシャへ語る。
「俺が我慢できないのは、高潔な魂と高い知性とを備えた人間が、聖母マリアの理想から出発しながら、最後はソドムの理想に堕してしまうことなんだ。(中略)いや、人間は広いよ、広すぎるくらいだ、俺ならもっと縮めたいね。なにがどうなんだか、わかりゃしない。そうなんだよ!」
知性家としては次男イワンが勝るものの、ドミートリイの哲学も恐ろしいほど深く複雑だ。カテリーナに借りた金を返す返さないで悩むのだが、「俺は卑怯だ、愚劣だ」という彼の苦悩はこの小説の重要なテーマの一つだ。
その知性故にやがて精神を病み破滅するインテリ、次男イワン。アリョーシャに向かって現在のロシアの言論について。
「ロシアの小僧っ子たちが今までどんな活動をしてきていると思う?(中略)飲み屋でのわずかな時間をとらえて、いったい何を論じあうと思う?ほかでもない、神はあるかとか、不死は存在するかといった、世界的な問題なのさ。」
1878年に書かれた本作だが、当時のロシアの学生の論争は「神はあるか」といった問題だったという。すごいレベルが高くないか?「我が愛する偉大なるロシア」みたいな愛国的台詞もちょくちょく出てくるし、けっこう熱い時代だったようだ。
三男アリョーシャはカラマーゾフとは思えないほど純粋で可愛いキャラだ。ロシア正教一本の生活からやがて心変わりして修道院を出る。その心の変化が興味深い。
他に個人的に好きなのはカラマーゾフ家のコック、スメルジャコフだ。フョードルが知恵遅れとみられる乞食の少女を犯して出来たという、悲しい出自を持つ。ひねくれているが非常に頭が良く、独自の無神論を展開し他の登場人物を困惑させる。髪を櫛でなでつけ、外国製のシャツを着、ピカピカに磨いた革靴を履く伊達男でもある。影がある男の生き様、カッコいい!
ゾシマ長老の若い頃の話などは、人間の善の部分を切り取った心洗われるような挿話である。ロシア文学は決して暗いだけではないのだ。
作中に強烈な無神論が登場するのでキリスト教の信者は読みにくいかもしれない。だが登場人物が醜く争い、悩む姿は人間の本性を正しく描いている。「神と人間」、「善と悪」、「罪と罰」を読者に激しく問うてくる。
本作をもしも東大の全新入生が読んだら、どうなるだろう?東大生はやがて政治家や官僚や企業の幹部になるので、社会に与える影響は大きいはずだ。善と悪を深く考えさせれば、汚職や天下りは少しは減るのだろうか?
僕が考えるに、この小説は全国の高校2、3年生にムリヤリ読ませて欲しい。本当は義務教育で読ませて欲しいが内容がキツすぎてPTAが許さないだろう。
世の中には、精神が成熟しないまま大人になった人間が多すぎる。善と悪について深く考えたことがないから、恥知らずな行動ができてしまう。人生で一度でもこういう思索をした経験があれば、ホームレスを集団暴行したり、子供を車に置き去りにしてパチンコに興じたりできないと思う。教養無き人間は悪いことをしている最中に罪の意識にさいなまれることも無い。
道徳教育にとって小説は有効だ。優れた小説は人生を仮想体験させる。読者の心に強力な楔を打ち込むことができる。やがて読書で得た知識が、価値判断の基準になったりする。
高校生の段階で、一度人生や善悪の基準について、徹底的に考えさせる必要がある。世の中には素晴らしい先生もいて、生徒の人生を良い方向に導いたりするらしいが、そんな先生はごく一部だ。大抵の人間は手本となる大人を見つけられないまま、善悪の曖昧なまま大人になる。
全ての高校生がカラ兄を読んで、成熟した大人への一歩を踏み出してほしい。
今後もっと知りたいのは解説に書いてあったドストエフスキーが西欧文明に幻滅したという話だ。ドストエフスキーがヨーロッパ巡りに出かけて、西欧文明の実態を目の当たりにしてショックを受け、完全に幻滅したらしい。日本はその頃に明治維新が起こり、当時の西欧の物真似をして現在までひたすら西欧化してきたわけだが。
こう考えると、ドストエフスキーの作品は現代日本にまだまだ示唆を与え続ける物凄い本だとわかる。
(写真は映画「少年たち」、HP:本嫌いさんの読書感想文よりお借りしました。)
追記:本嫌いさんの読書感想文 このページはカラ兄の楽しみ方を面白く紹介していておすすめだ。
少し前に紹介した「坂の上の雲」は日露戦争の話で時代も近く、ロシア側からも描いているので時代背景などを知る手がかりになった。
また、評論家の小林秀雄もドストエフスキーについて書いているので、その評論文を読んで理解が深まったらまた何か書きたいと思う。



















