■エサを用意する-わらびうどん編
仕掛けの用意が整ったところでエサの準備です。かなり重要なアイテムです。
ただ、季節や水温、天候等に大きく左右されるし、このエサなら絶対というものがありません。
先人たちが多くの経験から得た「基本」をマスターすることから始めましょう。
<エサの種類>
大別すると、以下の三つに分けられます。
・ダンゴエサ…麩系とペレット系があります。
集魚に富んでいて、喰わせも兼ねます。
・バラケエサ…ダンゴエサの粘りのないもの。
喰わせエサの集魚を図るためのもの。
・喰わせエサ…針がかりさせるためのエサです。
わらびウドン、グルテン、マッシュ、オカメ(角麩)、トロロ、簡易ウドン、etc
!!エサのポイントは、大きさ・硬さ・粘り
基本はダンゴ(練り餌)かわらびうどんです。
鯉は雑食性なので何でも食べるようですが・・・
<わらびうどん>
澱粉系の粉を水で溶き、火にかけてゼラチン状に固まったものをポンプに入れて、水の中に絞り出して冷やしたものです。
集魚のためのまぶし粉(ペレット)をつけて使用します。
わらびうどん(単にウドンと言うことが多い)のメリットは、表面の粘りが強く、まぶし粉(ペレット)の付きがよいため、底まで粉のついた状態で沈みやすいこと。もう一つは比較的比重が軽いため、活性の低い時期でも吸い込みやすい、ということ。また、明確なアタリが出ることが多い。
デメリットは、保存が利かないため、当日の朝に作る(私は手をぬいて前夜作ったりもする)必要があったり、そのままだと乾燥するけど、水を入れると吸収してふくらんでしまうところ。そのため安定剤を使ったりしますが、夏場以外は特に必要ないでしょう。
わらびうどんの粉は釣り餌メーカーからも各種出ています。集魚剤配合だったり、比重を重くしてあったり、はたまた電子レンジで作れるものまで。

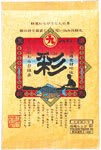
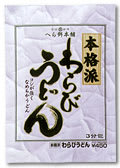
私はコストパフォーマンスもあって、スーパーとかで売ってる普通の「わらびもち粉」使ってます。(近所に菓子材料専門店があります)
作り方ですが、釣り餌メーカーものならパッケージの説明どおり、市販の粉なら、粉1:水2.5ぐらいで混ぜて充分に溶かし、強めの火にかけます。(季節によって硬さを調整しますが、何回か経験を積んで硬さを調節できるよう毎回分量を正確に測ってください。→私は、わらびもち粉15gに対し水45ccを標準としています)
なるべく泡を練りこまないよう、竹ベラのようなもので慎重にゆっくりかき混ぜ続けます。この時絶対に焦がさないこと。鍋底から少しずつ固まり始め、段々混ぜるのに力がいるようになり、綺麗に火が通ってくるとそれまで少し濁った感じだったものに透明感が出てきます。それからもう少し練りこみますが、この加減によってコシや粘りが出たり出なかったりしますので、焦げそうな時は少し火を弱めたり、火から遠ざけたりして2~3分練りこみます。
(私は緑の色粉を入れることが多いのですが、気休めかも)

出来上がったら竹ベラですくい、熱いうちに搾り出すための専用の「オカユポンプ」に入れますが、隙間があると気泡が出来てしまいますのでキッチリ入れます。
(ポンプを回しながら入れるとうまくいくようです。)

ボールに冷水を入れ、搾っていきます。この時、ポンプの口から水面までの高さを調節することで、太さが調節できます。水面に近いほど太く、遠いほど細く(着水するまでに伸びるから)なります。ポンプの口の径によっても出来上がりの太さが異なるため、ノズルが交換できるタイプもあります。一般的な「オカユポンプ」は出口が細めなので好みで先端を切ったりして調節します。
(夏場は必ず氷水を使うこと。5分ぐらい漬けておくと締まってダレにくくなる。漬け過ぎるとかたくなるのでご注意を)。
出来上がりは気泡の入っていない滑らかな状態がベストです。また、長くつながった状態で持ち上げ、切れるようでは粘りがない証拠です。
搾り出したウドンをザルに上げ、良く水を切ってから1回ハリにつける大きさに(太さと長さが同じになるように)切ります(標準は直径5mmぐらい?)。
適当な長さに切ったあと安定剤に浸して釣場へもって行き、釣場で小さく切って使うというようにと書いてあることが多いのですが、ペレットがつきにくくなるので私の場合、安定剤はウドンを練る前に水と一緒に入れてしまいますし、あらかじめ小さく切っていきます。
(夏場はダレ防止のため切ったウドンを二つに分け、それぞれをサランラップにくるんでから別々のタッパに入れ持って行き、一つは池に入れた網の中へ入れて水冷したりもしていますが、普段はとくに何もせずにそのままタッパに入れているだけです。)

うまく作れない人の強い味方として、エサを切らしたときの予備として釣場で作れるインスタント・タイプのものもあります。「オカユポンプ」で絞り出しながら使います。(感嘆=白色タイプ、感嘆Ⅱ=黄色やや重タイプなど)
1分で準備が整うのと、必要な分量だけ作れるので便利かつ経済的です。

個人的に私はウドンの代わりに乾燥タピオカ(パール)を茹でたものを多用しています。(夏場だけ)
夏場はスーパーやコンビニで売っている「わらび餅」を5,6㎜ぐらいの角切りにして釣っている人も結構います。
わらびうどんは普通「まぶし粉」(ペレット系が主)をつけることが基本です。
ウドン自体に集魚効果がないためです。
市販のヘラ用ペレットやコイミー粒、粒戦、熱帯魚のえさ(沈降タイプ)などを使いますが、比重が重いことが条件となります。
このペレットを底までもたせるためにウドンの粘り(粘着力)が必要になるのです。
ペレットにも大粒のものから細粒までいろいろな種類があります。
当然、状況によって使い分けるのが常道なのですがなかなか難しい問題です。
一般的に大粒はうわずりを押さえたい時、細粒は食い渋り時に使用するといいようです。
仕掛けの用意が整ったところでエサの準備です。かなり重要なアイテムです。
ただ、季節や水温、天候等に大きく左右されるし、このエサなら絶対というものがありません。
先人たちが多くの経験から得た「基本」をマスターすることから始めましょう。
<エサの種類>
大別すると、以下の三つに分けられます。
・ダンゴエサ…麩系とペレット系があります。
集魚に富んでいて、喰わせも兼ねます。
・バラケエサ…ダンゴエサの粘りのないもの。
喰わせエサの集魚を図るためのもの。
・喰わせエサ…針がかりさせるためのエサです。
わらびウドン、グルテン、マッシュ、オカメ(角麩)、トロロ、簡易ウドン、etc
!!エサのポイントは、大きさ・硬さ・粘り
基本はダンゴ(練り餌)かわらびうどんです。
鯉は雑食性なので何でも食べるようですが・・・
<わらびうどん>
澱粉系の粉を水で溶き、火にかけてゼラチン状に固まったものをポンプに入れて、水の中に絞り出して冷やしたものです。
集魚のためのまぶし粉(ペレット)をつけて使用します。
わらびうどん(単にウドンと言うことが多い)のメリットは、表面の粘りが強く、まぶし粉(ペレット)の付きがよいため、底まで粉のついた状態で沈みやすいこと。もう一つは比較的比重が軽いため、活性の低い時期でも吸い込みやすい、ということ。また、明確なアタリが出ることが多い。
デメリットは、保存が利かないため、当日の朝に作る(私は手をぬいて前夜作ったりもする)必要があったり、そのままだと乾燥するけど、水を入れると吸収してふくらんでしまうところ。そのため安定剤を使ったりしますが、夏場以外は特に必要ないでしょう。
わらびうどんの粉は釣り餌メーカーからも各種出ています。集魚剤配合だったり、比重を重くしてあったり、はたまた電子レンジで作れるものまで。

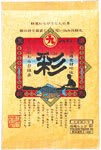
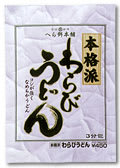
私はコストパフォーマンスもあって、スーパーとかで売ってる普通の「わらびもち粉」使ってます。(近所に菓子材料専門店があります)
作り方ですが、釣り餌メーカーものならパッケージの説明どおり、市販の粉なら、粉1:水2.5ぐらいで混ぜて充分に溶かし、強めの火にかけます。(季節によって硬さを調整しますが、何回か経験を積んで硬さを調節できるよう毎回分量を正確に測ってください。→私は、わらびもち粉15gに対し水45ccを標準としています)
なるべく泡を練りこまないよう、竹ベラのようなもので慎重にゆっくりかき混ぜ続けます。この時絶対に焦がさないこと。鍋底から少しずつ固まり始め、段々混ぜるのに力がいるようになり、綺麗に火が通ってくるとそれまで少し濁った感じだったものに透明感が出てきます。それからもう少し練りこみますが、この加減によってコシや粘りが出たり出なかったりしますので、焦げそうな時は少し火を弱めたり、火から遠ざけたりして2~3分練りこみます。
(私は緑の色粉を入れることが多いのですが、気休めかも)

出来上がったら竹ベラですくい、熱いうちに搾り出すための専用の「オカユポンプ」に入れますが、隙間があると気泡が出来てしまいますのでキッチリ入れます。
(ポンプを回しながら入れるとうまくいくようです。)

ボールに冷水を入れ、搾っていきます。この時、ポンプの口から水面までの高さを調節することで、太さが調節できます。水面に近いほど太く、遠いほど細く(着水するまでに伸びるから)なります。ポンプの口の径によっても出来上がりの太さが異なるため、ノズルが交換できるタイプもあります。一般的な「オカユポンプ」は出口が細めなので好みで先端を切ったりして調節します。
(夏場は必ず氷水を使うこと。5分ぐらい漬けておくと締まってダレにくくなる。漬け過ぎるとかたくなるのでご注意を)。
出来上がりは気泡の入っていない滑らかな状態がベストです。また、長くつながった状態で持ち上げ、切れるようでは粘りがない証拠です。
搾り出したウドンをザルに上げ、良く水を切ってから1回ハリにつける大きさに(太さと長さが同じになるように)切ります(標準は直径5mmぐらい?)。
適当な長さに切ったあと安定剤に浸して釣場へもって行き、釣場で小さく切って使うというようにと書いてあることが多いのですが、ペレットがつきにくくなるので私の場合、安定剤はウドンを練る前に水と一緒に入れてしまいますし、あらかじめ小さく切っていきます。
(夏場はダレ防止のため切ったウドンを二つに分け、それぞれをサランラップにくるんでから別々のタッパに入れ持って行き、一つは池に入れた網の中へ入れて水冷したりもしていますが、普段はとくに何もせずにそのままタッパに入れているだけです。)

うまく作れない人の強い味方として、エサを切らしたときの予備として釣場で作れるインスタント・タイプのものもあります。「オカユポンプ」で絞り出しながら使います。(感嘆=白色タイプ、感嘆Ⅱ=黄色やや重タイプなど)
1分で準備が整うのと、必要な分量だけ作れるので便利かつ経済的です。

個人的に私はウドンの代わりに乾燥タピオカ(パール)を茹でたものを多用しています。(夏場だけ)
夏場はスーパーやコンビニで売っている「わらび餅」を5,6㎜ぐらいの角切りにして釣っている人も結構います。
わらびうどんは普通「まぶし粉」(ペレット系が主)をつけることが基本です。
ウドン自体に集魚効果がないためです。
市販のヘラ用ペレットやコイミー粒、粒戦、熱帯魚のえさ(沈降タイプ)などを使いますが、比重が重いことが条件となります。
このペレットを底までもたせるためにウドンの粘り(粘着力)が必要になるのです。
ペレットにも大粒のものから細粒までいろいろな種類があります。
当然、状況によって使い分けるのが常道なのですがなかなか難しい問題です。
一般的に大粒はうわずりを押さえたい時、細粒は食い渋り時に使用するといいようです。




















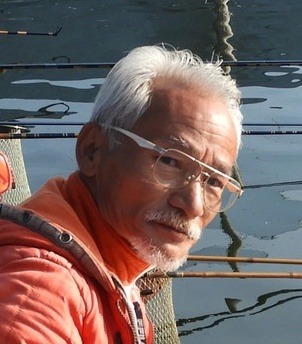





エサで試行錯誤するのも、楽しいですね。
安定剤を水と一緒に入れるところなど、参考にさせてもらいます。